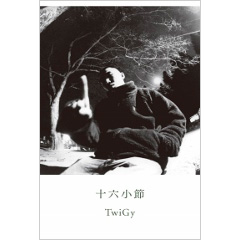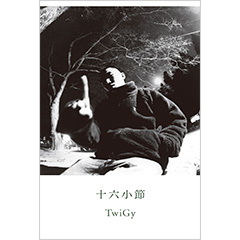MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with TwiGy - さ、みんなききなっよ!
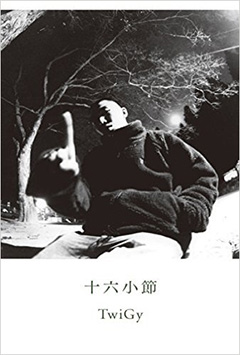 十六小節 TwiGy Pヴァイン |
ツイギーはたしかに日本語ラップの“レジェンド”である。先駆者であり、開拓者である。1971年生まれのツイギーはアイス・Tやラン・DMCに感化され、ラップを始めている。80年代後半に早くもDJ/ビートメイカーの刃頭とビートキックスを名古屋で結成、本格的に活動を開始する。その後、ムロらとのマイクロフォン・ペイジャーでの活動を経て、今度はウータン・クランに触発されて雷を立ち上げる。先日刊行された自伝『十六小節』には、生い立ちはもちろん、そのあたりの詳しい経緯や背景についても書かれている。非常に興味深い自伝だ。
だが、闇雲に“レジェンド”と祭り上げるだけではツイギーの半分も知ったことにはならないだろう。2016年現在だから強調したいことがひとつある。それは、ツイギーがこの国の“トラップ・ラッパー”のパイオニアであるということだ。USアトランタ発のトラップの源流となるサウス・ヒップホップ/ダーティ・サウスにいち早く着目して独自の日本語ラップを創造した功績を忘れてはならない。その試みは2000年に『FORWARD ON TO HIP HOP SEVEN DIMENSIONS』という傑作として結実している。そして、その後も走り続けてきている。つまり、いとうせいこうからKOHHにまで至る日本におけるラップ・ミュージックの進化/深化のミッシング・リンクとなるのが、ツイギーというラッパーなのだ。先日放映された『フリースタイルダンジョン』でのライヴを収録した翌日にツイギーに話を訊いた。
■自伝『十六小節』を刊行したあとにいろんな反響があったと思うのですが、どんな手応えを感じていますか?
ツイギー:音源を出したときとは違うから、こそばゆいような感じですね。
■刃頭さんをはじめ、ユウ・ザ・ロックさんやリノさんといった面々が出てきたり、初期から一緒に活動されている方がかなり登場されるじゃないですか。そういう方からの反応はどうでしたか?
ツイギー:みんな、面白かったよ、とは言ってくれているからね。その時代の同じ場面にいた人たちだから、そのときのことを思い出させることができてよかったとは思ってる。
■なぜこのタイミングで出すことになったんですか?
ツイギー:最初は俺が小学6年生のときに幽体離脱した話を表に出したい、ということだったんだよね(笑)。途中で、“HOW TO RAP”本にするとかいろんな案があったんだけど、結果こういう形になったね。
■自伝を作ることは、これまでの活動や人生を客観的に振り返る作業だと思うのですが、記憶していた事実を整理したり言語化する過程で発見はありましたか?
ツイギー:思い出す作業の連続だったから、それを文字に起こして見てみると、当時はこうやって見てたんだな、と思うよね。そのときは無意識にやっていたことだから、そんな風に考えてもいないし、見ようともしていなかった。いまだからこそ、自分がやってきたことがこのときはこうだった、と理解できている。そのときは説明もしないし、無意識にとにかくやるということを前提に作っていたね。音楽に関して言えば、実験の途中経過をずっと見せてきた感じですね。
■「実験の途中経過を見せてきた」という発言は興味深いです。自伝の中で「言葉をフォント化する」という話がでてきますね。例えば、「さ、みんなききなっよ!」という“ツイギー節”としか言いようのないフレーズやラップの技法を生み出すときに理論化していたわけではなかった、と。
ツイギー:考えていなかった。韻を踏むということについてもそうだしね。まだラッパーの数も少なかったし、印象づけるにはどうするか、ということを前提にラップしてた。声にしろ、言葉の喋り方にしろ、ファッションにしろ、フロウにしろ、全部をベタベタにやっていたと思う。アイコン的な言葉を意識して作っていたのはあるね。ヒップホップの最初のころは、ビック・ダディ・ケインはビック・ダディ・ケインでしかなかった。彼を真似しているヤツはビック・ダディ・ケインではないから。でもいまは、みんなの言葉遣いやイメージがけっこう被っているよね。芸人のネタみたいに、もっとわかりやすくした方がいいと思うけどね。
■そこで思い出すのが、ウータン・クランをユウ・ザ・ロックさんとニューヨークで見たときのエピソードですね。まだ売れる前の街のあんちゃんみたいなウータン・クランを生で見て、ツイギーさんが「関西芸人みたいな雰囲気」という感想を書いています。オール・ダーティ・バスタード(ODB)が酒を盗もうとして店主に銃を突きつけられる場面を目撃したエピソードも衝撃的ですね。
ツイギー:あのときのウータンがまさに売り出し中だったからね。スタテンアイランドから渡ってきて、マンハッタンやブルックリンでライヴをしてた。フライヤーには他のアーティストの名前が書いてあるのに、クラブに行ってみたらウータンが出てくる、みたいなことも多々あった(笑)。MUSEというクラブで観たライヴがとにかくすごかった。青竜刀を振り回してるヤツがいたり、ゴーストフェイスはまだ指名手配中だったのか、顔をストッキングで隠していて……ストッキングで顔隠しているヤツがラップしてるんだよ? まずおかしいじゃん(笑)。しかもみんなしてハーレムのストリートの露店なんかで売ってるパチモンのブランドを着てた。ODBだったらエルメスの柄がプリントしてあるスカーフとベストと半ズボンとか着て、杖を持っている(笑)。あとはみんなウータンのTシャツを着てたね。ステージからはみ出さんばかりの人数でライヴをやってて、スピーカーの前にもウータンのTシャツを着たキッズがいるような状況だった。ホワイト・オウルという葉巻があるんだけど、スピーカーの前でそれでクサを笛吹童子のようにして巻いていたり、レイクウォンは棒状のスタンガンを持って、それを重ねあわせてバチバチバチって火花散らしながら出てきたり、「もうなんだ、これは!?」という感じだったんだよね。
■それはすごい……(笑)。
ツイギー:それまでニューヨークには集団でやるノリがなかったけど、たぶんウータンがそれを作ったんだよ。ウータンが全員同じTシャツを着たり、ステッカーをクラブで投げて撒いたり、みたいなノリを作ったんだよね。街にもあの“W”マークがいっぱいあったんだけど、それだけだったから何もわからなかった。だから俺も何が起きているのかを把握していなかったのだけれど、MUSEに行ったら“W”がウータンのマークだというのがわかった。「プロテクト・ヤ・ネック」の白黒のビデオがバーのモニターで流れたときに、「見ろ! 俺らのビデオだ!」みたいなことを言ってたね。
で、MUSEでのライヴが終わって、ユウちゃんと水を買おうと思って近くのデリに入っていったら、ODBが店のおじさんに銃を突きつけられながら、「出せ! 出せ!」と言われていて、ODBがおじさんに酒を渡して走って逃げるところを見たんだよね。そのとき俺の前にいた若い黒人の男がそれを見て、腹から酒を2本出して、「こいつもだったんだ!」と思った(笑)。
普通にODBがそのへんを歩いててストリートのヤツと話をしてたりするのも見たね。そういう経験をして生活の延長線上にヒップホップがあるのを感じた。日本だとどうしても普段の生活とステージが切り離されている。俺はそういうものに違和感を抱いたからヒップホップを選んだ。そういう考えがあったから、ウータンには感じるものがあったんだ。ODBのやってることにしたってもちろん悪いことは悪いことだけど、そういう部分も含めてすごく俺らと似通っている部分があった。だから、NYでウータンを観て雷をやろうということになったんだよね。みんなキャラ立ちしすぎているし、これを何とかしないともったいないと思ったしね。だから、ウータンからの影響は大きかったよ。
■なるほど。ツイギーさんが本格的にラップを始めるきっかけとなったのが、ラン・DMCとフーディニのライヴであったとも書かれています。彼らに見たヒップホップとウータン・クランに見たヒップホップにはどういう違いがありましたか?
ツイギー:ラン・DMC、フーディニ、ビースティ・ボーイズを観たときの俺はまだ子供だった。大人のショーを見ている俺だもん。ニューヨークに行ったときからその価値観というか考え方が変わったんだよね。ウータンをニューヨークで観たときに俺はヒップホップの一部になっているつもりだったから、ライヴをお客さん側として見るという気持ちはない状態なんだよね。だから、ファンとして観るというよりかは、仲間として観ているという感覚のほうが強くなっていたのかもしれない。
でも、日本ではヒップホップの一部になっているという価値観でこのムーヴメントと関わっている人はいまよりも圧倒的に少ないわけでしょ。だから、ずっと闘ってきた。「日本語でラップなんてできるわけないじゃん。バカじゃないの」という人が圧倒的に多かった。だから、「そんなことないんですよ」と言ってやってみせる。そのくり返しだったね。
ラップは日本語でやってもいろんな国の人に伝わる素晴らしいものだと考えていたから、日本語でやろうと思ったんだよね。俺が英語でラップをやったら、その中の一人でしかないじゃん(笑)。だけど、俺がやりたいのは日本語のラップでヤバいと思わせることだったんだよね。
■例えば、いとうせいこうさんや高木完さんもラン・DMCを観た時に「自分にもラップができると思った」と口をそろえておっしゃるのですが、ツイギーさんはどうでしたか?
ツイギー:俺はラン・DMCやフーディニを観る前から心は決まっていたのだと思う。だから、ラップをやるきっかけというよりは最終確認だった。俺のきっかけは、『ブレイキン』のアイス・Tだから。それからずっとラップを日本語に変換してできないかと考えてた。ラン・DMCとフーディニが来たときは、それまでの考えを構築していく感じだった。でも、やっぱり簡単にできるものだとは思わなかったね。だから、他の人の曲を聴いてもやり方に納得がいかなかったし、素直にカッコいいとは思えなかった。だから、自分自身で作ったんだと思う。横浜銀蠅スタイルだよね(笑)。彼らも自分の車でかけたいカッコいい日本語のロックがないから、自分らで作ったんでしょ? それと同じだと思うよ。当時は英語を入れてごまかしているものか、笑かそうとして作っているものしかなくて、カッコいい日本語のラップがなかった。
だけど、いとうせいこうさんのラップのやり方は、俺にギリギリ入ってきた。みんながオン・ビートでラップしていたけど、俺はずっとオフ・ビートでやろうとしていた。せいこうさんもそうだった。その上で俺は恥ずかしくない聴こえ方を意識していた。日本語でラップをするなんていうのは、やっぱりお笑いになる確率がすごく高かったから、どっちの振り幅に傾けるかというのがとても重要だった。たぶんムロくんもラップをするにあたってそこを考えたと思う。面白いことを言いたいし、聴かせたいけど、笑われるのは嫌だった。当時はカッコよくて面白いんだ、というところをずっと追求していたんだと思う。
■「カッコよくて面白いことを追求した」というのは重要なテーマですね。かつては日本語でラップをするときに、どこかでトリック・スター的にならざるを得ない状況があったと思います。せいこうさんはそこを逆に強みにしたと思います。ツイギーさんは同世代とそういう議論することはできていました?
ツイギー:いや、ひとりで考えていたね。そこの部分はシェアできないもん。せいこうさんが同世代にいたら、その話はできただろうね。せいこうさんは曲によってスタイルを変えていたでしょ。あの当時から曲によって違うフロウを乗せているし、俺はそれにすごく影響を受けているんだよね。その重要さにみんな気づかないで、ただ普段しゃべっていることを言えばいいと思っていたんだよ。いまでさえそれにちょっと近い部分はある。言葉を大事にしていないから、パンチラインも作れない。決定的なところでパンチラインを出すべきなんだけど、そういう意識がないと他のラインと同化してしまって、デコボコは生まれないし、聴く側の感じ方も平坦なものになっていくよね。日本語のラップでもっといろんな実験ができるはずなんだけど、(日本のヒップホップは)終わりに近づいているな、という感じはするね。2007年くらいにシンゴ02が日本に来たときに初めて会ったんだ。そのとき彼に「ツイギーさん、諦めないでくださいね」って言われたんだよね(笑)。ちょっと腹が立って、「何をだよ!? 俺はやってるよ!」って言ったけど、あいつの言っている意味はわかったね。「日本でヒップホップを諦めない」という意味だということはわかるんだよね。それをいまでもやっております、という感じ(笑)。
■90年代初頭にオーディオ・スポーツ(恩田晃、竹村延和、山塚アイ)にゲスト参加して作品を出していますよね。マイクロフォン・ペイジャーや雷の以前にツイギーさんがオーディオ・スポーツと一緒に曲を作っていた史実は非常に興味深いですよね。どのような経緯だったんですか?
ツイギー:俺はさっぱりわからない。当時は刃頭が全部セッティングして決めてきたからね。オーディオ・スポーツも同じように、「星野(ツイギー)を呼びたいってヤツがおるんだわ」と言われて、ちょこっとオーディオ・スポーツの音源を聴いて、名古屋から恩田くんのいる京都に行った。牛丼食べたんだけどあまり美味しくなくて、「京都は水がマズいんですわ」「盆地やから詰めて固めたものばっかり食べさせてる」という話をされたのをおぼえているね。それから竹村くんのところに行って、レコード選んで、2、3日間かけてアイちゃんとスタジオでレコーディングしたんだよね。いくらもらったのかもおぼえてない。まだ10代だったし、全然おぼえてないね。俺は多分もう音源も持っていない。ただ、レコーディングしてからしばらくしてCDとアナログが出たんだよね。
■ツイギーさんが客演で参加したオーディオ・スポーツのシングル「Eat & Buy & Eat」は1992年に出ていますね。
ツイギー:当時名古屋でヒップホップの音を作るヤツは刃頭ひとりだし、ラップするヤツは俺ひとりしかいなかった。オーディオ・スポーツとやったあとに、イベントとかやりだして、ネイキッド・アーツの前身のスキップスが出てきたり、PHフロンが出てきたりしたね。何も生まれていないころだね。だからオーディオ・スポーツも新しいことをやっていたということだよ。あの当時にヒップホップをやってんだもんね。関西のムーヴメントだよね。でもなんで俺に話が来たのか、ということは刃頭に訊かないとわからないね。
■オーディオ・スポーツのメンバーとはその後交流はなかったんですか?
ツイギー:一切ないね。何年後かに恩田くんやアイちゃんに会った気はするけど。まぐれでCD出せちゃったような運命的なものなんだよね。
■話は少し戻りますが、さきほどツイギーさんはラップの抑揚、フロウに関して“デコボコ”という表現を使われていましたよね。いかに日本語でリズムやアクセントを作るか、ツイギーさんはその探求をされてきたラッパーだと思います。2000年に『FORWARD ON TO HIP HOP SEVEN DIMENSIONS』を出しますが、日本でいち早くサウス・ヒップホップを取り入れて独自に表現した作品でした。あの作品について語ってもらえますか。
ツイギー:せいこうさんもそうだけど、俺は(ヒップホップを)聴いて“ひっかかり”にすごくこだわっているような気がしたんだよ。俺はそれを自分ではどうやればいいのか、ということを考えながらやっていたんだよね。せいこうさんはそのやり方や言葉の使い方を知っている人なんだと思う。せいこうさん以外はカッコつけにしか聴こえなかったわけ(笑)。俺はパッと聴いて無条件に音として「カッコいいじゃん」と思わせるものをいかに作るかということをいつも考えてきた。
日本語は棘がなくてやわらかい、なめらかなものだからこそ、とっかかりを作ってデコボコにするということを意識してきたね。その手法が倍速のラップとかにつながっていく。なだらかなものをガタガタにするということ考えていたら、その手法になったんだよね。それは日本語が英語ともパトワとも違うからであって、それを構築していくことには時間がかかったね。文法はめちゃくちゃになるし、意味はどう伝えればいいのかということも考える。
サウスのラップを聴き始めて、『SEVEN DIMENSIONS』を作ったのもそういったことを考えていたからだね。ライムの乗せ方のアプローチが違うから、それをやりたかったんだよね。トゥイスタとか、レゲエのダディー・フレディーとかの早口が好きだったから、それを日本語でやってみたかった。アメリカのテレビ番組やライヴでラップを見ると、とにかくすごく速いわけ。だけど日本のラップは、相変わらず遅かった。俺は、ライヴで早口のラップをするとみんなが盛り上がる感覚が欲しかった。
いまトラップが流行ってきて、その手法が簡単に見えて実は難しいということにみんな気づいている。しかも速くしゃべると、言葉に表情を持たせられないから、「あーーー」って言うのと「あっ」って言うのとでは聴こえ方も感じ方も違うから、なおさらそこにどんな言葉を使えばいいか、どんな感じで言えばいいのかということもすごく重要になってくる。
日本語の使い方も内容も見せ方も含めて、いまはKOHHが一番だと思っている。それ以外は頑張った方がいい、という感じはするよね。あと何枚アルバム出すのか、早く死ぬのか、ヒップホップを茶化しただけなのか、なんでもいいけど、みんなに名前を知られるというのはそういうことだからさ。だったら頑張ったほうがいいよね、俺も。
■『SEVEN DIMENSIONS』の“七日間”、“GO! NIPPON”、“一等賞”、“もういいかい2000”を当時聴いたときの衝撃はすごかったですし、古びていないですよね。いま考えると、ツイギーさんは日本のトラップのラッパーのパイオニアだと思うのですが、“GO! NIPPON”にはマッチョさんも参加していて……
ツイギー:そう、あのときあのスタイルを理解していたのはマッチョだけだよ。俺らはスリー・6・マフィア・スタイルでやってるよね。いまトラップが流行っているのを見ていて、俺は『SEVEN DIMENSIONS』ですでにやったし、ラップの仕方もそれの真似じゃんとは思うよね。
■『SEVEN DIMENSIONS』、そして『The Legendary Mr.Clifton』 でデコボコを強調する実験を経たのち、『BABY’S CHOICE』『Blue Thought』ではささやくようなラップのスタイルにギア・チェンジをしているように思うのですが、変化をうながした何かしらのインスピレーションがあったのですか?
ツイギー:変化というよりかは、俺の中のジャンルのひとつだよね。ペイジャーもそうだし、その前からもいろんな声を登場させているわけ。俺の曲を初めて人に聴かせたりすると、よく「これ、ひとりなんですか?」とか「何人でやっているの?」とか言われたりするんだけど、全部俺だから(笑)。その感じでずっとやってきているから、細分化されただけなんだよね。番外編が登場みたいな感じ。俺はライヴであってもメロウなものから激しいものまで全部の曲をそういう風にやるし、そこに変化はないんだよ。だから、「昔のスタイルが良かった」とかみんな言っているけど、俺のライヴでは全部やるから、そういう人なんだ、という合点がいくんだよね。俺自体はなにも変わらないんだよ。次はまた激しいのをやろうかなとか、スカのアルバムを出そうかなとか、なんでもいいわけだから。HAKUEIとRUKAくんとやった“砂ノ街”も賛否両論あったけど、ヴィジュアルとかパンク聴いているヤツらには評判いいもんね。イメージつけて鍵かけないでくれよ、とは思うよね。
だから何ひとつ断らず全部にフィーチャリングして、ムチャクチャにしてやろうと思ってやってきたよね。でもそれをやっている最中、ある先輩に「セル・アウトだ」と言われたんだよね(笑)。「ふざけんな!」と俺は思ったんだけどね。ヒップホップはユナイトだろ、どれだけでもつながってやるぞ、相手が嫌だろうがなんだろうが、全部活かしあってつながっちゃうんだから。
ロックっていう音楽は全部をつっぱねていた気がするんだよね。「俺はロックだからそんなことはできねえ。そんな曲はやらねえ。レゲエ? そんなの知らねえ。ヒップホップ? そんなのわかんねえ」と言っていたのがロックだと俺は認識しているんだよね。ロックは手法から何からヒップホップに食べられてしまったから、いまは長い髪やモヒカンや革ジャンが残っているだけでしょ。でも、ヒップホップはそんなものはいらない。パンツ一丁でもラップしてやる、という話だよね。それがヒップホップだもん。それをみんなは箱に入れたがるよね、ずっと。それに我慢ができない感じ(笑)。だから続けてる。
■ツイギーさんは今後の活動のイメージはありますか?
ツイギー:いや、何も決めていない。決めようかとは思っているけど(笑)。5年以上ソロ作品は作っていないから、音楽は作りたくなってきたという感じかな。フィーチャリングだのはやったけど、自分の作品ではないからね。枯枝楽団をどうするかはわからないけど、誰かにトラックを提供してもらうかもしれないし、バンドになるかもしれないし、未定ではあるけども、作りたい感じはちょっとある。ここ数年は音楽を意識的にやめている感じだったからね。
■そうだったんですか。音楽を作るということに関して、5年のブランクがあるという意識だったんですね。
ツイギー:そうだね。2011年に『Blue Thought』を出した時点でやめようと思っていたから、まあある意味やめられた感じもあるけどね(笑)。
Black File #276 ONAIR INFOMATION
ONAIR NO.276
10/21(金)27:00〜
PROGRAM
INTERVIEW FILE:TwiGy
LIVE FILE:Mary Joy Recordings Presents "Diversity Vol. 1"
オタク IN THA HOOD:呂布カルマ
Exclusive MV “NEIGHBORHOOD”:Y2FUNX
DRIVER:V.I.P. HI-POWER & KEN U
http://blackfile.spaceshowertv.com/post/151510951867/black-file-276-onair-infomation-interview-file
Profile
 二木 信/Shin Futatsugi
二木 信/Shin Futatsugi1981年生まれ。音楽ライター。共編著に『素人の乱』、共著に『ゼロ年代の音楽』(共に河出書房新社)など。2013年、ゼロ年代以降の日本のヒップホップ/ラップをドキュメントした単行本『しくじるなよ、ルーディ』を刊行。漢 a.k.a. GAMI著『ヒップホップ・ドリーム』(河出書房新社/2015年)の企画・構成を担当。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE