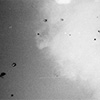MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Okada Takuro - 眠れぬ夜のために
森は生きているの3枚目が作りたくてしょうがなかったです。一応『グッド・ナイト』が出てから1年くらいはずっとライヴに回って、5曲くらいは新曲があったんです。“手のひらの景色”はそのなかの1曲で、次のアルバムに入れようとしていた曲だったんですね。
■解散したのが2年前?
増村:そうですね。
岡田:けっこう経ってんだな。
増村:だから『グッド・ナイト』の発売からは3年ですね。
岡田:年間ベストに合わせたのに載らないっていう。
(一同笑)
■解散をファンのかたはどういうふうに受け止めていたのかは気になりますね。
増村:それは僕らも気になるところだけど(笑)。どうなんですかね。
岡田:ポーンとやめたからね。
■とはいえ、(『ノスタルジア』は『グッド・ナイト』と)違うものではあるけども、結果として(森は生きていると)メンバーは重なっているじゃないですか(笑)。そういう意味では、『ノスタルジア』は森は生きているの発展型としても聴けるんですよね。
ただ、最初に今作のタイトルとなった『ノスタルジア』という言葉を聞いたときに、一瞬戸惑ったんですよね。「らしいな」とも思ったんだけど。というのも、ポップ・ミュージックの世界にはいろんなトレンドやスタイルがある。森は生きているがそうだったけど、そのなかにあって自分たちは常にトレンドとは違うところにいるみたいな感覚というか、言い方を換えれば居心地の悪さというか……
岡田:日本語詞は情念がないほうが好きなんですけど、このタイトルにはあまりにも情念がこもりすぎていて(笑)。言わないほうがいいのかなって(笑)。
■ぼくも情念がこもっているのかなと思ったよ! 「ノスタルジー」という言葉のなかにはコマーシャルな響きと、アイロニーと、ある種の自虐性があるんじゃないかなと(笑)。
岡田:そこは誰も突かないんだけど、自虐性は意図していたかもしれないですね。
■だから複層的な意味が込められている「ノスタルジー」なわけでしょ?
岡田:コマーシャルでキャッチーな言葉、そして誰もが知っている言葉なぶん、イメージが人それぞれに浮かぶ言葉だと思ったんですね。いくつか要因はあるんですけど、自分は新しい音楽を作りたいと思うなかでも、やっぱり文脈的な音楽を作りたいとも思ったんです。それはフォーク・ミュージックがこれまであったような歌いかたを変えて更新されていく、楽器が変わって更新されていく、音響が変わって更新されていくポップスみたいなことへの「ノスタルジア」ですね。なぜならいまはそういう時代ではなくなっていて、とくに日本はそうであるという思いが強くあるからタイトルにしたということもあるし、もちろんやっていくなかでバンドに戻りたい「ノスタルジア」もあったと思う(笑)。
今回は新しい音楽を作りたいと言っても、結局一番参照にしたものは2010年前後のブルックリンなんですね。森のときの音楽的な参照になったのが6、70年代のフォーク・ロックと、00年代のポスト・ロックだったんですけど、それは2013年に1枚目を出したときにはある意味でもう「ノスタルジア」だったという。でもそれが新しいものになりうる可能性を秘めていて、普遍的なものにも感じたということもあって。もちろんほかにもいろんな意味合いはあるんですけど。
増村:いっぱい(意味が)こもっているから、僕は「ノスタルジア」にしてはすごく強度があると思うんですよ。あんまり儚くないというか、壊れやすくもないというか。歌詞を見ても「こぼれ落ちていくような感覚、これはなんだ」っていう希求している精神だったり、「ただの霧さ」(“アルコポン”)と言ってもただの霧だと認めたくないような雰囲気だったり、そういうものを感じるんですよね。『グッド・ナイト』のときにかたちにならないものをどうにかしようとしてみたものを、もう1回ひとりでやってみた、ということもあるかもしれないんですけど、『グッド・ナイト』のときと違って、そういう音楽的な欲求も含みつつ、岡田がさっき「情念がこもっている」と言ったのがおもしろいと思いました。「ノスタルジア」だけど言いたいことが混ざっているように感じたんですよね。さっきも言ったけど、希求していたり格闘していたりするところが反映されていると思うんですよ。それはアルバムを聴いていていいなと思いますね。
岡田:すごく言葉にしづらいよね。こんなアルバムばっかり作っているね(笑)。
■でもあんまりそこの部分はこれ以上説明しないほうがいいと思うよ。
(一同笑)
■ぼくは今回のアルバムを本当にうっとりするように聴いたんですね。1曲目のギターのイントロを聴いたときに「なんていい音楽だろう」と思ったよ(笑)。このメロウな感覚がたまらないと思って最後まで聴いたんだけど、また最初から聴きたくなるんだよね。ネガティヴな思いが全然聴こえないんですよ(笑)。
岡田:それを表に出したらやっぱりJポップになっちゃうから、そういう表現はしたくなかったですね。「辛い辛い辛い」って言って、「ああ、辛いね」って聴かれてもしょうがないし、僕はそういう音楽は例外なく嫌いだし。
■難しいことを難しいまま出さないよね。
増村:この人、その二点に関しては信じられないくらい敏感ですよ。
■はははは、そうなんだ(笑)。
増村:その見せ方の作戦もうまい(笑)。
■そうした作り手の苦労を考えずに、例えば普通に車のなかで聴いていたらすごく気持ちいい音楽だと思うんだよね。
岡田:あんまり難しくしたくなかったというのは意識としてありましたね。
■ただひとつ思ったのは、ヴォーカルとトラックの音量のバランスで言うと、通常よりもヴォーカルが低いと思ったんだよね。
岡田:それは大瀧詠一の影響ですね。
■はははは。
増村:大瀧師匠のやりかただよね(笑)。だけどはっぴえんどもそうとう小さいですよ。
岡田:はっぴいえんどはリヴァーブがかかっていないからけっこう前に出てくるけど、『ナイアガラ・ムーン』とかほとんど聴こえない(笑)。だから『ノスタルジア』をトラック・ダウンして半年経ったいまの自分がミックスをやるんだったらもっとヴォーカルを上げるんですけど、ただ恥ずかしがり屋というのがミックスのバランスにすごく関わっているんですよね(笑)。それとミックスをやりすぎて「自分の声が聴きたくない」と思って、だんだん小さくなっていったっていうシンプルな理由かもしれないですけど(笑)。
■歌詞は自分で書いているでしょ? 増村くんも書いているけど。
増村:僕は1曲だけですね。
岡田:いや、1曲半ですね。
増村:あの半分はもうほとんど岡田くんが書いたというか、(“手のひらの景色”は)森のときにやっていた曲で、そのときの歌詞が残っているという意味で半々なんですよね。実質は1曲ですね。
■ほとんど自分で書いているんだ?
岡田:そうですね。
■最後の曲は増村くんが全部書いたの?
増村:そうですね。あれは全部僕です。
岡田:僕が電池切れになって書けなくなったから……(笑)。
■歌詞に関してはどんなコンセプトがあったんでしょうか?
岡田:はっぴえんど特集をした『ユリイカ』が僕の日本語ロックのバイブルなんですけど、細野さんが「日本語ロックの情念を消したかった」ということを言っているんですね。僕がはっぴいえんどフォロワーや喫茶ロックと呼ばれている音楽にそんなに入れ込めなかったのは情念的なものが情報として多すぎて、自分のなかではトゥー・マッチに聴こえた。英語に比べて、日本語は音楽的な響きの語彙がすごく限られているように感じます。洋楽を聴く感覚で日本語の音楽を聴けないものかというのは常に考えています。
■情念というのはどういうものなんだろう。演歌的なものってこと?
岡田:情念の違和感ってどう説明すればいいんだろう(笑)。
増村:松本隆が言っていておもしろかったのは、「なにを歌うかじゃなくて、どう歌うかで俺らはやった」という話で。「なにを歌うか」というところがみんな強すぎるというか、そういうところなんじゃない?
■早川義夫じゃないってこと?
増村:そうそう、そうです。それではっぴえんどのときには日本のフォークのカウンターとしてあったんだとしたら、僕らにはJポップがあるんで、そうはなりたくないというのがひとつあるんじゃないんですか?
岡田:そうだね。
■ぼくなんか10代の頃はRCサクセションだったからなぁ。清志郎の反抗的でわかりやすいラヴ・ソングを聴いていたからね。
岡田:意外っすね。
■ライヴ行きまくって、“ようこそ”とか。ああいうので「うぉー」ってなっていたんだよ。
岡田:ああいうものが人の心を動かしたりするのはすごくわかるし、あれはあれで素晴らしい音楽だけど、僕はそれにただハマらなかったというだけの話であって。なにかが間違いということではないですね。うまく切り返せたかな(笑)。
増村:いいと思います(笑)
■でもJポップと言ってもいろいろあるからね。Jポップと言われたときに一番に思い浮かぶのはなんなの?
岡田:Jポップが何かというか……それとカウンターになるような日本のインディ・ロック自体もJポップとなにが違うんだと言えば、どちらもある種の情念で同じ共感を生んで客商売をするようなものだと思う。ポップ・ミュージックの要素のひとつとして娯楽があるとしたら、全然ある要素だということはわかるんですけど、ただすべてのJポップやインディ・ロックが娯楽であるべきかと言ったらぼくは別にそうは感じない。
そういう娯楽じゃない部分というのもやっていいはずなのに、そこは完全に売れないものとして流れ続けてきたのが日本のポップ・ミュージックの歴史として強く感じる部分なんですよ。USとかだったらインディ・ロックでたまにチャートに入ったりもするし、それは世界中にパイがあるからというのもあるとは思いますけど。じゃあそれで僕が好きな渚にてだったり、山本精一だったり、パドック(Padok)だったり、ランタンパレードが、向こうでファーザー・ジョン・ミスティーがポンとチャートに入ってくるような感覚で、強度があるから評価されるということは日本ではやっぱり少ないと思っています。
■じゃあ今回はそういう意味で言ったら、アジカンの後藤正文さんのレーベル・マネジメントというのは大きいよね。
岡田:そこはひとつチャンスに思った部分でもあるし、逆にゴッチさんはインディ・ロックと日本の大衆的な意識をリンクさせようというところで意識的にぼくを拾ってくれたとも思う。実際にそういうものを紹介したいということを常にやっている人ですけど。
取材:野田努(2017年11月20日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE