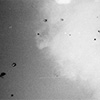MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Okada Takuro - 眠れぬ夜のために
はっぴいえんどリヴァイヴァルでまずいなと思うのは、なんだかんだ言って結局は、なんとなく叙情的で、なんとなく口当たりのいいフォーキーなポップスを肯定するしかないというどん詰まり感だ。ああそういえば、ソフトに死んでいく──と言ったのは誰だっけ?
岡田拓郎(そして増村和彦)の内には、そうした極めて表層的なはっぴいえんどリヴァイヴァルへの違和感があり、後期森は生きているのライヴにおける超越的な一瞬は、バランスを崩しながら、なにかしら彼らが乗り越えようとしていることの情熱のひとかけらだったとぼくは思っている。
 岡田拓郎 ノスタルジア Hostess Entertainment |
どう来るのかとずっと楽しみにしていたところ、しかしながら彼のソロ・アルバム『ノスタルジア』は、自らの内に燃えるそうしたもの、ある種の熱狂を抑制し、メロウで口当たりのいいポップスとしての体裁を保っている、表向きには……。彼のことだから、考えに考えに考え抜いた結果、いまはこれなのだろう。まあ、コーネリアスが象徴的だったように、はからずともメロウなこの2017年らしい作品となった言えるのかもしれない。
26歳の青年の最初のソロ・アルバム『ノスタルジア』は、あさい夢に浸っているようだ。3曲目の“アモルフェ”のように。そして圧倒的に素晴らしい、7曲目の“手のひらの景色”のように。このアルバムにもっとも似合わないのがデジタル社会で、『ノスタルジア』は、その意味ではまさしくポスト・インターネットであり、楽曲は、かつてあった物思いに耽る時間を取り戻そうとしているかのようである。
せっかくなので、増村和彦も呼んで取材をすることにした。ele-kingのコラムでもお馴染みの偏愛的読書家のこのドラマーは、いうまでもなく岡田の音楽的同盟者である。

もっとフォーマットを置き換えて現代的なものにしたいと思ったんですね。それは日本語のフォーク・ロックとして新しいものにしたい、ということなんですけど。
■今回の作品が出来るのに時間がかかった理由、時間がかかった理由はたくさんあるとは思うんですが、それも今作の内容や方向性に関わるもっとも重要な理由とはなんですか?
岡田:単純に時間がかかった理由としては、森は生きているのときと完全に違うことをする意識のひとつとして、「フォーク」というフォーマットの音楽を新しいものとして落とし込みたかったというのがあります。それは森(は生きている)のときみたいに60、70年代の音楽の文脈はもちろんあるけど、それを全面に出すわけではなくて、もっとフォーマットを置き換えて現代的なものにしたいと思ったんですね。それは日本語のフォーク・ロックとして新しいものにしたい、ということなんですけど。
じゃあ、「新しいものってなんだ?」ってことになると難しい話ですけど、この2年間くらいの音楽の流れがすごく早すぎて、自分のなかで消化した途端に別のものになっているというか。これはUSに限った話かもしれないですけど、ボン・イヴェールを消化したと思ったら、次にフランク・オーシャンがいて、みたいな。いままでの森のときにやっていたのはいつの時代であろうと“自分が作っていた音楽”だったとは思うんですけど、今回はソロになって、90年代に生まれた自分が新しいフォークを作ろうと意識したときに、そこの流れを汲むのが困難な時代に対してどうアプローチしていくのか、というのがすごく難しかったし、時間がかかった大きな理由ですね。だから1ヶ月ごとにアルバムができ上がって、それを増村に送って「いいじゃん」と言われた途端にみんなが新譜をリリースして、そうすると途端に自分のアルバムが良くなく聴こえてきてしまう、だからそれをまた壊して曲をボツにするというのを繰り返していたんですけど、こんな作りかたをしていたらそりゃ2年はかかりますよね(笑)。
(一同笑)
■いまの話を聴くと、まあ2年でよくできたなって話ですけど(笑)。そもそも岡田君がフォーク・ロックをやるというのが面白くて、何故なら岡田拓郎とはアンダーグラウンド・シーンでは名の通ったインプロヴァイザーでもあるんですよね。新世代のね。そうしたラディカルな自分をどのようにポップとバランスを取っているんでしょうか?
岡田:僕のなかですべての音楽の中心になっているのはギターという楽器であって、それこそインプロを好きになったものは、(デレク・)ベイリーを初めに聴いて、高柳昌行とかもいたけど、一番好きなのは秋山徹次さんやローレン・コナーズなんですよね。あとは杉本拓さんのギターを全面に出したメロディックな響きのアルバムがあるんですけど、そういう音楽ってギター特有の牧歌的な音の響きがして、それはフォーク的な音楽に繋がりやすいんですね。そういうものと自分が作っているエクスペリメンタルなフォークというのはそう遠くないものというか、近いものではあるのかなと思いますね。
これは脱線ですが、レニー・トリスターノが49年にリー・コニッツやウォーン・マーシュとかと“Intuition”という、ビートも旋律もない、ちょっとイレギュラーなフリー・インプロヴィゼーションの走りのような曲を録音しているのですが、その後フリー・ジャズが栄えるまで時間が空きます。リー・コニッツがそれについいて「楽理の決め事が無いというのは、とても自由で刺激ではじめの2、3テイクは聴いた事がない音楽が飛び出すけれど、その後は、何回録音しても同じものに聴こえたから、再び和声と旋律のなかでのインプロヴィゼーションに戻った」みたいなことを言っていて。これが、すごく言っている意味がわかるというか、普通のポップスを聴く耳で聴けば、たぶんデレク・ベイリーもアート・リンゼイ、フレッド・フリスもどっちがどっちかなんてわかんないし、たぶんどっちだって良い(笑)。けど、そこにはそれぞれの違いがもちろんあるわけで、そういった観点はポップスを作るときは大切にしたいという意識はあります。「何を聴くか」ということはもちろん大切ですが、「どう聴くか」ということは、また違うことだと思っています。
■増村くんはこのアルバムを最初に聴いたときどう思った? でも、プロセスを知っているからね! いま岡田くんが言ったように、作っては壊してを聴いていたんでしょう?
増村:そうですね。やっぱり時間がかかった理由は単純にそこでしかなくて(笑)。普通はあんまりないですよね。
■率直な感想は?
岡田:はははは。
増村:率直な感想は、よくひとつのかたちにしたな、ですね。個人的にもすごく好きな作品になったんですけど、一番いいと思うのはプロセスで、プロセス自体が作品になっているようなところがある気がしていて。というのも例えばコンセプトとか、なにかを目指してそこに向けて作っていこうということではなくて、プロセスをやっている最中の火花が散る瞬間が格闘している姿自体が音楽や歌詞に反映されているんですよね。
■格闘している……それは一緒に作っていたからわかるんだろうね。
増村:そうですね。でもその瞬間が作品として残って、絶妙なカオスのなかでひとつ均衡を保っているところになんとか作り上げた、という感じがある作品ってけっこう少ないと思うんですよ。(森は生きているの)『グッド・ナイト』なんかもプロセスが大事ではあったんですけど、僕の歌詞なんかはもう見えていたところがあって、それをどうしようかというプロセスだったんですね。『ノスタルジア』はプロセスの最中にスパークしている瞬間がかたちをなしているというか(笑)、そこはおもしろいと思いましたね。
岡田:でも『グッド・ナイト』は俺には見えていなかったから、それは地続きかもしれない(笑)。
増村:地続きかもしれないね(笑)。それで音楽的なところだと、その瞬間瞬間にやりたいことがあると思うんです。だけどそれをまた壊すじゃないですか(笑)。壊して今度はどうするかっていう連続のなかでやっていて、最終的に出来たものにはやっぱりその瞬間瞬間が刻み込まれているというか。そういう感じがいまの時代の現代という意味ではなくて、彼のなかでいましか出来なかった作品じゃないかなという気はしましたね。これは勝手な解釈だけど(笑)。
岡田:ありがとうございます(笑)!
■いまベストなものを作ったと。
増村:そうですね。
■「森は生きているとは違うものをやる」ということを言っていたけど、例えば“手のひらの景色”という曲は、森は生きているとそんなに切れていないと思うんだけど、森は生きているから岡田くんのソロへの流れはどういう感じだったの?バンド活動が終わって、すぐにソロに切り替えられた?
岡田:切り替えられていたし、でも実際は(森は生きているの)3枚目が作りたくてしょうがなかったです。一応『グッド・ナイト』が出てから1年くらいはずっとライヴに回って、5曲くらいは新曲があったんです。“手のひらの景色”はそのなかの1曲で、次のアルバムに入れようとしていた曲だったんですね。イントロはいまのアルバムに入っているかたちで固まっていたんですけど、ただAメロ、Bメロ、歌メロ、歌詞は森のライヴをやっているなかでも2、3回変わっていて、最終的な落としどころが見つからないままバンドが解散しました。3枚目を作りたいという意識がすごくあったなかで、ただ『グッド・ナイト』を作ったはいいけど次にどうすればいいかわからなくなるくらい、作っているあいだの体験が強烈過ぎました。それは僕と増村は一緒だったと思うし、あれができたあとに次になにをするかというのが見つからなかったのがバンドを続けるのが難しかった要員のひとつだったんですよね。どう(笑)?
増村:いや、そうだと思います。
■森は生きているは難しいバンドじゃないですか。
増村:そうですか(笑)?
岡田:そんなことないですよ(笑)。
■自分たちが理想とするものと、現実で自分たちが出しているものとのズレみたいなものに対してすごく意識的だったし、言葉はよくないかもしれないけどあまりにもナイーヴというかね。
増村:まあ、わかります(笑)。
■「これでいいんじゃない?」という落としどころの共有って、森は生きているの場合はとくに難しかったんだろうなぁと。まあ、ふたりのなかでは意思疎通できていたんだろうけど。
岡田:『グッド・ナイト』は僕と増村の密な関係で作ったアルバムだったし、演奏とかみんなのアイデアでアルバムを作ったとはいえ、やっぱりどういう音楽を作るかというよりは、どうしてこの音楽を作ったかというところがポイントでした。明確に目に見えないものをどう捕まえるかという作業を常にしていたんですね。僕と増村で今後あるかどうかわからないくらい削りあった作業だった(笑)……だから作っているうちに、そこが共同体としてやっていくうえでの意識の差みたいなものに出てきてしまったのはありましたね。
増村:だからもう1回やろうとしたときに、そのままだと難しくなるんですよね。もう1回ふたりでなにかをするというには『グッド・ナイト』は一旦やりすぎた。サードを作るんだったらちょっとヘルプが欲しかったところもあるし、6人もいるから誰かが新しい曲を書いたらよかっただけの話だったのかもしれないし(笑)。
■森は生きているは、すごく甘くてメロウな音楽をやっていたんだけど、その音楽の背後には、演奏の技術もそうなんだけど、あと、すごくいろんな音楽を聴き込んでいるなっていう、リスナーとしてのスキルみたいなものもあるでしょ。だから、その両方から思考に思考を重ねながら作っている感じがあって……、本当にもう1枚作ってほしいと思っていたよ。ファンはみんな思っていたと思うよ。
岡田:でもあのバンドを引っ張るのはすごく辛かったし、後期のザ・バンドでロビー・ロバートソンだけみんな悪者扱いで叩くじゃないですか。ロビーの気持ちがすごくよくわかった(笑)。こいつらをどうケツを蹴ればいいんだろうと思って、ひとりでどうにか引っ張るには自分が前に出るしかないから、ライヴで40分くらいギター・ソロを弾いたりしていたんですけど。そんなのやりたくないけど、でもそうしないと引っ張れなかったから、最後は辛くて辛くてしかたなかったですね。
増村:悪循環みたいなものはあったよね。
岡田:だからいろんな要因が混ざり混ざって、やっぱりこのバンドのかたちではできないからいったん解体しなければならないということになったんです。でも案外その切り替えは早くて、最後のツアーのときには、バンドかソロかでは迷ってはいたんですけど、次の録音でやりたいメンバーとやりとりをしていました(笑)。薄情だとは思うんですけど、ツアー最後の広島に向かう車のなかで「来週のリハどうしよう?」みたいな電話を平気でできちゃうタイプではあったんですけどね。実際に制作に入ると、壁があまりにも多すぎて、『ノスタルジア』を作っているときにそういうのを思い返して辛くなってくるみたいなことはありましたね。
■なるほどねえ。
増村:ちょっと思い返しちゃったんだね(笑)。
取材:野田努(2017年11月20日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE