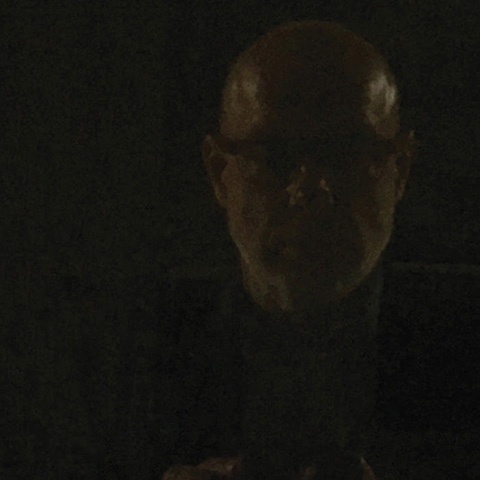MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Tom Rogerson - 穏やかな岸辺、侵された楽器
 Tom Rogerson with Brian Eno Finding Shore Dead Oceans / ホステス |
00年代を代表するバンドのひとつにバトルズがある。彼らが圧倒的だったのは、グライムやダブステップのようなエレクトロニック・ミュージックが大きな衝撃を与えていた時代に、ロックやバンドといったフォーマットが為しうる最大限のことを実践していたからだが、それは彼らより後に来る世代から次々と選択肢を剥奪していく行為でもあった。バトルズ以降に可能なロック・バンドとはいったいどのようなものなのか――そんなポスト・バトルズの時代に一筋の光を差し込ませていたのがスリー・トラップド・タイガーズである。バトルズという存在をしっかりと見定めたうえで、改めてテクノやIDM、ドラムンベースなどからの影響を大胆にロックやバンドの文脈へと落とし込んでいくその様は、当時ひとつの希望として映っていたのではないだろうか。
そのTTTのキイボーディストにしてヴォーカリストでもあったトム・ロジャーソンが、彼らのことを推薦していたブライアン・イーノとアルバムを作っているという情報が流れたのが2016年の早春。かつてのタイヨンダイと同じようにロックやバンドという枠組みから離れた彼が、アンビエントのゴッドファーザーと手を組んだら、いったいどんなサウンドが生み出されるのか――その答えが2017年末にリリースされたこの『Finding Shore』である。
そもそもふたりが初めて出会ったのはトイレだったそうなので、そこから一気にデュシャンまで線を引っ張りたくなるけれど、それより少し前のサティや印象派からそれより後のケイジやライヒまで、このアルバムにはクラシック音楽の大いなる遺産の断片が随所に散りばめられている。基本的にはロジャーソンのルーツたるピアノを大きくフィーチャーした作品と言えるが、ジャズの即興性や電子音楽の音響性、ピアノの打楽器的な側面も当然のように踏まえられており、ドローンやノイズといった手法も惜しみなく導入されている。そこにアンビエントの創始者たるイーノ当人まで関与しているのだから、このアルバムそれ自体がちょっとした音楽史になっているわけだけれど、とはいえ教科書的な堅苦しさとは無縁で、すべてのトラックがポップ・ミュージックとして気楽に聞き流せる作りにもなっている。極私的には2017年のベストな作品のひとつだと思う。
このようにいろんな意味で味わい深い逸品を送り届けてくれたトム・ロジャーソンが、自身の音楽的経歴やイーノとの出会い、ピアノという楽器の持つ可能性や即興の重要性について、大いに語ってくれた。
とにかくトイレの前だった。で、顔を見たらブライアン(・イーノ)だったから、挨拶しちゃおうかな、と思って、したんだ(笑)。そして一緒にレコードを作るに至ったんだから、なかなかすごい展開だよね。
■あなたはロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックでクラシック音楽を学んだそうですが、セルフタイトルの最初のソロ・アルバム(2005年)もトム・チャレンジャーとの共作(2010年)も、ジャズやエレクトロニックな即興音楽だったということで、まずはあなたのなかでのジャズとクラシックの位置付けから教えてもらえますか?
トム・ロジャーソン(Tom Rogerson、以下TR):ああ、まず、僕はそもそもピアノの即興演奏を子供の頃からやっていたんだよ。そこからどう展開したかというと……、本格的にピアノを学ぶようになる前から自己流で弾いていて、そのきっかけは姉がやっていたからで、自宅にピアノがあって両親ともに弾いていたから見様見真似で……という感じだったんだが、10歳か11歳の頃に、自分が即興で弾いたものを書き留めて残しておきたいと思うようになってね。つまりは、自分で曲を作るということに興味が向いていったんだ。当時から20世紀の現代音楽の作曲家をよく聴いていたので、それを真似るようにして作曲らしきことをやり始めたんだ。その後15歳ぐらいになると、僕がピアノの即興をやれるということで、学校の友だちから「ジャズやってみたら? 即興ばっかりやってるから、きみ、きっとジャズいけると思うよ」と勧められた。その友だちとはいまだに付き合いがあるんだけど……とにかく、それがジャズとの出会い……そして、そいつを含めた何人かでジャズのバンドを組んだのが16歳のときだった。大学卒業後にニューヨーク・シティに3年住んで、最初のレコードを作ったのはそのタイミングだった。ただ、――これは強調しておきたいんだけど、いま話に出たふたつのアルバムは大々的にリリースされたわけじゃない。作りはしたものの、変な話、ほとんど公になっていないんだ。だから、僕の最初のレコードはジャズだったと言うと……、いや、ジャズといってもラフな即興演奏でしかなかったんだけど……、でもサックスが入っていたからジャズってことになるのかな(笑)。
■(笑)。
TR:とにかく、CDにはしたものの、今でもその9割は僕の手元に残ってる。自宅に。売る努力もしなかったし。こう言うとなんか変だけど、たぶんビビってたんだと思う。作りはしたものの聴いてもらう勇気がなくて、宣伝したくなかった、みたいな。
■そうだったんですね。
TR:でも、その後にやったバンドは知られてると思う。スリー・トラップト・タイガーズ(Three Trapped Tigers、以下TTT)ていうんだけど。
■はい、もちろん。
TR:あれはレコードが出回っているはずだ。
■ロック・バンドですよね。
TR:うん、ロック・バンド。不思議なインストの……エレクトロニック・ロック・ミュージック、かな。
■友だちに勧められるまでジャズには親しんでいなかった?
TR:ぜんぜん。僕の背景は、そこに至るまで完全にクラシックだった。16歳ぐらいまでは。なのに即興で演奏していたというのがおもしろいところで、もちろん、それがジャズに通じるということも意識していなかったんだけど、いざジャズをやり始めてからの適応力はすごくあったと思う。後にジャズのランゲイジを……アメリカのブルーズを踏まえたジャズのランゲイジを学ぶようになってからも覚えは早かったんじゃないかな。割とスムースにいろんなジャズのバンドでライヴをやる機会に恵まれるようになったよ。ただ、それが自分の母語だと感じたことはなくて、やっぱりアメリカで形成された言葉だな、と。英国やヨーロッパにも独自の素晴らしいジャズ・ミュージックはあるから、そっちのほうが究極的には僕にはピンとくるように思う。ある意味、こんなに時間をかけて……いま、僕は35歳なんだけど、最初から自分がやっていたものに戻ってきたという……、6歳ぐらいからひとりでやっていたこと、あれが僕のやりたいことだったんだと気がついた、というわけさ(笑)。ジャズがやりたいんでも、ロックをやりたいんでもなくて、やりたいことを僕は最初からやっていたんだ、とね。いちばん近いのはキース・ジャレットかな。彼はアメリカの人だけどね。英国人ピアニストならキース・ティペット。ふたりともすごく個性的なピアニストで即興能力が高い。もっとも、僕がやっていることはそのどちらともまた違うんだけどね。ブライアン・イーノとのアルバムではエレクトロニクスを導入しているし……
■とにかく、一巡して自分の居場所を見つけた、という感じのようですね。
TR:そう、そういうこと! だから今回のアルバムは『Finding Shore』というタイトルなんだ。
■なるほどぉ!
TR:家に帰ってきた、という感じ。あちこちを訪ねて、いろんなジャンルの音楽を経験して、どれも最高に楽しかったけど、気がついたら子どもの頃にやっていた音楽の岸辺にまた辿り着いていた。
■おもしろいですね。ジャズの岸辺で最初に聴いたのはどんなアーティストでしたか?
TR:友だちから聴かされたのはアート・ブレイキーの『Moanin'』だったと思う。あれは……50年代か60年代か〔註:1958年録音〕……〈ブルーノート〉の名作アルバムのひとつだよね。僕らのバンドが覚えた最初の曲もそれだったんだ。他にも〈ブルーノート〉の作品に一時期かなり入れ込んで、ホレス・シルヴァーとか、デューク・エリントンとか……デューク・エリントンの〈ブルーノート〉のアルバムで、えぇと……なんてタイトルだったかな、「マネー・ジャングル」とか、そんな名前のやつ〔註:『Money Jungle』は1963年に〈ユナイテッド・アーティスツ〉からリリースされたアルバム〕。そこから始まって放射線状に広がってマイルス・デイヴィス、チャーリー・ミンガス、コルトレーンなどなどをひと通り。ニューヨーク・シティで暮らすようになったのは2003年なんだけど、その頃にはジャズにもそうとう詳しくなっていたつもりだ。というわけで、最初に自分で演奏してみたのはハードバップの名曲で、あれはいまプレイしてもものすごく楽しいし、聴くのも楽しい。
■最初からそう思いました?
TR:思ったよ。
■お友だちはきっと、ピアノで即興がやれる仲間がなかなか見つからなくて苦労していたんじゃ(笑)?
TR:そうだろうね。何しろ小さな町だし、彼も最初はロックが好きでレッド・ゼップリンなんかをカヴァーしてたんだけど、そこからジャズに目覚めたルークは……そいつ、ルークっていうんだけど、ものすごく熱い男で、ドラマーで、じつはいまでもロンドンでバンドをやってるし、あいつにはジョアンナって姉妹がいて彼女はいまアメリカでシンガーとして活動してる。当時からずっと一緒に音楽の旅をしてきた地元の仲間が生き残って続けているんだから、不思議なものだよ。とはいえ、あの頃やっていたこととはだいぶかけ離れている。あの経験で僕は新たな音楽のランゲイジを身につけることができて、クラシック一辺倒だった僕の世界が広がったのは間違いないけど……、こんな言い方は変に聞こえるだろうけど、ピアノと本気で向き合ったのは21歳くらいになってから、なんだ。
■へえ……
TR:ずっと弾いていたけど、さっきも言ったように10代の頃からコンポーザー志向で、しかもクラシックの……現代音楽のコンポーザーを目指していたから、ピアノというのは……とくにジャズをやっている間は趣味というか、弾いていて楽しいだけのもの、という存在だった。ライヴをやる、そして人前で即興をやる。それまでは即興といってもひとりでやって楽しんでいただけなのが、ライヴで人前でやることで評価を得たというか、自分にはそういう能力があるんだって実感できたんだ。つまり、ジャズが僕に与えてくれたのは、ライヴにおける自信、あとは鍛錬……とくにニューヨークに行ってからは周りにビックリするほど才能のある若い子がいっぱいいて、競争がハンパなく厳しかったから、そのなかでなんとか生き延びていこう、自分を評価してもらおう、と技術もだけど個性も磨いていけたのはとても自分のためになったと思う。感謝してるよ。その後、ジャズは諦めてしまうんだけどね。最初のジャズのレコードを作った後で、22歳の頃、ジャズには見切りをつけたんだ。

あちこち旅して回って最後には出発した場所に戻っていくという感じを出したかったのかもしれない。ぐるっと長い環状線を歩いて、出発点に戻ってきたときに、最初とはまったく違う新しい視点で同じ場所を眺められるようになっている……、旅をしてきたおかげで、ね。
■そこでTTTが始まるんですか?
TR:ニューヨークからロンドンに戻って、その頃にはもう、ジャズは音的に僕の求めるものじゃないと考えるようになって、聴くのも英国のエレクトロニック・ミュージックが多くなっていた。ロックも一部聴いてはいたけど、ほとんど電子音楽だったな。ロンドンに帰ってまず旧交を温めたのが昔からの音楽仲間で、そいつらがいたインディーズのシーンの連中と知り合って僕もバンドでピアノやキイボードを弾いたり、一時期は一緒に暮らしたりもしていたんだ。そのときのルームメイトが僕を入れて4人で、ミュージシャンが3人とレコード会社に勤めてるやつが1人。だからもう、毎晩のようにどこかで誰かの関連するライヴがあって、出かけて行っては出演したり観覧したり……それがすごく楽しくてね。バンドでやる楽しさも味わったし、お客さんも若いから一緒に楽しめる雰囲気が僕には新鮮だった。ほら、ずっとクラシックとジャズをやってたから、どうしてもお客さんは年齢層が高い上に、ごく限られた層の人しか来ない、ある意味エリート主義なところがある……って、これも後から客観的に気づいたことなんだけど、とにかく僕らがわりと実験的な即興を入れた風変わりで複雑なロックをやっても300人くらい入る会場が若いお客さんでソールドアウトになる様子を見ているうちに、こういうのもありなんだと自信を深めていったんだ。ジャズもクラシックも演奏の場はあるけれど、それほど波及力があるようには思えなかった。個人的な音楽の嗜好もどんどんロック寄り、電子音楽寄りになっていた時期なので、じゃあ自分でもバンドをやってみようか、と。発想としては、ライヴでやる電子音楽。エイフェックス・トゥイン、オウテカ辺りを僕は最初アメリカで耳にして、「こういうのをライヴでやったらカッコいいだろうな」と思っていたんだ。そういえば、アメリカのクラシックのグループ〔註:アラーム・ウィル・サウンドか〕がエイフェックス・トゥインのアルバムを丸ごとライヴでやったんだよな。あれは素晴らしかった。ただ僕の考えでは、それを踏まえて即興を展開するというもので、たとえばドラムもただ機械的に叩くんじゃなくて即興で対応してほしかった。となると、ものすごく難しい仕事だよね。ありがたいことに、アダム・ベッツ〔註:TTTのドラマー〕という適任者と出会うことができて、始動したのが2005年……2006年だったかな。その前に僕はギタリストのマット(・カルヴァート)〔註:TTTのギタリスト〕とふたりで完全フリー即興のライヴをやっていたから、そこからの発展形としてすべてが整ったのが2007年。そしてTTTを名乗って最初のアルバムを出したのが2009年……いや、2008年か。音楽仲間と暮らしていて、そこにレコード会社の人間もいたから人脈は豊富だった。結局、僕らのためにレーベルをスタートするという友だちと組んだんだけど、知り合いが多かったからあっという間に注目が集まった。その時点で僕らがやっていた音楽って、かなり変わってたと思う。バトルズが解散した直後で……バトルズって覚えてるかな、ライヴ電子音楽をやっていたバンドで……
■はい。彼らの『Mirrored』が出てから10年になりますね〔注:この取材は昨年おこなわれた〕。
TR:ああ、10年前か。だからまあ、ああいうライヴでやる実験的な電子音楽がおもしろかった時期ではあって、ワクワク感があったんだ。僕らのバンドもエネルギー満載、怒りあり、ユーモアあり……僕は25歳くらいで、(TTTは)人生のあの時期にやるのにふさわしいバンドだったんだと思う。じっさい、僕もいろいろと腹の立つことがあって(笑)、エネルギーを持て余していたから(笑)。ピアノで美しい叙情的な演奏ばかりしている気分じゃなかったんだろう。ツアーらしきこともやって、ほんとうに楽しかった。10年の間にソフトウェアが様変わりして、いまや電子音楽をライヴでやるなんてごく当たり前のことになっているから、若い人はピンとこない話かもしれないけどね。いまはどこへ行ってもそういうライヴを観られるし。次から次へと、みんなが便乗してきてさ。TTTのドラマーはいま、ゴールディとスクエアプッシャーのドラマーをやってるよ〔註:つまりショバリーダー・ワンのドラマー、カンパニー・レイザーの正体はアダム・ベッツだったということ〕。
■へえ。
TR:あいつ、あのスタイルのドラミングの世界的なエキスパートになって、当初の僕らが必死になって真似しようとしてたバンドでプレイしているという……
■(笑)。
TR:でも、 僕も喜んでる。そもそもうまいやつだったけど、あのバンドでの経験がなかったら、いまの活躍はなかったと思うんで、見ていてワクワクするよ。現状、あの分野のパイオニアとしてのしかるべき評価をあいつはまだ得ていないと思う。そのうちそうなるだろうけどね。理由はさておき、あいつより有名になっているドラマーは他にいるけどさ。あいつのソロ作にも、完全にイッちゃってるすごいのがあるから、ぜひチェックしてみてよ。TTTと同じレーベルから出てるから〔註:『Colossal Squid』〕。あいつもいつか日本で活動できるといいんだけど。
質問・文:小林拓音(2018年2月28日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE