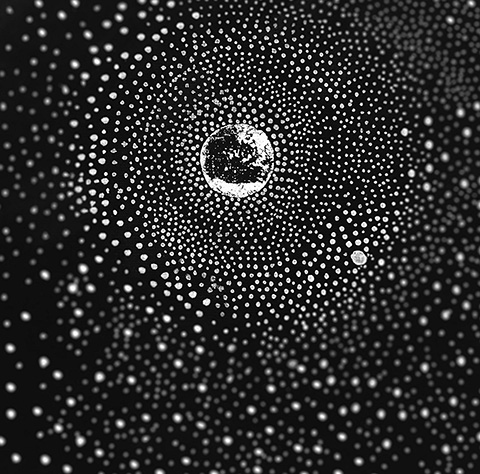MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Gonno & Masumura - テクノ、アフロ、そして喋るリズムとは?
ゴンノさんの音源だと、はまるんですよね。リズムがはめやすいというか。バンドだと、先にドラムを録って他の楽器を重ねたら、最初にドラムを叩いた意思と全然違う形ででき上がることがけっこう多いですが、ふたりということもあるし、ゴンノさんのトラックの柔らかさみたいなものがあるので、叩いているときの感じでできてくれるというか。それが嬉しかったです。逆に言うとミスもはっきり出るんですけどね(笑)。──Masumura
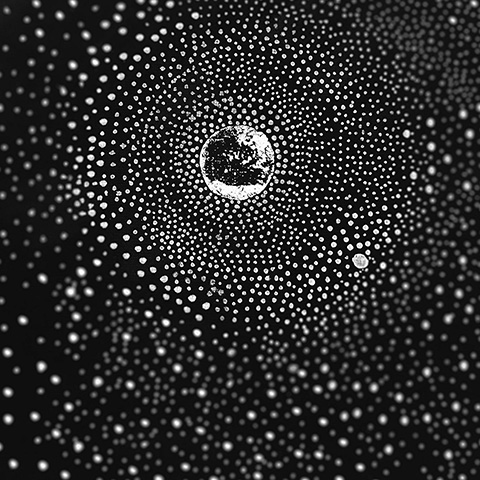 Gonno & Masumura In Circles Pヴァイン |
■このプロジェクトですごく重要だなと思うのは、科学反応みたいな音楽的な面白さももちろんあるんですけど、ひとつのジャンルを超越する面白さというか、増村くんはインディ・ロック出身ですからね。増村くんが〈ベルグハイン〉で踊っている姿なんて想像できないじゃん(笑)。
一同:(笑)。
G:そうですね。
M:〈ベルグハイン〉ってなんすかってかんじですからね(笑)。
G:ベルリンにある、世界でもっとも面白いと言われているクラブがあって。ふたつのフロアがあって、パノラマバーというハウスのフロアがあるんですけど、僕はそこでよくDJしたりしますよ。
M:そうなんですか! 全然踊りますよ(笑)。
G:いわゆるゲイ・クラブ。
M:まじすか!
G:すごく良いですよ。けっこう価値観が変わります。こんな自由な場所があるんだって。
M:そうなんや。
■ゴンノくんからすると、やっぱ現状のクラブ・ミュージックの型にはまった感じを破りたかった?
G:ハウスやテクノは、やっぱり、4つ打っていないと踊らない。4拍子じゃないと踊らないというのが沁みついちゃっているんですよね。なので、その規則性からなかなかはみ出せない。いろんなテクノとかハウスのアーティストがアルバムを出していますけど、どうしてもそこからはみ出せられない。そのフォーマットのなかで何かするしかないみたいな。4つ打っている、4バイ4のキックって強力じゃないですか。レゲエの裏を取るのと一緒で、もうこれ以上ないという引き算だと思います。そこから発展させていくのはなかなか難しいんでしょうね。
M:僕が逆に意識したことは、クラブの4つ打ち的なところを外さないようにすることです。7拍子の曲とか、7をふたつに割って2拍7連にして。そうしたら均一にベードラがくるんですよ。もしくは2小節またいで14拍あるので、ドッ、ドッってやっていったら……。
■2拍7連って難しいね。
M:難しいですが、聴いている方はベードラが均等にきていれば絶対踊ってくれると思うので、それを7拍子の曲で意識したというか。5拍子の曲でもやっています。2拍5連とか2小節10拍で5発ベードラを打つ。その辺を意識しましたね。
G:途中で4つ打っているふうに聴こえるんですけど、気が付いたらまた7拍子に戻っているみたいなところがだまし絵みたいな感じで入ってます。
M:ちょっとそういうところはありますね。規則性みたいなものからはみ出ないというルールは変拍子のなかでも作っていたんですよね、一応。
G:ただ、聴感上は4拍子みたいに聴こえる。こんなトリック明かしちゃっていいんですか?
M:いいんじゃないですか(笑)?
■リズムを楽しむというのは、このアルバムの重要なところ。リズムだけでも面白いんだっていうところがあると思いますよ。
M:アフロビートだって、いっぱいそういうことをやっているんですよ。でも、なかなか分析している人は少なくて。それをわかりやすい形でドラムに置き換えて叩いたというところはあります。そういう意味ではわかりやすく楽しんでもらえるかもしないですね。
G:僕も増村くんに言われるまでわからなかったです。例えば、エルメート・パスコアールの曲でじつはこれ、7拍子なんだみたいなのを教えてもらったりして。
M:それくらい気持ちよく7拍子で来ていて。
G:シェイカーが7拍子で振られているというのが。
M:「オーガニック変拍子」と僕は呼んでいるんですけどね。
■なんでオーガニックなの?
M:オーガニックというか、ポスト・ロックとかプログレじゃない……
■ようするに数学(マス)的じゃないと?
G:あんまりロジカルじゃない、身体感覚で鳴らされているような。
M:その身体感覚というのがすごく良くできているんですよね。現地の人は……現地っていうのは変ですけど、だってここに来てないと踊れないじゃんみたいな、当たり前の感覚があるみたい。その身体感覚を元にやっているから。その辺が民族音楽からいちばん学べるところなので、そこをちょっとドラムに置き換えて、あとは機械に置き換えて。そういう楽しさはやっていてありました。
G:増村くんから聞きましたけど、南米の人とか逆に4拍子で取るりも…
M:6/8拍子しか取れない人もいるみたいです。
G:普通に欧米のいわゆるポップスの世代とかは4拍子が当たり前で、4拍子から外れるとどうしても、ちょっとエクスペリメンタルという発想になってきちゃうけど、逆に4拍子が普通じゃないという世界もあるということを知れて良かったです。
M:もしかしたら、人口分布とか面積だったら、6/8拍子系の国の方が多いかもしれないですよね。アメリカと日本くらいかもしれないですよ、4拍子が主流すぎるのなんて。
G:あとヨーロッパですかね。
M:ヨーロッパも6/8拍子系は多いみたいですね。
■ジャズも多いもんね。
M:ジャズこそ6/8拍子の応酬というか、わりと世界的には当たり前な話。けど、いずれにせよ、何を取るにせよ、日本人の僕たちは自覚的になって、ちょっと研究者的な視点も入って、それを元に作品にしたという楽しみ方でもあるし、そうやるしかないというか。
■これをジャズとは呼ばないけれど、ジャズ的な要素があるなと思ったんですよ。それは何かというと、ジャズって演奏者の個性によって作品が作られていくし、やっぱり、同じ曲でも演奏者によって違う。例えば、クラフトワークやコーネリアスっていうのは誰がやってもクラフトワークになるし、コーネリアスになると思うんだよね。でもジャズ的なものって演者によって違うものになるじゃない。そういう意味でいうとジャズ寄りであると思うんだけど、演奏するパートナーとしてお互いのバックグラウンドがぜんぜん違うじゃない。
G:ジャズを即興と解釈するなら、今回あとあと上音をたくさん足してるけど、実際のベーシックな録音は2日間しかなかったので、基本的にはインプロ具合というか、ジャム具合がそのままパッケージングされている感じです。
M:けっこうふたりの良いヴァイブスが出たかなと。それこそ化学反応みたいなことを書いてくれている人がいましたけれどね。
G:そういう反響は多かったですね。ロラン・ガルニエもラジオでジャズとテクノのハイブリットだって紹介していましたね。
https://worldwidefm.net/show/it-is-what-it-is-laurent-garnier-6-2/
■増村くんはスティーヴ・リードが頭にあったわけでしょ?
M:スティーヴ・リードとフォー・テットのあれは頭にありました。けどトニー・アレンとロイ・ブルックスとマイケル・シュリーヴと、ほんのちょっとだけビル・ブラッフォードを入れれば自然とオリジナリティが出るなと思って(笑)。というか、僕が一生懸命研究してきたことを、キーラン・ヘブデン×スティーヴ・リードを参考にしながらやればオリジナリティが出るなと思ったので、きっかけをくれたのがスティーヴ・リードかなという感じです。スティーヴ・リードでは、あんなおじいちゃんになってもばりばりスティーヴ・リードの音がしているんです。スティーヴ・リードの何が好きかって、パッションだったんで。ビートとかというより、あんな独特な4ビート、すごい熱量のある4ビートをやるから。喋るドラマーという言い方は変ですけど。あんなにドラムで精神性を発揮できるのかっていう。
■タイムキープのためのメトロノーム的な役目をするドラマーと表現するドラマーってやっぱり……
M:表現するドラマーが少なくともいるじゃないですか。その最たるのが、やっぱりスティーヴ・リードとロイ・ブルックスで。ゴンノさんとやるにあたって、僕もタイムキープもするけど、ちょっと喋ってもいいのかなと思いました。それは良いところに最後落とし込んでくれたのかなという感じですけどね。
G:喋るドラムっていいですね。
■めちゃくちゃ喋っていたじゃん(笑)。俺がちょうどスタジオ行ったとき……
M:オラついてましたね(笑)。ポップスとかでオラついちゃうと、けっこう聴けないってなっちゃうんで。
■やかましいよって(笑)。
M:そういう意味で、最初にも言ったけどすごい自由にやらせてもらったから気楽でした。何をやってもゴンノさんが受け止めてくれるという感じがあったから、やりやすかったですね。
■あのときのゴンノくんは様子を見ていると、増村くんをいかに本気にさせるかみたいな。
G:そうだったかな(笑)。
■スタジオのなかの指揮者みたいな感じ。
M:指揮者をやってくれていましたね。
G:リズムのタイムが狂っているとかそういうところよりも、ドラムのサウンドがどういうふうに鳴っているか、単純にスネアドラムはどんな音が鳴っているかとか。そういう音をずっと聴きながらやっていました。
M:もうミックスがはじまっていた感じですね。
G:そうですね。
M:すげぇ……。
G::リズムマシンと違って、生ドラムは叩き方の強弱で音自体が変わるじゃないですか。なので、これくらいの強さで叩いてくれていた方が増村くんのドラムが録れるだろうなということを、僕が煽っていたくらいですね。あとは何もしていないです。
■最後は全部ゴンノくんがまとめたんだよね?
G:そうです。ミックスまで。マスタリングは風間萌さんというスタジオATLIOの方が。
■ミキシングを自分のなかのどこで終わらせるか、という境界線みたいなものはどういうふうに考えたの?
G:毎度のことなんですけど、締め切り当日1時間前までずっと触り続けます。毎回そうなんですけどね。ここで終わりというのはないですね。ただ、生ドラムのマイクをたくさん立てて、生ドラムをミックスするということは今回が初めてだったんですよ。それは本当に面白かったですね。ステレオマイクの音量がどれくらいだとか。そこはけっこう増村くんにアドヴァイスをもらいました。
M:アドヴァイスというか、僕はミックスをやったことがないのであれなんですけど、スネアがもうちょっと大きくなって、ハットが小さくなった方が……とか。
G:この曲はハットがもっと小さい方がいいとか。
M:そういうのは伝えていました。
G:僕が迷ったときはけっこうラフ・ミックスを送ってという感じでやりました。
■空気が振動する感じがちゃんと録音されているところがすごいよね。
G:それはエンジニアの葛西(敏彦)さんの成せる業ですね。
M:葛西さんっていまでは生楽器の音を録るには天下一品みたいな人なんですけど、テクノ出身で、元々地元でテクノのイベントのオーガナイザーとかやっていて。野田さんの本とかも読んでて。
■コニー・プランク(の役目の人)がいたんだ!
M:完全に生のこともテクノのことも知っている人だから、葛西さんしかいないだろうって。
G:共通言語がすごく多くて良かったですね。
■それでこの短期間でここまでのクォリティーのものができたんだ。
M:録音は葛西さんのおかげですね。
G:ドラムをミックスするというところがいちばん難しかったので、だいぶ助けて頂きました。やっぱりいままで自分が触っていた909のキックだったり808のキックだったりというのが、いかに……、良い言い方をすると、効率良く快楽的な音が簡単に出ていたものなんだなとすごく痛感しました。
M:気持ちいいですよね。かつてはリンドラムやなんかの。普通に気持ちいいですもんね。ドラムなんて気持ち良い音を出すには、相当ミュートして、チューニングしてとか。
G:リズムマシン単体も規則性はあるんですけど、音の揺れというのがやっぱりあるので。んですけど、さっき言っていた、歌っているドラムとか喋っているドラムというのは生ドラムにはやっぱりかなわないですよね。ドラムマシンは0.01秒後にこういう音を入れようということが、予めプログラムしないとできないじゃないですか。融通が利かないんです。そこを生ドラムでやってもらうというのが、いちばん難しくもあり同時にスリリングで面白かったところですね。
取材:野田努(2018年5月09日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE