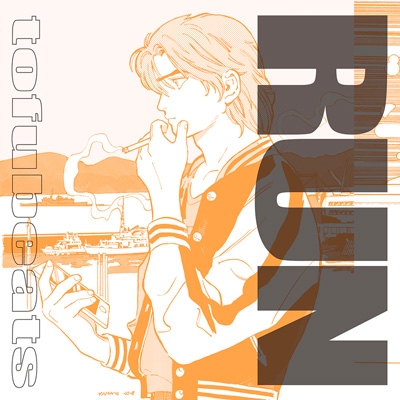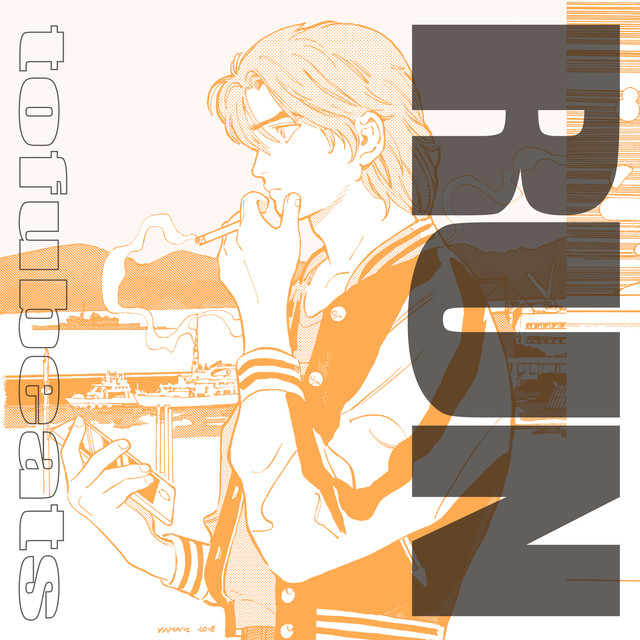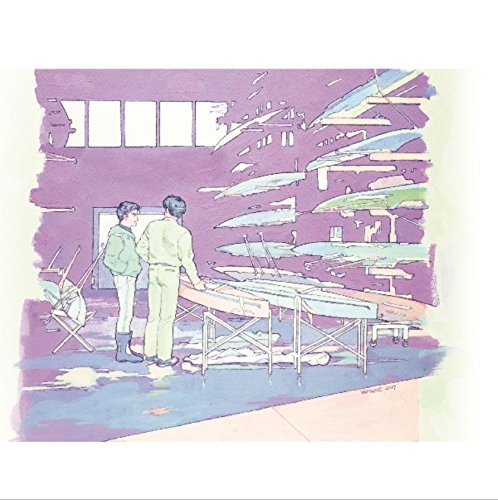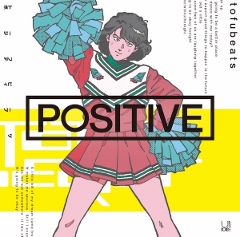MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with tofubeats - 走る・走る・走る
トーフビーツ、この男は本当に走り続けている。2009年の“しらきや”で笑わせ、2012年の“水星”ではヒップホップ・ビートのうえに切ない夢を描いた若者は、それからほぼ毎年のように作品を作っては出している。思春期にSNS文化に親しんだほとんど最初のほうの世代のひとりとして、シンプルなメロディを持った彼の音楽(主にヒップホップとハウスかる成るダンス・ミュージック)にはネット・レーベルの古参〈Maltine〉と同じように、非日常ではなく、日々の営みのなかにこそインターネットが存在する世代への感覚的なアピールがあったのだろうけれど、それと同時に、トーフビーツの汗をかいている感じ、自分の人生を一生懸命に生きている姿にも共感があったのだと思う。がむしゃらさは、彼の切ない夢の音楽と並列して、つねにある。この実直な思い、熱さこそ、大人たちから失われてしまいがちなものだ。トーフビーツの音楽を聴いていると、ぼくも走りたくなる(自転車だけど)。
“朝が来るまで終わる事の無いダンスを”が特定秘密保護法への学生による抗議デモで使われたときには、自分の曲を政治に利用しないで欲しいと眉をひそめていた青年も、前作『FANTASY CLUB』では、それまでのスタンスをひっくり返したように、ありありと社会への異議申し立て(ことポスト・トゥルースに関して)を噴出させたのだった。新作『RUN』は、その問題作に続くアルバムだ。1曲目の、タフなビートを持つトラップ調の“RUN”には、閉塞状況をなんとかしようという思いに駆られた歌詞のように、力の入った彼のヴォーカルが挿入されている。
とはいえ今作『RUN』は、トーフビーツのポップスへのアプローチがより洗練された形となって聴けるアルバムでもある。『FANTASY CLUB』で見せた彼の社会への問題意識は継続させつつも、映画(『寝ても覚めても』)やドラマ(『電影少女』)の主題歌となった彼のポップ路線が、決して明るくはない主題のいくつかの曲──愛の不在を嘆く“SOMETIMES”、孤独が強調される“Dead Wax”など──とのバランスをなんとかうまく取っている。
まあ、それでも物憂いは今作でも重要な要素で、しかもそれは魅力的であったりもする。“NEWTOWN”という曲は21世紀の洒落たベッドルーム・ガラージであり、みごとなモダン・メランコリック・ハウスだ。ぜひチェックして欲しい。クラブの熱狂におけるふとした不安を歌った“MOONLIGHT”も良い。ある意味トーフビーツの現在のアンヴィバレンスな心情がそのまま反映されているようなこの曲は、いわば80年代末スタイルのポップ・ハウス、その現代版といった感じで、ほかにも今作には、彼の現場(DJ)からのフィードバックによるものなのだろう、ハウシーなトラックがいくつかある。『RUN』という動きを示唆するタイトルとも、これらダンス・ミュージックはリンクしているのだろう。動き続けること、それ自体が大きなメッセージのように思える。
そんなわけで、神戸を拠点に走り続ける男=トーフビーツに会ってきた。いつものようにいまの思いを率直に語ってくれた。

『FANTASY CLUB』は、仲の良い人にはすごく評価してもらえたり、近しい人とかでわりとセルアウトしたと思っている人には、意外と真面目にやっていたんだみたいな(笑)。そういう近しい人で離れていった人がちょっと戻ってきたみたいな意味ではすごく効果があったアルバムでした(笑)。
■ちょうど『FANTASY CLUB』から1年?
tofubeats(以下、TB):1年ちょいですね。
■すごくコンスタントに作ってはいるけれど、自分で歌う楽曲を全面に打ち出すようになってからは2枚目とも言えるような(笑)。
TB:そうですね(笑)。第3期くらい。
■第3期トーフビーツ(笑)。
TB:今回こんなに自分が歌う予定はなかったんですよ。毎回そうなんですけど。『FANTASY CLUB』もあんなに歌うつもりじゃなかったんですよ。今回もこんなに歌うつもりではなかったのに、ここまで来てしまったみたいな。たとえば今回も最初はドラマのタイアップで作った"ふめつのこころ"という乃木坂46の子が歌うヴァージョンのためにほぼ当て書きした曲なんで、自分が歌うやつは暫定的というか、一応作るし出すけど、ピークはそこだよなと思って作っていたんです。けど、そのヴァージョンは出せなくなっちゃって(結局自分が歌ったものが収録されている)。映画の主題歌も書いている時点では人に歌ってもらうつもりで書いたんですよ。
■そういえば、『FANTASY CLUB』のリアクションはどうだったの?
TB:まぁ良いリアクションが帰ってきたとは思いますが、ちょっと不足している気持ちもあるというか……。
■どこが?
TB:いわゆる仲の良い人にはすごく評価してもらえたり、近しい人とかでわりとセルアウトしたと思っている人には、意外と真面目にやっていたんだみたいな(笑)。そういう近しい人で離れていった人がちょっと戻ってきたみたいな意味ではすごく効果があったアルバムでした(笑)。俺はずっと真面目にやっていたつもりなんですけど(笑)。ある意味あんまり良くない方の偏見が取れたというのはすごく嬉しかったんですけど、一方で、思ったよりもエンドユーザーというか、いわゆる普通のリスナーに届かなかったなと。例えばele-kingとかじゃない普通の雑誌のレヴュー欄とかそういうところで全然取り上げられなかったなみたいな。それこそ年末のベスト・アルバムみたいなやつとかでも、全然取り上げられなかったなぁっていうのはちょっとありましたね。
■それは悔しい?
TB:悔しいっす。あと、海外版もピッチフォークであんなに評価してくれたのに、出すのに1年かかって、バッて広がっているときに全然アクションが起こせなかったというのもガッカリ。作品としてはけっこう切り替わったタイミングでイメージを発信できたのに、そこらへんで手をこまねいてしまったというのが反省としてあります。
■『FANTASY CLUB』は、聴きどころはたくさんあるんだけど、ある意味では真面目で重たいアルバムという側面もあったからね。
TB:そうなんですよ。ファンぽい人にはこれまででいちばんうけたんですよ。それはすごく嬉しかったですね。これまで応援してくれた人にはうけたと思うんで。
■そのファンぽい人たちというのは、同じ時代感覚を共有しているというか、世代的にもすごく近い人たちということ?
TB:そうですね。
■それはトーフビーツが抱えているような問題意識、インターネット、デジタル時代以降が抱える可能性と、負の部分もひっくるめて。
TB:あとぼくがちょっとだけひそかな期待を抱いていて、世代が一緒で音楽ジャンルが違う人に刺さらんかなと思っていたんですけど、全然そんなことはなかったので、そこは残念かな。
■それはなんでだと思う?
TB:やっぱりクラブ・ミュージックだからじゃないですか(笑)。
■クラブ・ミュージックだからなの?
TB:自分で言うのもあれなんですけど、これ(『FANTASY CLUB』)以前にこういう問題意識を打ち出したアルバムは日本では出ていなかったと思うんですよ。別に自分のことをクラブ・ミュージックのオーソリティとは思わないですけど、いわゆるバンドの人とかほかの若手ミュージシャンとかいろんなミュージシャンがいまめっちゃいるじゃないですか。前回のインタヴューで「次は政治的になるぞ」みたいなことを野田さんが言っていましたけど、多少そういうものを孕んだものってけっこうみんな忌避しているじゃないですか。やらないところで、こういうのをやってみたみたいなことは、自分のなかでは一個前に何かを進めようとした行為だったんで、そういうことに対するリアクションは、思ったより、ミュージシャンサイドからこなかったな。なんかガッカリではないですけど、多少残念やったなみたいなのはあるというか。
「政治的になりたくない!」ってあのときも言っていましたけど、ただならざるをえないみたいな情勢というか、普通にこんな悪いニュースとかが入ってくる生活をしていて、それに対してなんも思わないほうがおかしいみたいなそういうことはこのときくらいから思いはじめました。そういうことを音楽とかを作っている人は思っていないんかな? みたいな。それで思ってないんや……と思って。『FANTASY CLUB』が出て1年経って、言い方が悪いですけど、相変わらずのんきって言ったらあれですけど、そこはそんなに別か? みたいな。音楽を作るってけっこう反映していないと。
■海外は多いけどね。そんなのばっかりとも言えるというか。
TB:そうなんですよね。そこもそれはそれでちょっと、俺はそこまではやらないで良いっていうか。
■OPNほどやらなくて良いと(笑)?
TB:そうそうそう(笑)。あとはそこを評価できるところはほんとにムズイ。日本においては、そことの距離感みたいなことはけっこう美学というか。美学というのもなんか綺麗な言葉ですけどね。そこを逆に言い過ぎることによって伝わらなかったりすると言ったほうがいいですかね。そういうことをある意味抽象的なやり方で、例えばこの(『FANTASY CLUB』)ときのインタヴューでも政治的なことは言いたくないということへの批判とかもあったんですよね。でも政治的なことは言いたくないと言うことはめっちゃ政治的じゃないですか。なんか難しいですけど。そういうことやのになぁとか思いながら、いまいち難しいというか。だからこれ(『FANTASY CLUB』)はこれで別枠として、このアルバム(『RUN』)はもうちょっと宣伝を頑張りたいなと思いますけどね(笑)!
■そうだね(笑)。
TB:こうして『RUN』も出ましたけど、契約のこととかもあって大急ぎで出たということもあって、『FANTASY CLUB』はもうちょっと長いこと宣伝しても良かったのかなとはいまでも思います。リミックス盤とかも出ましたけど。という感じですね。
取材:野田努(2018年9月28日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE