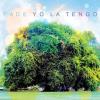MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Yo La Tengo - ヨ・ラ・テンゴ来日直前インタヴュー
ストリートで行進している人びと、落胆している人びと、怯えている人びと。美しい風景とは真逆なんだ。
暴動が起きている。静かに。それはあのチャイルディッシュな元実業家がいちばん「偉い」立場に座っているアメリカ合衆国はもちろんのこと、ここ日本でも、どこであろうとそういえるだろう。しかしその暴動は主に、例えばワッツ暴動や西成暴動のように怒号や流血を伴ったものではない(そういった暴動ももちろん起こるであろうことを否定しているわけではない)。おそらくいま起こっているそれは主に、内面における暴動である。
我々はいま、どのような形にせよ、後期資本主義体制下における効率主義と各種マネージメント思想の跋扈により心身の疲弊に絶え間なく晒され、(俗流の理解では最後の聖域とされてきた)「内面」までもが徐々にその戦いの場に供出させられるようになっている。しかも明確に指弾できる誰かにそうさせられているわけでなく、主には我々自らがすすんで、だ。「やり甲斐」は労働の場における新たな付与価値となり、それが収奪されることで個々の内面は切り崩されていく。また、「思想」は分類され、マーケティングされ、その結果として再び商品化(特定の“クラスタ”向けに調味)され外から内面へとやってきて、思想の顔をして内面を牛耳る、といったように。
こうした趨勢を好ましいと思う人はあまりいないと思うが、悔しいことに、こうした趨勢には火炎瓶の投擲では対抗することが難しい。なぜなら倒すべき「敵」が内面化してしまっているから。
1971年、躍動する肉体を鼓舞するようなそれまでのロック調ファンクをかなぐり捨て、スライ&ファミリー・ストーンとその首領スライ・ストーンが、『There's A Riot Going On』(邦題:『暴動』)というタイトルの暗く内省的な作品で愛と平和の時代の終焉をあぶり出したことと、ヨ・ラ・テンゴという尊敬を集めるベテラン・オルタナティヴ・ロック・バンドが同名のタイトルを据えたアルバムをこの2018年にリリースをしたということに、何かロマンチックな関連性を見出さないでいられる音楽ファンはいないだろう。事実、以下のジェイムズ・マクニューに対するインタヴューでは明言が避けられているにせよ、その関連は認められているし、別のインタヴューで彼らは「なぜこのタイトルにしたかは皆それぞれに考えてほしい」とも言っている。
おそらく本作はバンド史上もっとも儚げで、しとしととした、そして類まれに美しいアルバムだ。最大のアイドルであるヴェルヴェット・アンダーグラウンド由来のギター・ロックを基軸に、ディープなリスナーとしてつねに様々な音楽を吸収し、茫漠としたサイケデリック風景を呼び込むグルーミーな音像、そして極めてメロウな旋律と詩情が融合した世界を作り続けてきた彼らは、世界中に熱心なファンをたくさん生んできた。つねに身近な題材や内面を描いてきた彼らは、もしかするといま、各種のせめぎ合いの場が我々の内面にまで伸長していることを、敏感に察知しているのかもしれない。美しい音楽へと耽溺し、エスケープすることは誰にも止める権利はないし、ときにそうすべきときもあるだろう。けれど、エスケープする先たる我々の内面そのものが何者かによって(それにも増して我々自身によって)侵食/破壊されているのだとしたら。その侵食の脅威にハッと気づかせてくれ、我々を立ち上がらせるのは、このように美しく鎮かなヨ・ラ・テンゴの音楽こそが得意とするところなのかもしれないし、内面で起こりつつある「暴動」を静かに焚き付けてくれるのかもしれない。
その真摯さゆえなのだろう、相変わらず質問をはぐらかそうとしているように見えるジェイムズ(ライターとしては困ってしまうが、ファンとしては妙に嬉しくもある……)だが、要するに彼はこう言いたいのではないか。「全ては君の解釈さ。解釈するその内面の自由を大事に」
すべての解釈をいたずらに肯定するのではなく、解釈が成り立つ場として、我々の内面を慈しむこと。来る3年ぶりの来日ツアーで、彼らがいまどんな演奏を我々の内面に届けてくれるか、とても楽しみだ。
※ 以下の電話インタヴューは、アルバム発売時におこなわれたものです。
音楽学校に行ったり、ミュージシャンになるためにプロからの教育を受けなくても、経験でそれができるようになったのはすごくありがたいことだったし、良い気分だった。
■最新作『There's A Riot Going On』は、みなさんのこれまでのディスコグラフィーのなかでももっとも美しい作品の一枚だと思いました。今作のオフィシャル・インタヴューで、アルバムがリリースされるまでの「待つ時期」は辛い、とおっしゃっていましたが、それから開放されて、いまどんな心持ちでしょうか?
ジェイムズ・マクニュー(James McNew、以下JM):ははは(笑)。でき上がってからリリースされるまでの期間は、なんとも言えない時間なんだ。皆が聴けるようになるまで、ただ待って、待って、待ちまくる。その期間は緊迫の毎日だから、アルバムがリリースされていまは本当にハッピーだし、ホッとしているよ。日本にも行けるしね。日本は好きだから、また訪日できるのが待ちきれないよ。
■本作はみなさんの作品のなかでも、楽曲もサウンドもとりわけジェントルでメロウな印象を受けました。そのようなモードになったのはなぜなのでしょう?
JM:それは意識してそうなったわけではないから、僕たちに理由はわからない。あと、僕たち自身はあまりジェントルでメロウな作品とは感じていないんだ。レコーディングも緊張感に溢れていてまったくメロウではなかったし(笑)。アメリカでライヴをしたんだけど、ライヴ自体もすごく緊張感があった。だから、僕にとってはまったくリラックスの要素はなくて、どちらかと言えば張り詰めた感じのアルバムなんだ(笑)。
■皆さんのレコードからは、ありし日の美しくも儚い情景がふと浮かんでくるような、記憶や風景を喚起させる力を感じます(そして今作ではその感覚をより強く感じます)。あなたたち自身でも、曲作りをおこなっている際や演奏している際に、そういった感覚を覚えることはありますか?
JM:それも、君がそれを感じるとすれば、たまたまそういった音楽になったということだと思う。前回のアルバムを除いては、僕らはアルバムの音楽の方向性を初めからわかっていたことがないんだよ。コンセプトを考えたことがなくてね。だから、今回もコンセプトはない。自分たちが特にそれを感じることはないけれど、君がそう感じてくれたなら僕らはハッピーだよ。リリースされたいま、音楽はリスナーのものだし、自分たちの音楽が人に何かを感じさせることができているなんて本当に嬉しい。でも、僕たちはそういう風景は感じないんだ(笑)。というのも、僕らがアルバムで歌っている内容は、そう言った風景とはまったく逆のものだからね。ストリートで行進している人びと、落胆している人びと、怯えている人びと。美しい風景とは真逆なんだ。
■今回は元々サウンドトラック作品の制作がきっかけとなり、その流れでオリジナル・アルバムの制作へ入っていたっと伺いました。劇伴音楽の特徵たる「映像とともにある音楽」、そのような意識は今作にも受け継がれていると思いますか?
JM:この質問に答えるのは難しいな。自分たちの周りにあるものすべてが受け継がれているからイエスとも言えるし、かといってそれがどう受け継がれているのかは自分たちにもわからない(笑)。自分たちのライフすべてがインスピレーションだからね。でも、サウンドトラックのプロジェクトの流れでアルバム制作がはじまったのは事実。あれがうまく行ったからアルバム制作につながったとはいえるね。作業と曲作りがテンポよく進んだんだ。すごく良い勢いがついているところでムーヴィーのプロジェクトが終わってしまったから、ムーヴィーなしで自分たち自身のためだけの作品を作りはじめたんだよ。
■今回のアルバムに限らず、映像のための音楽を作る経験から何か得たことはありますか?
JM:ムーヴィー用の音楽のために、2004年から徐々にニュージャージーにあるリハーサル場所みたいなところで作業してきて、そのときは、エンジニアもプロデューサーも雇わず、ずっと自分たちだけだったんだ。そこには小さなレコーディングのセットアップなんかがあるんだけど、徐々にその場所での作業が上手くなっていったし、そこでの居心地が良くなっていった。自分たちの楽器も全部そこにあるしね。そういう面では、そこで自分たちだけで作業するようになったのはムーヴィーの経験からだから、それがいちばん大きな影響かもしれない。自分たちだけでも作品が作れるということを、その経験から学んだんだ。30年以上の活動のなかで、まったく新しいやり方で作品ができたときはすごくエキサイティングだったよ。新しい経験だったし、自分たちがやりたいだけミスをすることができたし、すごくスリルがあって自由だった。それを感じることができるようになったのは、ムーヴィーのプロジェクトの経験を通してだね。

いまのインディ・ロック・シーンは、すごく良い状態だと思うね。良いバンドがいないとか、勢いが落ちてきていると言われてもいるけれど、自分が好きな音楽、バンドというのは、探し続けている限り必ず見つかると思うんだ。
■前作『Fade』ではジョン・マッケンタイアがプロデュースを担当していました。今作はバンド自身のセルフ・プロデュース作です。「プロデュース」という言葉の定義はときに曖昧でもあるかと思うのですが、あなたたちにとって「レコードをプロデュースする」とはどういったことなのでしょうか?
JM:すごく自然。僕たちはプロデューサーでもエンジニアでもないけれど、何年もかけて、素晴らしいプロデューサーやエンジニアと一緒に作業してきて、多くを学んできた。ロジャー・ムジュノーやジョン・マッケンタイアたちは、僕たちに多くを教えてくれたんだ。今回も、わからないことがあったときはメールで教えてもらったりしたし(笑)。音楽学校に行ったり、ミュージシャンになるためにプロからの教育を受けなくても、経験でそれができるようになったのはすごくありがたいことだったし、良い気分だった。自分の頭のなかにあるアイディアをそのまま、かつどうにか表に出すというのは、直感的でもあったね。
■今作は、スライ&ザ・ファミリーストーンの『暴動』(71年作)と同名であることが話題となっています。ご自身たちで思う、あのアルバムと今作の共通点と、また相違点は何だと思いますか?
JM:それは僕らにはわからない。自分たちとそのタイトルとの繋がり方と、スライとそのタイトルとの繋がり方は違うんじゃないかな。でも、感情的に、スピリチュアル的に何かコネクションがあるんじゃないかとは感じているよ。
■音楽および社会的な面において、1971年と2018年に何か象徴的な共通点と、また異なった点があるとすれば、どんなことだと思いますか?
JM:どうだろう(笑)。もっと変わってくれていたらと思うけど、問題はまだまだ残っていて、その問題の数々は全然変わっていないと思う。解消されつつある部分もあるかもしれないけれど、状況は同じなんじゃないかな。
■このような時代だからこそ声高にプロテストを叫ぶ流れもあるなかで、本作ではむしろ何気ない日々を慈しみ、それを丁寧に伝えようとするような印象を抱ききました。いまこの時代において、そうしたパーソナルなことを歌い続けていくことの意義というものがあるならば、どういったことだと思いますか?
JM:僕自身は、そこに違いは感じない。皆、自分が言いたいことを表現しているのは同じで、表現の仕方が違うだけだと思うよ。例えば(初期の)ボブ・ディランのようなやり方もあるし、僕自身はボブ・ディランも好きだし、表現方法や音楽との繋がり方に選択肢がたくさんあって、皆がそれぞれに混乱や自分たちの周りにあるものを表現しているんだと思う。
■オルタナティヴ・ロックがシーンに登場してから長い年月が経ちました。80年代からつねにシーンの一線で活動を続けてきたみなさんの目からみて、現在のインディ・ロックのシーンの状況はどのように映りますか?
JM:すごく良いと思う。素晴らしい若いバンドがたくさんいるし、長年活動していて、いまだに、そしてさらに力強い音楽を作り続けているバンドもまだたくさんいる。それらのバンドが共存しているいまのインディ・ロック・シーンは、すごく良い状態だと思うね。僕自身が好きな音楽が溢れている。良いバンドがいないとか、勢いが落ちてきていると言われてもいるけれど、自分が好きな音楽、バンドというのは、探し続けている限り必ず見つかると思うんだ。
■みなさんとも深い交流のある坂本慎太郎さんですが、みなさんの催促も届いたのか、ついに昨年からライヴ活動を再開しました。今回のツアーでも10/11の東京追加公演では対バン共演をされますね。彼との出会いによって与えられた影響というのは、今作にもどこかへ表れていたりするのでしょうか?
JM:彼がライヴ活動を再開して、僕は心から嬉しい。でも、面白い質問だけど、僕には彼との出会いの影響がどう反映されているかはわからない。彼の音楽は大好きだし、彼らと一緒に演奏ができたのは素晴らしい経験だった。すごくマジカルな瞬間だったし、坂本さんとは良い友情を築けているんだ。彼がまた音楽を作りはじめてライヴ活動をはじめたことが、本当に嬉しいよ。

ずっと自分たちのレコードもアナログでリリースし続けているから、あまり復権という感覚はないね。僕らにとって、レコードというものはすごく自然な存在なんだ。
■交流のある坂本慎太郎さんやコーネリアスといったアーティスト以外に、近頃注目している、もしくはお好きな日本のアーティストがいれば教えてください。
JM:たくさんいすぎて、誰からはじめればいいか……日本のサイケデリック、エクスペリメンタル音楽、70年代の音楽がとくに好きなんだけど、はっぴいえんどは好きだね。あとは、細野晴臣、ボアダムス。彼らの音楽にはどれも独特のソウルがあって、彼らのような音楽はこの世にふたつとない。ヨ・ラ・テンゴは彼らからとてつもなく影響を受けているし、彼らは、僕たちがこれからも絶えることなくインスピレーションを受け続けるアーティストたちだね。
■ここ日本でも、この10年ほどでインディ・シーンが成熟してきつつあり、あなたたちのように長い年月にわたって質の高い作品をリリースし続け、ライヴもおこない続けているバンドに対しリスペクトを持っている若いアーティストたちも多くいます。「バンドを続けていくこと」にはどんな喜びがあるのか、また続けていくにあたってのコツはなんでしょうか?
JM:わからないな(笑)。じつは、僕はあまりそれを考えたことがない。バンドを続けるということを意識していないんだ。僕らは、お互い3人が出会ったことがただただラッキーだと思っているし、自然に作業していくなかで達成感が感じられることを皆で続けているだけ。何がコツかはわからないけど、若いバンドの皆が自然体で自分たちの作りたい音楽を作り続けていってくれることを願っているよ(笑)。
■ヘヴィな音楽リスナーでもあるみなさんに伺います。ここ日本でも現役バンドが新作をアナログ盤でリリースしたり、過去の埋もれた作品がヴァイナルでリイシューされたりすることが定着しつつあります。みなさん、レコード蒐集は続けていますか? また、データ~サブスクリプション配信時代におけるこうしたレコード文化の復権についてどんな思いを持っていますか?
JM:もちろん、レコードはいまだに集めている。自分たちは昔からずっとヴァイナルを買っているし、1993年からずっと自分たちのレコードもアナログでリリースし続けているから、あまり復権という感覚はないね。僕らにとって、レコードというものはすごく自然な存在なんだ。でも、ウォークマンやカセットプレイヤーを持ち歩いていた時代を考えると、iPodがやはり素晴らしいとも思う。移動中はよくCDボックスを持ち歩いてなくしたりもしていたけど(笑)、iPodだと、何千もの音楽をあんな小さいもののなかにすべて納めて持ち運ぶことができる。まさにミラクルだよ。
■最近購入して、これは日本のファンにもぜひオススメしたい! という音楽作品(新譜旧譜問わず)があれば教えてください。
JM:ニューヨークのバンドで 75 Dollar Bill というバンドがいるんだけど、彼らの作品はオススメ。そのバンドはたまに2人だったり、たまに8人だったりするんだけれど、インストゥルメンタル音楽で、サウンドが本当に美しいんだ。彼らのような音楽は他にないと思う。すごく壮大な音楽だからぜひチェックしてみて。誰もが気にいると思うよ。
■National Sawdust にておこなわれた Pitchfork Live の映像がアップされていますが、今後、今作の楽曲がライヴ演奏されていくにしたがい、本作収録曲たちはバンドにとってどんな存在になっていきそうでしょうか?
JM:まだツアーをはじめて2週間だからわからない。これから時間をかけてわかっていくんだろうね。これまで演奏した感じでは、すごく自然に感じているし、本当に楽しい。セットに新しい感情やサウンドが加わるのは、やはりエキサイティングだね。アルバムがリリースされ、みんなの前で演奏されていくことで、曲は成長し、変化していく。いまは、生まれたばかりの子どもを見守っている親みたいな感覚だな(笑)。
■ありがとうございました。来日公演楽しみにしています!
JM:ありがとう! 僕たちも日本に行くのを楽しみにしているよ。
Yo La Tengo Japan Tour 2018
■朝霧JAM 2018
10/6 (Sat) 静岡県富士山麓朝霧アリーナ
information: 03-3444-6751 (SMASH)
http://asagirijam.jp/
■大阪
10/8 (Mon) UMEDA CLUB QUATTRO
information: 06-6535-5569 (SMASH WEST)
http://smash-jpn.com/live/?id=2881
■名古屋
10/9 (Tue) NAGOYA CLUB QUATTRO
information: 052-264-8211 (クラブクアトロ)
http://smash-jpn.com/live/?id=2881
■東京
10/10 (Wed) SHIBUYA TSUTAYA O-EAST
SOLD OUT!
information: 03-3444-6751 (SMASH)
http://smash-jpn.com/live/?id=2881
■W追加公演 Yo La Tengo + 坂本慎太郎
10/11 (Thu) SHIBUYA TSUTAYA O-EAST
SOLD OUT!
information: 03-3444-6751 (SMASH)
質問・文:柴崎祐二(2018年10月03日)
Profile
 柴崎祐二/Yuji Shibasaki
柴崎祐二/Yuji Shibasaki1983年、埼玉県生まれ。2006年よりレコード業界にてプロモーションや制作に携わり、これまでに、シャムキャッツ、森は生きている、トクマルシューゴ、OGRE YOU ASSHOLE、寺尾紗穂など多くのアーティストのA&Rディレクターを務める。現在は音楽を中心にフリーライターとしても活動中。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE