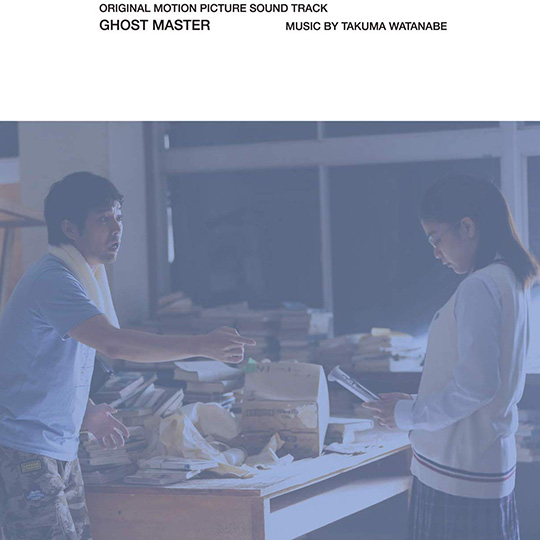MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Takuma Watanabe - イマジナリー・ラストアフタヌーン
interview with Takuma Watanabe
イマジナリー・ラストアフタヌーン
──7年ぶりのソロ作が照らし出す渡邊琢磨の現在地
1日のなかで音を奏でる時間はどんどん減っていると渡邊琢磨はいう。本文では割愛した一節だが、その前段で私たちは仕事における知識と経験の蓄積、それが導く予想と結果について話しており、1日でいかほどの時間を仕事に割くか話題にしていた。冒頭はそのとき渡邊琢磨の口をついたことばであり、以下の発言がそれにつづく。
「昔のように四六時中楽器を弾いていることは少なくなりましたが、頭のなかで音楽をつくる行為はどんどん肥大化していてその占有率たるやものすごいものなんです」
イギリスの新興レーベル〈Constructive〉がリリースする渡邊琢磨のソロ・アルバム『Last Afternoon(ラストアフタヌーン)』には上の発言を音で裏打ちする趣きがある。2014年の『Ansiktet(アンシクテット)』で生楽器を素材に字義どおりのコンポーズをやってのけた渡邊琢磨は映画音楽での実践と並行するかたちで、ストリングス・カルテット──ときに十人を越える規模に拡大することもある──で挑戦的な試みにのりだしていく。なかでも弦楽器の旋律の動きと関係という対位法の側面は中心的な課題となり、課題そのものを変奏するように音響や質感といった生理〜感覚との統合的な領野へ横滑りしはじめる。トランスフォームした弦の響き、電子音、椅子が軋むような、ものが落ちるような、小物がカタカタ鳴るような現実音や、ささやく人声──無数の音のイベントからなる『ラストアフタヌーン』はそのとりくみが実を結んだものだが、耳につくのは探究の深まりより生成変化する音のひろがりである。渡邊琢磨が日々の暮らしでもおそらく似たような出来事が起こっており、傍目にはたんにブラブラしているだけでも、内面には音があふれ、いまさまに閾値を超えそうになっていることもなくはない。終止形を迂回するかのような楽想は表題がしめすとおりで、もとより意図のうちだろうが、観念的であるばかりかこの想像的な音のあり方はあらゆる感覚を横切り、聴き手に多面的に作用する。新たな動きがはじまっているのはまちがいない。

結局、ヨハン・セバスチャン・バッハが何かしらの起点になっているのかもしれません。いまも音楽はいろいろ聴きますが、バッハの『平均律クラヴィーア曲集』は分析しだしたら一生かかるんじゃないかと思うくらい、あの曲集には音楽の基礎的な部分と和声学の極地のような部分があると思います。
■『ラストアフタヌーン』は〈SN Variations〉の姉妹レーベルにあたる〈Constructive〉からのリリースになります。
琢磨:はい。レーベルオーナーのエイドリアン・コーカーと僕のタイトルのみの新進レーベルです。
■レーベルとしては2作目ですか。
琢磨:カタログ番号的にはエイドリアンがサントラを手掛けたドラマ『Tin Star (Liverpool)』が「00」番で、『ラストアフタヌーン』が「01」になります。
■エイドリアン・コーカーと琢磨さんの出会いを教えてください。
琢磨:アルバムのミックスが佳境に入ったあたりで、クリス・ワトソンとジョージア・ロジャースという電子音楽家のスプリット版(Chris Watson Notes From The Forest Floor/Georgia Rodgers Line of Parts)LPを偶然買ったのですが、内容はもちろんのことパッケージングのコンセプトなどもおもしろかったので、ジャケットに記載されてあった〈SN Variations〉というレーベルのサイトをチェックしたところ、実験音楽やケージなどの現代音楽にサントラまでリリースしていて、カタログがすくない一方、独自のポリシーやアイディアがあっておもしろいなと。自分のアルバムに限らず、制作全般に関していろいろ提案できる余地もあるなと思って、マスタリング前のアルバムのデータをおくったのですが、すぐにおりかえしがあって話しがまとまりました。
■絵に描いたような話ですね。
琢磨:当初エイドリアンとは、Skypeを通してリリースの話しなどを進めていたったのですが、そのながれでおたがいの国のことやパンデミックの状況のこと、好きな音楽や映画音楽の制作プロセスのちがいなどいろいろと話しをしたのですが、その際とてもポライトで話しが合う人だなという印象をもちました。エイドリアンがどう思ったかはわかりませんが(笑)。
■琢磨さんはレーベルもやっているし自分でも出すこともできたのになぜそうしなかったの?
琢磨:こういう(パンデミックの)状況下で海外に行くことも難しいので、エイドリアンも僕も国外のことが気になっていたのかもしれません。それでお互い素性がよくわからないまま、Skypeで長々と議論するという……。
■『ラストアフタヌーン』をつくろうと思い立ったのはいつごろできっかはなんだったんですか。
琢磨:14年頃から活動を継続してきた弦楽アンサンブルがありまして、そのアンサンブルでのライブやレコーディングがアルバム制作の契機になっています。アンサンブル結成の土台にあったのはパーソナルなことなのですが、対位法の独習をおしすすめたいという思いでした。
■ユニゾン的な求心力ではなく、それぞれを自律的に動かしていくニュアンスを主体にして曲を書いた?
琢磨:縦の響きがきらいなわけではないのですが、それぞれの音の動きがまちまちである状態は好きですね。
■仮に作家を縦と横の志向性でわけるなら、琢磨さんは後者だろうね。
琢磨:結局、ヨハン・セバスチャン・バッハが何かしらの起点になっているのかもしれません。いまも音楽はいろいろ聴きますが、バッハの『平均律クラヴィーア曲集』は分析しだしたら一生かかるんじゃないかと思うくらい、あの曲集には音楽の基礎的な部分と和声学の極地のような部分があると思います。バッハのフーガのようなものは書けませんが、こういう音楽のナゾにとりくむことは作曲上の基点にもなります。
■対位法の探究の先に『ラストアフタヌーン』はあると。
琢磨:対位法を独習していく過程でなにが起こったのかを言葉にするのはむずかしいのですが……各々の線の響きを譜面上で伸縮させたり緩慢にしたりする実験を重ねた結果、ポリフォニーが薄れていって、音色やテクスチャーに興味が推移していったような感じです。そこから、ひとまとまりの弦の響きがコンピュータによってジェネレートされたとき、どのような音が生成されるのかという、いわゆる「音響作曲」的なことに関心をもつようになりました。逆に対位法の独習の成果は、映像の動きやムードを、旋律や和声進行などでフォローする映画音楽の仕事にスライドしていきました。
■いまおっしゃったジェネレートされた音というのはあらかじめ録音した弦の音を事後的に処理するということですか。
琢磨:本作に関しては先に弦の録音を行い、後日、その演奏内容をもとにコンピュータによるサウンドの生成を行いましたが、このプロセスはライブでも可能です。基本的には、オグジュアリー(AUX)に原音を送ってエフェクトをかけるようなことと一緒なので、弦の音自体を処理するというよりも、弦の演奏にコンピュータがどのような反応をするかが趣意になっています。ただ、そのプロセス自体はさほど重要ではなく、弦楽と電子音が合奏している音のイメージが元々あって、それを具体化する上で用いたアイディアのひとつに過ぎません。
■生演奏とコンピュータと相互作用までふくめた作曲なんですね。
琢磨:テクノロジーと生演奏の諸関係という課題は、IRCAMやGRMなどの研究機関で昔から試みてきたことですし、真新しいものではありませんが、そういった構想をアカデミズムや様式にとらわれず、自分なりの方法で試行錯誤していきたいと思っています。
■その場合ストリングスのスコアは事前に用意するんですよね。
琢磨:事前に用意します。ただ不確定な音が譜面上に混在していることが多々あって、たとえば、特定の小節内にリズムや音価が記されていない音があったり微分音があったり。そういうセクションの解釈は演奏者にゆだねています。演奏上の指標を部分的にオミットすることで、摩擦のある雑然とした演奏になるのですが、そういうセクションを設けることで、演奏するたびにちがった結果を得ることができますし、コンピュータの反応も変わるので、作曲上のねらいとも合致します。
■ねらいというのは不確定性ということですか。
琢磨:エラーみたいなものですね。不確定な小節と厳密な記譜が混在していると、エラーが楽曲全体に侵食してくるという。ジャズでいうところの「ロスト」した状態のような、どこをやっているのかわからない状態ができてくるんですね。
■あの瞬間はいいですよね。
琢磨:ええ(笑)、あのザワザワとした感じ、あれがほしいという(笑)。
■意地悪だな(笑)。
琢磨:いえいえ(笑)。スコアから大きく逸脱することはありません。僕がジャズを演奏するとたいていロストして、どこを演奏しているかわからなくなってしまうのですが、そういうザワザワ感とは違います(笑)。
■となるとスコアはアンサンブルへの宛て書きでもあったということになりますね。
琢磨:メンバーや編成も可変的なアンサンブルではありますが、演奏者同士が旧知の仲ですし、弦奏者各々の音のニュアンスも自分なりに把握していますので、作曲時にその音をイメージしていることもあります。あと、楽曲の初演会場などを念頭に置くこともありますね。
数年おきにくりかえしみる夢がありまして、住み慣れた家のなかに隠し扉を発見して、そこを開けてなかを覗くと壮大な図書館があるとかいう感じの内容なのですが、こういう日常と非日常の連続性というのは自分に限ったことではなく、今日的なテーマではないでしょうか?
■さきほどおっしゃったコンピュータ上のジェネレーターは演奏中に具体的にどのような動作をおこなっているんですか。
琢磨:Maxで組み立てたユーザーインターフェイスがあって、先述のとおり弦の音が送受信されるたびに作動して結果を生成するというだけのことですが、プログラミングと生演奏の作曲の決定的なちがいは、個人的にヴァイオリンという楽器の制作方法や工程は詳細にはわかりませんが、そのことが作曲上のデメリットになることはほとんどありません。しかじかの音色を出すにはどういう演奏をすればよいのかとか、どういう音域の楽器なのかとかそういった知識があれば、ある程度結果を予測することができます。しかしコンピュータ・プログラミングの場合、その制作方法を知る必要がある一方、結果が未知数なことが多いと個人的には思います。自分の技術上の問題も多々ありますが……。特定の動作を実行するプログラムを組むことはできても、それによって事前に想定していた音を得ることができるかは、また別の問題です。だからこういう手法でイメージ通りの結果を出すには、多少の時間と試行錯誤をくりかえす必要がありますし、弦楽の演奏内容によってインターフェースの反応も様々なので、デバイス自体を作り直すこともあります。なので、わりと出たとこ勝負の方法かもしれません。
■たがいに干渉し合っているということですね。作品の中身では物音やフィールド録音の音も使用されていますよね。
琢磨:フィールド・レコーディングの音に関しては、ミックスの際、特定のレンジ(音域)に音を補足する上で、虫の声や外気の音が適宜に思えたので取り入れましたが、具体音以外でイメージしている音像やバランスをつくれるのであれば、シンセの音でもデジタルノイズでも構いません。なので、ミュージック・コンクレート的な着想というよりはミックスダウンをする上で必要な音素材ということですね。
■微細に聴いているとほんとうにいろんなことが起こっている作品ですよね。
琢磨:とっちらかっていますよね……
■とっちらかっているというよりは出来事があちこちで派生しているといいますか。聴くたびにいろんなイベントが方々で起こっていて、発見の多い作品だと思います。
琢磨:ありがとうございます。アルバムに収めた8曲は録った時期もまちまちで、あとから似た傾向や雰囲気の作品を8曲分あつめたので、コンセプトに一貫性があるわけでもないんです。弦楽アンサンブルでの公演やレコーディングのたびに初演曲を用意してきた結果、アルバム1枚分くらいの曲が揃った感じです。そういう機会があるごとに新曲をつくって発表していかないと、つくるだけつくって忘れてしまうことも多々あるので。なので、未収録曲も30曲以上あると思います。室内楽編成の曲やルネッサンス期の声楽曲を弦にアレンジして録音し、そのデータをアキラ・ラブレーが彼独自のソフトウェアでドローン化した作品もありますが、アルバムへの収録はみおくりました。
■アキラさんは5曲目の“シエスタ”に参加していますね。アキラさんとは昨年の染谷将太監督の映画『まだここにいる』のサウンドトラックを再構成したEPでも共演されていますが、継続的にやりとりしているんですか。
琢磨:その“シエスタ”という曲は18年くらいには完成していました。アキラさんとはたまに連絡とっています。わりとフランクなやりとりが多いですね、「最近どう?」とか(笑)。
■ただの友だちじゃないですか(笑)。
琢磨:そうですね(笑)。アキラさんはけっこうナゾなひとで、彼がどういうことに関心があるのかという片鱗にふれるだけでもおもしろい。かなり固有の時間のなかで音楽やソフトウェアをつくったり生活したりしている方なので、話しているとパラレルワールドにいる気分になります。
■独自の時間がながれているんですね。
琢磨:ちょっとプルースト的といいますか。現在の話しなのか過去について語っているのかわからなくなることもあります。アキラさんは南テキサス出身で、ジャズ・トランペッターのビル・ディクソンに師事していたこともあります。
■ビル・ディクソンでジャズの十月革命は想い出しても、プルーストと関係なさそうだもんね(笑)。
琢磨:でも彼のノスタルジーとリアルが交錯すような話しは、なにもかもがネット内時系列的であるような今日においてはとても貴重だと思いますし、実際タイムトラベラーなのかもしれませんよ(笑)。
■彼はソフトウェアをつくっているんですよね。
琢磨:以前ele-kingでインタヴューしたのですが、C言語、C+も使っていてソフトウェアの開発も行ってます。既存のアプリケーションは使わずに、独自のソフトウェアを使って音楽制作をするアーティストです。おそらく米国のパーソナル・コンピュータの黎明期にインスパイアされた方だと思います。GRM所縁の個々のアーティストとは交流があるものの、あくまでインディペンデントなスタンスで活動しているのも興味深いです。
■ほかに『ラストアフタヌーン』のゲストでいえば、ジョアン・ラバーバラさんがクジレットされていますね。
琢磨:僕が昔リリースした『Agatha』というアルバムがありまして。
■2004年のアルバムですね。あの作品にもラバーバラさんは参加しています。
琢磨:今回のアルバムに入っているジョアンの曲は『Agatha』制作時に録音したアルバム未収録の音声データを使って作りました。パンデミックになって予定が全部飛んだので、家の掃除や資料の整理をしていたのですが、そのさい古いHDDを発見しまして、なかをみたら「Joan」と書いてあるフォルダに、アルバム未収録のジョアン・ラバーバラの音声データがまとめてあって、一通り聴いてみたらとても良かった。2002年の録音だったので、タイムカプセルを掘り起こしたような気分になりましたよ。それで、当時収録しなかったトラックデータは削除して、ジョアンの声だけを元に新曲をつくり直しました。
■『Agatha』の録音は2002年だったんですね。
琢磨:前年にレコーディングする予定だったのですが、セプテンバー11で延期になりました。
取材:序文:松村正人(2021年8月29日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE