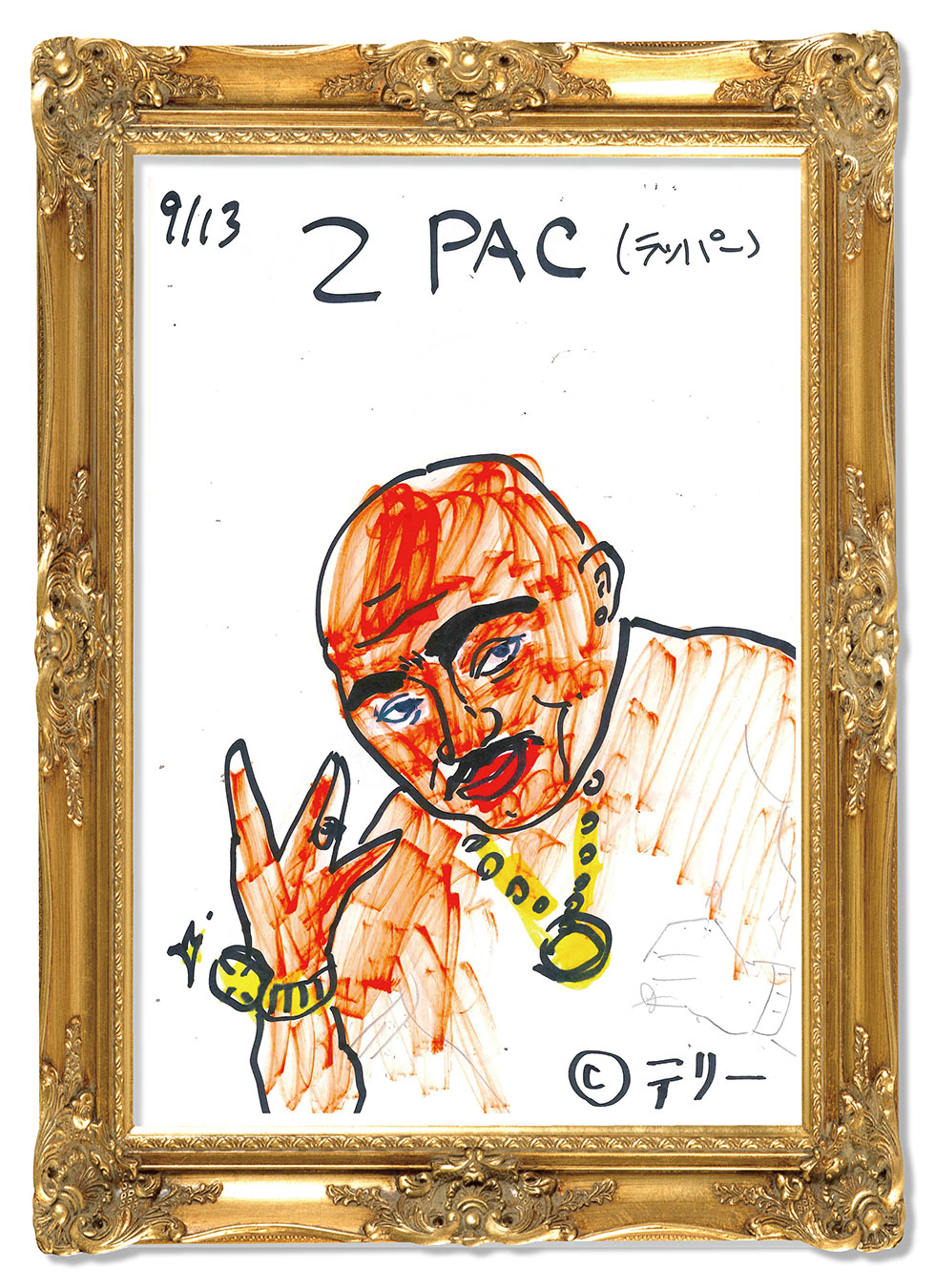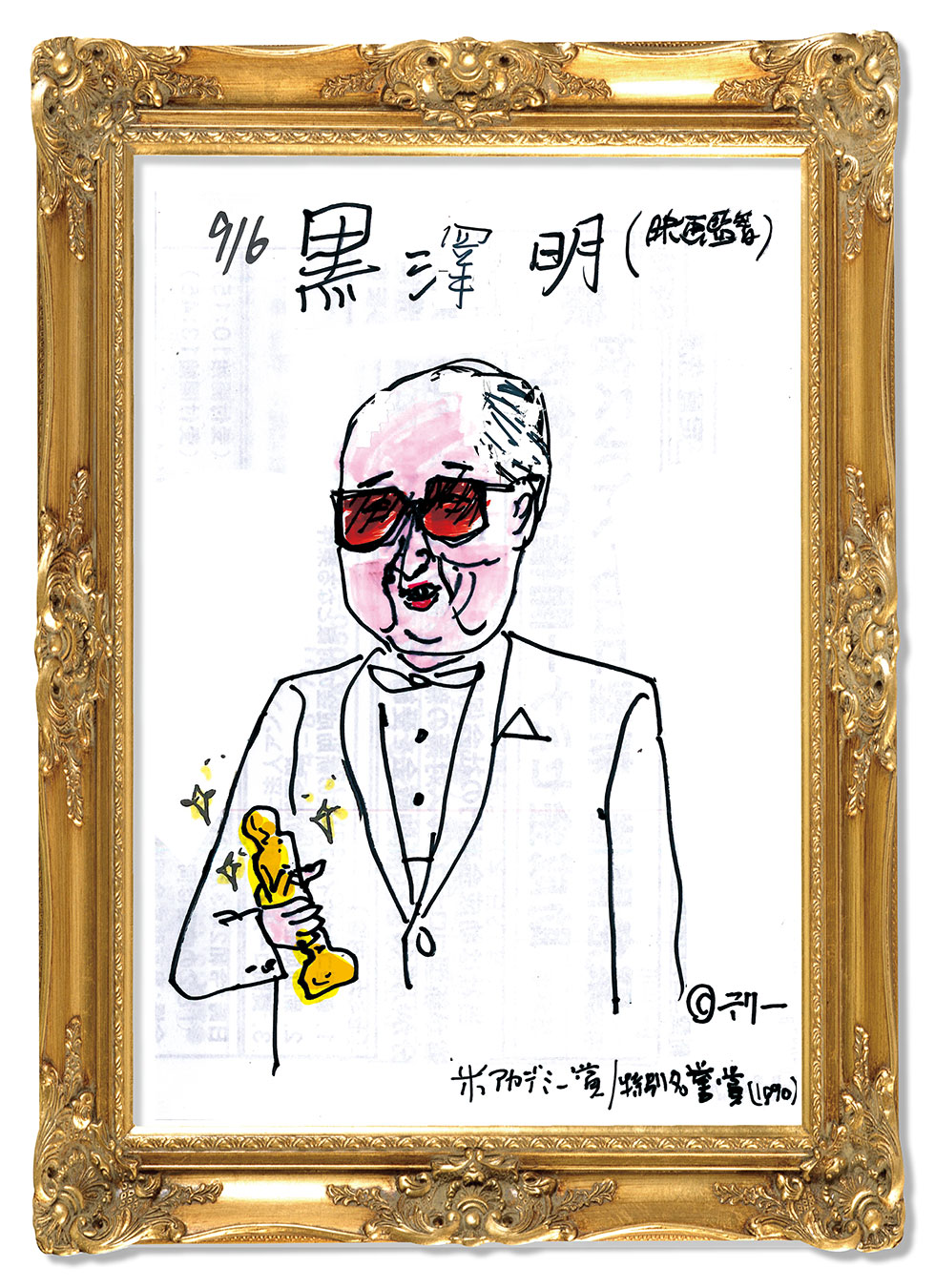まずはじめに感じたのは、歌の変化だった。
この『Turn Around』は、見汐麻衣にとって、アルバムとしては2017年の『うそつきミシオ』から8年ぶりの作品になる。それだけの時間が経っているのだから、当然、歌いかたも歌声自体も、なにかしらの点で変わっている。ただ、私が感じたのは、そういうことだけではない。
前作では――もちろん、曲によってアプローチはちがうのだけれど――まっすぐ、真正面に、まるで目の前に障害がなにもないかのように声が進んでいく発声だと感じていた。穏やかな海面をすっと進んでいく船の航跡のような、あるいは、晴天に残された飛行機雲のような。たとえば、“沈黙 Nothing To Say”では、ヴィブラートもなにもかけずに16秒ほどのロングトーンを聴かせる場面がある。このときの見汐の声は、かなり器楽的に聞こえる。
『うそつきミシオ』についてのインタヴューでは、「歌謡曲と黎明期のニューミュージック」というテーマに向きあい、軽やかに歌うことを心がけ、エンジニアの中村宗一郎との共同作業のなかで「自己表現みたいなのはいらない」と言われたことを明かしている。「自己表現」なるものにつねに絡みつく典型的な泥臭さ、えぐみは、たしかにあのアルバムでは霧消していた。状況描写的な歌詞もあいまって、歌や声が透明な管として音と言葉を運んでいるように聞こえた。透徹した歌はバンドの演奏から幽体のように遊離して感じられ、そうであるからこそ、「歌のレコード」という印象が強かった。
ところが、その後、見汐がライヴ・バンドとして活動をともにしているGoodfellasとの録音作品が届けられるようになると、その感触は変わっていった。端的に言えば、バンドのなかの歌になっていったのだと思う。ギターやベースやキーボードやドラムといった楽器の音と等価で並列にある歌、アンサンブルのなかに溶けこみ、そのなかの一要素としてあるもの、といったふうに。しかも、どこかひりひりとした緊張感があった埋火のころのそれとも異なる、ほかの楽器奏者の演奏と対話しているような歌。卑近な表現だが、バンドとの一体感がある歌に聞こえた。
そこにきて、『Turn Around』での歌はどうだろう。見汐の声は、ここでは湿度を含み、軽やかで直線的というよりも、多少の膨らみをもって、ふわっと漂い、浮かんでいるように感じられる。少々掠れたノイズや倍音成分が増え、再び卑近な表現をすると、包容力がある。“無意味な電話 Pointless Phone Calls (Rusuden Ver.)”のような曲では、吐息、時に囁き声が強調され、これまでにない顔を見せている。透明な管のようではなくて、身体から発せられている、たしかな手触りがある。アルバムの終幕である“Quiet Night”は、まるでデモ・レコーディングのような質感で、いままでになく不明瞭な発声、こう言ってよければ、ひじょうに抽象的な歌い口だ。歌い手として歌に向きあってきた見汐が、いま新しく辿りついた場所がここなんだ、と驚いた。
『うそつきミシオ』での試みを言いかえると、見汐は、そこで私性をいったん捨てたのではないだろうか。かといって、この『Turn Around』で、いかにもシンガーソングライター然とした私性や自己表現を歌に宿している、というわけでもまったくない。むしろ、とても中間的な、曖昧な温度をもったものとして歌が響く。私的な領域と、バンド・メンバーや聴き手などの他者と共有する場所とのあいだを絶妙な塩梅で漂い、楽器が発する音と交差する、とても実体感を伴った歌に聞こえる。
その変化は、たとえば、歌詞においてもそうで、一人称を意識的に排したという前作から翻って、ここではいくつかの曲で一人称や二人称が歌われる。しかし、もちろん、その「わたし」が見汐だったり、「あなた」が見汐の周囲の人間だったりを指している感じはしない。以前、“永い瞬間 Eternity As An Instant”で歌われていたように、拾いあつめた「言葉の落穂」のなかに、「わたし」や「あなた」という言葉がたまたまあった、という感触なのだ。
見汐と共同でこのアルバムのプロデュースをおこなったのは、岡田拓郎である。2024年には柴田聡子の『Your Favorite Things』と優河の『Love Deluxe』という優れた作品をものにし、岡田は、いまシンガーソングライターのプロデューサーとして重要な立ち位置にいる。
そんな岡田との協働によって、見汐の歌は新しい音のなかに……馴染んでいる、と言えばいいのだろうか。プロダクションのなかに自然と、もともとそうあったかのように、ただある。これには、岡田によるミキシングも確実に大きく寄与している。
“Cheek Time”や“わたしのしたことが Things I’ve Done”といった曲は、坂本慎太郎のレコードにおけるハワイアン歌謡やムード歌謡への接近、またはトロピカリズモの要素を感じさせるも、一方で意外だったのは“無意味な電話”で、近年ひとつの潮流をなしている、いわゆるヴィンテージ・ソウルのマナーでこの曲はアレンジされている。
そして、“Cheek Time”の密室的なリズム・ボックスのビートにしても、“Turn Around”の浮遊するコーラスやミュートされたドラムの打音にしても、“昨日の今日 Yesterday and Today”のゴーストリーなメロトロンやオルガンの音にしても、“Quiet Night”のひどくざらついたテープ・ノイズや狭い音像、音のゆがみにしても、アルバムを覆っているのは、埋火の音楽にあったものとはまた別種のサイケデリアだ。それが湿り気を増幅させ、見汐の歌をバンドの演奏と接着し、ひとつの心地よい音の風景に落としこんでいる。
いずれにせよ、『Turn Around』は、見汐の「歌のレコード」として聴ける。『うそつきミシオ』と異なった面持ちではあるが、しかし、確実にそうなのだ。そして、このアルバムにおける見汐の歌は、新しくもありながら、どこか懐かしくて親しみやすい。


 ライヴ観に行ったとき謎の遊びをしている写真...
ライヴ観に行ったとき謎の遊びをしている写真... 一緒に新宿御苑行ったら急にストレッチをし始める文太くん
一緒に新宿御苑行ったら急にストレッチをし始める文太くん 初めてお会いした時に撮ったツーショ!!
初めてお会いした時に撮ったツーショ!! りんご音楽祭で会ったときの写真!!
りんご音楽祭で会ったときの写真!! はじめてみのりさんとbonoboでお会いした日
はじめてみのりさんとbonoboでお会いした日 りんご音楽祭で会ったときの写真!!
りんご音楽祭で会ったときの写真!!