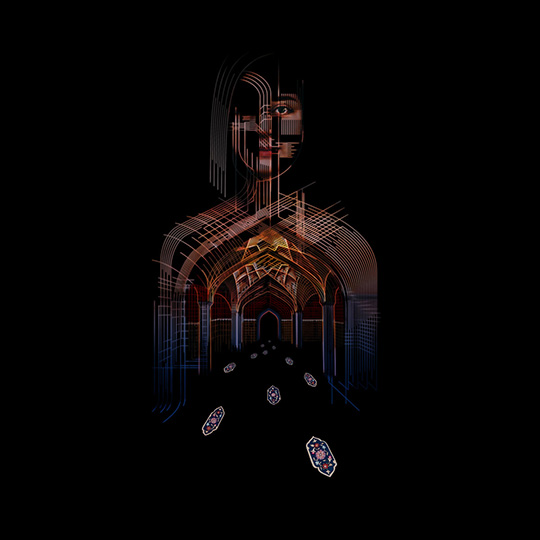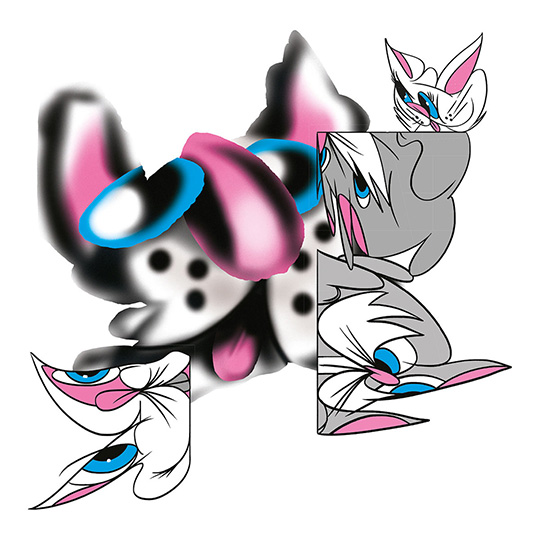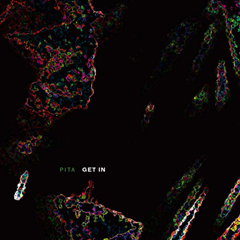MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Jim O’Rourke - 私は音楽を楽しみのために作っているわけではありません(笑)
interview with Jim O’Rourke
私は音楽を楽しみのために作っているわけではありません(笑)
──ジム・オルーク、インタヴュー
ジム・オルークのようなミュージシャンについて書くことはつねにひとつの挑戦となる。彼の作品が表面的に見える部分にとどまることはまずありえない。リスナーにたいしていかに作用しているかという部分を見えなくするためのその慎重なメカニズムは、ほとんど不可視の創造的プロセスなのである。おびただしいほどの複雑さや音楽的知性が、まるではじめから存在していたもののように、作品を完全に自然なものにし、わかりやすいものにさえしている。制作のさいに彼がとるアプローチには、アカデミックな訓練からくる要素がはっきりと含まれているにもかかわらず、その一方で、出来上がった音楽のなかには、あふれるほどの情感がこもっている。
最近の比較的目立ったリリースであり、予期せぬかたちでロック的な作曲に回帰するものだった、2015年の『シンプル・ソングス』は、すぐに親しみをもてるロックなリフレインが、聴く者がどこをどんなふうに旅しているのかをまったく気づかせないままに、未知なる音楽的領域と完全に混じりあうようなものだった。アンビエントにフォーカスをあてた新しいレーベルである〈NEWHERE〉からリリースされた最新作『Sleep Like It’s Winter』で彼は、冷たく、危なっかしく、しかし生気にあふれた、美しい45分のインストゥルメンタルの楽曲とともに、また根本的にまったく別な音の世界に身を置いている。
  Jim O'Rourke sleep like it’s winter NEWHERE MUSIC |
『シンプル・ソングス』と『Sleep Like It’s Winter』のあいだに、バンドキャンプ上でおよそ2ヶ月に一度のペースで配信された、オルークの『Streamroom』シリーズとして、22曲の別々の作品がリリースされている。そのうちのいくつかは、アーカイヴから過去の楽曲を発掘して出したもののようだが、これほど急激なリリースの流れのなかにはきっと、彼の制作を解きあかす手がかりとなる何かが見つかるはずだ。じっさい、『Sleep like It’s Winter』の直前に『Streamroom』でリリースされたもののなかには、共通する部分もある。
アンビエント・ミュージックとは、これほどレイヤーが重ねられ、何層にも織りなされるものではない。それは定義上ほとんど分析を拒否するようなものであり、もっぱら意識の外側の部分に作用するものだ。だがそれにもかかわらず、『Sleep Like It’s Winter』は、聴きかえすたびに新たな発見がもたらされる、さまざまなアイデアに満ちた、非常に意識的なアルバムだと感じさせるものである。

たいていの人はイーノと答えるんでしょうね。だけど私の場合それは、マイケル・ナイマンの『実験音楽 ケージとその後』という本までさかのぼることになると思います。高校生のころに初めて読んだんですが、とてもすばらしい、重要な本です。
■一般にアンビエントとかドローンといった言葉で評されている音楽について語るのは難しいと、個人的にはずっと思っていて……。
J:ですよね。じっさい私も、アンビエントの作品を作ってほしいというかたちで依頼されて、だからこそやってみようという気にもなったわけですが、はじめからアンビエントの作品を作ろうとしたりはしませんでしたしね。これがアンビエントのレコードだっていうものよりも、アンビエントに近いものを作ろうという感じです(笑)。私のやっていることはたいてい、〈それに近い〉ことだといえると思います。それは、〈これこそがそれだ〉っていうものとは対立するものなので。
■それを聞いて思いだしたのですが、以前にもあなたは、批評家のようなやり方で音楽制作にあたるというご自身のアプローチにもとづいた発言をされていましたね。
J:はい。私は音楽を楽しみのために作っているわけではありません(笑)。たしかにそんなようなことをいいましたね。自分と比べようというわけではないですが、若いころに私は、ゴダールからのある引用を読んだんですよ。それは、「映画について批評する最良の方法は、自分でもう一本映画を作ることだ」というものでした。幸運にもまだ若いころにその言葉を知って以来、その言葉はいまもずっと私に突きささったままで、自分の制作の基礎の部分になっています。
■新作にはどのくらいの時間をかけられたんでしょう?
J:だいたい2年です。
■制作をはじめられたころはまだ東京に?
J:まだ東京にいました。うん、最初に依頼のあったときは東京でしたね。だけどそのころはまだほかにもいろいろと進行中の仕事がありました。なので最初の6ヶ月はたしか、じっさいに何かはじめるというよりは、いろいろと考えをめぐらせていたという感じだったと思います。いったいぜんたい「アンビエント」ってどんな意味なんだろうとか、世代によっても意味が違ってくるぞとか、そんなようなことについて、いろいろと考えていました。はじめはに依頼されたときは、「新しくアンビエントのレーベルを立ちあげたんです」といわれて、私としてはただ、「ああ、そうですか……」という感じだったんです(笑)。「特定のジャンルのレコードを作る」という発想のもとにレコードを作るなんて、ひどく忌まわしいことな気がして。だけどやってみることに決めました。逆にこんなにゾッとするようなアイデアもないなと思ったからです(笑)。アンビエント・ミュージックが嫌いなわけではありませんよ──そういうことじゃない。自分ならそんなふうに制作にはのぞまないというだけのことです。ともかく、奇妙な依頼だからこそ受けてみようと決めたわけです。
■アンビエント・ミュージックと聞いて、あなたがいちばん最初に参照する足場というか、その枠組みになるようなものはなんですか?
J:うーん、たいていの人はイーノと答えるんでしょうね。だけど私の場合それは、マイケル・ナイマンの『実験音楽 ケージとその後』という本までさかのぼることになると思います。高校生のころに初めて読んだんですが、とてもすばらしい、重要な本です。その本のなかで語られていることのなかには、イーノはほんのすこししか出てきませんし、それに(イーノ自身は)まだそのころ、「アンビエント」という言葉は使っていません。かわりに彼が参照しているのは、「家具の音楽」という(エリック・)サティのアイデアです。あとはきっと、イーノの『Discreet Music』のジャケットの裏面だと思います。あのレコードの裏では、ほかでもなく彼自身が作品の背景にあるアイデアを語っていて、あとはそれが技術的にどんなふうに作られたかを示すダイアグラムも載っているんです。あれには若いころ、かなり感化されました。だけど、アンビエント・ミュージックについて考えるとなっても、私はかならずしもイーノのことは考えませんね。というのも私は、イーノのじっさいのアンビエント作品が、つまり彼がその後にむかっていった、『アンビエント』と名づけられた一連の作品が、正直なところそれほど好きじゃないんですよね──彼を尊敬していないというわけじゃないですよ。ただ私の好みではないというだけです。ある意味では、サティによる定義のほうが好きですね。つまりそれは、「家具の音楽」で、ようするにBGMのようなものなんだということです。だとすればそうした音楽は、積極的な目的意識をもって聴かれるためのものじゃないということになりますし、リスナーは、流れてくる音楽の形式的な構造に従う必要はないということにもなるでしょう。サティの定義はある種、「アンビエント」という言葉が何を意味するかという、その言葉の捉え方の変化を促してくれるものだと思います。この作品を作りながら、私にとっていちばん大事だったのは、「ひとが作品の形式的な構造に、完全に見切りをつけてしまおうと決める境界線はどこか」ということであり、「形式的な構造は感じられるままでありながら、それがうるさく迫ってくることのない境界線はどこか」ということでした。
■形式的な構造という点で、話をイーノに戻すなら、彼はどこか、音楽から演奏家をすっかり取りのぞいてしまうというアイデアに興味をもっているような部分がある気がします。
J:そいう音楽観は、私も自分の全生涯をかけてすこしずつ、ですが確実にむかっていっているものですね(笑)。その点では、ローランド・カイン(※Roland Kayn/ドイツ出身の現代音楽/電子音楽家)の存在が私にとっていちばん大きかった。彼の音楽はアンビエントだといわれたりしますが、そう呼ぶにしてはあまりに攻撃的すぎます。彼の音楽のアイデアは、システムを生みだしておきながら、あとはそれを好きなようにさせておくというものです。そんなふうに好きなようにさせておいたとしても、当初にあったアイデアが表現されたままであるような、そんなシステムをいかにして作りだすか、そこに挑戦があるわけです。過去10年のイーノの作品のいくつかや、ナンバー・ピースのようなケージの作品のいくつかに注目してみれば、彼らがそうしたシステムを作っているのがわかると思う。ケージ後期のナンバー・ピースはかなりおもしろくて、一見したところそうは見えないにもかかわらず、じっさいにそれを正確に演奏してみようとすると、かなりの厳密さが要求されるものなんですよね。カインのような人物や、イーノがやっていたこと、とくに70年代にやっていたことからいえるのは、彼らは、いずれにしろ何かしらの成果はもとめていつつも、だけどそれにたいして自分からはけっして干渉しようとはしないということだと思います。
■このところ、だいたい2ヶ月に一度くらいはバンドキャンプ上に新しいものをアップされていますね。ああしたものを聴いていると、リアルタイムにではないですが、この最近あなたが何をしているか、もうだいたい把握しているような気分になります。
J:そうですね。バンドキャンプは、インターネットが生みだしたもののなかでも、例外的に好きなもののひとつなんです。聴きたいひとが50人しかいなかろうが、とにかくそこで聴けるというところが気に入っています。レコードをリリースすることで生じてしまういろんなこととは一切なんの関係もなくいられるなら、それにこしたことはありませんからね。わかってもらえると思いますが、私にとって、作品ができあがったらもうそこで終わりなんです。そのときにはもう私は、別のどこかへむかっていますからね。
■そんなふうにバンドキャンプで発表された作品は、今回のアルバムに何か影響を与えましたか?
J:あのなかのひとつかふたつは、今回のアルバムの失敗したヴァージョンだといえるかもしれません(笑)。正直にいってバンドキャンプの曲は、ああいうものが聴きたいひとたちのなかの、50人とか80人のためのものなんです。「ほら、みんなこんな感じのが聴きたいんだろ、聴いてみてくれよ」っていうふうにやっているだけです。あんな感じのものは今回の作品には関係ないですね。バンドキャンプの作品にかんしていえば、80曲なら80とおりの失敗した部分があるっていう感じですかね。
序文・取材:イアン・F・マーティン(2018年6月27日)
| 12 |
Profile
 Ian F. Martin
Ian F. MartinAuthor of Quit Your Band! Musical Notes from the Japanese Underground(邦題:バンドやめようぜ!). Born in the UK and now lives in Tokyo where he works as a writer and runs Call And Response Records (callandresponse.tictail.com).
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE