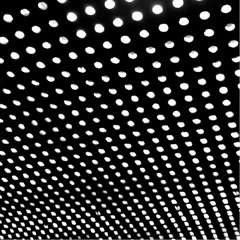MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Beach House- Bloom
歌はつねにパフォーマンスであり、歌の言葉はつねに声に出して発せられる――声を運ぶものなのだ。(略)歌は詩よりも劇に近い。(略)
ポップ・ソングでは、明瞭さではなく不明瞭な発声が歓迎される。そしてポップ歌手の価値は、歌詞にではなく、サウンド――歌詞にまつわる雑音――にかかっている。日常生活では、もっとも直接的で強烈な感情の表現は、あえいだり、うめいたり、笑ったり、泣いたり、などなどの、たんなる雑音と関わっている。感情の深さや真正しさは、言葉を見つけられないことによって計られる。「怖い」とか、「愛している」のような言葉になった表現だけでは、説明しようとしている心の状態には不適切に思えるのだ。これこそが歌がうたわれる第一の理由だ。そして、日々の生活で人びとは、雄弁家、女たらし、政治家、セールスマンなど、多舌の才に恵まれた人に不信を抱く。詩的であることでなく、不明瞭さこそ、ポピュラー・ソングの作詞家の誠実さの徴なのだ。
サイモン・フリス『サウンドの力』(細川周平、竹田賢一訳)
ヴィクトリアの歌は、まさにそのパフォーマンス、その不明瞭さにおいて圧倒的な生命力を持っている。彼女の声は中性的で(二コやマリアンヌ・フェイスフルの系譜)、そして実にありふれた、たわいものない主題を、しかし力強い、何か特別なものに変換する能力を持っているのだ。
重厚なストリングス・サウンドがその感情の起伏をうまくサポートする。『ティーン・ドリーム』が出た2010年の1月、個人的に人生の崖っぷちに立っていた時期でもあってので(まあ、つねにそうだとも言えるが)、僕は新幹線のなかで、流れる景色を追いながら初めてそのアルバムを聴いたときに、おそろしく深い感動を覚えたのである。ポップにおいては「何が歌われるかではなくいかに歌われるか」が重要だというサイモン・フリスの分析は、我々日本人が長いあいだ洋楽に親しんでいることの根拠でもある。だからといって、『ティーン・ドリーム』を『ラヴレス』と比較しようとは思わないけれど。
とにかく、『ティーン・ドリーム』はドリーム・ポップの代名詞となった。『デヴォーション』の薄明かりの憂鬱は、"浜辺の家"というバンド名のちょっとした逆説の延長線上にあったに過ぎなかった......が、『ティーン・ドリーム』は海から遠く離れて、いわば夢のなかを自由に歩くソウルだった。自分の感情を抑えずに行動することが自由と呼べるのなら、ビーチ・ハウスの3枚目のアルバムにはそれを誘発する力がある。"ゼブラ"、そして"ウォーキング・イン・ザ・パーク"......これらある種凡庸な主題も、しかしヴィクトリアの歌とストリングスによって、不明瞭さのなか、何か別の意味をふくらませるのである。
我々がラヴ・ソングを好むのは、動物的な本能から来る性愛もさることながら、愛の告白にマニュアルがないように、求愛という行為が創造的でなければならないからだ。優れたポップスはときとしてそうした生活のなかの創造を後押しするものだが、2010年において『ティーン・ドリーム』はその行為におけるエースだった。最強のカードであり、切り札だった。鳴っていたら耳に入ってくる音楽であり、大衆操作や商業的戦略に支配されたポップスを本来の無垢な姿に戻すという意味においても、それは正真正銘のドリーム・ポップだった。
買ってからまだ10日ほどしか経っていない現時点で、『ブルーム』を批評するのは難しい。基本的には『ティーン・ドリーム』の方法論の焼き直しと言える。たしかに魅力的なドリーム・ポップではある。憂鬱やためらい、それら説明しづらい感覚は、"神話(Myth)"や"時間(The Hours)"といったビーチ・ハウス節と呼べる曲からズキズキと伝わってくる。"野生(Wild)"の気だるく甘美なメランコリーも自然と耳に、いまもなお、無垢に入ってくる。彼らは自分たちの良さをわかっているし、おそらく、ファンの期待にも応えているのだろう......が、完成度という点で前作を上回っているとは言い難い。
『ブルーム』の重大な欠点をひとつ挙げるなら、センチメンタリズムの王道が少なからず混在していることだ。とくに"他人(Other People)"のような、テレビのコマーシャルにでも使われそうなほどのMORには違和感を覚える。いわゆる「前作以上にポップになった」というクリシェで説明されるのだろうが、たんなる迎合的なメロディにも思える。
とはいえ、まあ、たとえば1枚のアルバムを買って、そのなかに3~4曲、胸がときめくようなポップスがあれば充分に満足できるのであれば、『ブルーム』は間違いなく良いアルバムだ。2曲であれば先に挙げた"神話"と"時間"。3曲であれば"アイリーン(Irene)"。俗事におけるささやかな夢が待っている。夜、街が静かになったときに再生しよう。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE