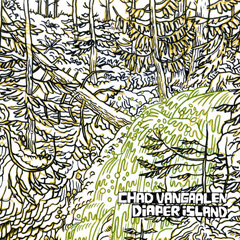MOST READ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 三田 格
- Beyoncé - Renaissance
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場
- Beyoncé - Lemonade
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
Home > Reviews > Album Reviews > Chad VanGaalen- Diaper Island
インディ音楽において、作り手から直接音楽が届けられている実感というのはどの程度重要なのだろうか? 最近、ときどきそんなことを考える。というのは、ここのところこれだけ宅録、ローファイというものがキーワードになっているのは、良くも悪くも音楽の受け取り手がアーティストの側により生々しい表現を求めていて、できるだけそこに手が加わらないことを期待しているからではないか、と推測するからである。ネットを通してそれに直に触れられるインフラが整ったこともあるだろう。ディアハンターのようにそれが功を奏している例もあるが、現在のローファイ・サウンドの多くは、ある意味ではその拙さを屈託なく晒すことによって、生々しさであるとか本物らしさであるとかを割と気軽に自己演出している面があるのではないか。そこに共感が生まれるのであれば、それはコミュニケーションとしてやや安直に思えるところがある。
USインディの90年代においてローファイ・サウンドが大きく浮上したのは、その頃には巨大産業として成立していた音楽業界に対するアンチの意味もこめられていた。だが、もはやアメリカにおいて音楽業界がかつてのように力を持たなくなった昨今では、ローファイの価値観も変わってきたように思うのだ。昨年ペイヴメントの再結成ライヴ――僕は初めてだったが、予想以上にいい加減で痛快なものだった――を観て感じたのは、「自分たちは選択の下にこれをやっているのだ」という自覚と「自分たちは洗練にははじめから興味がない」という少しばかりシニカルな目線だった。かつてのローファイ・サウンドには、たしかにそれだけの気骨のようなものがあった。
チャド・ヴァンガーレンはカナダはカルガリー出身のシンガーソングライターで、本作『ディアパー・アイランド』は4作目となる。すべて〈サブ・ポップ〉からのリリースであることは、彼が大きく北米のインディ・ミュージックの一員であることを示している。そして彼の音からは、「かつてのローファイ・サウンド」を目指しているような気概を感じる。あらゆる楽器を自分で演奏し、それらを組み立てて力の抜けたバンド・サウンドを鳴らしているのだが、どこかが壊れている。正確なピッチを外すギターの音色や、不安定なヴォーカル、揺らぎのあるリズムにそういったものを感じるのだろう。ペイヴメントやセバドーを連想する"ピース・オン・ザ・ライズ"や"バーニング・フォトグラフ"といったバンドっぽい音を、ひとりで作り上げているのはそれだけその辺りのサウンドに執着していることの表れだ。関節がひとつ外れたようなギター・サウンドの"キャン・ユー・ビリーヴ・イット!?"などに顕著だが、あり方としては『オディレイ!』の頃のベックに通じる部分もある。明らかに、最近のローファイよりも90年代のオルタナティヴと呼ばれた頃のそれを思い出させるものだ。いま30代のインディ・リスナーには懐かしいところがあるだろうし、20代にはかえって新鮮に聞こえるかもしれない。
ヴァンガーレンはノイジーなギター・サウンドを鳴らす同じくカナダのバンド、ウィミンのプロデューサーとしても知られているが、彼の音は実のところよくコントロールされている。情報としては、地下室でのレコーディングであった過去3作とは異なり、本作は広いスタジオで制作されたそうだ。しっかり練られ、音にこだわりつつ構築されたローファイ・サウンド。その意味で、そこには倒錯がある。
だが、それでも彼の音楽から聞こえてくるものは、危うさや彼個人の生々しいエモーションである。内省的なトーンのリリックもそうだが、「サラ、家にいるときは僕を起こしてくれ」と震える声で繰り返す"サラ"や、"ワンダリング・スピリット"の物悲しい歌声が危なっかしいバランスで成り立っている演奏と重ねられているのを聴いていると、それが気軽なものには思えない。彼が8、90年代のバンド・サウンドを執念のようにひとりで作り上げているのは、スタイルや美学と言うよりは、自らの感情の受け皿として適しているからだという判断、切実な選択があったのではないだろうか。
最後の"シェイヴ・マイ・プッシー"では、素朴な弾き語りに微かにノイズを重ねながら、ヘロヘロした声で「ベイビー、僕を愛してくれるかい?/僕はほんとうにいやな気分だよ」と歌う。それは孤独な呟きで、聴き手である僕たちには簡単にそれを理解したり共感したりすることはできない。あるいは、ジャケットを開くと出てくるヴァンガーレン本人のイラストによるアートワークでは、腹の辺りから植物のようなものが生えてきている、寄生された人間が累々と横たわるシュールで不気味な光景が描かれている。それもまた奇妙で、独特の居心地の悪さを覚える。そして僕は、そんなミステリアスな奥行きこそがチャド・ヴァンガーレンの音楽の魅力だと思う。たしかに生々しい感情がここにはこめられているはずなのに、いっぽうで簡単に共感されるのを拒むかのような複雑な構造を内包している。そしてその正体が知りたくて、何度も繰り返し聴きたくなってしまう。ジャケットに描かれている鬱蒼とした森に分け入っていくような、そんな体験を誘発する1枚である。
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE