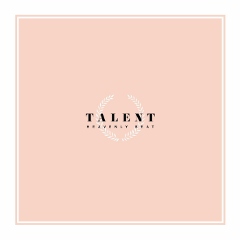MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
Home > Reviews > Album Reviews > Heavrnly Beat- Talent
このヘヴンリー・ビートにはじまり、ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートのドラマー、カート・フェルドマンによるアイス・クワイヤーのデビュー作がつづき、イェンス・レクマンが締めるかたちで、夏季の清涼ポップス・リリース月間は終了するようだ。彼らにしてみれば、いまシーンの趨勢がエイティーズからナインティーズへと移りつつあるとか、その機運のなかでR&Bに新しい求心力が宿っているとか、そうしたことはおそらく些事である。〈サラ〉や〈チェリー・レッド〉の時代から、幾多のギター・ポップ・バンドがつぎ足しつぎ足しやってきた超秘伝のダシに浸かり、またレクマンの背景ともなる北欧ポップの系譜――エール・フランスやタフ・アライアンスらの活動に顕著なように、エレクトロニックな切り口を持ったアクトも多い――とも重なりながら、ときにいぶかしまずにいられないほどきらきらとした歌と旋律を振りまいている。ファンもずっと存在するし、音楽的にもまったくまよいがない。これはこれで幸福な音楽のありかたかもしれない。ただ、この三者はそれぞれに意趣があり、突出したセンスに恵まれていることにはまちがいない。
ともあれ、ヘヴンリー・ビートも無邪気にネオアコ的な残像を謳歌し消費するポップ・アクトのひとりである。ビーチ・フォッシルズのツアー・メンバーとしても知られるジョン・ペーニャのソロ・ユニット。バンドのブレイク後にはじめたのかと思えば、どうやらバンド加入前からの名義であるようだ。中心メンバーであるダスティンとはマイスペースを通じて知りあっている。ビーチ・フォッシルズは〈キャプチャード・トラックス〉など2010年前後を盛り上げたリヴァービーなローファイ・ポップを象徴するバンドのひとつで、シューゲイザーの名盤発掘に余念のない同レーベルの性格から考えても、ペインズとは共通するところが大きい。80年代英国のインディ・バンドを愛好し、そのフォームを真似る彼らにいつまでも「リヴァイヴァリスト」の名が冠されなかったのは、おそるべきことにこの種の音をいまだ死んだとは認定していない人びとの存在の多さをほのめかすものなのかもしれない。
レイク・ハートビートに近いだろうか。"メサイア"ではアコースティック・ギターがコード感を出しながらもパーカッシヴに作用していてとても心地よい。ハイ・トーンの甘やかなヴォーカルをうまく運んでくる。こうしたタイトなリズム感覚においては彼はとくに優れている。この曲や"トレランス"その他で聴かれるシンプルなベースの音にはいわく言い難い軽妙さがあり、独立したステップを踏むかのようで魅惑的だ。全編にわたって施されたストリングスのアレンジは過剰なほどに甘く装飾的なのだが、そうしたものをうまく減じている。すべてひとりで制作しているというが、セッションではなく内部完結する制作環境が、彼の陶酔的できらきらとした世界を削ぐことなく放出するために重要なのだろう。思えば比較したふたりの音楽についても同じことが言えるかもしれない。
シックなジャケットは、彼の作品をすべて手がけている友人によるもので、今回のアート・ワークにはもっとも時間がかけられているという。つねにデザイン性が勝るこうしたヴィジュアルも、先述のベースやリズムに見られるような一種の抑制力でもって、砂糖のようなポップ・ソングを最大限スタイリッシュに仕立てているように感じられる。粒ぞろいの作品である。夏のフィーリングを感じるのは筆者の偏見で、ものさびしい季節をこそ彩ってくれるアルバムかもしれない。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE