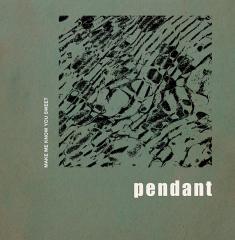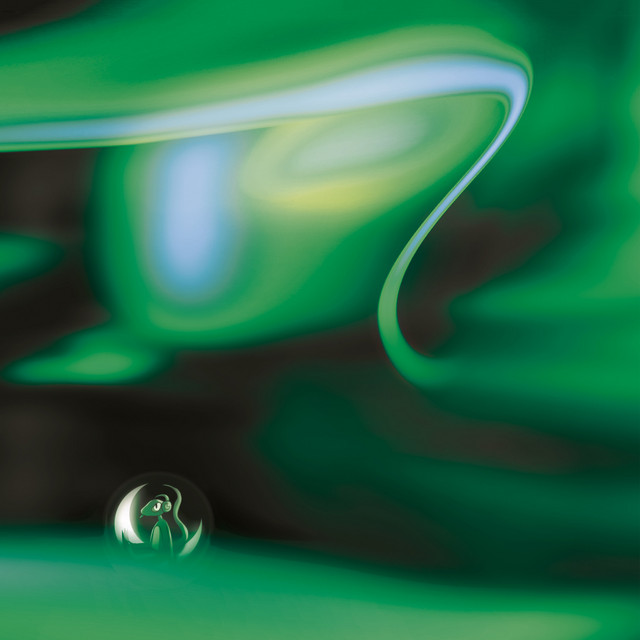MOST READ
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- DJ Python and Physical Therapy ──〈C.E〉からDJパイソンとフィジカル・セラピーによるB2B音源が登場
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- aus - Eau | アウス
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- 橋元優歩
- Geese - Getting Killed | ギース
- Ikonika - SAD | アイコニカ
- interview with Ami Taf Ra 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ | アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
Home > Reviews > Album Reviews > Huerco S.- Plonk
ゲーム・チェンジ的な傑作が、といった印象の作品です。USカンザス出身~ニューヨーク拠点のアーティスト、ブライアン・リーズのプロジェクト、フーエアコ・エス名義の3作目となるフル・アルバム(間にカセット・リリースのアルバム大の作品『Quiet Times』もあり)。リリースはアンソニー・ネイプルズと写真家でもあるジェニー・スラッテリー(Jenny Slattery)によるニューヨークのレーベル〈Incienso〉から。
2010年代初等、キャリア初期のハウス・トラックで朋友アンソニー・ネイプルズとともに注目を集め、なんといいますか、そのセオ・パリッシュをベーシック・チャンネルがクアドラント名義でミックスしたような、そんなビートダウン・ハウスをガス状のダブ・ヴァージョンにした2013年のファースト『Colonial Patterns』を OPN のレーベル〈ソフトウェア〉からリリース。続く、2016年の本名義のセカンド『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』(アンソニーの〈Proibito〉よりリリース)では、さらにダブ・アンビエント・テクノ色を強め、その表現においてひとつの転機とも言える作品になりました。そして続く2018年のペンダント名義『Make Me Know You Sweet』や、昨年の同名義『To All Sides They Will Stretch Out Their Hands』などでは、さらにアブストラクト、かつダークなアンビエント・テクノをリリースしています。
ここ数年は上記のようにアンビエント・タッチの作品が多かったのですが、まず本作の大きな変化は本名義でひさびさとなるリズムを主体とした作品(といってもハウスではない)となりました。1曲目 “Plonk I” では、それまでどこか避けていたように思えるクリアなニューエイジ的なサウンド感覚も援用しつつ、リズムの躍動感を主眼にした展開に。まさにイントロとして本作品の新機軸感を醸し出しています。この曲が象徴するように、これまでの作品のトレードマークでもあったエコー/リヴァーブ感、ガス状のダブ感が晴れて、全体的にクリアな質感が増幅された点も、同名義の作品としてはわかりやすい変化と言えるでしょう(ラスト・トラックなどにはダブの残り香はあり)。そして2曲目~4曲目 “Plonk II~IV” と、アルバムが進むうちに否応なしに本作の主眼が「リズム」にあることが明白になっていきます。インタールード的に、過去のダブ・アンビエント路線を彷彿とさせる “Plonk V” を挟んで、キラキラとしたシンセ音と後半はスロウなブロークンビーツがグルーヴをノッソリと刻む、アルバム・ハイライトとも言える “Plonk VI”。ノンビート的な “Plonk VII” にしても、エコーの重奏的な絡み合いにしてもベースラインとともにリズムの幻惑をさせるような感覚。どこか90年代後半のエイフェックス・ツインを彷彿とさせるエレクトロ “Plonk VIII”、そして次いで繰り出されるのは初となるヴォーカル(ラップ)トラック。〈Future Times〉からの Tooth Choir による濃いアシッディーなトラックでのラップが印象深い、気だるい SIR E.U のラップのバックには、まるでスピーカー・ミュージックの強烈なドラム連打を煙に巻いたような、もしくはドリルンベース的とも言えるドラム・サウンドが亡霊のように揺れ動いています。最後の曲こそ、同名義の前作を豊富とさせるダブ・アンビエント(とはいえこれも圧巻のクオリティ)ですが、本作の中心は、やはりリズムのアプローチというのが大方のリスナーの印象ではないでしょうか。
小刻みなリズムが絡みつくストレンジなシンセが有機的に融合した感覚は、ある意味で90年代中頃までのまだリズムの冒険に意欲的だったテクノ──「ハウス」、もっと大きく言えばダンス・グルーヴのループ・リズムからの脱却と、それに伴うリズムの打ち込みの細分化は、1990年代前半のデトロイト・リヴァイヴァルやリスニング・テクノの先鋭化にも通じる感覚ではないでしょうか。また肝としては、IDMというほどエレクトロニカ的なグリッチ感覚が薄いというのも重要ではないかと。それこそパリスのところで書いたような〈リフレックス〉が標榜していた “ブレインダンス” 的とも言えそうな感覚でもあります。
アンビエントものから、こうしたリズム主体の動きということで言えば、なんとなく思いつくのが彼のここ最近の周辺の動きです。ペンダント名義の作品をリリースしている、自身のレーベル〈West Mineral〉から、Ben Bondy、Ulla Straus、uon といったアーティストの作品や自身とのコラボ作品をリリース。言い換えると、ほぼ同様の人脈が交差する(はじめは傘下のレーベルかと思ってました)、Special Guest DJ(という名義のアーティスト)主宰の〈3XL〉(傘下に〈Experiences Ltd. / bblisss / xpq?〉あり)周辺人脈と、ここ数年は関係を深めているように見えます。ブライアン参加のプロジェクト(Ghostride The Drift など)も含めて、これらの動きには、ダブ・アンビエントやエコーの残響音の中に、アブストラクトに亡霊化したジャングル、ダンスホール、IDM、などなどさまざまな要素を含んだまさにレフトフィールドなテクノの最前線的な作品が目白押しといったところでとても刺激的です。NYとベルリン・スクールを結ぶ地下水脈としてここ数年おもしろい動きを見せています。最近では〈West Mineral〉からは、〈3XL〉のオールスターとも言える、virtualdemonlaxative というプロジェクトがブルータルなノイズ~ブレイクコア的な作品をリリースし話題にもなりました。前述の Ghostride The Drift や Critical Amnesia のような〈3XL〉周辺人脈とのコラボは、本作につながりそうなブレインダンス的なリズムの援用がなされており、そのあたりに本作のリズムへのアプローチの出自があるのではという見方もできます。
生楽器を取り入れながらも、なんというかポスト・ロックやフュージョンの呪縛にハマらない、エレクトロニック・ミュージックとしてのいい塩梅を提示した、アンソニー・ネイプルズの『Chameleon』とともに、リスニング・テクノの、新たな可能性を示したそんな感覚の作品でもあって、これまたその周辺の動きも含めて、まだまだ注目させるに相当しい作品を世に問うてしまったという、そんな作品ではないでしょうか。
河村祐介
ALBUM REVIEWS
- aus - Eau
- 見汐麻衣 - Turn Around
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations
- Ikonika - SAD
- Eris Drew - DJ-Kicks
- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet
- DJ Narciso - Dentro De Mim
- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion
- Debit - Desaceleradas
- Sorry - COSPLAY
- K-LONE - sorry i thought you were someone else
- claire rousay - a little death
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer
- Roméo Poirier - Off The Record
- TESTSET - ALL HAZE


 DOMMUNE
DOMMUNE