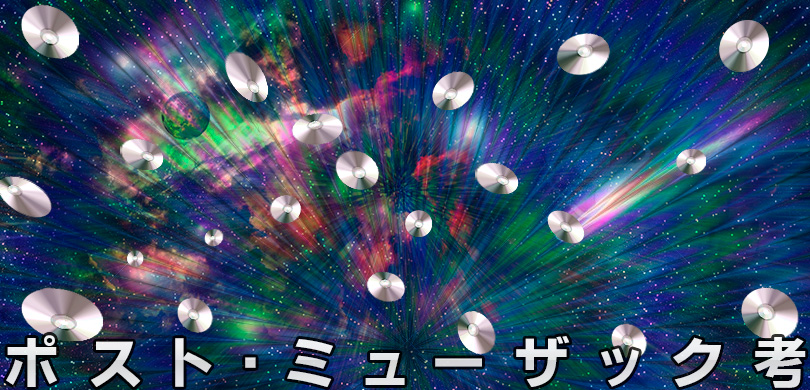MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Regulars > ポスト・ミューザック考 > 第三回「なぜ、ミューザックが蘇ったのか?」
前回の本コラムでは、〈俗流アンビエント〉という概念の成り立ちを紹介し、そこから見えてくる音楽蒐集・聴取の新しい意識について考えてみました。〈俗流アンビエント〉というタームに限らず、第一回目で紹介したオブスキュアな90年代シティポップのような、かつては音楽評論的な価値を付与されてこなかった音楽が、逆転的にその魅力をあらわにしてくるという状況は、いまさまざまな愛好家たちによって可視化されつつあるものです。こうした状況というのは単に、旧来の〈ディガー〉的な嗜好を持つ一部マニアが新たな漁場を発見し、そこで戯れるさまがたまさかSNS上で観察されるようになった、ということによるものなのでしょうか。まあ、そういう要素も少なからずあるとは思うのですが、そうした個人の趣向性云々の地平へ簡単に回収できない、もっと大きな流れが用意した状況であるようにも思うのです。
ひとつには、前回も少し触れたとおり、ロック音楽に象徴されていた、表現主義的、作家主義的、記名主義的な、ポピュラー音楽における真正性崇敬とでもいうべきもものの弱体化ということが挙げられると思います。そうした真正性の不在というのは、例えばレゲエ~ダブなどの分野では、ダブプレートなどにみられるように自明の発想であったし、初期ハウスやテクノがその制作過程において人間の生演奏によらずリズムマシンやシーケンサーをたまたま駆使したこと、あるいはサンプリングを当然のものとしたヒップホップのトラックメイキング、それらが〈クール〉の地位へ登っていったことでもたらされた予想外の結果でもあったわけですが、いまやその傾向は音楽制作における不可逆的常識になっているといえるでしょう。また、そうした匿名性、反真正性志向を自覚的に展開し、ドラスティックに展開したのが初期Vaporwaveだったともいえるかもしれません。
加えて、意味や政治性からの逃避(エスケーピズム)というものも大きな要因のひとつだと考えます。ある音楽が持つ、あるいは持たされている固有的意味性、もっといえば政治性というものを漂白したいという欲求は、現実世界における政治的言説の横溢と反比例的に符合するようにして(音楽と政治を不可分であるとする言説の興隆とパラレルな関係として)、リスナーの内に無意識的に肥大化するものだと考えます。実際、現実世界におけるきな臭い政治言語の跋扈は、いま誰しもが鋭く感得できるものでしょうし、そうした状況論と音楽を巡る議論も日々様々な形で現れています。(*1)
〈オルナタティヴ〉以降のわかりよいエポックを挙げるなら、90年代後半から2000年代にかけて喧伝された〈音響派〉があるでしょう。いまになって考えるに、〈ロックの後〉を直截に表す〈ポストロック〉というジャンル名と連動するようにして急速に人口に膾炙した〈音響〉という言葉には、音の響きそのものを、音そのものに付与され続けてきた意味論(政治性)から開放させようとする欲求が孕まれていたように思います。このジャンルの成り立ちとして、それまでポスト・ハードコア的音楽(いうまでもなくそれは政治性と分かち難いジャンルでした)を実践していた音楽家が〈変節〉し、〈音響〉を志向したということがそうした欲求をよく表しているようにも思われます(もちろん様々な例があるので一概には言えませんが)。そういった視点でみるとき、〈音響派〉の音楽表評論上の華々しい成功を一旦捨象するなら、エレーベーターミュージック~ミューザック的なるものとの本質的共通項(脱意味論的、脱政治的傾向)が自然と浮かび上がってくるのではないでしょうか(じっさいに当時〈ポストロック〉を指して、毒にも薬にもならない〈ウォールペーパーミュージック=壁紙音楽〉と揶揄する言説も見受けられました)。
また、脱政治性ということでいえば、いまリヴァイヴァルが喧伝されるAOR~ヨットロックも、あるいはシティポップもそうだと思いますし、ダンス・ミュージックにおける非政治的享楽性を抽出する用語としての〈バレアリック〉などもそうでしょう。
さらにもうひとつ大きな要因として考えてみたいのは、エレーベーターミュージック~ミューザック的なるものに対立するものとして、これまでは前景的且つ自己完結的な存在であると見做されてきたポピュラー音楽が、背景・実用音楽化=ムード音楽化しているという趨勢です。
そのためにまず、そもそもポピュラー音楽がもつ自己完結性とはいったいどのようなものなのかについて整理しておく必要があるでしょう。もちろん、「歌は世につれ世は歌につれ」という俗諺の通り、元来ポピュラー音楽にも、特定の時代のエートスやそれを形作るものとしての個人的経験の背景装置としての性格が備わっているということもできると思います(例:「あの夏の日、みんなで海にドライブに出掛けた時はヒットしていたあの曲かかっていたなあ」)。しかし、そうした性格と同じくらい、あるいはそれ以上に重要であろう、ポピュラー音楽をポピュラー音楽たらしめてきた大きな要素は、楽曲自体がその楽曲が形作る世界そのものを表象し、あるいはその世界そのものを指す存在として前景的に機能するという、ある種の自己言及性・自己目的性だったのではないでしょうか。よりわかりやすくいえば、「様々な文脈や用法から独立して、その曲それ自身だけで音楽としての価値がある」、そういうものがポピュラー音楽である、と言い直すこともできるでしょう。(*2)
また、ポピュラー音楽の持つこうした性格は、録音技術並びに複製技術の亢進によってさらに強められることになっていきました。個人でレコードを蒐集し、オーディオシステムの前に鎮座してじっくりと作品を味わう……。こうした「聴くためだけの聴取」を可能にせしめたのは、レコードという複製メディアの特性でもありました。ヴァルター・ベンヤミンがかつて指摘したような、複製技術が芸術の真正性(アウラ)を霧消せしめてしまうだろうという予想は、いまひるがえって考えると、それが複製物であろうとも外殻をもった物体であり、それを所有するという物理的行為が担保されているうちにおいては、あまりに急進的に過ぎた見取りだったのかもしれません(*3)。それどころか、ポピュラー音楽においては、むしろそこに記録された音楽の自己存立性や真正性は、大量精算・大量消費という手順を経て多数の享受者間に大きな共同幻想が立ち上がることで、むしろ激しく亢進されてきたのではないでしょうか。
また、メディア形態の変化という面からも、円筒レコードからSP盤、さらにLP盤へと収録時間や所持簡易性が向上するにつれて、産業側からのポピュラー音楽供給量も飛躍的に伸長し、果ては〈コンセプトアルバム〉のような、自己存立的音楽の極限ともいえるような表現主義的作品も頻出するようになっていったのでした。あるいは、レコードというメディアから目を転じても、ステージという殿堂に音楽を奉じ、そこへ多数の聴衆の一方向的な視線を過密させるロックコンサートなどの生演奏の場で、〈鑑賞するためだけの音楽〉としてのポピュラー音楽の自己存立性は力強く培養されてきたといえるでしょう。
しかしながら、我々が永らく自明なものとしてきた、ポピュラー音楽のそうした一面が徐々に瓦解してきたのが、ここ3~40年の趨勢なのです。まさしく、ポピュラー音楽の実用音楽化、あるいは実用音楽への回帰、とでもいうべき状況を出来させた要因には、一体どんなものがあるのでしょうか。
そしてまたそのことが、現在観察できるエレーベーターミュージック~ミューザック的なるもの前景化にとってどんな役割を果たしてきた、あるいはいま果たしているのでしょうか。次回はその部分について具体的な事例を挙げながらじっくりと考えていきたいと思います。
*1
こうした議論のわかりやすい例が「音楽に政治を持ち込むな」というやつでしょう。政治的言説への不満をつのらせながらも、一方では旧態然とした作家的人格を音楽家へ要求するがゆえ、ガス抜き(脱イデオロギー的方法論)の不全に陥っている例が、件の「音楽に政治を持ち込むな論」の気まぐれで間欠的な噴出だと言えるでしょう。いつも妙に不機嫌にみえる「音楽に政治を持ち込むな」論者が自らの鬱憤を抜本的に克服するためには、「音楽家が政治を語ることが好ましいかどうか」という議論ではなく、彼らが前提とする象徴主義的作家観を反省的に捉えるところまで遡らねば叶わないでしょう。しかし、「音楽に政治を持ち込むな論」自体が何やら党派的性格を帯びてきているいま、それもなまなかではないかもしれません。*2
一般的イメージからすると、クラシック音楽にこそそうした自己完結性が元来備わっているように見做されますが、主にバロック期までは宗教的儀礼に伴うものであったり、宮廷や上流階級家庭内でのバックグラウンドミュージック的な役割が支配的でした。クラシック音楽においてそうした自己完結的作品性が前景化してくるのは、ロマン派以降の交響曲など大作主義的作品においてでありました。また、それと平行して集中型鑑賞を能動的に行う〈聴衆〉という存在が浮かび上がってくることを通して、更にその作品の自己存立性が強化されていくことにもなりました。ソナタ形式の洗練などを経て、そうした傾向が極限に達したのが19世紀であったとされますが、後の現代音楽界においても、〈純粋音楽〉といった用語の元、音楽の自己存立性を保全しようとする動きもありました。本稿では触れられませんでしたが、〈家具の音楽〉のエリック・サティを端緒として、現代音楽界においても自己完結性を批判的に捉える動きは反復的に発生していきます。先だってele-king booksから刊行された松村正人氏の著による『前衛音楽入門』は、そうした問題意識の元で読んでみても大変面白い本だといえるので、興味がある方は是非。*3
ここでの筆者の論旨としては、外殻性をもったレコードというメディアについては「アウラの消失」という事態をただちに敷衍することは困難なのではないかというものだが、次回以降検討することになる〈外殻〉を持たないデジタル技術における複製については、この限りではないかもしれません。このあたりの問題は次回改めて立ち戻れればと思います。
Profile
 柴崎祐二/Yuji Shibasaki
柴崎祐二/Yuji Shibasaki1983年、埼玉県生まれ。2006年よりレコード業界にてプロモーションや制作に携わり、これまでに、シャムキャッツ、森は生きている、トクマルシューゴ、OGRE YOU ASSHOLE、寺尾紗穂など多くのアーティストのA&Rディレクターを務める。現在は音楽を中心にフリーライターとしても活動中。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE