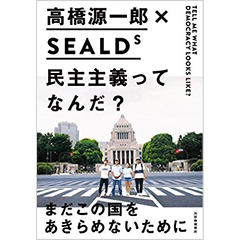MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Regulars > UCDの「適当に敬意を」 > 1:個人的な体験
たとえ馴染みがなくても、それに付き合うだけの労力と善意をもち、その眼差しや表情をじっくりと眺め、奇矯な点をも大目に見なければならない。──そうすれば、やがてはわれわれが音楽に慣れてしまう瞬間がやってくる。音楽を期待し、音楽がなくてはいられなくなるだろうと予感する瞬間が。そうなると音楽はさらにとどまることなく威力と魅力を発揮し続け、ついにわれわれはその献身的で心酔した愛人となり、もはやこの世にそれ以上のものを求めず、ひたすら音楽だけを願うようになるのだ。──しかしこれは何も音楽に限った話ではない。いまわれわれが愛しているものすべてについても、ちょうど同じようにして、われわれは愛することを学んだのだ。 ──フリードリヒ・ニーチェ『喜ばしき知恵』
最初にあの体験をしたのは、いつだっけ、たぶん中学2年の夏休み、昼下がり、歌詞カードを片手に大瀧詠一の『ALONG VACATION』を聴いたときだ。あのときの体験はそれまでとは何かが違っていた。それが明確に言葉になるなら音楽なんて必要なくなってしまうような、絶対的に個人的だけど、たぶん普遍的なあの感覚。あれから音楽に魅せられてしまった。
中学生くらいまでは、僕の音楽体験は父と共にあった。家のスピーカーや休みの日に通った父の美容室では、ユーミン、大瀧詠一、山下達郎、小野リサ、スタイル・カウンシル、ダイアナ・ロス、なんかが流れていて、いま思えばすごくいい環境だったと思う。小さいころから日々の中に当たり前に音楽があった。
高校に入ってからは、なんとなく軽音楽部に入ってベースを弾いた。スラップ奏法が好きなこと、ダンス部でブレイクダンスをやっていたことがあいまって、いわゆるブラック・ミュージックに惹かれていった。特にくらったのは、エリス・レジーナだったかもしれない。部活から帰ってぼうっと聴いていると、そのときの家庭環境のやるせなさとかも含めて宇宙のすべてを受け入れることができた。
それとは別の文脈だったけど、日本語ラップにどっぷりハマっていったのもそのころだ。はじめは特に「さんぴん世代」を絶対視して聞いていた。とにかく好きだった。ライムスターでブレイクダンスを踊って、キングギドラで社会問題を分かった気になっていた。
少し話はそれるけど、いま思えば、僕が現実の政治問題に関心を持つようになったのは日本語ラップの影響が大きい。周りで日本語ラップを聴いていたやつは一人しかいなかったけど、そいつとの思い出は最高で、第3会議室でのコッチャンと宇多丸みたいに、そいつと俺は右翼と左翼のそれぞれをレプリゼントして、いつも議論をしていた。左翼的だった俺に対して、そいつの家は祝日に日章旗を掲げていた。高校を卒業してから会ったとき、韓国に対するヘイト記事を紹介してきたりして俺は愛想を尽かしたけど、俺が国会前でコールをするようになったころ、ふとそいつのツイッターを覗くと、「国会前にきたけど牛田いないな」ってツイートしていて、とても嬉しくなったのを覚えている。
高校の卒業と同時期に3.11を経験し、漠然とだけど、深く染み入るように、この社会と政治に不安と怒りを感じるようになった。このころには新譜に手が伸びるようになり、鬼やANARCHYなどをよく聴いた。部落や貧困な地域からリアルなヒップホップが出現していることを知った。想像する限り、想像を絶するような苦難の中でも決して腐敗しない、生きることそのものの初期衝動がそこにあった。
そのあと、僕が徹底的にのめり込んでしまったのは、PUNPEEとS.L.A.C.K.だった。大学の先輩である、パブリック娘。に誘われて、初めて行ったクラブイベントは「SUISEI IS HIGH」というtofubeatsのアンセム「水星」のリリースパーティで、右も左もわからず、失礼なことにPUNPEEだけを目当てにしていた僕は、「クラブに来るの、初めてなんですけど、これってずっと前の方にいてもいいんですか」とかDJブースの近くいた人に聴いたりして笑われていたら、その周りにtofubeatsさんがいた。顔を認識してなかった僕は、誰か変わらないまま話していて、それを察したtofubeatsさんは「僕はtofubeatsといいます。クラブに来るの初めてなんだ、なんかおごるよ、なにがいい?」と言ってくださって、酒が飲めない僕はカルピスをおごってもらった記憶がある。その後PUNPEEにも「初めてクラブに来たやつ」として紹介されて、その日の夜に「今日初めてクラブに来たという、大学で友達あんまりいなそうなダサいやつを見て感慨深かった」とツイートされたのが懐かしい。
S.L.A.C.K.は今後の連載で詳細に書きたいと思うけど、今までで一番ハマったアーティストだと思う。それまでの日本語ラップで一番しっくりきたのがS.L.A.C.K.だった。その理由はまた書きたいけど、ひとつは僕が生きているリアルと似ている「現実」を肯定的に謳っていたからだ。「普通の生活して楽しくできればいいと思うんだよ」って、俺も本当にただそう思ってた。くそみたいなこともあるけど、それほど悪くない生活。でも、その普通の生活が少しずつ崩れようとしている。よく考えると、普通が剥がれ出して、この現実がよく見えるようになっただけなのかもしれない。S.L.A.C.K.が5lackになる頃、「適当にいけよ」って、どうでもいいってことじゃなくて、本当の意味で「適当」にやらなきゃいけないってことに気づいた。初めてデモでコールをしたとき、僕は5lackの「気がづけばステージの上」を聞きながらデモのスタート地点に向かったのを覚えてる。「いまもステージの上/始まってるぜ本番/お前のLIFE」。僕は僕の人生というステージに立っている。いつだって、死ぬまでは。なら本気でやんなきゃなと思って行動してきた。
こんな感じで、僕のこれまでの短い人生は音楽と共にあって、時に音楽に型どられ、音楽から生きるための道標を得てきた。それに長く触れることで、僕は音楽を愛することを学び、同時に、この世界と自己を愛することをも学んだ気がする。今回の連載では、そんな「生き延びるための技藝(アート)」としての日本語ラップについて書いていきたいと思う。よろしくお願いします。
Profile
 UCD/ラッパー
UCD/ラッパーCOLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE