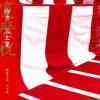MOST READ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- 『成功したオタク』 -
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Oneohtrix Point Never with Jim O'Rourke and Eiko Ishibashi ──OPNの来日公演にジム・オルーク&石橋英子が出演
- 5lack - 情 | SLACK
Home > Interviews > interview with Kan Mikami - もうひとりの、“日本のパンク”のゴッドファーザー
明日で世界は終わるだろう
明日で世界は終わりさ
けれど誰がそれを信じるだろう
誰がそれをきくだろう
"アンコ椿外伝"(2011)
ディストピアを声高く歌うひとを、昨年の11月、麻布の〈新世界〉で見た。「カモメよカモメ~、この世の終わりが~」、彼は未来のなさを、海の荒々しい彼方の情景を、独特の節回しの唄とギターの演奏のみで、これでもかと言わんばかりに展開した。東京という街がとにかくナイーヴで、相変わらずの励ましソングか、口当たりの良いヒューマニズムを繰り返すしか脳のないときに、1960年代末に青森からやって来て、寺山修司と精神的に結ばれながら、放送禁止用語集のような楽曲を発表していた三上寛は、いまも堂々と、そうした甘い感傷を吹き飛ばす、荒波のような唄を歌える。演奏が終わったあと、しばらく席から動けないほどに打ちのめされた。それが今回の超ロング・インタヴューの動機だ。
さて、今日のポップ・ミュージックでは、「ちんこ」「まんこ」「うんこ」といった言葉は、文脈によっては品性を欠いた挑発(からかい)、あるいは使い方によってはダダイズムの延長、ときにはずばりそのものの猥褻な名詞として、たとえばジョージ・クリントンのファンクないしはパンク・ロックを起爆剤としながら、表現の自由という大儀のもと、道徳的な見地からの批判をとうの昔に抑え込んでいる。セックス・ピストルズでもエミネムでも、彼らのこうした言葉づかいは、学校から与えられたボキャブラリーの外側へと受け手を連れ出すがゆえにときとして爽快な気持ちにさせる。
三上寛が1970年代初頭に試みた実験にもそれがある。"ひびけ電気釜!!"は、彼のけしかける無秩序の、もっとも有名な曲のひとつである。「飛んでいくのか片目の赤トンボ/キンタマは時々叙情的だ/泥沼の奥底はペンペン草の肉欲だ/赤いまむしはあみだくじだ/生命は神の八百長よ/希望の道は下水道だ」
手短に言おう。フリー・ジャズやアヴァンギャルドを取り入れた『Bang!』(1974)、死と隣り合わせの美しいバラード集『負ける時もあるだろう』(1978)といったアルバムは、日本のロックの急進派における古典としていまでは広く知られている。そして、いっさいの新曲を作らなかった10年を経て、1990年代以降の三上寛は、〈P.S.F. Records〉から怒濤のリリース・ラッシュを開始している。それら近年の作品には、1970年代の三上寛を特徴づけていた猥褻さと敵対心ないしは俗悪な描写はない。その代わりに、詩的な描写と唯一無二のギター演奏による独創的な音楽性は着実に磨かれ、光沢を増している(ブルースと講談と演歌のブレンド、津軽三味線とジャズの混合など、いろいろな説があるが、どうやら自然の成り行きで定まっていったスタイルのようである)。
多くの犠牲を払って手に入れた豊かさもぐらつき、我々は、恐怖と不安のなかでびくびくしながら生きている。学歴の高いひとの言葉ばかりを鵜呑みにしたり、金持ちに媚びてしまったり、他人の目を気にしたりする。そんなこと、まっぴらごめんだ。三上寛の音楽は我々を自由にするだろう。第三者的な良心よりも優先すべきことがあるんじゃないかと思わせる。たったひとりで行動するひとに勇気をもたらすだろう。教育システムの埒外にころがっている人生を差し出し、我々の生活をタフにする。
取材は、アンダーグラウンドの巨匠(......この巨匠という言葉は三上寛という筋金入りの反権威主義者には失礼だろうけれど、敢えていまそう記したい)がいま住んでいる津田沼のサンマルクの小さなテーブルでやった。あっという間の3時間。以下、そのほぼ全記録である。
お茶の間のヒューマニズムというのは大嫌いでしてね。「かわいそうだな、がんばれよ」っていうひとはね、どこからも突っ込まれないわけじゃないですか。世界的なレヴェルで良いことになってるわけですから(笑)。ところがね、「いちどでもそう言われたひとの身になって考えたことがありますか?」っていうね。
■津田沼にはどんなきっかけで住みはじめたんですか?
三上:津田沼はね、うちの奥さんが西千葉のひとで、それで子どもが生まれたときに実家に手伝ってもらったりで近くのほうがいいだろうということで住みはじめましたね。それで、1987年に来たからもう25年になりますね、千葉はね。
■ああ、そうですか。
三上:それが幕張だったんだけど、そこを越さなきゃいけなくなって、ひと駅こっちに出てきたって感じですね。それでこっちに出てきて6年かな。
■千葉自体は長いんですね。
三上:長い。
■90年以降の大量リリースに入る頃には、もう千葉に住まわれていたんですね。
三上:千葉にいたわけです。ですから「Jan Jan サタデー」(注)が終わったときに引っ越してきたんですよ。1986年までやりましたからね、わたしはね。あとはバトンタッチして。だからちょうど静岡に通ってたころは、阿佐ヶ谷から通ってました。そのときはまだ阿佐ヶ谷に。千葉はなかなか面白いですよ。何もないけどね。
■千葉に住まわれたことと、三上さんの音楽性に何か関連性はありますか?
三上:あるね。
■どういったところでですか?
三上:こういうことがあったんですよ、自分のなかでね。18のときに東京に出てきて、それで18年いたなあと。それで東京と青森にいた年数が同じになっちゃったなあと。そういう自分なりのある種の物語みたいなものもあって(笑)、それでどっかへちょっと行こうかなっていうのが先になったんですね。だからちょうど良くて。
そこで自分の音楽性に関係するのはね、そこは江戸川と利根川にちょうど囲まれててね、橋が両方ぶっ壊されると無法地帯というか(笑)、独立国みたいになっちゃうんですよね。水に囲まれてるっていうのが、ちょっとこう浮世離れした感じがあって。千葉に来ていちども気持ちが落ち込むということがなかった。これはびっくりしましたね。結局ね、漁師町なんだね! なんかこうね、ほかと違いますよ。だからみんな中津川ですね、ある意味で。
■ああー。天然の。
三上:天然の。
■それはいいですね(笑)。
三上:それは住んでみて初めてわかりましたね。まあむろん人間としては浮き沈みはありますよ(笑)、気持ちの上でね。ところがね、まず最初ここで暮らして「変に落ち込まないとこだな」っていうのはありましたね。そういう意味でね、土地柄と言いますかね、原始的と言おうか......自分たちから「わたしは漁師でございます」なんて言わないけれども、江戸時代はほとんど完全に漁師町だったでしょ。浦安とかあの界隈。だから染み付いてますね、漁師の感覚が。それも東京湾の豊かな漁師。それは海外に行ってた横浜と違って、ほんとに江戸のための漁師だったんじゃないですか。
■出ましたね。漁師という言葉は、"海男"であるとか、三上さんの音楽のなかでひとつ重要なキーワードですよね。
三上:ほんとにそうですね、漁師と海の歌っていう。たとえばリバプールなんかもね、ほんとに漁師町ですよ。わたしたまたま4、5年前にちょっと行ってきたんだけどもね。ほんとにもう、「あ、小泊だ」って思うぐらい(笑)、景色が似てて。カモメは飛んでるわ。まあもちろん、いまは漁業はなくて観光中心みたいになってるけれども。
そういう海どころって感覚の音楽が生まれるじゃないですか。アメリカ西海岸でも、東海岸でも。日本だけ海イコール演歌っていうことでね、そういう意味である種――まあ古い言い方かもしれないけれども、サブカルチャーというか、我々がやってきたようなことで海をテーマにしてるって意外とないんですよ。音楽で。
■ポップスで海が出てきても南国的な海だっりしますよね。
三上:湘南だったりね。わたしは北の海だったり、そうそう、働く海っていうんですか。
■そうですね、漁師がいる海っていう。
三上:意外とないんですね。 それは北島三郎さんと鳥羽一郎の特許みたいな感じでね、ふたりが歌ってればいいっていう。だから演歌がそれを示してましたわな。だから必然的にわたしの歌い方もどうしたって演歌、ってふうになるだろうし。環境もそうでしたね。海の町で聴いた音楽でしたからね。漁師が好きな音楽ばっかり聴いてましたからね。
(注)「Jan Jan サタデー」
静岡市の第一テレビ局にて1981年の春からはじまったヴァラエティ番組で、筆者は高校生のときにこの番組を通じて三上寛を知った。ロック・バンドが静岡に来ると紹介してくれたので、よくVHSに録画した。そのテープはいまも実家にある。
取材:野田 努(2012年3月09日)
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE