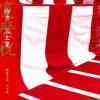MOST READ
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- TechnoByobu ──テクノ屏風、第2弾は『攻殻機動隊』
- KEIHIN - Chaos and Order
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- Reggae Bloodlines ——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催
- interview with Louis Cole お待たせ、今度のルイス・コールはファンクなオーケストラ作品
- Columns Aphex Twin テクノ時事放談──エイフェックス・ツインの澄んだ音は我々をどこへ導くのか
Home > Interviews > interview with Kan Mikami - もうひとりの、“日本のパンク”のゴッドファーザー
歌い手、ものを作る人間の予感ですよ。予感のないアートはダメですよ。アートはね、後付けじゃダメ。政治とかジャーナルは後付けだけどね、アートは先に行ってそこで「まさか」って言われるんだけども(笑)。誰でもみんなそうですよね。
■なるほど(笑)。ところで三上さんの歌には、多くの固有名詞が出てくるじゃないですか。木下明夫とかね。古谷くんとか弥吉とか落合恵子とか(笑)。あれはどういうような意図なんですか?
三上:要するにね、固有名詞ってね、ある種浄化みたいなものでね。ある種リスナーに対する拒絶ですよね、ええ。つまりテクニックとしてはね。ただね、リスナーに対しての拒絶なんだけれども、そこで諦めないんですよ、いまのリスナーっていうのは。その固有名詞にあるね、まあ三上なら三上の等身大の見方を想像していくんですよ。
だから日本のお客さんがいないとあれできないですよね。俺のいまのやりかたって。固有名詞がいままで拒絶していままで使われてたんだけれども、放射能じゃないけど、そういうものを乗り越えていく感覚っていうのが日本人はあるし。また俺本来言葉ってね、固有名詞の羅列なんじゃないかと思うんだよね、意外と。
■あの、外国の歌って固有名詞が出てくるじゃないですか。ひとの名前が。でも日本の歌でひとの名前が出てくることってあんまりない。まずありえないですよね。
三上:そして、アメリカの映画でもヨーロッパの映画でも、我々が観るでしょ。すると字幕があるけど、ヒアリングが優れてるひとはどうか知らないけれども、わたしなんかだと何言ってるのかほとんどわかりませんよね。全部ひとの名前ですから。ジョージが何したとか、ジャックが何したって話でしょう。あと行くか行かないかぐらいは小学生でもわかるから、あと80パーセントぐらいはひとの名前呼び合ってますからね。ジョージがどうしたとか、あいつがどうしたとか、どんなギャング映画でも。それと同じですよね。だから結局無意識にでも想像してるわけですよ。固有名詞の意識でね。
■外国の方って、知らない分サウンドとして聴くからわかるんですよね。
三上:そうなんですよ。固有名詞を使えば使うほど、外人には伝わるっていうのはこれも不思議なんだよなあー!
■ゆらゆら帝国っていうバンドをやっていた坂本慎太郎くんっていますよね。彼と昔飲んだときに「三上さんは海外ですごいんだよ」ってことを僕に教えてくれたんですね。それを聞いたときは意外に思ったんですね。三上さんは言葉が面白いから。でも、実際、海外からも作品を出されているし、よくよく考えれば、三上さんの好きなコルトレーンなんかもそうですけど、ものすごく土着的なものを追及していくとユニヴァーサルになっていくっていうか、そういうことなんだろうなと思ったんです。海外に関しては意識されたんですか?
三上:うーん、意識したのはねえ、昔は何と言いますか、文化的なナショナリストと言おうか、「てめえらにわかるわけねえだろ」っていうのがスタンスだったんですよね。
■はははは。
三上:「わかってたまるか」っていうね。それが70年代ごろの私のスタンスで。実際あの当時はドラッグ・カルチャーっていうか、アメリカのインテリたちがみんなインドに行ってた時期で。そこそこレヴェルの高い連中は一回新宿にいたんですよね。だからそういう外人を見てきてるから、「てめえらにわかるか」っていうね。あるときね、ピンク・レディーの振り付けか何かでたまたま俺のライヴ観に来たやつがいて、「お前、いますぐニューヨークへ行こう!」って(笑)。それが24~5のときですからね。そういう意味では、なめてかかってたっていうか。それでずっといたんですけれども。
ですから最初にヨーロッパに来ないかって言われたときも、破格のギャラをね提示するくらい思い上がってたっていうかね(笑)。意識も何もあんまりなかったんだけれどもね。ところがね、アイヌ民族と自分の血のルーツってことを考えていろいろ部落を回ってみたり話を聞いたりして、それでネコヤナギっていうのが物凄くキーワードになってるんですよね。
■ネコヤナギ?
三上:はい。ネコヤナギってアイヌ民族のキーワードになってるんですよ。なぜかと言うとね、川端に咲くんですけれどもね、キラキラとパール上に光るんです。それが大きくなるとネコヤナギの木を5センチぐらい切りましてね、それを乾かして、イナウっていうのを作るんですよ。だから日本で言うと何て言うんですか、神社にこうついてるのがあるじゃないですか。あれと同じようなのでイナウっていうのがあって、それをネコヤナギの木で作るんですよ。ナイフを曲げてきゅうっと縮れさせて、作るんですよ。
ネコヤナギのツアーを10年北海道で毎年やりまして。そのなかでぜんぶ曲を考えて。で、やっていくうちにそういう話が来て。「じゃあヨーロッパにネコヤナギ見に行く」っていう。どうせアイヌなんてヨーロッパから来たんだからね。それがあったんですよ。そして初めてパリに行くと、あのセーヌ川の領域っていうのは、もうわーっとネコヤナギだったんですよ。
■へえー。
三上:それで筋が通ったの。だからそれが自分のなかで10年間の遠心力ですよね。ぐーっと置いてどーんと行った感じですよ。だからアイヌ民族の血の流れですよ。そういう意味じゃ、きっと。流れで言うならばね。戦略的なものも多少あったにしろ、自分のなかじゃそういうことになってますね。で、向こうのひとなんかネコヤナギなんてまったくみないですからね。「ネコヤナギ? 何だその木は?」って全然興味ないですけど(笑)。
■ハハハハ。
三上:そういう導きみたいなものがありましたけどね(笑)。
■ちなみにパリで出したアルバム......2004年の『Bachiー撥(ばち)』ですか、あと、2009年にも出してますよね。『Nishiogi No Tsuki』とか。
三上:うんうん。2枚出しましたね。
■現地でライヴもやられてるわけですよね。
三上:やりました。
■どのようなリアクションなんですか?
三上:だから最初にね、レコーディングしたときに......『撥』のときですね。録音するじゃないですか。するとね、いままで聞こえていなかった音がいっぱい入っているわけよ。ていうことは、エンジニアが聴いたとおり録音されているわけじゃないですか。たとえばその「青い空」って歌ったときに、意味の分だけ音が引かれてるんですよね。「青い空」ではわかっちゃうわけですから。ところが「青い空」っていう意味を知らないと、「あ」「お」「い」「そ」「ら」っていう音になるわけじゃないですか。しかし我々は、無意識に意味の部分でまとめてるんですよ、輪郭をつけてですよ。意味がないと、「あおいそら」ってこんな声を出してるんだな、ってことに物凄くびっくりして。それでさらにさっきの固有名詞に対する自信もそこで深めたんですよ。
■なるほどね。
三上:「やまだひろし」、「きのしたあきお」、微妙に違うわけじゃないですか。それでこっちが固有名詞だと言わないにしろ、絶対薄く匂ってるはずですよね、名前から。
これも非常に感覚的なことかもしれないけれども、わたしは物凄くひとの名前を覚えにくいんですよ。だから自分の言葉にするまで、たとえば「山田一郎」でも半年ぐらいかかっちゃうんですよ。これは変な感覚で。やっぱり最初からそういうものとして捉えてるのかもしれないですね。ひとの名前が一番ねえ......一度覚えたら自分のなかにぱっと入ってきて、物語の仕組みを作ってくれるひとっていうと変なんですけれどもね(笑)。
■なるほどねえ。
三上:これはだからまあ......謎っていうか、隠してるわけでも何でもないんですけれども。不思議ですよね。たとえば人名でも土地の名前でもいいから、固有名詞に力があるんだったら全部羅列でラップでもやってみようかっていう。でもこれはまったく違う話ですよ。それを「固有名詞でございます」って周りで仕掛けてやらないと、固有名詞にならないですよ。ばーっとやったからって、誰も固有名詞と思わない。いかに固有名詞で、そこを浮かせないとね(笑)。
だからこういうことかもしれないね。拒絶させたと見せかけて、入り込む、あるいは入ってもらうっていうね。これは隠しですよね。意外と。だからね、音楽には絶対隠しがないとダメ。
■トリックみたいなものですよね。
三上:ええ。でないと、風化しちゃうんですよ。つまり権力、お上、既成事実に吸い込まれちゃうんですよ。だからわかるやつにしかわからない部分がないと。
■隠語みたいなものですね。
三上:隠語がないと。ちゃんと「訓練がいる」っていう風に緊張感を持ってないと、音楽っていうかありとあらゆる芸術はここまで伸びてこなかったと思うんですよね。力のあるものは壊すことができるわけですから。
■それこそ日本の大衆音楽に「うたごえ運動」(注)があったことを忘れちゃいけない、ってことをおっしゃられてましたけど。
三上:それだよ。だって全部バレちゃったらさ。
■とは言え僕は、三上さんの言葉からはこう漠然としたイメージというか、「どうとでも取れる」ってものではなく、ある方向性というものはすごく強く感じまして。近年の作品に。たとえばまあ、それこそ「丘の上で転んで乞食に笑われる」とかね。あるいは「覚えたての英語を忘れる」とかね。何かを失っていく感覚。それは先ほどから言われている死っていうことに繋がるのかもしれないですけれども。
三上:100パーセント伝わってるっていうかね、お互い入れ替わることができるんならそうですけど、それはないですよね。音楽っていうのは完全に入れ替わることはできない。それはありますよね、おそらくはね。
■入れ替わるっていうのは?
三上:要するにつまり、わたしはね、人間のなかにある語彙っていうものはね、同じだと思ってるんですよ。わたしが知らない言葉をみなさんがいっぱい持ってるだけでね。言葉の仕組み、ひとのDNAを支える言葉のロジックというものは、それを支えている言葉っていうものは、まず立って歩いている限り、みんな同じだと思ってるんですよ。
大学の先生が多いっていうわけではなく、たとえばうちのじいちゃんなんて本なんか読んだことあるかっていうか、まず字が書けるのかよっていうまさに無学なひとだったですけれども、それでも何万という言葉を持ってるわけですよね。魚の動きから、風の流れ。それはわたしがわからないだけで。で、残る言葉、自分を支えているっていうか気になる言葉っていうものが同じではないにしろ、配置が同じだから気になるんじゃないですか。この言葉を歌ったとか、あるいは「何でここにこういう言葉があるの?」とか(笑)。で、「何でここにこういう言葉があるのか」っていう、自分の番号とあってるんじゃないですか? そこに反応してるんじゃないでしょうか。
(注)
「うたは闘いとともに」、1950年代に日本で大きく展開された、おそらく唯一の政治的な大衆音楽のムーヴメント。三上寛は自分の音楽の源流のひとつをこのうたごえ運動にも求めている。
取材:野田 努(2012年3月09日)
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE