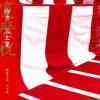MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
Home > Interviews > interview with Kan Mikami - もうひとりの、“日本のパンク”のゴッドファーザー
つまり中津川で歌ったときに、このまま世のなかにばっと広がっていくんじゃないかと思いましたよ。で、3年ぐらいその気でいたら、まわりを見たら誰もいなかったっていうのが、まあ現実でしたね。それはものすごくショックだったですね。
■で、もうひとつ今日テーマにしたかったのが、三上さんが「田舎」というものをどのように考えてらっしゃるか、っていうのを聞きたかったんです。というのは、たとえばいまのミュージシャンの音を聴きますとね、シティ・ポップスが多いんですよね。シティ・ポップスが悪いとはべつに思わないんですけれども、たとえばアメリカだとカントリーという田舎の音楽が若いひとたちにいまも支持されている。ブルースなんていうのはまさにメンフィスの音楽であって、僕はデトロイトの黒人なんかと話す機会が多いんですが、彼らは北部の工業都市で暮らしていてもいつかはメンフィスの田舎に戻りたいという気持ちを持っているんですね。あるいは、イギリスだったらアイリッシュ・トラッドとかケルト文化が、ビートルズの曲にもレッド・ツェッペリンの曲にも、いまのテクノにも出てくるわけです。つまり権力に対抗するときに、欧米の音楽はいまも田舎を持ち出すんです。それが日本で「田舎」というと、「田舎もん」という言葉が侮蔑の言葉として使われているように、いっぽうで田舎は美化されながら片方では否定されているような、奇妙な意味を持ったものになってます。三上さんの音楽は、そういう意味では、日本が隠蔽したがる田舎を物凄く開放しているというか、さらけ出している。さっきも漁師っていうものが自分にとっては重要だからとおっしゃっていましたが、漁師が重要だというミュージシャンに初めてお会いしました(笑)。とにかく、三上さんには周縁化されてしまった「田舎」というものに対する何か強い気持ちを感じるんですよね。
三上:ありますね。その、何て言うんでしょうかね......。まず「田舎もん」というのはだんだんなくなりましたよね。要するにイギリスで「ジェントルマン」っていうのは「田舎もん」って意味らしいのよ。要するに3代も前のじいちゃんの三つ揃えを着て、こんな帽子かぶってるっていう(笑)。まあそれはいいとして、ミュージシャンにとってそれはいますごく重要な話ですよね。要するにね、ロックっていうのはほとんど田舎もんですよね。まずエルヴィスがそうでしょ、ジョン・レノンもそうじゃないですか。イモなんですよ。イモのパワーなんですよね、音楽って。
■ハハハハ(笑)。
三上:ええ。土着のパワーなんですね。というのは音楽っていうのは元々作物ですから。やっぱり土地がないと生まれないんですよ。音楽って大根と同じですよ。それがいちばん顕著なのが声質でしょ。これは田舎の声なんですよ、わたしの声は。ジョンはね、アイリッシュとかケルトとか、あの声なんですよ。
■イギリス人ではじめてロックを歌うときに、アメリカ訛りでなくイギリス訛りで歌ったひとがジョン・レノンって言いますよね。
三上:そうでしょ。あれも完全に田舎ものの声なんですよ。あの潮枯れしたようなね。エルヴィスなんかも南部の畑のなかで、音楽でカッコつけてたやつの声ですよ。よくいるじゃないですか、田舎で音楽でカッコつけるやつが(笑)。
■黒人のブルースもまさに黒人訛りなわけですよね、南部の訛り。
三上:だって黒人の声なんていうのは完全にアフリカの作物でしょう。
■ははははは!
三上:そうだと思うんですよ、わたしは。
■たしかに(笑)。レゲエに至っては完全にジャマイカ訛りでね、ほんと堂々としてますよね。
三上:そういう意味で言うとね、音楽は都会からは生まれないですよね、だって作物ないわけですから。消費文化でできてるわけですから。でしょう? 世界に話広げなくたって、日本でもそうですよね。わたしのような声、それから九州の連中のような声。わたしはああいう甲高い声出ませんし、これはもう声聞いただけでわかるっていうぐらいですよね。どこの出かっていうのはね。だからわたしは「あんたどこ出身?」っていうのはね、声で想像を巡らすっていうのがあるぐらいですよ、ええ。
田舎っていうことで言えば、それはねえ、どうなんですかねえ。結局日本はみんなね......わたしなんかも最近ふと気づいたことなんだけれども、やっぱりそれはあれでしょ、近代化っていうことでしょ。要するに明治維新が起きて、それまでは藩っていうものが、田舎がそこのポップだったわけですよね。標準語も何もない。
そうじゃなくて、近代的になるっていうことは、なるべく同じヨーロッパ・スタイルと言いますか――まあヨーロッパだって普通に田舎だけどね、ほんとはね(笑)――そういうものにしようじゃないかっていうことで、自らが田舎を否定しようっていう流れに乗ってしまったんですよね。もっと詳しく言うならば、田舎にはね、死があるんですよね。ひとの死があるんですよ。近代化っていうのは死から遠ざかることだって言ったひとがいますけれども、死人からつき離れていく状態ですよね。田舎イコール死人ですよ。父が死に、母が死に、兄弟が死に、っていうね。都会ではやっぱり、そういう意味では死はないですよね。養老孟司も言ってたけれども、都会とは言ってないけれども、いまある死はただの「数」だってね。死ぬのは他人ばかりですよね。今日何人死んだって新聞に出ているのが死であって、あのおばあちゃんが、俺と同じ景色を見た母親が死ぬっていうのとは、死の概念がぜんぜん違いますよね。
■たとえばイギリスなんかはね、アイルランド人とかってイギリスでは下層階級なわけですよね、白人でもね。主流では差別されてる。しかし、アイルランドとかスコットランドとかみたいなイギリスの上流階級が馬鹿にするようなひとたちを、「あいつらこそ最高だ、あのアイリッシュ・ソウルの素晴らしさを見ろ」っていう風にむしろ言うひとが同時にいるわけですよ、とくに音楽のシーンには。三上さんの音楽っていうのは、日本の近代化のなかで周縁に追いやられてしまったものを同じように取り戻そうとしているように感じるんです。
三上:これもっと話を広げるとね、結局東洋と西洋っていうものになっていくと思うんですよね。つまり仏教国とキリスト教みたいなことになっていくんじゃないかと思うんですよね。ていうのはアイリッシュなんかでも、元々は発祥はインドのほうですよね。東洋人なんですよ。これはヨーロッパのひとなんかもびっくりして。あの文化っていうのはやっぱりインドのどっかから発祥してる。ケルト民族なんていうのは、だから我々も不思議とわかるヴァイブレーションっていうものがありますし。日本の唱歌なんていうのは、ほとんどアイルランド民謡ですよね。
■ああ、そうですよね。スコットランドも多いですよね。
三上:何でアイルランドなんだろうと考えたら、血が呼び合うっていうんですか(笑)。結局我々はいま、どっちを選ぶべきかになってるんですよね。いま田舎ってものをもういちど見直そうってなるってことは、大きい意味ではヨーロッパ的な洗練された文化っていうものの反対を見ているわけですよね。反対ですからね、都市と田舎っていうのはね。田舎っていうのは土着的であり......もっと言うと、科学なのか自然なのかですよ。簡単に言うと。
■しかもまた都会っていうことで言っても、三上さんが住まわれた60年代や70年代の東京といまの東京ではまるで違いますからね。
三上:そう、そう。ただわたしは、土着がサイエンスだと思ってるんです、わたしはね。それは無知なだけで、我々が。
わたしが田舎に帰りまして非常に面白いこと発見しましたのはね、青森津軽町にイタコっていうのがいるんですよね。シャーマニズム的な。わたしはそういうものが嫌いで東京に出てきたわけですけれどもね、ところがあるとき何かの取材でそういうことをしたら、イタコが何かこういうことをやってるわけですよ。ひとがこういっぱいいて、で、わたしの隣にね、50ぐらいのひとかなあ、まあ百姓の親父が寄ってきましてね、「どうやってやるもんですか、どうやってイタコの話を聞けるんですか?」と。だからちょうど5~60代のひとはやり方がわからないんですよ。昔のばあさん連中は行って、イタコの前にいくらか出して「お願いします」って言えばやってくれるんだけど、そのひとは知らないわけだな。そういう文化にいないし、また忌み嫌ってたっていう。その男にですね、ばあさんの前に行っていくらか出せばやってくれるんじゃないのって言ったら、「ああそうですか」って言って、イタコのところに座って千円札かなあ、それを出して、座ったと途端に「わー」っと泣き出したんですよね。その親父がね。そのときにね、これはある種天然の都会だなって思ったんですよ。
要するに、想像するに彼は百姓の長男で母親を亡くしてるわけですよ。ところが百姓のうちっていうのは個人の部屋がないんですよ。ひとりだけでこもるなんてことがないんですよ。ガラガラなわけでしょ。で、長男は泣いちゃいけないんですよ。田舎の長男は母親が死んでも泣いちゃいけない。泣く場所がなかったんですよ。だからやっと泣けるわけだ。だから、イタコの前で泣くことには誰も後ろ指を指さないわけね。要するに気持ちの便所ですよ。それは音楽と同じですよ。音楽聴いて泣くのはいいんですよ。ところが一歩外に出たらね、泣いたら負けるんですよ。弱みと受け取られますからね。ちゃんと都会で音楽があるように、田舎には泣いてもいい場所がちゃんとあるんだっていうのは、これは非常に合理的ですよ。
■ゴスペルと同じような社会的な機能をしているんですね。
三上:でしょ? 泣いてもいいんだと思うんですよ。決してそれは人生に負けたことでもないし、闘いを放棄したわけでもない。
■行き場をなくした感情を開放してるんですよね。
三上:そういうことですよ。つまり、ガス抜きですよね、ある種のね。
■なるほどね。で、そういうことで言うと、三上さんがよくシュールレアリスムという風に昔おっしゃられてますけど、それこそ初期の頃の曲には、それこそ、「チンポ」「まんこ」「センズリ」......。
三上:近親相姦。何でもあり。さすがにカニバリズムはね、あれは都会のもんですから。うちらは畑に撒くものですから(笑)。
■はははは(笑)。とにかく夥しい放送禁止用語のリストがあるわけですけれども、これも田舎と同じように、タブーに挑戦していたというか、表現における自由の限界を試していたようにも思うのですが。
三上:そうですね。まあ......シュールでもダダでもね、要するにヨーロッパのああいう芸術運動ってのはね、ほんとに土着みたいなところから出てるんだよね。日本に来たりすると何かカッコいいものに見えたりしちゃうけれども、ああいうある種のデタラメって言うんですか、起爆力って言おうか、新しいものが。で、俺が使ったのもスラングでしょ。つまり日常会話じゃみんな言ってるわけですよ。
■そうですよね。しかもこれだけ時間が過ぎたいまでもパブリックになると包み隠されてるっていうね、おかしな話で。
三上:そうですよ。だからそれは自負がありますね。わたしからだろうな、こういうことをやったのは。それまでは、音楽の作詞っていうのはちゃんとありましてね、まず「センズリ」なんていうのは歌詞じゃないっていうね(笑)。わたしが歌う前はそうでしたよ、ちゃんと歌詞の作り方があるんだみたいなね。それが寺山さんの一言でね、「いや、いいんだ」っていう。そういうスラングでいいんだっていう。それはほら、寺山さんなんかが洗礼を受けたビートニクなんかがちょうどね、アメリカ60年代であって。それまでもギンズバーグ以前でも、ファックだのプッシーだのやってませんよね。それもわたしのあれも外来なんですよね。いきなりじゃなくて。筋というか流れで言えば(笑)。
■それにしても「キンタマは時々叙情的だ」は名文句ですけどね(笑)。
三上:それはまあそうですよね(笑)。だからあの当時の現代詩なんかは、「キンタマ」でも「女陰」でもそういったものがアカデミックな使い方をされてたんで、そこでああやって金玉を叙情的にしたんでしょうね。まったく遠いものを。
■ははははは。何でしたっけ......「荒波や 佐渡に横たふ わがチンポ」とか、最高っす(笑)。
三上:ひどい歌だよね(笑)。
■僕、すごく感心するんですけど、あれだけ「オマンコオマンコ」っていう、「女なんてやっちまえばいいんだ」っていう。ああいうのもひとつの逆説なわけじゃないですか。
三上:まあそうですわな。
■パラドックスですよね。日本社会の封建的なものに対する逆説的な表現としてあって、で、ちゃんと三上さんは中山千夏さんという、あの当時のフェミニストの代表格のひとりにもちゃんと理解されてるんですよね。中山さんのアルバムに参加してますもんね。
三上:だから千夏なんかにもさ、「結局寛しかいないね、女のことちゃんと考えてくれてるの」なんて言われて。わかるやつにはそうなんだよな(笑)。わかるやつって言っちゃあおかしいけれども。
■それを考えると、いま大衆文化の空間で話されているボキャブラリーっていうのは、ずいぶん見事にまた統制されてきてしまってるんじゃないかっていうね。
三上:そうですね。いまのポップスがこういう風にちゃんとなっていけばいくほどね、結局、「いったい何が失われていくんだろうな?」っていうのを考えるとね、意外とね、本当の意味でのエンターテインメントっていうのがなくなっていくんですよ、これが。不思議なことに。わたしはアンダーグラウンドっていうかサブのほうでやってきた立場なんでしょうけれども、わたしはエンターテインメントの視点っていうのは忘れてないんですよ。あれはあれでまた、狂気っていうものがないといけないし、やっぱりこのままだと第二のマイケルなんて生まれないだろうっていうぐらい。マイケルだって相当おかしいやつですからね(笑)。
■黒人音楽の芸当に対する思いはすごいものがありますからね。
三上:でしょう。それが表現以前に、何て言うんでしょうかね、エンターテインメントってことは、わたしももちろん他人事じゃ言えませんけどね、我々との結びつきって言いますか、アングラとの太い絆って言いますか(笑)、あるんですよ、これが何となく。
■たしかに三上さんのステージを観ると、エンターテインメントってことをすごく意識されている。
三上:意識しますよ。そこがギリギリわたしがノイズ・ミュージックと離れる部分でね。やっぱり完全なアートになりすぎないっていう。それはやっぱり街のもんだっていうのがありますよね。エンターテインメントっていう考え方がこれを支えてくれてるっていう、どこかでね。オールアートって行くとあれはやっぱりどこか閉じこもって、2、3年かけてCD1枚作ってさ、「どうだ」っていうので気が済むわけですよね。それはちょっと違うんですよね。やっぱり自分を支えた言葉っていうのは、全部エンターテインメントのひとたちですよね。わたしを支えてくれたのは。
■寺山さんも歌謡曲やってますしね。
三上:寺山さんもそうですしね、モハメド・アリの「チャンプ、次はいつの試合だ?」って「町のひとと相談する」というのも「いいなあ」って。アリが「次のボクシングの試合はいつだ」っていうのを聞くのはプロモーターじゃないっていう。町のひとに聞くっていう、「これは何だろう、町のひとと相談するのか」って。「そうか、町でいいんだな」って思ったり。それはいろいろありましたね、エンターテインメントとかそういうものに支えられたっていうものはありますよね。
■なるほど。そのエンターテインメントの変遷で言いますと、三上さんは「ストリッパーはいない」と歌われてますけど、やっぱりストリッパーとAVとの確固たる違いっていうのはあると思いますか?
三上:そうですよ、それは手書きとワープロの違いみたいなもんじゃないでしょうか(笑)。
■ははははは。
三上:要するにストリップにはほら、死があるじゃないですか。バッと開いてさ、あそこで生まれるものはエロスっていうか、死があって。AVには想像力とかね、そういうものが必要でしょ。死っていうのはまたちょっと違うよね。だからエロスつうもんでもないような気がしてますけどねえ。うん。あれはある種こちら側の想像力で成り立っている世界であって、そのものがどうのっていうもんじゃないですよね。まあもちろんストリップもたしかにそうだけれども、ストリップはもっと強引でしょ。想像を拒否するわけじゃないですか、だって、バカッと開くわけですから(笑)。「参りました」しかないわけでしょ(笑)。
■ハハハハ! ほんとそうですよね(笑)。
三上:そういう部分かもしれないですよね、エンターテインメントっていうのはある種強引に語りかけていくっていうのがあるんじゃないですか。観客を圧倒しちゃうってことじゃないですかね、おそらく。独裁ですよね。
■はははは。三上さんの音楽っていうのは「怨歌」という言葉で形容されてますけれども、そもそもその言葉はどこから出てきてるんですか?
三上:その論争が起きたのがちょうど70年代ぐらいなんですよね。「演歌とは何か?」みたいな。誰もそんなものを一流誌で議論する以前の歌だったわけでしょう、あれは民衆の歌、まさに漁師だったり百姓だったりが聴く音楽であって。もちろん都会のひとも聴く。そこにインテリたちが入り込んできたわけですわな。「演歌とは何だろう?」、「怨みなのか? 演ずるなのか?」と。それは五木寛之さんなんかが入ってきたことで。ヤクザ映画なんかもそうですよ。何かいままでサブカルチャーというか、下々のものだったものが、さっきの質問の通り「この力は何か?」ってことですよね。みんな気になっちゃったんだと思いますよね。
で、あの当時それからだけども、大衆演劇なんて観に行くやつをみんな馬鹿にしてたものでしょ。つまり、踊って村祭で行くひとたちを。いまやもう歌舞伎座で公演やるぐらいになるわけじゃないですか。インテリがやって来るわけですからね。それは嗅いでるわけですよね、力をね。きっと。だからいまの話が全部繋がると思うんだけれども、パワーだったり、死だったり、自分の遠い遠いルーツだったり。つまりひとっていうのは自分のなかに物語がないと生きていけませんよ。どんなひとでも。そのネタがないんだよ、いま。それが「田舎」だったりね、そういうもののなかにあるんですよ。いままで差別したり軽蔑したり蔑んできたもののなかに自分たちの物語があるんですよ。それらを無視してきて、物語を作れなくなって、それで占いブーム宗教ブームでしょ。代わりにストーリーを作ってくれたものに黙って入っていけばいいわけですから。そしてそれも崩壊するわけでしょ。そうすると、もちろんコンクリートの上でも物語ははじめられると思うけれども、人間ってもっとヤワですから。だって我々の腹を切ったらもう臭いんですから。ただの糞の塊ですよ。だからそういうことに気づいてきたっていうことですよ。でないと物語を作れない、自分を成立できないんですよ。
取材:野田 努(2012年3月09日)
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE