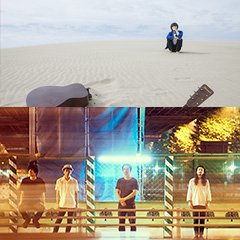MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Shugo Tokumaru - 会話をはじめた音たち
だんだん自分の音の1個1個のなかにオリジナルをちょっとずつ超えてるものがあるのが見えたりすることもあって。たとえばリズムであったりメロディであったり。それをちょっとずつ積み重ねて、組み合わせていってみよう、それがわりと間違いじゃないと考えられるようになってきましたね。
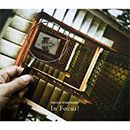 トクマルシューゴ In Focus? Pヴァイン |
■"Gamma"って曲を聴いたときに、マリンバ風っていうか、パーカッシヴな心地よい音が入っていて・・・ブラジルのウアクチってバンドご存じですか?
トクマル:はい、はい。
■彼ら、ビニール・パイプとかで打楽器みたいなの作ったりしていますけれども、そういうものに通じるような気がしたんですが、特に関係はないですか?
トクマル:これはパーカッシヴなイメージと民俗っぽい音色を足して、子どもが喜びそうな、スピーディでわかりやすいメロディを作ってみたいと思って。
■トクマルさんはいっぱい音楽を聴いていらっしゃると思うんですが、世界には伝統的なスタイルのポピュラー・ミュージックがたくさんありますね。それぞれ独特の間とかリズムを持っているんだけど、そういうものを真似ようというつもりはないんですよね? 、「トップランナー」というテレビの番組に出られたとき、観客の人たちに手拍子を打ってもらうくだりがあって、あれはキューバ音楽のクラーべというパターンに近いものですよね。
トクマル:そうですね。
■でも、曲自体はキューバ音楽とは縁もゆかりもないという(笑)、その組み合わせがおもしろいなと思ったんですね。日本人は几帳面だから、自分が素晴らしいと思う音楽があったら、勉強してまねることができちゃう。けれど、そういう方向性じゃないですね。トクマルさんが几帳面じゃないという意味ではないんですが。
トクマル:ぼくも、どちらかというと几帳面で、はじめはまず完全に真似てみたりするんですよ。
■あ、そういうプロセスを経てるんですか。
トクマル:いちど完全に真似てみて、でも聴き比べてみると、やっぱりどう考えても追いつけないレベルだったりするんです。結局それはぼくでしかないというか、ぜんぜん本物の音楽の足元にも及ばないなって気づいてしまうと、やっぱり人には聴かせられないというか。でもそういう作業をいっぱいしていくと、だんだん自分の音の1個1個のなかにオリジナルをちょっとずつ超えてるものがあるのが見えたりすることもあって。たとえばリズムであったりメロディであったり。「あ、この音楽にはないけど、僕の作ったものにはちょっといいメロディがあるな」とかって思えたものをちょっとずつ積み重ねて、組み合わせていってみよう、それがわりと間違いじゃないと考えられるようになってきましたね。
■リズムの面でも音色の面でも、ロックだけやっている人よりずっと間口が広いですよね。トクマルさんの音楽をロックと呼ぶのかどうかわからないんですが(笑)。今回はいつもより各地の伝統的な生楽器の音が目立つようには作ってあるかなと思いました。これは意識されていたんですか?
トクマル:さっきの音の人格化の話のつづきのようでもありますけど、だんだん(アルバムのなかに)いろんな世界の人たちを住まわせよう、みたいな感覚になってきて。たとえば東南アジアの人とか南アメリカの人とかを、ちょっとだけ限定的に、現実寄りに想像してみたときに、南アメリカなら南アメリカの楽器を持ってきちゃおうと思ったんです。それでその音を入れてみたら、いままでのアルバムよりもうちょっとだけ現実味が出たというか。
■あまりアーティストに曲のことをこまごまときくのは申し訳ないんですけれども、"Decorate"という曲はどのようにしてできたんですか?
トクマル:ジャケットのデザインもそうなんですが、螺旋というか、円というか、回っているという自分のなかのイメージを再現したものですね。ちょっとサビも強めの曲を作ってみたいなと思って。
■アレンジの段階で、ラテン系の曲とかあるいはカリプソなんかを参照にするようなことはあったんですか?
トクマル:特別にこれということはないんですが、今回はわりとそういうものが残りましたね。
■スティール・パンっぽい音の聴こえる、"Call"ですとかね。"Shirase"は、ちょっとフォルクローレっぽい。他にアメリカの伝統的なフォークを思わせるものもあるし、サンバっぽいものもある。一枚岩ではぜんぜんないですね。10代の頃はアメリカにいらっしゃったそうですけど。
トクマル:アメリカに行ったのは、そもそもアメリカの古いミュージシャン、レジェンド的なミュージシャンを観たいと思ったのがきっかけだったんです。
■古いというのはどのあたりの?
トクマル:たとえばジャズの大御所......エルヴィン・ジョーンズとか。演奏できるおじいちゃん、他にも日本に来ないような人たちがいっぱいいたので。来てもブルーノートとか、大きなところでしか観れなかったりしましたし。そういう人たちを身近に、真後ろとかから観たい! と思いました。そうするとサポート・ミュージシャンが南米の人たちだったりすることが多かったし、連れまわっているので、どうしても目が行っちゃうんですよね。そういう人びとに惹かれたというのが、当時の体験として強く残っていますね。
■そのあたりから南米の音楽も聴きはじめたということですか。
トクマル:はい。特にキューバ、行きたいなと思ってるんですがまだ行けてないんですよね。
■アメリカに行ったらキューバや南米の人たちとかがいっぱいいた、という感じなんですね。
トクマル:そうですね。いてくれた、という感じです。それ以外にもさまざまな国の凄腕ミュージシャンたちが集まっていて、その体験は大きいですね。
■レコードやCDをこっちでたくさん聴いてから行ったというよりは、まず向こうで生で体験したことなんですね。
トクマル:そうですね。ギターから入ったので、ギター・ミュージックの中に入っているパーカッションってイメージで、ラテンの音楽も聴いていました。生で聴くと、CDに入らない音っていっぱいあるんだなって思うことがありましたね。そこでしか伝わらない......音というか。そういう体験がはじめにありました。
文:北中正和(2012年11月07日)
Profile
 北中正和/Masakazu Kitanaka
北中正和/Masakazu Kitanaka1946年、奈良県生まれ。J-POPからワールド・ミュージックまで幅広く扱う音楽評論家。『世界は音楽でできている』『毎日ワールド・ミュージック』『ギターは日本の歌をどう変えたか―ギターのポピュラー音楽史』『細野晴臣インタ ビュー―THE ENDLESS TALKING』など著書多数。http://homepage3.nifty.com/~wabisabiland/
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE