MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Kenichi Hasegawa - 極北の歌のなかの光景
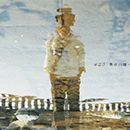 長谷川健一 423 Pヴァイン |
2010年の『震える牙、震える水』はうたものあるいは弾き語り“群”、といういい方が正しいかはわからないが、在京都のシンガー・ソングライター、長谷川健一は、そろそろそうなりつつあった歌手たちのなかでも異彩を放っていた。静かで美しく透き通った歌の数々に、私はその3年前の〈map/comparenotes〉からの2枚同時リリースのミニアルバム「凍る炎」「星霜」を見過ごしていたのを悔やみつつ、まだこんな歌い手がいるのか、京都という街はまことに底知れぬものよ、と詠嘆調で独りごちたのである。そこから2年、長谷川健一のセカンド『423』は、初期集成的な位置づけの前作からさらに進んだ歌の地平にある。世界観とかいう知った顔の言葉ではない、奥行きのある情景があり、歌のなかに暮らすひとびとの目からそれを描く。目に映る光景は移動していくが、ロード・ムーヴィ的というのではなく、1曲目のタイトルにもなっている“あなたの街”が歌のなかに突如現れるような感じである。音楽は前作よりも、余白をつくり、石橋英子(ピアノ)、山本達久(ドラムス)、波多野敦子(ヴァイオリン)、石橋英子ともう死んだ人たちの面々が色を、しかし淡色の色を添える。プロデュースはジム・オルーク。今回、インタヴューして、長谷川健一の音楽遍歴を知って聴き返すと、前作から今回にかけて、多大な影響を受けたというジェフ・バックリィやフリージャズの要素は完全に声と音と言葉の響き合いに昇華されていることに気づく。そしてやがてそれらさえ歌になってふりそそぐのである。
基本というヘンですが、何かが足りないからひとりというのではなくて、ひとりでつねに100パーセントという感じを、ジェフ・バックリィに感じたので、ひとりでやることに抵抗はなかったです。
■長谷川さんの前作『震える牙、震える水』を拝聴しまして、めずらしいタイプのシンガーだと思いました。こと日本においては、といういいかたをしていいかはわかりませんが、昨今のフォーク・ブームには長谷川さんはあまりそぐわない存在なんじゃないか、と思いました。
長谷川:だと思います(笑)。
■歌の歌い方にしろ、歌に描かれている世界にしろ、そういうものがどこから来たのか気になりました。歌いはじめたのはいつくらいからだったんですか?
長谷川:大学出るころなので、15年くらい前ですかね。
■1976年生まれですよね。
長谷川:そうです。もともと歌謡曲だったり、そういうものは聴いていたんですけど、フリージャズとか即興とか、わりとそういう音楽にのめりこんだ時期があって、それが二十歳すぎとかですかね。
■フリージャズというと、ジャズの十月革命とか〈ESP〉とか、そういった感じですか?
長谷川:阿部薫がすごいなと思ったんです。そういうひとたちをたどっていって、現役のフリージャズのミュージシャンを観に行ったりしました。高木元輝さんとか、観に行ったちょっと後に亡くなったり、そういったこともありました。
■フリージャズを聴いて弾き語りをはじめるのもめずらしいと思いますが、ちなみにハセケンさんはそのとき楽器をやられていたんですか?
長谷川:オヤジがずっとクラシック・ギターをやっていて、中学2年のころ、ガット・ギターをもらったんです。家にさだまさしの本があって、弾いてみたいんですよ。“秋桜(コスモス)”だったと思うんですが、あんまりおもしろくなかった。それでちょうど高1のころに尾崎豊が死んだんです。それまで知らなかったんですが、聴いてみたら、気に入って、『弾き語り全曲集』を買ってきたら、シンプルにつくっている曲が多かったんですが、なかには本人が歌ったものに、アレンジャーか何かがピアノで合わせたんじゃないかな、という曲もあるんですね。そういった曲のコードを全部ギターに置き換えているものもあるので意外と複雑だったりもする。和音をひと通りそこで覚えて、そうしているうちに曲をつくりたいなと思うようになったんですが、フリージャズも聴いていたので、好きな音楽とやりたい音楽をどう折衷するか、という課題がめばえました。いま思えば、折衷しなくてもいいんですけど(笑)。
■たしかに(笑)。
長谷川:若かったのかもしれません(笑)。それまで僕は宅録していたんですね。ベースとかほかの楽器も全部自分で入れていたんですけど、バンドは組んでいませんでした。それで、テープをあげたひとに、ライヴやらないんですか、といわれて、じゃあやろうか、と。消極的に(笑)、はじめたんです。人前で歌ったことがないので、恥ずかしいし、技術もなかったので、ムチャクチャ練習しました。そのころから、ファルセットを使っていたんですね。ジェフ・バックリィはご存知ですか?
■もちろんです。
長谷川:僕はジェフ・バックリィが大好きなんですね。他にはブラック・ミュージックとかが好きなので、男の裏声って好きだったんですけど、いざ弾き語りとか、うたものを聴いているひとの前で出て歌ったときに、なんだこれは、という反応があったんです。15年前ですから、平井堅とか森山直太朗とかがラジオで流れる時代でもなかった。そのときから声質は変わりましたが、スタイルはあまり変わっていないんですね。
■好きな音楽の影響から自然とそうなった?
長谷川:家で音楽を聴きながら歌ったりしているうちに、わりと普通にそうなりました。自分でも曲をつくっているうちに自然にできたというか。そこはあまり意識してはいなかったです。高いところを歌うから高い声を出すんだ、という単純なものでした。
■曲のイメージに身体を合わせていったんですね。
長谷川:身体を改造していくというか(笑)。
■ジェフ・バックリィの『グレース』が出たのは90年代前半(1994年)ですよね。
長谷川:はっきり憶えていないんですけど、ジェフ・バックリィがデビューしたとき、テレビで“グレース”が少しだけ流れたんですね。7時54分とか、番組の合間の数分の音楽番組だったと思います。それを聴いて、不思議な音楽だな、と思ったんです。高校生のときは『ロッキング・オン』を読んでいて、そこに情報が載っていたので、CDを買って聴いてみたら、すごかった。彼はバンド・サウンドでもやっていますけど、彼の弾き語りがすごい表現力だと思ったんです。ひとりでこういった世界観がつくれるんだ、と。そういうのが最初にあったので、出発がひとりだったんです。
■それが指針になった?
長谷川:基本というヘンですが、何かが足りないからひとりというのではなくて、ひとりでつねに100パーセントという感じを、ジェフ・バックリィに感じたので、ひとりでやることに抵抗はなかったです。
■バンドを組む必然性は感じなかったということですね。
長谷川:バンドというよりも、まわりには即興をやっているひとが多かったんですよね。バンドを組んで、歌ものをやっているひととはあまりつきあいがなかったんですよ。
取材:松村正人(2013年3月05日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE


