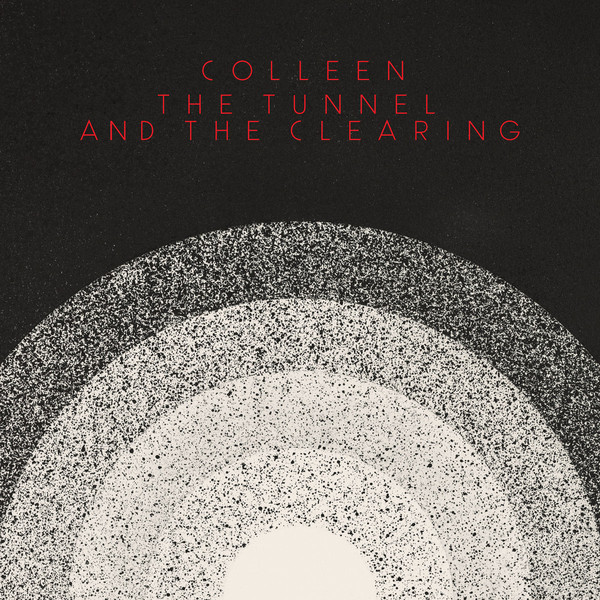MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Colleen - 炎、わたしの愛、フリーケンシー
年末に刊行されるele-king vol.23では「non human」というテーマの特集を組んでいる。近年の音楽、とくにエレクトロニック・ミュージック周辺では、「人間以外」をテーマにした音楽が目立つようになっている。OPNが人類滅亡後の世界を空想したり、このご時世、ダーク・エコロジーを反映した音楽は少なくない。日本でもceroが動物たち(人間以外の生命)のことをテーマにしたり、少し前ではビョークが自然をテーマにしたり、そんな感じだ。詳しくはぜひ本誌を読んでいただきたい。ここではその予告編もかねて、去る11月に来日したコリーンのインタヴューをお届けしよう。
だれかにもっとも美しい音楽を聴きたいと言われたら、ぼくならコリーンの『A Flame My Love, A Frequency(炎、わたしの愛、フリーケンシー)』というアルバムを差し出す。2017年の年間ベスト4位にした作品(ちなみにFACT MAGは2位)。これだけ消費スピードが速いご時世において、いまでも聴きたくなるし、じっさいいまでも聴いているたいせつな1枚だ。彼女が来日すると知って、これは取材せねばならないと思った。11月初旬のことである。
もっともぼくにはほかにも推薦したいアルバムがもう数枚ある。2013年の『The Weighing Of The Heart(心の計量)』は間違いなくその1枚に入るし、2015年のダブにアプローチした『Captain Of None 』も、初期の作品では『Les Ondes Silencieuses(沈黙の波)』もぼくは好きだ。ヴィオラ、チェロ、クラシックギター、こうした弦楽器の音色とエレクトロニクスとの有機的な絡み合いから生じるおおらかな静寂が彼女の音楽の魅力である。
コリーンことセシル・ショットは1976年パリ郊外で生まれ、2年間イギリスで暮らし、そしてパリに移住し、現在はスペインに住んでいる。日本には2006年の11月に来ているので、今回は彼女にとって12年ぶりの2回目の来日となるわけだが、彼女が泊まっているホテルは渋谷の公園通りを上がっていって少し脇道に入ったところにあった。通りの向こう側では、建設中のビルがインダストリアルなビートを打ち鳴らしている。なんともアイロニカルなシチュエーションだなと思いながらロビーに座って待っていると、彼女は爽やかな笑顔でやって来た。ぼくは彼女にいかに自分があなたの音楽好きかを説明し、2017年の年間ベストでは『A Flame My Love~』を4位にした旨を話ながら誌面を見せた。5位が坂本龍一の『async』であることを見ると、「FACT MAGでは坂本が1位でわたしが2位だった。知ってる?」と言った。それから「うん、ジェイリンが3位は良いね」「じゃ、1位はなんでしょう」とページをめくってコーネリアスであることを確認すると、ひとこと「わお、ナショナリスティック!」とおどけた。なるほど、こういうリアクションもあるのかとぼくは妙に感心した。
わたしは反消費主義。たとえば、服は全部自分で作る。(着ている服をつまみながら)これも、これも、このジャケットも自分で作ったものよ。基本的にショッピングとかしない人間なの。
■渋谷は、世界でもトップクラスの過剰なまでの商業都市で、あなたの音楽性とは真逆の世界でもあるんですが、滞在していてどうですか?
C:答えるのは難しいな。渋谷でじっくり時間を過ごしたことがないから。商業地区は避けるようにしているの。できるだけミニマリストな生き方をしたいからね。わたしは反消費主義。たとえば、服は全部自分で作る。(着ている服をつまみながら)これも、これも、このジャケットも自分で作ったものよ。基本的にショッピングとかしない人間なの。だから渋谷や商業地域で時間を過ごすことがないから、そこがどうなのかわからない。この後、谷中や上野に行こうと思っている。わたしが好きでいつも行く場所よ。東京が魅力的なのは、たとえ渋谷や原宿でも路地裏に行けば低層の建物が並んだ、味のある街並みがまだ残っているところ。パリだとすべてが高い建物で覆われてしまって、小さい住宅はもうほとんど残っていない。わたしから見ると、東京にはまだいくつか孤立した穴場があって、木造の掘っ建て小屋のような個性あふれる風景が残っている。
■あなたの音楽が好きなのは、ぼくがふだん見ている世界とは違った世界が見えるからなんですね。この世に感情がかき立てられる音楽があるとしたら、あなたの音楽は世界が広がる音楽なんです。たとえば『Les Ondes Silencieuses』のアートワークには植物や星や動物が描かれている。あなたは動物や風や珊瑚や砂の音楽も作っている。
C:それはわたしにとっては大変な褒め言葉ね。わたしにとってひとりの人間としての進化とひとりのミュージシャンとしての進化は完全に連動している。そのふたつを切り離すことはできない。そして歳を重ねるにつれ、自然をより身近に感じるようになって、生きていく上で欠かせないものになった。たとえば、『Les Ondes Silencieuses』の後、わたしは音楽面そして個人的にも重大な危機に直面して、しばらく音楽を作るのをやめた。あまりに早いペースで物事が進んでいると感じたから。そしてまた音楽を作りたいと思えるきっかけを作ってくれたもののひとつが他の表現方法に身を置くことだった。だから陶芸と石彫を勉強した。そしてもうひとつは、より純粋で素朴な生き方をすることだった。
仕事とプライヴェートのバランスを見つけるのに日々悩まされるわ。わたしにとってプライヴェートの生活のなかで調和をとるのに役立つのが自然と接することなの。だからバードウォッチングをするんだし(※彼女の趣味で、取材の前日は代々木公園で野鳥の観察をしている)。もちろん鳥が大好きだからなんだけど、自然のなかにいると、自分のことについて考えるのを忘れるのよ。自分のあるべき姿により戻してくれる。大きな宇宙のなかでわたしたちというのは本当にちっぽけな存在でしかないのに、日常のなかでわたしたちは自分たちのことに囚われすぎてしまう。だからわたしとって自然を愛すること、そして自然界に生きる動物たちは当たり前のもの、うまく説明できないんだけど、自分を癒してくれる存在なの。わたしは瞑想を実践してはいないけれど、自然のなかにいて自然を見ていると、瞑想しているみたいに思える。心を癒してくれる薬のようなものね。だから、宇宙のなかに存在する他の生き物たちの存在を音楽のなかに感じ取ってくれたのなら、それは本当に嬉しいことよ。

わたしにとってひとりの人間としての進化とひとりのミュージシャンとしての進化は完全に連動している。そのふたつを切り離すことはできない。そして歳を重ねるにつれ、自然をより身近に感じるようになって、生きていく上で欠かせないものになった。
■あなたの音楽は、いくつかの生の楽器とエレクトロニクスとの融合だと言えますが、人間とテクノロジーの関係をどう考えていますか?
C:テクノロジーは我々の感情表現や生活を便利にするための道具として使うのであれば素晴らしいものだと思う。音楽という観点で見たとき、PCや誰もが使えるソフトが存在しなければ、わたしはレコーディング・アーティストになっていたとは思わない。わたしはテクノロジーをDIYのツールとして興味を持っているけど、決してテクノロジーに傾倒している人間ではないわ。たとえば、わたしはスマートフォンを初めて手にしてからまだ2年も経っていないのよ。ずっとスマートフォンなんて要らないと思っていた。2年前に、必要に迫られて持つようになっただけ。
制作面に関して言うと、テクノロジーとの関係性は5作目の『Captain of None』から変わってきていると思う。もしかしたらその前のアルバムからかもしれない。『The Weighing of the Heart』はほとんどが生楽器で構成されているけど、最後に作った曲の”Breaking Up The Earth”にはたくさんディレイを使っていて、この曲を作っていたときにたくさんのジャマイカ音楽を聴いていた。ジャマイカ音楽こそがいい例だと思うわ。貧しい国で、限られたテクノロジーしか持っていなくても、それを最大限に活用して、時代を超えた素晴らしい名作を数多く輩出している。だから、”Breaking Up The Earth”をアルバムの最後に作ったとき、自分が行きたい方向はこれだとわかった。
だからいまわたしにとってテクノロジーというのは、サウンドの世界をさらに奥深く、遠くへと探求させてくれるものなの。でも『A Flame My Love~』のように、全編エレクトロニックな作品を作るとは思っていなかった。このアルバムの前までは、わたしは生楽器の音しか好きじゃないと思っていた。もちろん生楽器の音を加工するのは前からやっていたわ。でも核にあるのはviola da gambaやアコースティック・ギターの音だとずっと思っていた。でも、自分でも驚いたのだけど、このアルバムを通じて、エレクトロニック・サウンドで旅ができることを発見したの。今夜のライヴもそうだけど、エレクトロニックの機材を操作していると自分がどこにいるかを忘れてしまうくらい、不純物のない、抽象的な周波数の世界に瞬間移動したかのような感覚になる。アルバムのタイトルに「周波数」という言葉を使ったのもそれが理由よ。だからいまは、とくにアナログ機材に興味がある。魔法を生む機械だと思う。電子機材を作る人も尊敬する。わたしは電子工学のことはてんでわからないから。でも、こういう機材を使うのは凄く面白いし、今後もサウンド操作が生み出すこの抽象的な周波数の世界をさらに探求し続けたいと思っている。
■『A Flame My Love~』はパリのテロ事件に触発された作品だという話をどこかで読みましたが、アルバムの最初の2曲は、悲劇的なテロを題材にした曲で、しかしこれほどパラドキシカルに美しい曲はないと思います。
C:アルバムはあの事件に影響を受けているのはたしかよ。わたしがあの夜にパリにいたのはまったくの偶然で、実際に事件があった場所にはいなかったのだけど、ほんの数時間前に近くを通った。ヴィオラの弓の修理をしなければいけなくて、本当にたまたま近くを通ったの。同時に家族と近しいひとが病気だったので、お見舞いも兼ねてパリにいた。本当に辛い体験だった。新しい音楽の制作にちょうど取り掛かろうとしていたところだった。アルバムを作る準備を進めていたときにあの事件が起きた。制作に戻らないとと思ったわ。
あの事件が作品に反映するのは不可避だった。これはわたしの人生に起きたことだったのだから。そして曲作りに取り掛かると、最初にできてきた曲は明るく喜びに満ちたものだった。なぜなら、わたしの人生、そして世界がいまどれだけ辛くても、それはどうすることもできない。できることがあるとしたら、少しでもその苦しみを和らげてくれるものを作ることだった。自分のためでもあり、それを聴いたひとたちもそう感じ取ってくれたら嬉しいと思った。そうやって最初はビートのある曲や明るい曲に自然と寄っていった。そしてアルバムの制作が進むにつれ、1年半近く経って、わたしの気持ちも少し落ち着いて、起きたことの重苦しいことも曲にすることができるようになった。矛盾しているかもしれないけど、気持ちが回復してから悲しい曲をかけるようになった。それしか方法はなかったの。わたしの歌詞はあまり直接的ではないかもしれないけど、わたしにとっては歌詞で表現しようとしたことと音楽は明確につながっている。
■あなたがムーンドッグやアーサー・ラッセルに惹かれるのはなぜでしょうか?
C:その質問に限られた時間で答えるのは難しいけれど、おそらくわたしは独自のやり方を貫いている人たちに惹かれるんだと思う。ムーンドッグやアーサー・ラッセルはふたりとも「非常に特異なミュージシャン」のいい例だと思う。どちらも多くの人に影響を与えながら唯一無二の存在だった。
アーサー・ラッセルにはいまでも強く共感するわ。彼の音楽を前ほど聴くことはなくなった。何度も何度も聴いたから、もはや自分のなかにあるんだから。基本的には自分独自のやり方を貫く人が好き。リー・ペリーもまた、限られた環境で独自の世界を作ったひとね。10万ユーロもかけて機材を揃えたスタジオがなくてもいい音楽は作れる。むしろ贅沢な設備はない方がいいのかもしれない。いまわたしが面白いと思うのは……、『A Flame My Love~』はエレクトロニックかもしれないけど、じつは作っているあいだ、エレクトロニック・ミュージックを聴いていたわけじゃないの。わたしのパートナーのIker Spozioの話をしないといけないわ。彼はわたしの作品のアートワークをすべて手がけているのだけど、彼は熱心な音楽ファンでもあって、幅広く何でも聴いている。彼のレコード・コレクションの恩恵に預かったわ。家にいるときはたとえばアフリカ音楽だったり、60年代のサイケデリック・ポップだったり、ジャマイカ音楽、そして夜にはバッハやモーツアルトを聴いたりしている。とくにアフリカ音楽はたくさん聴いているの。アフリカ音楽は、わたしのすべての作品に多大な影響を与えていると思う。それと……、リズムとメロディの関係性にも興味がある。パーカッションという意味でのリズムではなくて、どんな楽器でも弾き方によってリズム感を出すことができる。アフリカ音楽のそういう部分が面白いと思う。アフリカ音楽のギターの弾き方も凄くリズミカルよね。だから例えば『Captain Of None」ではヴィオラをよりリズミカルに演奏しようと試みた。音楽は果てしない海のようだと思う。自分が知らないものがまだまだたくさんあって、それと出会うことで新しい何かをもたらしてくれる。
世界がいまどれだけ辛くても、それはどうすることもできない。できることがあるとしたら、少しでもその苦しみを和らげてくれるものを作ることだった。自分のためでもあり、それを聴いたひとたちもそう感じ取ってくれたら嬉しいと思った。そうやって最初はビートのある曲や明るい曲に自然と寄っていった。
■子供の頃から楽器を習っていたんですか?
C:全然。15歳になるまで楽器を弾いたことなんてなかった。自分も音楽をやりたいと思わせてくれた最初に夢中になったバンドがビートルズだった。ビートルズは絶大な人気を誇りながらも、非常に質の高い作曲能力があって、それに加え革新的なテクノロジーも積極的に取り入れた最たる例であり、誰も真似できていないと思う。最初は素晴らしい曲を作るシンプルなポップ・バンドだったけど、数年という短い期間にテクノロジーを駆使してバンドとして進化し続けた。そういう点では、いまでもわたしにとって大きなインスピレーションの源よ。わたしの音楽は彼らのとは全く違っていてもね。で、えっと、質問は何だったかしら……、あ、クラシックの教えを受けたか、だったわね。わたしの両親は多少音楽を聴いたけどそれほどでもなくて、わたしはいわゆる中流家庭の出で、高価なクラシックの楽器を買うお金もレッスン代を賄うお金もなかった。だから最初の楽器はクラシック・ギターで、それからエレキ・ギター。そして26歳になって安いチェロを買った。しかも正規のよりも小型の。そのあとでちゃんとしたチェロを手に入れて、それからヴィオラ・ダ・ガンバを買った。弦楽器職人に依頼してヴィオラ・ダ・ガンバを作ってもらったのよ。もうその頃は働いていて、英語の先生をやって貯めたお金があったから、自分の夢を叶えようと思ってね。そうやってヴィオラを手に入れてレッスンも受けたけど、2006年頃だからすでに30歳だったわ(笑)。
■あなたの音楽はエレクトロニック・ミュージックであるとか、アンビエントであるとか、いろいろアクセスできると思うのですが、どこか固有のジャンルには属していませんよね。それは意識しているのですか?
C:そう。自分がどのジャンルに属するかといったことを意識したことはない。自由であることを大事にしてきた。生きているとわたしたちはいろいろな妥協をしなければならないでしょ。いろんな出来事や出会い、人間関係に直面し、人生のいろいろな場面で妥協を強いられる。そんななかでアートというのは、自分が表現したいことを妥協することなく表現することだとわたしは思っている。もし1時間の長いドローン・ミュージックを作りたいと思ったら作ればいいし、2分のポップ・ソングが作りたいならそうすればいい。わたしはメロディアスであると同時に実験的なものを作りたいと思っていて、それを追求しない理由はない。わたしがアルバムを出し続ける理由はたったひとつで、それは伝えたいことが自分のなかにまだあるから。ある日伝えたいことが無くなったら音楽を作るのをやめて他のことをするでしょう。何にも縛られず自由であることは大事で、もの作る者にとっての本分だと思う。
■あなたは英文学を勉強し、英語の教師をしていたということですが、どんな本がお好きなんですか?
C:最初に好きになったのは文学よ。子供の頃から本を読むのが大好きだった。学校で英語を勉強した際も文学の歴史に重点を置いて勉強した。高校のときもたくさん本を読んで、大学ではもっぱら英米文学を読んだ。いちばん好きな本はマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』。読破するのにものすごく時間が掛かった。ものすごく分厚い本だから(笑)。でもわたしの読書人生のハイライトのひとつだと思う。またいつか読み返したいと思っている。
それからしばらくは音楽制作で忙しくなってしまって本を読む時間がなくなってしまった時期があった。そして日本から戻って、フランスの図書館から日本についての本をたくさん借りて読んだ。もっぱら日本の陶器や伝統美意識、禅庭についての本よ。そのあと、またしばらく読書から離れた時期があって、今度は自然に関する本をたくさん読んだ時期もあった。たとえばバードウォッチングはとにかくまず野鳥について知らないといけないから、何冊も繰り返し読んだわ。他にはアートブックを読むのも好きよ。パートナーのIkerは絵描きだから家にはアートブックがたくさんある。アフリカのお面(マスク)についての本から、マティス、ミケランジェロまで、なんでも。アートについて読むのも大好き。そして小説もまた読むようになった。今年ようやくメルヴィルの『白鯨』を読んだわ。20年もの間ずっと本棚にいつか読まなきゃと思って置いてあったのをようやく読むことができた(笑)。最近はそうやって昔に読もうと思って買った本を読むようにしているわ。
■『The Weighing Of The Heart(心の計量)』というタイトルも気になっていたのですが、これはなにか書物からの引用ですか?
C:古代エジプトの『死者の書』の翻訳を読んだ。美しい絵とヒエログリフで構成されている巻物を写したヴァージョンよ。そして古代エジプト人が行なった埋葬の儀式に感動した。その儀式では死者の心臓を天秤にのせ、もう片側の皿には羽根を置く。純潔な人生を送った人はその心臓が羽根よりも軽くなる。なんて美しいイメージなんだろうと思ったわ。わたしはいい人間でありたいと思っているから、いい人生を送ることの難しさを表しているようで、余計にこのイメージが心に刺さったんじゃないかしら。わたしにとってぴったりのタイトルだった。
パリの「黄色いベスト」運動が起きたとき、アメリカのトランプ大統領は、ほら、だれから俺はパリ協定から脱退すると言ったんだという、まったくトンチンカンだが環境のために膨大な福祉予算などつぎ込みたくなる側からすればある意味スジが通った意見を述べている。逆に言えば、人間以外(生きる権利を持っている地球上の生物)のことを考えることは、新自由主義の暴走を否定する根拠にもなってきている。コリーンのような音楽が重要なのは、デジタルとアナログとの融合などということではなく、ポジティヴな未来を考えるうえでたいせつな感性が表現されているからだと思う。
ele-king vol.23に掲載されているアースイーターのインタヴューもぜひ読んでください。こちらは2018年もっとも感情をかき立てられたアルバムの1枚ですが、コリーンよりもさらにラディカルに「non human」というテーマが偏在しています。なぜなら彼女は本当に動物たちといっしょに育った人間であり……。(続く)
取材:野田努(2018年12月12日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE