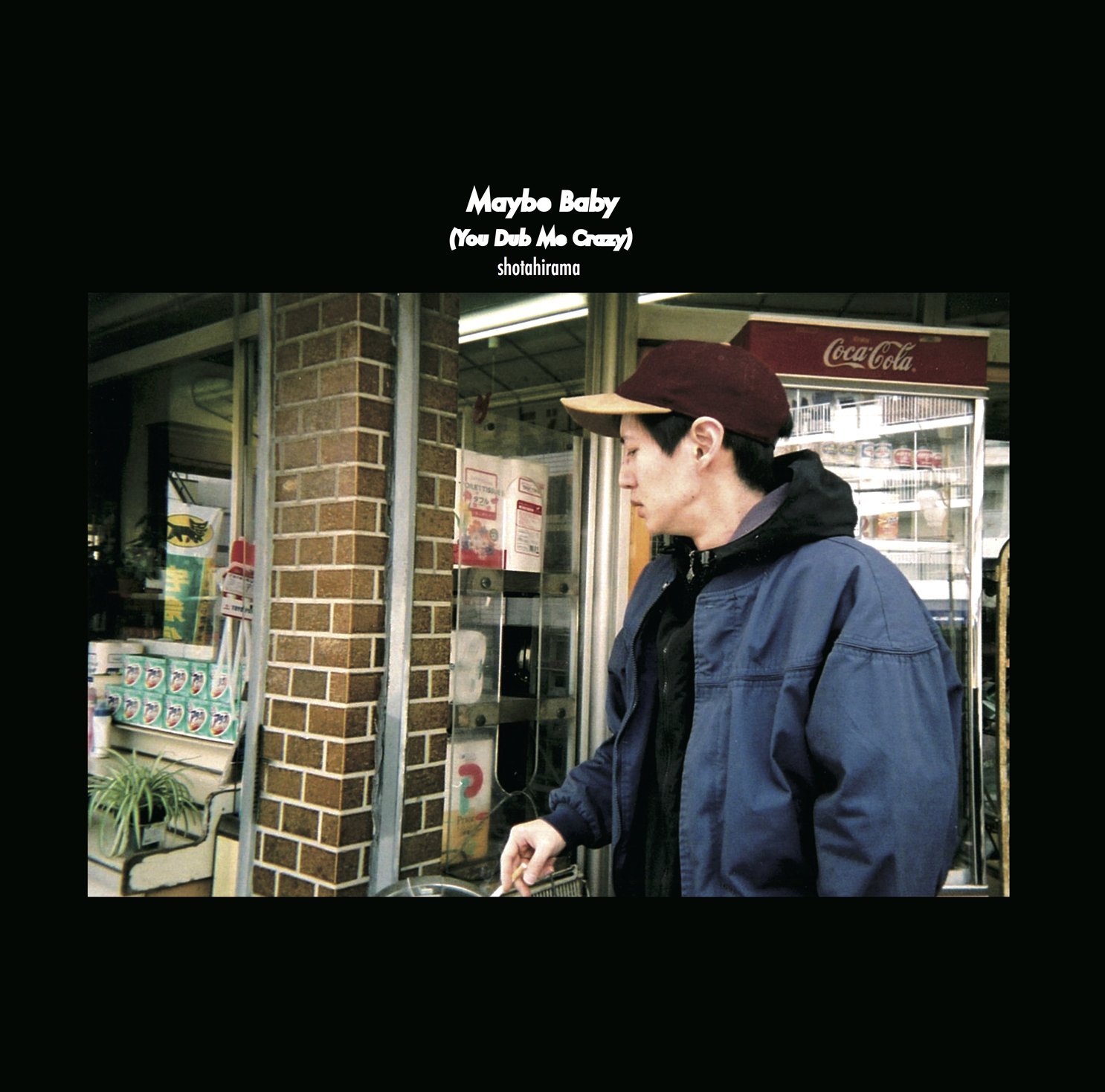MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with shotahirama - じぶんだけのオーセンティック
いったいなにごとかと、そう驚くことになるだろう。これまでノイズ~グリッチの領野でキャリアを重ねてきた孤高のプロデューサー、「きれいなひとりぼっち」こと shotahirama が、突如ヒップホップに開眼したのである。といってもいきなりラップをはじめたわけではなく、またごりごりのギャングスタに転身してしまったわけでもない。昨年末にリリースされたばかりの新作『Rough House』が、ターンテーブルを用いて制作され、無類のビート・ミュージックを打ち鳴らしているのである。
とはいえそこはやはり shotahirama、前作『Maybe Baby』ほどではないにせよ、グリッチ・ノイズやダブも細やかに取り入れられている。今回の新作がおもしろいのは、にもかかわらず既存のエレクトロニカ~グリッチ・ホップのようなスタイルとは微妙に距離を置きつつ、かといってクリスチャン・マークレーのような前衛に振り切れるわけでもなく、もちろんヒップホップのターンテーブリストたちのスタイルとも異なっているところで、なるほどたしかにこれは彼にしかつくりえないヒップホップといえるだろう。
このような「転向」のきっかけは2年前。それまでほとんど聴いてこなかったというヒップホップに、まずはリスナーとしてのめりこむことからすべてがはじまった。以下のインタヴューをお読みいただければわかるように、それはもうどっぷりだったのだという。有名どころは無論のこと、ずいぶんマイナーなものにまで関心の矛先は向かったようだ。それこそディギン・イン・ザ・クレイツよろしく掘って掘って掘りまくり、寝ても覚めてもまた掘って……なかでも強く惹きつけられたのは、90年代ニューヨークのアンダーグラウンド・シーンだったという。shotahirama はそこにオーセンティックを見出した。
今回が彼にとって初めての「アルバム」であるという点も注目しておくべきだろう。いや、もちろん shotahirama はすでに何枚もアルバムを送り出している10年選手なわけだけど、今回の新作『Rough House』は3~5分の曲が10トラックという、わかりやすい「アルバム」のかたちをとっているのである(最後の1曲をのぞく)。これまで長尺の曲ばかりつくってきた彼が、ストレートにアルバムという形態に挑戦──いったいなにごとかと、そう驚くことになるだろう。
と、このように二重に転機を迎えた shotahirama だけれど、今作に込められているのはたんにヒップホップにたいする熱い想いというよりもむしろ──や、それも当然あるのだけど、それ以上に──ハマったらとにかく一意専心、掘って掘って掘りまくるという、音楽文化そのものにたいする深い敬意と誠実さなのではないかと思う。つまり、至上の愛である。
最近の主流のヒップホップでもなく、逆にテクノとか、ノイズとかグリッチでもなく、そのぜんぶの中間地点というか、どこにも属していないものでできているような音になっていたらいいかな。
■前回のアルバムから2年半くらいが経ちましたけれど、この間はなにをされていたのでしょう?
shotahirama(以下、SH):ふたたびレコードを買うことに舞いもどりましたね。リスナーとしてしっかり店に行って、買って。またむかしみたいにディグりはじめているかな。レコードにもう一回興味が出てきた。
■おもにどういった方面のものを?
SH:前回の『Maybe Baby』の制作が終わってから、ずっとヒップホップばかり買っていましたね。妻がもともとディスクユニオンのヒップホップ担当だったので、有名どころはすでに家にあったんですよ。でも俺はノイズとかオルタナの人だったから、言い方は悪いけど、「ラップしてんなよ」という感じで(笑)。「ア・トライブ・コールド・クエスト聴いてればヒップホップ知ってるでしょ」くらいの感じだった(笑)。まわりの若い子たちがみんなヒップホップを聴いていて、かっこいいんだなと。それで、ちゃんと聴いてみよう、俺も買おうと思って、自然とヒップホップを探すようになった。一度のめりこむとそれだけになっちゃう性格なんですよね(笑)。じぶんでもとことん調べるし、お店の人や詳しい人に訊いたり。40歳とか45歳くらいの先輩たちは、リアルタイムで通っていた人たちだから。それでもうドハマりして、月いくらまでって制限しないと信じられないくらい買っちゃう(笑)。コレクターって厄介ですよね。音楽はもちろん聴くんだけど、所持してるフィジカルの数が増えていくことじたいにもけっこう昂奮しちゃう。
■買ったのに時間なくて聴けていないやつとかありますよね(笑)。
SH:あと、おなじの買っちゃったりね(笑)。
■それで今回ヒップホップのアルバムになったと。
SH:こんなにレコード持ってるし、じゃあ使ってみるかということで。がっつりターンテーブルで、マシンドラムと合わせてね。今回はラップトップのソフトウェアとかはあんまり使わないでつくりました。だから、レコードを買うことによって今回のアルバムが生まれたんですよ。
■ヒップホップのなかでも、いちばんハマったのはどの辺ですか?
SH:いちばんハマったのは、90年代半ばのニューヨークのアンダーグラウンドのものですね。ロード・フィネスやバックワイルドなどの D.I.T.C. (Diggin’ In The Crates)とか。あとブルックリンだとナチュラル・リソースとか、ハードコアだけど、ヘルター・スケルターとかのブート・キャンプ・クリックとか、その界隈にいるダ・ビートマイナーズとか。彼らがトラックメイクしている12インチをひたすら探した。ビートマイナーズのシーンはめちゃくちゃかっこいいんですよ。とくに、その界隈のシェイズ・オブ・ブルックリンやフィンスタ・バンディはめちゃくちゃハマりましたね。音数が少なくて、ネタが一個あって単純にワン・ループでっていうところがすごく好きで。キックとスネアだけで、音がこもっていて、ラップも暴力的じゃない。俺はこういうのが好きなんだなというのがこの2年間でわかった。
■2018年の秋に、アルバムからの先行シングルとして「Cut」を出していますよね。でも音を聴くと、そのあとにけっこう変わったのかなと。今回のアルバムには収録されていないですし。
SH:気持ちが変わった(笑)。気分屋というか気まぐれというか、やっぱりじぶんの思うままにやっていきたいじゃないですか。メジャーでもないし。でも今回も、「Cut」とおなじことはやっています。あれもノイズっぽさとかグリッチな感じはかなりなくしたし、サンプリングをつかっているし。でもまだちょっと『Maybe Baby』が入っちゃっている感じですね。
■新作を聴いて、たしかにヒップホップだけど、とはいえやっぱりグリッチだなとも思いました。
SH:ですね。ちょっとハウスっぽくないですか? クリック・ハウスみたいな。ドープな暗いギャングスタではないし、ウェッサイでもないし。ぼくがそういう人じゃないから。そもそも(生まれが)ニューヨークだし。なんとなく怖いという感じにはならないくらいが俺っぽいのかなと。踊れて、かつ聴かせられるようなものをつくりたかった。だからグリッチしちゃうし、ターンテーブルもずっと指でなぞってわざと速度を落としたり。といってもタンテを使っているグリッチの人、たとえばクリスチャン・マークレーとか大友(良英)さんとか、そういう感じでもない。俺だったらどうできるんだろう、というのは考えました。ヒップホップとは言っているけど、shotahirama っぽさはある。当然ヒップホップを意識してつくったんですけど、グリッチとかノイズとかを聴いているひとがたどりついてくれたらいいな。もちろん、ふだんヒップホップしか聴かないひとにも聴いてもらいたいし。
■いまの主流のトラップでもないですよね。そっちは肌に合わない?
SH:トラップのシーンをそんなに知らないから簡単にはいえないけど、少なくとも今回やろうとしていたこととはまったくちがうだろうなと。たぶん、前回のアルバムに比べて今回は音がすごく少ないと思うんです。音が多いものだったり速いものだったり、あとエレクトロニックな感じにもあまりしたくなかった。クラブ的というか、ファッショナブルな感じにはしたくなかったんです。きらきらしてつやっぽいものではなく、ハイが削れていて中音域が豊かな、アナログっぽい質感で、ロウで。
■ビートがヒップホップだからかもしれませんが、以前よりポップさも増したように思いました。
SH:聴きやすくなっていたら嬉しいな。
■むかしの〈Ninja Tune〉に近いのかなとも思いましたね。キッド・コアラとか。
SH:最近の主流のヒップホップでもなく、逆にテクノとか、ノイズとかグリッチでもなく、そのぜんぶの中間地点というか、どこにも属していないものでできているような音になっていたらいいかな。俺じゃないとできない感じ。
■どことなくマウス・オン・マーズも思い浮かべました。
SH:マウス・オン・マーズめっちゃ好きですよ! 制作中はぜんぜん頭をよぎらなかったけど、いまそう言われてみて「ああ、俺めっちゃ好きだわ」と思った。それは嬉しいですね。

ナインティーズっていうところに、たぶんじぶんのモードというか、基本的にそこになにか核のようなものがあるのかなって。くすぐられるものがたくさんあるというか。じぶんのなかのオーセンティックが90年代なんですね。
■制作過程で〈Anticon〉や〈Definitive Jux〉あたりは聴きました?
SH:少なくともこの2年間では聴いてないですね。たぶん、もともとじぶんが持っていた(グリッチなどの)要素と、新しく掘ったもの(ヒップホップ)が混ざった結果、〈Ninja Tune〉とかマウス・オン・マーズとかにつながっているんだろうな。それはすごくおもしろい。
■ちなみにオウテカは?
SH:オウテカはめっちゃヒップホップ好きですよね。でもそういうじぶんに近いところのは聴かなかったですね。オウテカ聴いていたらまたべつな方向にブレただろうし。だからこの間、ギター・サウンドも聴けなかったんですよ。嫌っているわけではなくて、一度ハマるとそればっかりになっちゃうから。
■“ROUGH HOUSE” なんかはいわゆるJ・ディラ以降のもたつくビート感に近い瞬間もありますけど、そういうものにも触れなかった?
SH:触れてないですね。ディラもマッドリブも。あー、でもディラは、トライブがらみで少し絡んでいたかも。
■そういう話を聞くと、すでにあるグリッチ・ホップなどから影響を受けたのではなくて、かつてそういうものをつくったパイオニアの人たちとおなじように、オーセンティックなヒップホップを聴いて、オリジナルのなにかをつくろうとして、こうなったという流れなんですね。
SH:むかしの偉人たちのインタヴューとかアルバムの解説とかを読むと、たとえばアルバムをつくるためにどこどこへ旅行に行ってとか、その地方の楽器だけ使ってとか、ありますよね。その限定された条件のなかで集中して、たとえばもともとじぶんたちが知っていたギターを弾くようにシタールを弾いてみたり。ラップトップを触るようにターンテーブルを触るとか。そういう感じなんじゃないかな。
取材・文:小林拓音(2020年2月10日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE