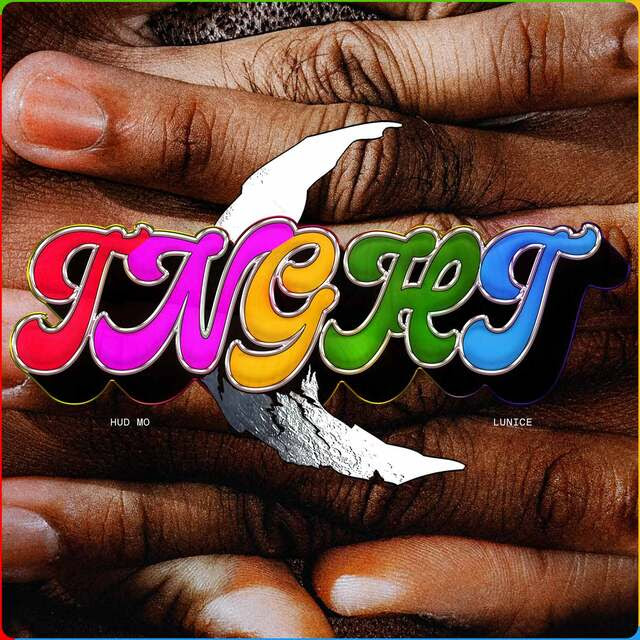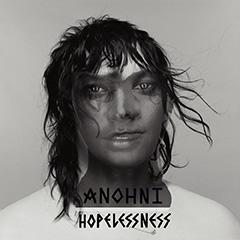MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Hudson Mohawke - 待っていたよ、ハドソン・モホーク
interview with Hudson Mohawke
待っていたよ、ハドソン・モホーク
──7年ぶりの新作と飛躍
トラップ(ラップ・ミュージックのではなく、ダンス・ミュージックのそれ)のヒットメイカーとしてハドソン・モホークが自身の名をメジャー・シーンにまで轟かせたのはいまから遡ることちょうど10年前、2012年のことだ。彼とモントリオールのプロデューサー、ルニスによって結成されたユニット TNGHT がリリースしたEP「TNGHT」は、2010年代初頭からトラップがビート・ミュージックから巨大なダンスフロアを沸き立たせるサウンドへと進化する過程を語るには欠かせない作品であり、そのサウンドの鮮やかさはいまもなお保たれている。2015年にはソロ名義では 2nd アルバムとなる『Lantern』をリリース、その後もカニエ・ウェスト、クリスティーナ・アギレラ、FKA・ツイッグスなど数々のビッグネーム・アーティストとのコラボや Apple のCMへの起用、ゲーム『Watch Dogs 2』のサウンドトラックを手がけるなど、フロアからデジタルな画面の中までをも席巻してきた。
そして悪夢のようなパンデミックが世界中を襲った2020年、マッチョでクレイジーなアートワークが特徴の未発表音源集「B.B.H.E.」「Poom Gems」「Airborne Lard」のミックステープ3作品を突如リリース。この作品群にはビート・ミュージックやヒップホップ、IDMなどと自由度が高く、かつレイヴィーな彼のエッセンシャル的サウンドがみっちりと詰め込まれており、彼がビートメイカーの神童として登場してから、世界中のシーンを席巻するいちプロデューサーになるまでの道筋をリスナーに深く実感させたはずだ。そうして2020年代初頭も、ハドソン・モホークはサウンドの進化をじわじわと重ねながらユニークなアイデアを世に放出し、ついに2022年のこの夏、新作としては7年ぶりとなるニュー・アルバム『Cry Sugar』を引っ提げてエレクトロニック・ミュージック・シーンに華々しく帰ってきた。
アメリカの退廃といった背景がある本作は、マシュマロマンとジャックダニエルの瓶が描かれたアートワーク、けたたましい彩度で次々と繰り出されるサイケなティザームービーは彼らしいユニークさがありながらもどこか薄暗さを感じさせる。アシッドでレイヴィーな “Bicstan” ではカオスに弾けながら、壮大なストリングスが響く “Lonely Days”、ブラック・ミュージックからのインスピレーションが感じられる “3 Sheets To The Wind” ではメロディアスな側面を垣間見せ、7年の間にアップデートされたサウンドの裏に潜む彼の心象が伺えるだろう。
カオスな現実に対して独自のレイヤーを高精細に投影し、創造性を体現するハドソン・モホークが今日のシーンに示すものは一体何か。この10月には来日も決定し、待望の帰還を果たす彼に話を聞いた。
人気のレコードを作ることに成功すれば、それを再び作ることはもちろん難しくはない。でも、創造的に自分が面白いと思うことができ、満足できるものを作るためには、そのアプローチじゃダメなんだ。
■今年で自身としてはデビューEPのリリースから14年、TNGHT としてのデビューから10年とアーティスト活動の節目を迎える頃になります。ファースト・アルバムのリリースや(“Chimes” が) Apple のCMで起用されたこと、ゲーム『Watch Dogs 2』のサウンドトラックを手がけるなどいくつかのターニング・ポイントがあったと思います。この十数年の軌跡をどのように振り返りますか?
ハドソン・モホーク(以下HM):多くを学んだ10数年だったと思う。いい意味で、成功するぞという意欲に駆り立てられて突き進んできた10数年だったと思うね。僕はすごくシャイな性格だから、本当は積極的に何かをやるタイプではないはずなんだけど、仕事に関しては成功したいという大きな向上心を持っていたんだ。金銭的な成功というよりは、音楽で自分のメッセージを伝えられるようになりたいという成功。活動の中で起こったことのいくつかは、僕の想像をはるかに超えたものもあったね。良い意味でも悪い意味でも。この10数年内には、すごくエキサイティングな瞬間もあったし、同時に、こんなことになるなんて、と、自分が行きたくない方向に物事が進むこともあった(笑)。でもまあ、人生ってそういうものだから仕方がない(笑)。
■ロックダウン中はどのように過ごしていましたか。住んでいたのはLAでしょうか? 当地の状況を教えてください。
HM:ロックダウンの直前に、パンデミックが起こるとは知らずに、LAに自分のスタジオを買ったんだ。でも、そのタイミングは良かった。家の他に時間を過ごす場所を持つことができたからね。誰かに会う必要まではなかったけど、もしそのスタジオを持っていなかったら、ずっと家にこもりきりになってたと思う。家以外どこにも行けなかった人たちは、本当によくやったと思うよ(笑)。期間中はほとんどLAにいたけど、イギリスにまた入れるようになった段階で、すぐ戻ったんだ。僕の姉妹がコロナ期間中に子どもを産んだけど、ずっと会えていなかったから。僕にとって初の姪っ子なんだけど、彼女が1歳になるまで会えなくてさ。でも、ロックダウン中にLAにいられたのはよかったと思う。あの街は開放感があって、閉じこもるのに悪い場所じゃないからね。
■パンデミック下の2020年にリリースされた未発表音源集「B.B.H.E.」「Poom Gems」「Airborne Lard」のミックステープ3作品はあなたのビート・ミュージックやヒップホップ、IDMなどといったサウンドのエッセンスが多彩に詰め込まれているように感じました。あのタイミングでリリースに至った経緯を教えてください。
HM:もう何年も、未完成のトラックがいろいろなハードドライヴにたくさん放置されていたんだ。それをわかってはいたんだけど、まあ、もうそれらのトラックを完成させることはないだろうなと思っていた。忙しくて時間がないし、何か劇的なことが起こらない限り、そのための作業をすることはないだろうって。でも、パンデミックという劇的な何かが起こって、作業をする時間ができた、というわけ。その曲の中には、ライヴやラジオでだけ披露したことがあるものもあって、周りから「あの曲はどうなったの?」なんて聞かれることもけっこうあったんだよね。だから、完全な自由な気持ちで新作作りに挑みたければ、そういった曲の数々をまず世に送り出す必要があると思った。外に出して処分するってわけじゃないけど、振り返って作業すべきものがあるっていう気持ちを持ったまま新しい作品にとりかかるのは少し落ち着かなくて。まっさらなクリーンな気持ちで新作にとりかかりたかったから、あのミックステープをリリースして、まずは気持ちをリセットすることにしたんだ。

状況から目をそらして、全てがうまくいっているようなフリをするレコードは作りたくなかった。物事がうまくいっていないことは事実で、いま世界はゾッとするような状況下にある。僕は、それを認識しつつも希望を抱くようなアルバムを作りたかったんだ。
■いま現在の(ダンス・ミュージックの)トラップは、10年代にシーンで勃興した初期に比べ、ビート・ミュージックの文脈からメインストリームのヒップホップやダンス・ミュージックにも浸透し、かなり異なるサウンドへと進化を遂げたように思います。EDMやヒップホップに影響を与えたトラップ・ミュージックの立役者としてあなたの名が挙げられることが多々ありますが、進化過程をどのように見つめていたか興味があります。
HM:僕がルニスと曲を作りはじめたとき、トラップ・ミュージックはラップの一種とみなされていた。当時はまだEDMではなくて、ラップ・ミュージックのサブジャンルだったんだ。だから、僕自身はEDMとしてのトラップがあまりしっくりこないんだよね。僕とルニスが作った最初のレコードは、あれは偶然でき上がったとさえ言える作品で、ふたりでただ楽しみながら音楽を作っていた結果でき上がったのがあの TNGHT のアルバムなんだけど、あれを作っていたときは、あの作品をパフォーマンスしたいとか、人にどう受け取って欲しいなんて思ってもみなかった。でもリリースされると、これまた偶然人気になってしまった。もちろんそれは嬉しいことだったよ。でも、そのあとあれと同じ音楽を作ることを人びとから求められるようになってしまって、僕はそこにフラストレーションを感じるようになってしまったんだ。そして結果的に、トラップ・ミュージックはジャンルとしての進化が止まってしまったと思う。フェスティヴァルで盛り上がるエキセントリックな音楽になってしまってからは。トラップ・ミュージックといえば花火、みたいになってしまったし、男性アーティストが中心になった。あのときは、僕もルニスも、これは自分たちが進みたい方向じゃないなと思ったね。あれはもう、僕たちがアルバムを作っていたときに作りたいと思っていた音楽とは方向が全然違ってしまっていたから。だから僕たちは、少し距離を置くことにしたんだ。トラップというものが、もう何なのかわからなくなってしまったから。もちろんトラップは僕のキャリアの一部であり、ディスコグラティの一部でもある。でも、僕は自分の音楽がトラップだと認識される必要はないと思っているし、僕は新しいアイディアで、あのときの音楽とは全く違うものを作りたいと思ってる。人気のレコードを作ることに成功すれば、それを再び作ることはもちろん難しくはない。でも、創造的に自分が面白いと思うことができ、満足できるものを作るためには、そのアプローチじゃダメなんだ。同じことを繰り返さず、何か新しいものを作ってこそ、自分の創造性を満たすことができる。所属しているレコード会社が自由に好きな音楽を作ることを認めてくれているのは、すごく幸運だと思うね。あと20年同じレコードを作りつづけろ、なんてレーベルもきっとあると思うから。
■前作『Lantern』はポップ・シーンを席巻するハウシーな要素だけでなく、ここ数年のベース・ミュージックやハイパーポップなどに繋がる要素も含まれているかと思います。近年のシーンの流れを踏まえ、前作からどのように制作軸やサウンド面がアップデートされていったか教えてください。
HM:それをどう思うかは聴く人次第だとは思う。僕自身は、自分が作る音楽の核は変わらず存在しつつ、少しだけ洗練されたと感じるかな。今回のアルバムでは、他のプロジェクトの中でさえも試したことのないサウンドに挑戦してみたりもしたからね。生演奏をここまでフィーチャーしたことも初めて。これまでそれをやってこなかったのは、自分の音楽がシンセやサンプルベースだったから。だから、ここまで生演奏をフィーチャーしていると、今回のサウンドを嫌う人も必ずいると思う。でも、やっぱり僕にとっていちばん大切なのは、自分自身が納得のいくサウンドを作ることなんだ。
■今作はハウスやUKG、ガバ~ハードコアといった様々なダンス・ミュージックの要素がありつつ、一方ではアッパーなだけでない側面も感じさせますよね。改めてアルバムのコンセプトを教えてください。
HM:コンセプトはひとつではないんだけど、メインのひとつを説明すると、いま僕たちは、怖くて、気が遠くなるような世界の中に生きているけど、その状況から目をそらして、全てがうまくいっているようなフリをするレコードは作りたくなかった。物事がうまくいっていないことは事実で、いま世界はゾッとするような状況下にある。僕は、それを認識しつつも希望を抱くようなアルバムを作りたかったんだ。
■アルバムの制作はいつ頃からはじめましたか? 構想のインスピレーションを受けたものなどがあれば教えてください。
HM:制作をはじめたのは、たぶん2020年の初めだったと思う。インスピレーションというか、僕がつねに意識していたのは、自分自身の鳥肌が立つようなサウンドを作ること。パンチが効いて、明るくて、エキサイティングでありながら、効いた瞬間にゾクッとするような作品をイメージしながら作業したんだ。例えば、高揚感のあるサウンドと30秒間の奇妙なインタールードが組み合わさっているとかね。自分自身が聴きたくなるような、自分自身がその展開に驚かされるような作品を作るというアイディア、自分自身を驚かせたいという気持ちが、アルバムのインスピレーションだったと思う。
■制作中に気になったトピックやアーティスト、作品は何かありますか? あるいは制作期間だけでなく、近年気に入っているアーティストや作品があれば教えてください。
HM:おもに聴いていたのは、ライラ・プラムク(Lyra Pramuk)の『Fountain』っていうアルバム。アルバムを聴いて泣くなんてめったにないんだけど、あのアルバムを聴いたときは涙が出た。ドラムもシンセも使われていなくて、アルバム全体がひとりの人間の層でできているんだ。まるで聖歌隊みたいなんだけど、人数はひとりだけ。あのアルバムは本当にたくさん聴いたな。自分のアルバムにも少しは影響していると思う。10分間の曲なんかもあって、聴いたらきっと気に入ると思うよ。是非チェックしてみて。
質問・序文:yukinoise (2022年8月09日)
| 12 |
Profile
 yukinoise
yukinoise1996年東京生まれ。OLのかたわら、AVYSS Magazine等でフリーライターとして活動中。
Twitter:@yukinoises
instagram:@yukinoise
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE