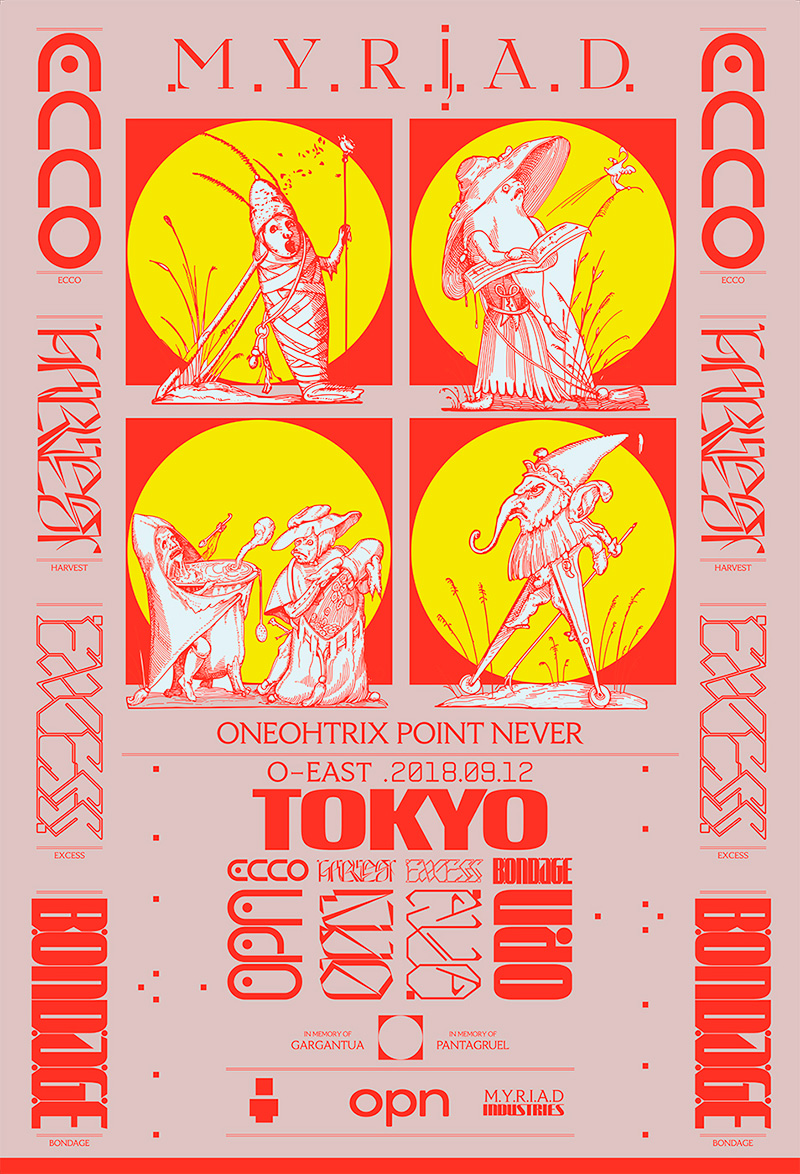そうじゃない。そういうことじゃないんだ――。
きっとあなたも経験したことがあるだろう。いわゆる正統なクラシカルの教育を受けたアーティストがエレクトロニクスを導入してテクノやIDMを試みたときの、あのどうしようもない違和感。たいてい電子音やノイズは装飾の域に留まっているし、それを肴にストリングスやピアノが酒宴を張るだけの結果に終わってしまうこともしばしば。あるいは逆に、身体性を意識するあまりビートが妙に強調されすぎていたり。違和感というよりも「残念」とか「無念」といったほうが的確かもしれない。
ジョニー・グリーンウッドとの共同作業によりぐんぐんと知名度を上げているロンドン・コンテンポラリー・オーケストラ、その一員たるオリヴァー・コーツもまた、そのようなクラシカルの文法をしっかり身につけたチェロ奏者だ。いや、「しっかり」なんてもんじゃない。かつて王立音楽アカデミー史上最高の成績を収めたというのだから、相当なエリートである。その気負いもあったのかもしれない。彼のファースト・アルバム『Towards The Blessed Islands』(2013年)は、クラシカル~現代音楽のなかで「しっかり」前衛を追求する作品だった。
ただ、彼がそのアルバムでスクエアプッシャーをカヴァーしていたことは心に留めておくべきだろう。原曲は『Ultravisitor』所収の小品“Tommib Help Buss”で、複雑なリズムや音響が展開されるものではないが、その選曲は、オリヴァー・コーツのなかにクラシカルとは異なるプログラムが走っていることを教えてくれていた。
そこから遡ること5年、彼はバービカンでおこなわれたミラ・カリックスのパフォーマンスにチェロで参加しており、その成果は『The Elephant In The Room: 3 Commissions』(2008年)として音源化されている。そのとき縁が結ばれたのか、翌年ふたりは〈Warp〉が設立20周年を記念して編んだコンピレイション・シリーズ『Warp20』でボーズ・オブ・カナダの楽曲をカヴァーしてもいる。これらの事実に、彼がオウテカのファンであるという情報を付け加えれば、いかにオリヴァー・コーツがIDM~エレクトロニカを愛好する音楽家であるかがわかるはずだ。
そんな背景を持つ彼もまたきっと、あの「そうじゃない」という感覚を味わったことがあるに違いない。だからだろう、その後オリヴァー・コーツは、映画のスコアなどを除けば、基本的にIDM~エレクトロニカの側に軸足を置くことになる。弦の音響効果から巧みにダンス・グルーヴを抽出した2014年のシングル「Another Fantasy」はその最高の成果のひとつだし、積極的にエレクトロニクスを導入したセカンド・アルバム『Upstepping』(2016年)もその延長にあるといっていい。そうした正統なクラシカルからの離脱運動は、〈RVNG〉へと籍を移して発表されたこの新作『Shelley's On Zenn-La』において、よりいっそう推し進められている。
彼の長年の相棒であるチェロはほとんどの曲においてエフェクトが施され、はっきりそれとわかるかたちでは鳴らされていない。本作を覆っているのはむしろ、リチャード・D・ジェイムスの影だ。“Charlev”や“Perfect Apple With Silver Mark”などは音の響かせ方やドラムの部分でいやでもエイフェックスを想起させるし、“Faraday Monument”や“Cello Renoise”なんかは完全にドリルンベースの再解釈である(前者はどちらかというとトム・ジェンキンソン寄りかも)。とはいえ、それがたんなるモノマネに陥っているわけではないところが本作の魅力で、そのような往年の〈Warp〉を彷彿させる音響空間に、「違和感」なく女性ヴォーカルや加工されたチェロを重ね合わせていく手腕は見事というほかない。“A Church”の紡ぎ出すグルーヴの心地良さといったら!
オリヴァー・コーツは近年、ミカチューことミカ・レヴィと何度もコラボを重ねているが、直近でもっとも注目すべきなのはアクトレスとの共演およびローレル・ヘイロー新作への参加だろう。クラシカル畑出身でありながらその文法に依拠しない彼の態度が、尖鋭的な電子音楽の俊才たちを惹きつけてやまないのだ。
この『Shelley's On Zenn-La』にはあの「そうじゃない」がない。本作はなによりもまずエレクトロニカとして優れた作品であり、だからこそモダン・クラシカルとしても高い完成度を有することができているのだと、そう思う。けっして、逆ではない。