MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Actress × London Contemporary Orchestra- LAGEOS
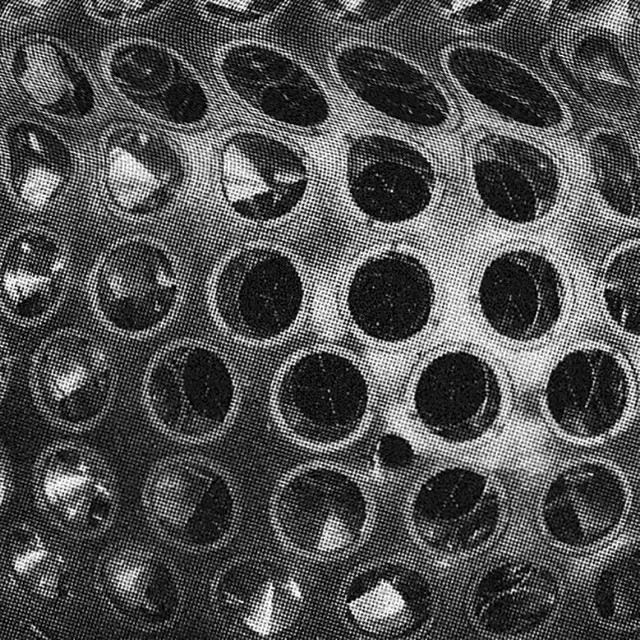
ここ日本からは想像しにくいかもしれないが、海の向こうにおいてアフロフューチャリズムは一定の文化的地位を獲得している。たとえば昨秋アテネでは、世界各地から多くのアーティストを招いたアフロフューチャリズムのフェスティヴァルが開催されており、サン・ラー・アーケストラを筆頭に、ドップラーエフェクトやア・ガイ・コールド・ジェラルドといったヴェテラン、ムーア・マザーやンキシといった新世代がパフォーマンスを披露している(アブドゥル・カディム・ハックやオトリス・グループなどもゲスト・スピーカーとしてレクチャーを担当)。アクトレスことダレン・J・カニンガムもそのフェスティヴァルに出演していたひとりだ。
自らをホアン・アトキンスの系譜に位置づけるアクトレスがデトロイトのエレクトロ~テクノから多大な影響を受けていることは間違いない。けれども彼はそのサウンドをあからさまに模倣することはせず、むしろ他のさまざまな音楽を参照し、それらの要素を独自に結び合わせ、まったくべつのものとして提出してきた。そのあり方にこそダレン・カニンガムのオリジナリティが宿っていたわけで、ようするに彼は物真似をしないということ、すなわち己自身の想像力を研ぎ澄ませるということをこそURやドレクシアから継承したのだろう。
そのアクトレスの新作『LAGEOS』は驚くべきことに、オーケストラとの共作である。これまでさまざまな趣向でリスナーを唸らせてきたアクトレス、彼はいま、どのような想像力をもって自身の可能性を押し広げようとしているのだろうか。
今回アクトレスの相方を務めているロンドン・コンテンポラリー・オーケストラ(以下、LCO)は、2008年にヒュー・ブラントとロバート・エイムスによって立ち上げられたアンサンブルで、近年ではレディオヘッド『A Moon Shaped Pool』への参加や、あるいはリン・ラムジー監督作『You Were Never Really Here』やポール・トーマス・アンダーソン監督作『Phantom Thread』といった映画のスコアなど、ジョニー・グリーンウッドとの絡みで注目されることが多い。
他方で彼らはこれまでマトモスやミラ・カリックスといったエレクトロニカ勢ともコラボしてきており、その経験が良き蓄えとなっているのだろう、エレクトロニクスと器楽が手を取り合うと、それぞれの歩んできた歴史の長さが異なるためか、往々にして音色/音響面で後者の支配力が大きくなってしまうものだけれど、本作においてLCOの面々はアクトレスの本懐を削がないことに苦心している。そのために彼らがとった方法は、それぞれの楽器を可能な限り器楽的な文法から遠ざけるというものだ。その奮闘ぶりは「RA Session」の動画を観るとよくわかるが、たとえばチェロのオリヴァー・コーツ(最近〈RVNG〉と契約)もコントラバスのデイヴ・ブラウンも、自身の相棒を打楽器的に利用している。
そのようなLCOのお膳立てのおかげで、ダレン・カニンガムには大いなる想像の余白が残されることとなった。彼の卓越した編集術はまず、冒頭の表題曲に素晴らしい形で実を結んでいる。か細いパルス音をバックに、ヴァイオリンとヴィオラが独特の酩酊をもたらす2曲目“Momentum”では、ゆったりとヴィブラートをかけることによって紡ぎ出された妖しげな揺らぎが、カニンガムによるエディットを経由することで何かの声のような奇妙な響きを獲得している。3曲目“Galya Beat”では、跳んだり跳ねたりする低音とノイズの背後で弦がドローンを展開しようと試みるものの、途中で弓を折り返さねばならないからだろう、持続は完遂されず、ここでも不思議な揺らぎが生み出されている。ミニマルに反復する高音パートを少しずれた間合いで低音がかき乱していく4曲目“Chasing Number”も、グルーヴという曖昧な概念をメタ化しようとしているようでおもしろい。
後半もよく練り込まれていて、パンダ・ベアからインスパイアされたという“Surfer's Hymn”では鍵盤とノイズがじつにスリリングなかけ合いを繰り広げているが、そこにさりげなくエレクトロのビートを差し挟まずにはいられないところがアクトレスらしい。「器楽インダストリアル」とでも呼びたくなる“Voodoo Posse, Chronic Illusion”も聴きどころ満載だけれど、キャッチーさで言えば、昨年シングルとして先行リリースされた“Audio Track 5”に軍配が上がる。坂本龍一がラジオでかけたことでも話題となったこの曲は、機能的なビートがひゅーう、ふゅーうとさえずるストリングスと手を組むことで、素晴らしい陶酔を生み出している。
とまあこのように、『LAGEOS』はカニンガムのたぐいまれな編集センスを堪能させてくれるわけだけれど、本作にはその逆、つまりLCOが既存のアクトレスの楽曲を再解釈したトラックも収められている。『Splazsh』の“Hubble”と『R.I.P.』の“N.E.W.”がそれで、いずれもまったくべつの曲へと生まれ変わっている。LCOの面々も負けていない。
アフロフューチャリズムがSF的な想像力を駆使することによって現実を捉え直したように、つまりは逃走することによって新たな闘争を実現したように、既存のテクノからもオーケストラからも遠ざかることによって未知の音楽の可能性を開拓した本作は、アクトレスとLCO双方のキャリアにとって画期となるのみならず、テクノとオーケストラとの、エレクトロニクスと器楽との共存のあり方をも更新している。これはもう素直に、LCOの寛容さ・柔軟さと、ダレン・カニンガムの冒険心を讃えたい。コラボたるもの、かくあるべし。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE



