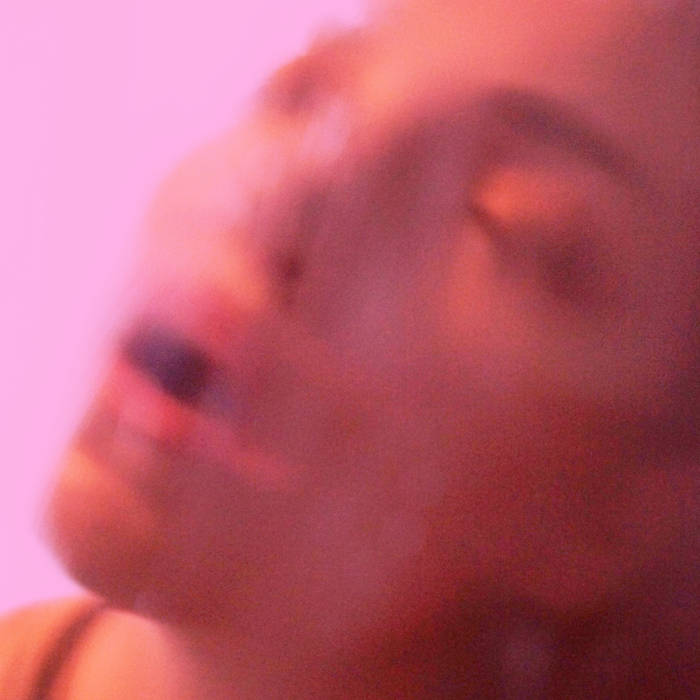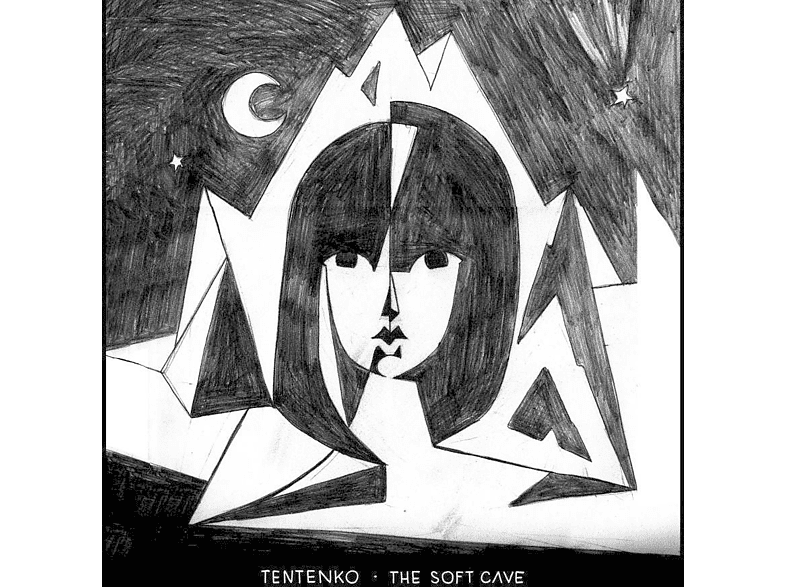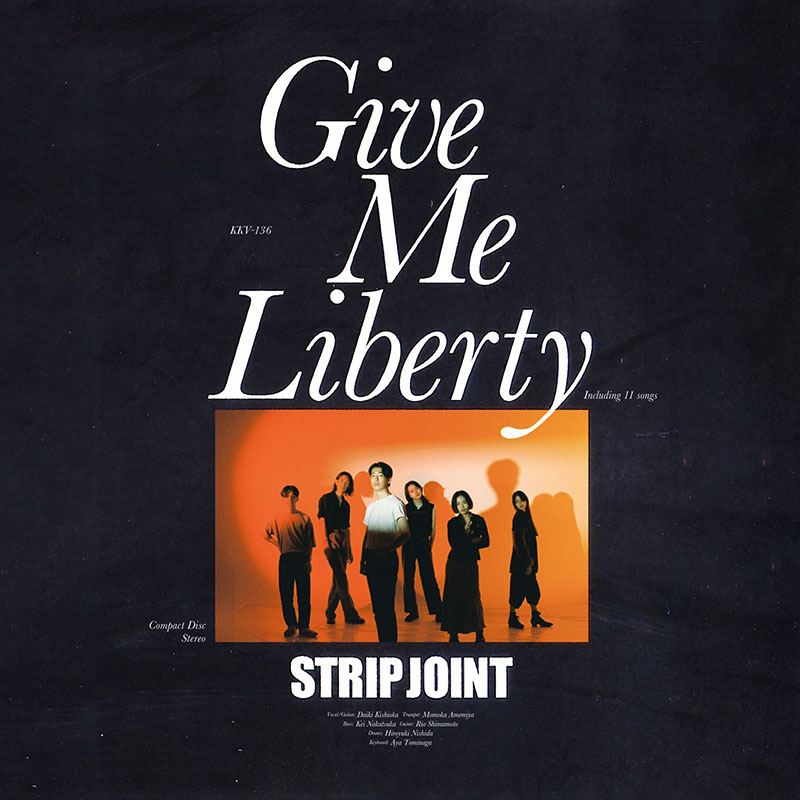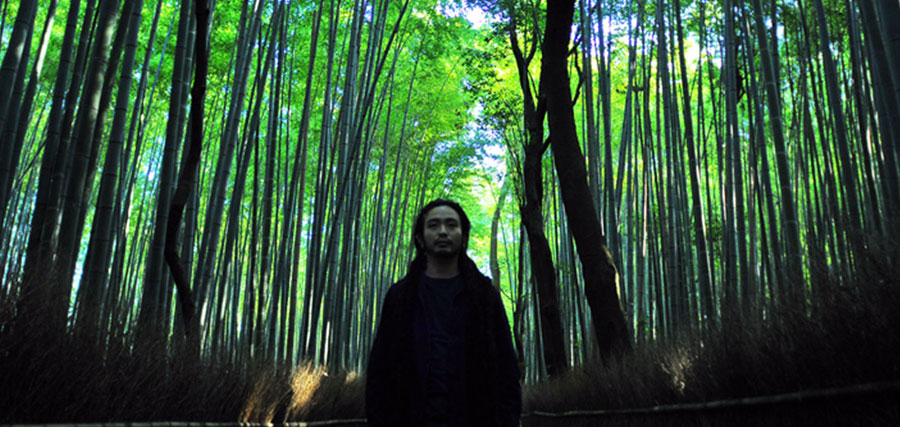来る12月2日、〈Milan〉より坂本龍一のトリビュート・アルバムが発売される。題して『To the Moon and Back』。彼の70歳の誕生日を祝してのリリースだ。アルヴァ・ノトやフェネス、デヴィッド・シルヴィアンにコーネリアスに大友良英といったおなじみの顔ぶれに加え、ザ・シネマティック・オーケストラなどが参加しているのだけれど、目玉はやはりサンダーキャットだろう。なんと坂本78年のソロ・デビュー作収録曲 “千のナイフ” をカヴァー。大胆に彼流のサウンドにアレンジしています。要チェックです。
title: To the Moon and Back - A Tribute to Ryuichi Sakamoto
label: Milan
release: December 2nd
Tracklist:
A1. Grains (Sweet Paulownia Wood) - David Sylvian Remodel
A2. Thousand Knives - Thundercat Remodel
A3. Merry Christmas Mr. Lawrence - Electric Youth Remodel
B1. Thatness and Thereness - Cornelius Remodel
B2. World Citizen I Won't Be Disappointed - Hildur Guðnadóttir Remodel
B3. The Sheltering Sky - Alva Noto Remodel
B4. Amore - Fennesz Remodel
C1. Choral No. 1 - Devonté Hynes Remodel (Featuring Emily Schubert)
C2. DNA - The Cinematic Orchestra Remodel
C3. Forbidden Colours - Gabrial Wek Remodel
C4. The Revenant Main Theme - 404.zero Remodel
D1. Walker - Lim Giong Follow the Steps Remodel
D2. With Snow and Moonlight - snow, silence, partially sunny - Yoshihide Otomo Remodel