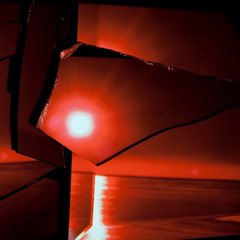MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
Home > Reviews > Album Reviews > TV On The Radio- Nine Types Of Light
先日、TV・オン・ザ・レディオのベーシストのジェラルド・スミスが肺がんで亡くなった。あまりに若い彼の死に多くのファンやミュージシャンが悲しみの言葉を捧げ、バンドはいくつかの予定されていたライヴをキャンセルしたのだが、そのとき、僕は彼らもまたたしかに「バンド」であったのだということを思い知らされた。
そのハイブリッドなサウンドがアメリカにおけるレディオヘッドの最大にして最良の回答だと称賛されたTV・オン・ザ・レディオは、しかしレディオヘッドと違って旧来のバンドの物語のようなものが希薄で、よく組織された音楽集団という印象が強い。とくにその頭脳であるデヴィッド・シーテックは感覚よりも論理でさまざまなジャンルを跨ぎコントロールするタイプのプロデューサーで、アフロ・ファンク、ポスト・パンク、ドゥワップ、ハードコアなどなどを混ぜ合わせて調理するその手際が良すぎるあまり、そのサウンドには良くも悪くも隙や破綻が見えにくいのだ。その言葉も抽象的かつ含意的で、政治的なモチーフを匂わせつつもあからさまな主張にまでは至らせない。彼らは実験精神がひしめくブルックリンにおいても最高の知性派であり、カオティックなニューヨークのゼロ年代を代表する音となった。ただ、その複雑でありながら理知的なサウンドのマルチ・カルチュラルなあり方は、ある程度の文化的な寛容さを聴き手に要求し、その点で日本では海外ほど火がつかなかった。ブルックリン以外には、彼らが属するわかりやすいシーンもなかったこともあるだろう。
しかしそれでも、2008年の『ディア・サイエンス』はバンドに距離を置いていた人間を引きずりこむほどの魅力を持ったアルバムだった。それはさらにさまざまな音楽をぶつけ合いながらもさらに隙がなく完成されたハイブリッド・サウンドになっていたが、同時に情熱的なエモーションに満ちていた。それはメディアによってオバマの登場と都合よく重ねられ、希望に満ちたファンク・トラック"ゴールデン・エイジ"の「黄金時代がやってくる!」という宣言は、偶然だったとしても時代の高揚感と併走した。"DLZ"の怒りに満ちたビートとノイズの迫力、そして"ラヴァーズ・デイ"の輝かしいユーフォリア......それらは、彼らプロフェッショナルな音楽集団のラボから生まれた実験そのものが、可能性を象徴するものとして花開いた瞬間であった。
その後のシーテックによるソロであるマキシマム・バルーンが音楽的にはバンドほどの多様性を見せなかったことを思えば、やはり彼らの複雑な化学反応はバンドという器で生まれるものなのだ。『ナイン・タイプス・オブ・ライト』は結果的にジェラルド・スミスが参加した最後のアルバムとなり、そしてこれまででもっとも穏やかなエモーションに満ちている。"セカンド・ソング"、"キープ・ユア・ハート"、"ユー"と、普通ならアルバムの中盤以降で出てきそうなスロウでジェントルなナンバーが頭から続くことがその印象を生んでいるのだと思うが、そこでとくに目立つのはファンクとソウルの要素で、それは『ディア・サイエンス』のような激しさよりもブラック・ミュージックにおける甘さを持ち込んでいる。"ノー・フューチャー・ショック"はそのタイトルから例の金融恐慌が連想されているそうだが、そこでもホーンが華やかな彩りを添えて禍々しくはならない。"キラー・クレーン"、"ウィル・ドゥ"と続く優しげなメロディのミドルテンポのナンバーもまた、アルバムのムードを決定づけている。なかでは"レペティション"がもっともアップリフティングな演奏を聞かせるが、そこでも荒々しさよりも軽やかさがある。
『ディア・サイエンス』の重厚さ、あるいは初期の重々しさを思えば、本作は彼らのなかでもっともリラックスしたものとなっていて、これまでのプロフェッショナル然とした佇まいはむしろファイティング・ポーズだったのだと思う。ここではそのサウンドの高度さや複雑さよりも、その歌のエモーションの幅や軽やかさが堪能できるが、それは彼らがバンドとして成熟した証だろう。
だからこそひとりのメンバーが永遠に失われたことは相当な痛手であったろうし、その悲しみは深いに違いないが、バンドは前に進むことを決めたようだ。この夏のフェスティヴァルに彼らは出演する。TV・オン・ザ・レディオの実験精神はそのまま、目の前の暗闇を照らす光としてある。
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE