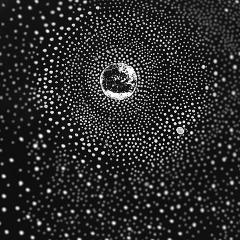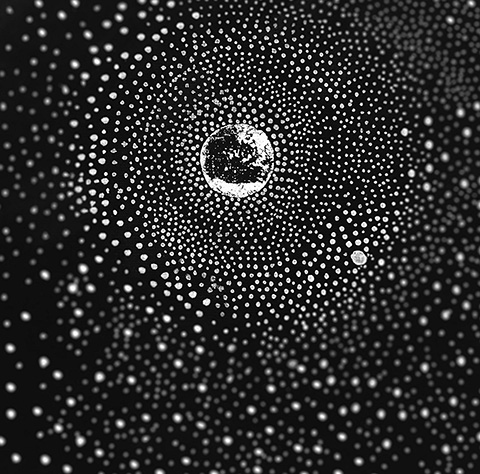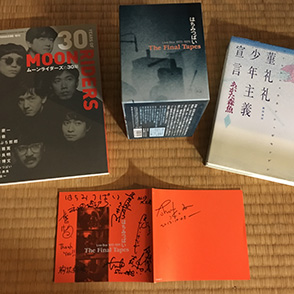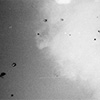MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Regulars > 打楽器逍遙 > 2 類似したものの中の異なったもの
いきなり興醒めな印象を与えかねないが、最近は定額制ストリーミングで新譜を聴いている。なかなかどうして面白い。特にアメリカとブラジルにハマっている。技術やセオリーが風靡していないというか、ちょっとしたアイデアで新たな聴こえ方を模索しているようなところが面白い。先日GONNOさんと少しミーティングした時に、アメリカは自分たちの音楽に若干飽きてきているような雰囲気がある、と言っていたが、その反映なのか、ソンゼイラのように、知っているはずのイかしたものを取り戻そうという意志なのか、ただただ深読みか、ともかく、量で煽ってくるストリーミングに弄ばれないためにはちょっとした自分なりのコツが必要だからそういうことから眺めてみている。アナログで買うのが一番いいですが……。

僕は、ドラムやリズムから眺めてみると記憶に残りやすい。山にドラムセットを広げて、iPhoneとイヤホンで気になった曲をコピーするという奇妙なことをやっているのだが、それをすると曲の仕組みみたいなものが少しずつ見えてくる。USインディーやブラジルの新譜をコピーすると、この曲にはこのパターンでとか、ビートを安易に対象化するのではなくて、一つリズムのエンジンをシンプルな形でフレーズに言わば物象化しつつ、そこからは外れないようにしながら曲展開に合わせて自由に展開していくという手法を感じる。例えば、ケヴィン・モービーの新譜のリード曲“City Music”。イントロはギア1からスタート、ギターインに合わせてリムショットとタム、フロア回しのシンプルなフレーズになるのだが、ベードラとスネアの関係は「ドッチ(タ)フードドチ(タ)」で、それは曲が終わるまで続く。ギターが抜けてベースと少し付き合ってから、タム、フロアが自然と抜ける。歌と共にハットが入る。至極シンプルなフィルのあと間奏でリムショットがスネアに変ってギアが少し上がる。また歌で少しギアが落ちるけど、前の歌よりは少しテンションが高い。それらが繰り返されてリスナーを揺さぶる。ギターリフとフィルでギアマックス、と思いきや歌になる度少し下げつつ、やはり揺さぶりながら全体のテンションが少しずつ上がっていく。しつこいまでの歌とギターリフの繰り返しに呼応するギアの変化。あからさまには上がらず、そこどこに気が配られているけど、エンジンがあるからノレるし、気付いたら上がっている。フレーズが物象化とは言い過ぎかもしれないが、それは、アフロや例えばエルヴィンのようなエネルギーの塊みたいなエンジンが自由に発信されていくことへのリスペクトとパロディ、そしてそこからの展開はちょっとしたアイデア、その聴こえ方は、実に気が利いている!

飽きていることの証明なのか、「クラブでアフリカものとか普通に流れている」とGONNOさんは言っていたが、その実は行ってないからわからない。でも、ハットを抜いて、キープはリズムギターに任せてみるとか、このノリで行きたいからエンジンは決めつつそこから曲に合わせて発展させていくとか、そういうちょっとしたことでも少し新鮮になるかもしれない。また、それは、色んな音楽を見渡せばいくらでもあって、別段新しいことでもないかもしれないが、それをポップスに落とし込もうとする意志が、ビートに、音楽に宿るだけでも聴こえ方は変わる。
ただ、ここに危惧がある。これだけ真似したら、今度はそれこそただの対象化になってしまう。彼らが何を考えて何を聴いてそうなったのか、正確に捉えるには話でもするしかないが、深読みでも勝手な詮索でもいいからルーツや出発点を見つけないといけない。彼らだってきっとそこから始まっている。僕はそこにアフロを感じる。どこがや、と思うかもしれないが、対象化の貼り付けリズムとの差はストリーミングでも充分にわかる。なんでもないビートが気持ちいいなんて、それだけでアフロ的だと、言い過ぎでも言いたい。
そこで、もう一つの危惧が、ストリーミングでのコピーという点。10代の最後の頃、ニール・ヤングをレコードで聴いてノリの違いにびっくりした。“Heart Of Gold”だったか、レコード屋もない小さな街でレンタル屋や一人の友達にかりてせっせとMDに移植して聴いていた頃は、所謂タメの効いたビートだと思っていたのが、7インチで聴いたらタマっているどころか躍動感に溢れていた。90年代のCDの音質のこともあると思うが、騙されたと思った。他にも例はいくらでもある。ライブもとても大事だけど、逡巡の傷跡が最もよく刻まれたレコードはノリも伝える。レコードはいい。
グリズリー・ベアの新譜なんて、フレージング自体もアフロ的で面白かった。レオナルド・マルケスプロデュースのミニマリスタ『Banzo』#1は、場面とフレーズの関係とビルドアップは“City music”に似ているかもしれない。#2は、パルチード・アルトの今!といったら言い過ぎだろうか。#3は、最高のアンサンブル隙間の効いたドラムの間を、ベースがいくのが頗る気持ちいい。ドメニコ・ランセロッチは、『オルガンス山脈』で、ショーン・オヘイガンと組んで、融合を見事にポップスに持ち込んだ。トニー・アレン新譜も楽しみだ。
もしかしたら、僕自身がハズレも多いレコード収集に若干飽きているだけかもしれない。少なくとも、一人で田舎にいるのも、何故かなんだか済まない気がしてくる時があるから、せめて新譜を聴きに、叩きに、山に行っていないといけない。そうしたら、昔のレコードもあらためて新鮮に聴けるような気がする。

Profile
 増村和彦/Kazuhiko Masumura
増村和彦/Kazuhiko Masumura大分県佐伯市出身。ドラマー、パーカッショニスト。2012年からバンド「森は生きている」のメンバーとしてドラムと作詞を担当。アルバム『森は生きている』、『グッド・ナイト』をリリース。バンド解散後は、GONNO x MASUMURA、Okada Takuro、ツチヤニボンド、ダニエル・クオン、水面トリオ、影山朋子など様々なレコーディングやライブに参加。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE