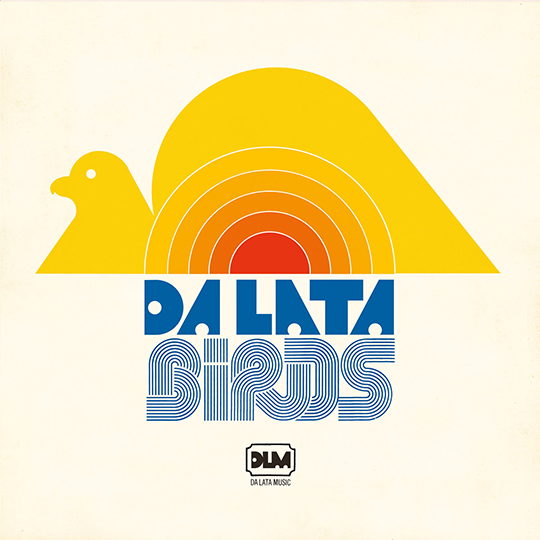MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Da Lata - ロンドン発ラテンの冒険
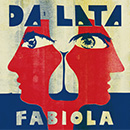 Da Lata Fabiola Agogo Records/Pヴァイン |
来年はW杯ブラジル大会。正直、来実感はまだない。が、しかし、ダ・ラータの10年ぶりのアルバムを聴いていると気持ちがブラジルに傾く。
ダ・ラータの登場はセレソンのように華麗だった。「Pra Manha」(1998年)は渋谷の人混みのなかをドリブルで走り抜け、90年代末のブラジル音楽ブームやブロークンビーツと合流しながら、ファースト・アルバムの『Songs From The Tin』(2000年)まで走り切った。メンバーのひとり、パトリック・フォージは、20年前にはジャイルス・ピーターソンと一緒にクラブ・ジャズの最初の盛り上がりに関わっていた名DJである。
再始動したダ・ラータの最初のリリースは、ザ・ジャムの“ゴーイング・アンダーグラウンド”のカヴァー(2012年)。ポール・ウェラーの新自由主義批判がラテン・ハウスの雄と出会ったとき、何が起きるのか……。
セレソンのような、素晴らしいラテン/アフロを詰め込んだ通算3枚目のアルバム『ファビオラ』を発表したばかりのパトリック・フォージに小川充さんが取材。クラブ・ジャズ黎明期からブロークンビーツ、そして新作にいたるまでの20年の歴史を話してくれた。
ダ・ラータの音楽は、言うなれば「グローバル・ミュージック」であり、それと同時に「ロンドンの音楽」でもある。これらすべてのフレーヴァーはロンドンで見つけられる。アフリカのコミュニティ、ブラジルのコミュニティ、すべてを見つけることができるんだ。異国の音楽は、僕らの世界の一部となっている。これはブラジルの音楽、あれはアフリカの音楽、これはロンドンのクラブ・ミュージック」として区別されて存在しているものではく、すべては同じものの一部なんだ。
■ダ・ラータはどのように結成されたのでしょう? それ以前にパートナーのクリス・フランクが参加するバンドのバトゥがあり、そこであなたも一緒にDJをする中からダ・ラータが生まれたそうですが。
パトリック・フォージ(以下PF):バトゥがはじまったのは1992年か1993年。その頃から僕とクリスは知り合いで、ある日彼が参加するバンドのメンバーを紹介してくれたんだ。そのバンドがバトゥだった。そして、ジャイルス・ピーターソンとフリッジでDJをしていたとき、メンバーのひとりがデモ・テープを持って来たんだ。土曜日の夜の「Talking Loud (and Saying Something)」のときさ。彼らの音楽は粗削りだったけど、光るところも感じた。そうして僕はバトゥの曲をかけるようになり、彼らに興味を持ち、一緒に活動するようになっていった。
でも、バトゥとして活動するのには難しい部分もあった。何人かのメンバーとそりが合わなかったんだ。クリスと僕は音楽の方向性とヴィジョンを共有していたけれど、他のメンバーの何人かはそれに乗り気ではなかった。それにバトゥは7人組のバンドで、グループとしてのまとまりを維持するのにも苦労した。それで、結局スタジオをベースにしたアプローチに切り替えようと思って、僕とクリスはバトゥから離れ、ダ・ラータを始めたんだ。ダ・ラータはバトゥの延長から始まったけど、ミュージシャンの演奏任せにするのではなく、僕とクリスがそれをコントロールしたプロダクション・ユニットと言える。正直なところ、バトゥのブラジル音楽に対するアプローチにはグチャグチャなところがあって、アレンジもいい加減だった。メンバーのまとまりにも欠けていた。そうした点にクリスも不満があり、僕と一緒にやっていきたいとなったんだ。僕らの考えに賛同できるミュージシャンは、その後ダ・ラータにも参加してもらっている。
■あなたはDJとして多くのブラジル音楽を紹介し、そしてダ・ラータは一貫してブラジル音楽をベースとした活動をおこなっていますが、当初はどのようなコンセプトを持ち、どういった音楽性を目指したのでしょう? その頃のロンドンはアシッド・ジャズ・ムーヴメントが沈静化し、DJを中心にブラジル音楽が盛り上がりを見せはじめていた時期にあたると思いますが。
PF:アシッド・ジャズはムーヴメントではなく、流行を作ろうとしたメディアが勝手に付けた名前であって、そもそもジョークとしてはじまったんだけどね……。アシッド・ジャズはファンキーなジャズを強調していて、最初は僕もそれが好きだったけれど、次第に僕のやりたい音楽ではなくなっていった。1990年代初頭だけど、当時はブラジル音楽が段々と広まってきていて、僕はむしろそれに興奮して、DJとしての興味はそちらに一気に向かった。それがバトゥと一緒に活動するきっかけにもなった。ファンク・バンドと組んでギグをやったりするよりも、何かもっと新しくて面白いことをやってみようと思っていたから、そうした方向に行ったんだ。
でも、いま言ったみたいにバトゥはバンドとしてまとまりがなかった。実は今回のアルバムに入っているジョアン・ボスコのカヴァーの“Ronco Da Cuica”は、バトゥも演奏していたんだ。そのときの彼らのアレンジは全く散らかっていて、ある日リハーサルでこう提案したんだ。「OK、フェラ・クティのサウンドを少し取り入れてみよう。フェラの“Shakara”のグルーヴを混ぜて“Ronco Da Cuica”をやってみよう」と。それは面白い試みだったと思うよ。いまは幾つかのブラジル人のアーティスト、たとえばクリオーラとかもアフロビートとブラジリアン・ミュージックを融合させようとしている。でも、僕たちはそれを20年も前にやっていたんだ。
ブラジリアンとアフロの結びつきはひとつの例だけど、そうした融合をバトゥやダ・ラータで試みてきたんだと思う。もちろんベースにはブラジリアン・ミュージックがあるけれど、ただ単純にブラジルの音楽をコピーしようというものではなかった。確かにバトゥにはブラジルで生まれ育ったメンバーもいたけれど、僕たちはイギリスのバンドだと自覚していて、ブラジル音楽のUKヴァージョン、UK流のひねりを加えた音楽を作ろうとしていたんだ。だから、僕たちがやるのは古典的なボサノヴァやMPBというわけではなかった。いつも違うアティチュードでやっていたんだ。
■1997年にエドゥ・ロボをカヴァーした「Ponteio」、1998年には「Pra Manha」といったシングルがヒットし、一躍クラブ・ジャズやディープ・ハウスのシーンで知られる存在となります。また、その後はウェスト・ロンドン・シーンのブロークンビーツ系アーティストとも交流を深め、ベンベ・セグェがヴォーカリストとして加わり、バグズ・イン・ジ・アティック、フィル・アッシャーなどにリミックスを依頼することもありました。こうしてダ・ラータはクラブ・ミュージック・シーンへもコミットしていきましたね。
PF:“Ponteio”は当初フローラ・プリンをフィーチャーする予定だったんだ。でも、彼女のヴォーカルは実際に僕らのトラックにあまりマッチしなくて、結局それは流れてリリアナ・チャチアンの歌になった。この曲は、そもそもヘヴィーなクラブ・トラックにしようと思って作ったんだ。エレクトロニックなテイストを持ち、ブレイクビートやアフロビートとかをミックスした強烈なトラックさ。ブロークンビーツのムーヴメントが来る前で、ある意味でブロークンビーツの元だったと言えると思うよ。人びとはこのリズムに魅了され、これは何だと探求しはじめたんだけど、それはブラジル北東部に由来するバイヨンのリズムだった。それをファンク・ビートとミックスして、エレクトロニックな要素も入れて、ヘヴィーにプログラミングされたグルーヴにした。あの曲はクラブ用の12インチだったけど、オーソドックスなやり方でブラジル音楽をやるのではなく、何かいつもとは違うことをするという点でも面白い試みだった。
あの曲がリリースされたとき、フィル・アッシャーと僕は面識がなかったんだけど、彼は“Ponteio”を本当にサポートしてくれたロンドンの数少ないDJのひとりで、それがきっかけで仲良くなり、一緒にDJもやるようになったんだ。それから彼をきっかけに、ウェスト・ロンドン・シーンとも交流がはじまった。ロンドンより、むしろアメリカからすごい反響があったね。フランソワ・ケヴォーキアンはじめ「ボディ&ソウル」のDJたち、そしてたくさんのニューヨークのDJが取り上げてくれた。彼らがこの曲をかけてくれてるんだと思うと、本当に満足だったし、ハッピーだったよ。
“Pra Manha”のデモは既に1993年か1994年に出来上がっていて、僕はそれをラジオでかけて、何人かがそれを聴いて「この曲最高だよ」って言ってくれた。だけど、最終的な仕上げに取り掛かれるまで4年も待たなければいけなかった。クリスは彼のパートナーのニーナ・ミランダとスモーク・シティというユニットもやっていて、そちらのアルバム制作などで忙しかったんだ。“Pra Manha”もリリアナが歌ったけれど、そもそも彼女はピュアなブラジル音楽の出身で、クラブ・ミュージックに馴染んでいた訳ではなかった。だから、僕とクリスはクラブ向けに作ったトラックと、彼女のヴォーカルをいかに馴染ませるかを苦心したね。
■いま話に出たスモーク・シティは2枚のアルバムを発表しましたが、ダ・ラータがMPBとサンバにハウスなどクラブ・ミュージックのエッセンスを加えたものだとすると、スモーク・シティはボサノヴァとダブやトリップホップをミックスしたような音楽性でした。ダ・ラータとスモーク・シティの違いについては、どのように捉えていますか?
PF:僕も当初はスモーク・シティには参加する予定だったんだ。実際、彼らのファースト・アルバムのなかの1曲に、作曲者としてクレジットされていると思う。ただ、僕とニーナの考えに食い違うところもあって、それでスモーク・シティには参加しなかったんだ。スモーク・シティはある意味で、ニーナがやりたかったことだった。そもそもニーナと、彼女の学校の同級生だったプロデューサーのマーク・ブラウンのふたりではじめたユニットで、そこにクリスが加わったんだ。彼らのデビュー曲“Underwater Love”が出たときは、ちょうどトリップホップのサウンドが流行っていて、そうした点であの曲はユニークなブラジリアン・トリップホップ・チューンだった。あの曲が、そのままスモーク・シティのアイデンティティとなった。一方で、当時ダ・ラータのアイデンティティは、ブラジリアンとクラブ・サウンド、そしてMPB。僕たちのなかではこのふたつのユニットをはっきり区別していて、ダ・ラータのファースト・アルバムがピュアなブラジル音楽に向かった理由のひとつに、クリスがスモーク・シティでできなかったことをやりたい、ということもあったんだ。
取材:小川充(2013年11月07日)
Profile
 小川充/Mitsuru Ogawa
小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE