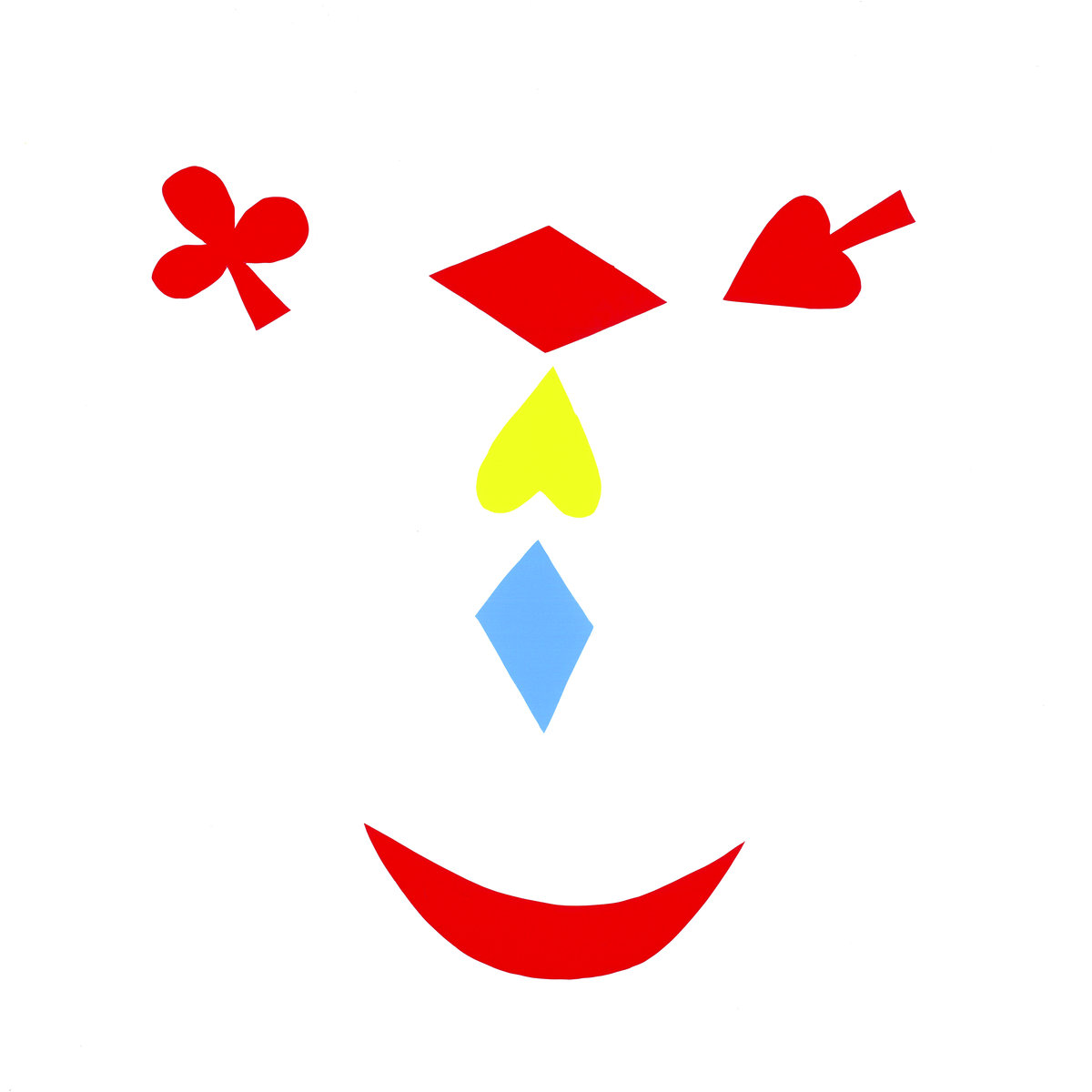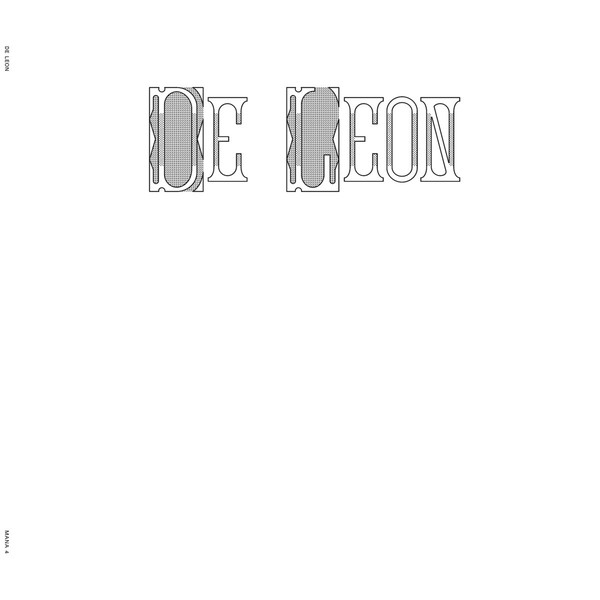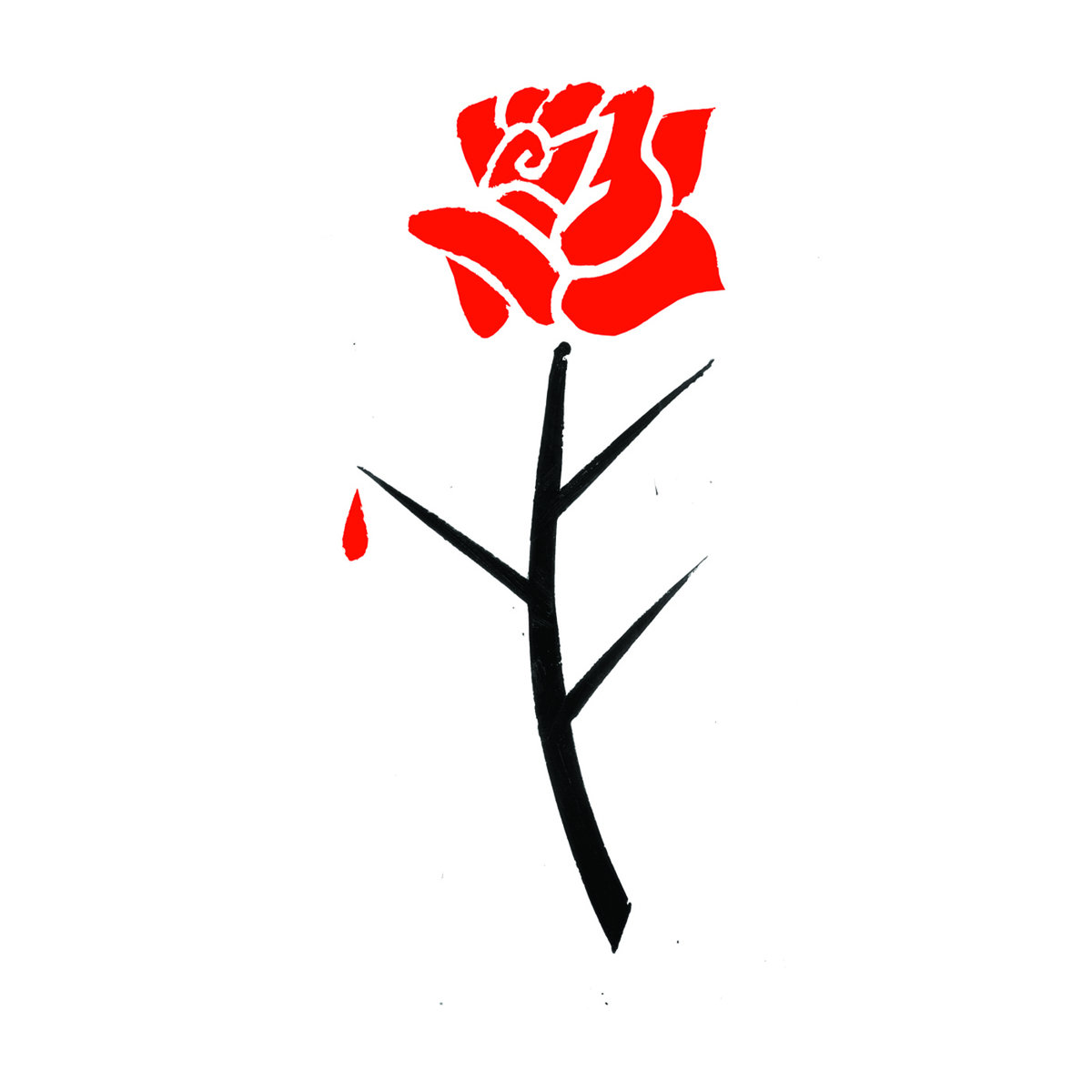MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with DJ Marfox - 声なき人びと、見向きもされない人びと、その顔が俺だ
ずっと待っていた。ベース・ミュージックの枠にもテクノの枠にも収まりきらない、かといっていわゆる「ワールド・ミュージック」や「アフリカ」のように大雑把なタグを貼りつけて片づけてしまうにはあまりにも特異すぎる〈Príncipe〉の音楽と出会い、昂奮し、惚れこんで、その中心にいるのが DJ Marfox だということを知ってからずっと、いつの日か彼に取材できたらと願っていた。だから2016年、タイミングが合わなくて初来日公演を逃したときはひどくがっかりしたけれど、幸運なことに彼はこの3月、ふたたび列島の地を踏んでくれることになり、こちらの期待を大きく上回る最高のセットを披露、まだ寒さの残るフロアを熱気で包み込んだのだった。
とまあこのように、およそ15年前に彼や彼の仲間たちによってリスボンの郊外で生み落とされたアフロ・ポルトギースのゲットー・ミュージックは、いまや世界各地のミュージック・ラヴァーたちの心を鷲づかみにするほどにまで広まったわけだけれど、ではその背後に横たわっているものとはなんだったのか、いったい何が彼らの音楽をかくも特別なものへと仕立て上げたのか──じっさいに対面した Marfox はきわめて思慮深いナイスガイで、誠実にこちらの質問に答えてくれた。

100%ポルトガル人じゃないし、100%アフリカ人でもない。自分たちは「50%・50%(フィフティ・フィフティ)」な存在なんだよね。
■そもそも音楽をはじめたきっかけはなんだったんでしょう?
DJ Marfox(以下、M):音楽をはじめたのは14歳のころで、創作というよりは、他の人の音楽──アンゴラのクドゥロ楽曲を再現するようなことをしていたね。それから徐々にリミックスを作ったり、いろいろな曲の気に入った断片をコラージュするようなことをはじめた。PCの、Virtual DJ というソフトでね。
2004年に Quinta do Mocho (訳注:リスボン郊外の移民たちが多く暮らす団地地域)のパーティで、DJ Nervoso と知り合ったんだ。彼はそこでDJをしていたんだけど、自分の知らない曲ばかりかけていた。そのころ、自分はアンゴラ帰りの人にCDを借りたりして、アンゴラの音楽はだいたい知っていたから、衝撃だったね。だから──これはパーティでいいDJがいたらふつうの行動だと思うけど、DJがどんなヤツで、なんて音楽をかけているのか知りたくて──DJブースに近づいていって彼に話しかけたんだ。「ねえ、自分もDJなんだけど、誰の曲をかけてるの?」と聞いたら彼は「ああ、これは俺が作った曲だよ。俺はプロデューサーだからね」って答えたんだ。それがきっかけで仲良くなって、彼は自分に「プロデューサー」という新しい世界を紹介してくれた。Fruity Loops みたいなソフトの使い方とかもね。
■あなたの音楽はクドゥロから大きな影響を受けていますが、ふつうのクドゥロとあなた独自の音楽との違いはなんですか?
M:子どものころからクドゥロを聴いてきたから、クドゥロは自分の音楽に不可欠な要素のひとつだ。クドゥロにはビートがあって、歌手がいる。でも、当時のリスボンにはクドゥリスタ(訳注:クドゥロ歌手のこと)がいなかったんだ。だから自分たちは、よりダンス・ミュージックにシフトし、躍らせるためのビートを構築することにフォーカスしていった。ホット・ビートと歌い手がいれば、リスナーにインパクトを与えることは簡単だけれど、ビートだけでそれを実現するのは難しい。クドゥリスタが不在であるがゆえに、自分たちリスボンのプロデューサーは、創意工夫をして独自の音楽性を確立していったんだと思うよ。
■2005年に DJ Pausas、DJ Fofuxo とのグループ DJs do Guetto をはじめた経緯を教えてください。当時の野心はどのようなものだったのでしょう?
M:自分も、DJ Pausas と DJ Fofuxo も、アフリカ出身の両親のもとに、リスボン郊外で生まれ育ったキッズで、自分たちのアイデンティティを「ポルトガル人」とも「アフリカ人」とも定義づけられずにいた。自分たちは黒人だから、欧州系のポルトガル人たちには「ポルトガル人」には見えないし、アンゴラやカーボ・ヴェルデやサントメプリンシペのような、ポルトガルの旧植民地から移民してきた人たちにも「君らはアフリカで生まれてないから、僕らとは違うよね」と言われ続けてきた。この作品を発表することは、ポルトガル人でも、アフリカ人でもない、という自分たちの新しいアイデンティティを主張するために必要なことだった。グループを結成したときは、何をしているのか意識的ではなかったけど、「自分たちは何者なんだろう?」というのは当時からの自問だった。100%ポルトガル人じゃないし、100%アフリカ人でもない。自分たちは「50%・50%(フィフティ・フィフティ)」な存在なんだよね。
■2011年の「Eu Sei Quem Sou (訳注:自分が何者か知っている)」は〈Príncipe〉の最初のリリースであり、決定的な一枚となりました。当時はどんな気持ちだったのですか?
M:〈Príncipe〉は自分にとってたいせつな存在で、この作品は最初の子どもみたいなものだ。一緒に〈Príncipe〉をやっている連中とは2007年に知り合っていて、彼らはリスボンの郊外で何が起こっているのか、どんな音楽が生み出されているのかをよく理解していた。でも、当時はまだそれらの音楽を都市部に、そして世界に紹介するコンディションが整っていなかったんだよね。自分たちの音楽はニッチだと思っていたから、適切なかたちでマーケットに紹介するためには準備が必要だった。その期間、自分自身もプロデューサーとして成長し、2011年に〈Príncipe〉は「Eu Sei Quem Sou」をリリースできたというわけさ。この作品は自分にとっては「表明」の作品で、この作品をリリースしたとき、自分が何者で、何がしたくて、どこに到達したいのかが明確な状態だった。〈Príncipe〉の連中も最初に出会った日から自分が何をしたいのか理解してくれていたし、準備期間にもずっと連絡を取り合っていたよ。
■やはりあなたや〈Príncipe〉の面々が郊外出身であるというのは重要なポイントなのですね。
M:そうだね。おもしろいことに、いつも都市部で活躍したいと思ってきたけれど、都市部は長いこと自分たちに関心を払ってこなかった。DJ Nervoso が活動をはじめたのが2001年、自分が〈Príncipe〉の連中と知り合ったのが2007年、「Eu Sei Quem Sou」をリリースしたのが2011年。それぞれのプロセスに5~6年かかっていて、そのあいだ自分たちはずっと、都市部もメディアも注目しない郊外のアンダーグラウンドな存在だった。でも、もしもっと早く注目されていたら、いまのような活動はできていなかったように思う。メディアが「これは一時的なムーヴメントなのか?」と取り上げはじめたころにはすでに、自分たちは長く活動していて準備万端だったから、すべての出来事はベスト・タイミングで起こったと言えるね。
■「Eu Sei Quem Sou」のころには自分が何者か明確になっていたとのことですが、あらためてあなたは何者なのでしょう?
M:自分は「顔」だ。声を持たない人びとの顔、居場所を持たない人びとの顔、見向きもされない人びとの顔、声を発しても聞いてもらえない人びとの顔。それらが「声」を持ったのが自分だと思ってる。思ったことを言い、何をしたいか主張し、互いに敬意を払う。これは「闘い」だったけれど、それはインディペンデントで、社会的な側面もある「音楽プロジェクト」という形態である必要があった。この音楽は人生を変えたんだから。
最近、自分はとても幸せな気持ちで眠りにつくんだ。眠りにつくいまこの瞬間も DJ Nigga Fox や Nídia や Nervoso が地球のどこかでDJをしている、と思えるのはとても幸せな気分だ。いまや〈Príncipe〉には30人近いDJがいて、みんな、レーベル主催のリスボンでの定期イベント《Noite Príncipe》から、イギリス、アジアやアメリカまでDJしに飛び回っていて、もはやポルトガルだけでなくヨーロッパがホームだと感じるくらいだ。人びとのために、音楽で成し遂げなければならないことをやっている。人がいなければ音楽ではないからね。
■他方で何がしたいかも明確になっていたとのことですが、そのあなたがやりたいこととは?
M:都市部と郊外の架け橋になることだね。自分の作る音楽がなければ、今日自分はここにいないだろう。音楽をやっていなかったら、自分は大学も出ていないし、多くの友人たちがそうしたように、イギリスかドイツにでも移民していただろう。この音楽は発表した当初から、国内外で注目されて、そのことによって「アフロ・ポルトギースも価値ある存在なんだ」「新しい存在、新しいリスボンを代表する存在なんだ」ということを革命的に示すことができた。以前より居場所があると感じているし、希望も感じているけど、まだまだ活躍の場を生み出すことはできる、ポルトガル社会においてアフロ・ポルトギースの存在を示すことはできると思っている。

自分は「顔」だ。声を持たない人びとの顔、居場所を持たない人びとの顔、見向きもされない人びとの顔、声を発しても聞いてもらえない人びとの顔。それらが「声」を持ったのが自分だ。
■ペドロ・コスタという映画監督を知っていますか? 彼の『ヴァンダの部屋(原題:No Quarto da Vanda)』という映画を観たことは?
M:彼の映画『ホース・マネー(原題:Cavalo do dinheiro)』は観たことあるよ。ポルトガルにおける移民の扱い、移民がいかに疎外されているかにかんして鋭い批判をしている人だ。移民たちの抱える問題はゲットーを作ることではなく、ゲットーを抜け出せないことにある、と彼はよく理解しているよね。自分たちの親や祖父母の世代がアフリカからポルトガルに移民してきたのは、植民地化から解放されて何も残らなかった故郷にいるよりも、良い人生を送りたかったからだ。でも、たとえばポルトガルでの教育ひとつをとっても、義務教育レベルで優秀な教師は都市部の学校にいて、郊外には質の高くない教師があてがわれる。ペドロ・コスタは、そういった状況……「移民支援」のような「嘘のシステム」についても指摘しているよね。『ホース・マネー』でも、若くしてポルトガルに移民してきたカーボ・ヴェルデ出身の老人が、長年リスボンの工事現場で、都市の、ポルトガルの発展のために働いてきたにもかかわらず、社会保障や年金を受けられないまま死の床にある様子が描かれている。30年以上、陽の当たらないスラムに住みながら働いて、何も得られない、という作中の彼のような状況に置かれたアフリカ系移民はたくさんいると思う。
とはいえ物事にはいろいろな側面があって、1974年4月25日(訳註:ポルトガルでカーネーション革命が起こり、独裁政権が終焉を迎えた日。同時に、各アフリカ植民地独立の契機となった)以前の祖父母世代の人びとの生活は、いまよりずっと苦しいものだったということも理解している。ペドロ・コスタはそういったことも含めた社会矛盾を指摘している映画監督だと思うよ。個人的にも知り合いだしね。
■知り合いだったんですか! 彼とはどのような経緯で?
M:共通の知り合いがいて、その人がペドロに「いままでのリスボンにはなかったような音楽活動をしている人たちがいる」と言ったら、彼が興味を持ったらしいんだよね。彼はうちに遊びにきて、自分の母親にも会ったことがあるよ。
■先ほど「架け橋になりたい」という話が出ましたが、郊外のあなたたちにとって都市はべつに「敵」のような存在だったわけではない、ということですよね。
M:ぜんぜん。僕らが Musicbox (訳註:リスボンのナイト・シーンの中心的クラブ)で毎月開催しているイベント《Noite Príncipe》は、Musicbox で続いているいちばん長い定期イベントで、2月20日にちょうど7周年を祝ったところだ。このときは特別に、ポルト含め5箇所でイベントを同時開催したんだけど、すべてソールドアウトだった。貧乏人も金持ちも外国人もほんとうにいろいろな人びとが遊びにきていて、これが音楽の力だなと実感したよ。リスボンも、世界も、ますますオープンになっていくし、世界じゅうの人びとが集まる自分たちのイベント《Noite Príncipe》がそれを証明していると思う。
■ではもしあなたたちに「敵」がいるとすれば、それはなんでしょう?
M:自分たちに唯一「敵」がいるとすれば、それは自分たち自身さ。自分たちが音楽を作ることをやめてしまうこと、諦めること──それが最大の敵だね。
■ということは、そろそろ DJ Marfox 名義の新作も?
M:うん、取りかかっているところ。だいぶ長いことかけているわりに、発表できていないんだけどね。自分は「アルバムを作らなきゃ」っていうプレッシャーだったり、「自分の作品を見てもらいたい」みたいな自己顕示欲が強いタイプじゃないから、気楽な気持ちで取り組んでる。こうしてあちこち旅行して、他のいろんなDJや音楽を聴いて影響を受けて、それでも自分のベースになる要素は忘れずに、プロデューサーもこなして……というスタイルが自分には合ってると思う。自分名義の作品は、プロデュースやリミックスの依頼をこなしつつゆっくり作っているよ。ヴェネツィア・ビエンナーレのドイツ館の音響を担当する話もあるし(註:7月には彼を含むドイツ館の楽曲を収録したLPもリリースされる模様)。
■それはすごいですね。ちなみに〈Domino〉の Georgia の曲を5曲、共同でプロデュースしたという情報を見かけたのですが。
M:もう公開されているはずだよ(註:取材後に再度調べたところ、たしかに新曲は公開されているものの、ふたりがコラボしたという情報は本人の発言以外見つからず)。1月にロンドンに行ったのもその繋がりで、Laylow という新しいヴェニューで彼女が1月のあいだ、レシデンス・アーティストとキュレーションを手がけている、その最終日に出演したんだ。
取材・文:小林拓音(2019年6月06日)
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE