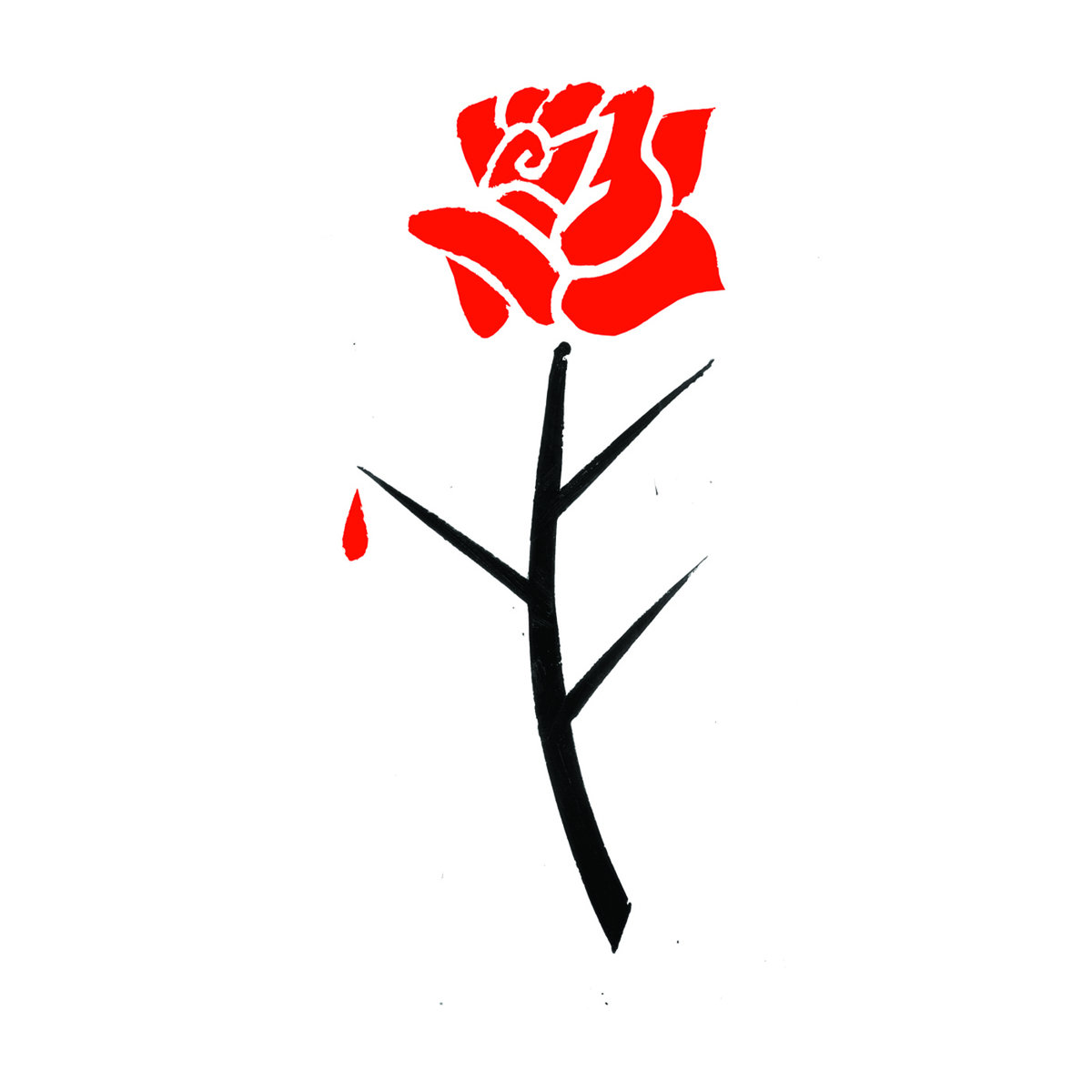MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > DJ Marfox- Chapa Quente
小林拓音 Oct 26,2016 UP
キツネだらけである。誰も彼もが尻尾に「フォックス」をくくりつけてなびかせている。DJ MarfoxにDJ Nigga FoxにDJ Babaz Foxに……数えだしたらきりがない。さりげなく「コックス」も紛れ込んでいるが、一体このキツネ崇拝集団は何なんだろう。たしかにキツネはかわいいし、僕も毎晩キツネ写真館の画像を眺めては癒されているけれど、〈Príncipe〉というレーベルのもとで彼らが展開している音楽は、「かわいい」からはあまりにもかけ離れたゲットー・サウンドである。
彼らの鳴らすトライバルでポリリズミックな音楽は、既存のスタイル名で呼称するのが非常に難しい。暴力的に単純化してしまえば、クドゥーロなどのアフリカン・ダンス・ミュージックが、ハウスやテクノ、あるいはグライムやダブステップといったベース・ミュージックと衝突する過程で、突然変異的に発生した音楽、と言うことができるだろうか。
キツネを信奉するこの風変わりなダンス・ミュージックのシーンは、リスボンの郊外へと隔離されたアフリカ系の若者たちによって00年代半ばに生み出された。つまり彼らの音楽は行政によるジェントリフィケイションの産物であり、多分に政治的な側面を具えたものであると言うことができる。彼らの背景に関する情報がなかなか入ってこないのがもどかしいけれど、『RA』誌の記事によれば、ポルトガルで大きな影響力を持つあるジャーナリストが、「〈Príncipe〉は1000の政治集会よりも影響力がある」と書いたことさえあるらしい。要するに、正真正銘のカウンターなのである。リスボンのゲットーというと、ペドロ・コスタの『ヴァンダの部屋』(2000年)を思い浮かべる人も多いだろう。個人的にあの映画の中で最も印象に残っているのは、アフリカ系の若者がボブ・マーリーの歌を口ずさんでいるシーンなのだけれど、あの強烈な諦念の数年後にこのゲットーのシーンが胎動しはじめたわけだ。
発火点となったのは、2006年にオンライン上に公開されたコンピレイション『DJ's Do Guetto Vol. 1』だったようである。しかしその時点ではまだ彼らの音楽は、リスボン内のローカルなものに留まっていた。彼らのシーンにとってより大きな転機となったのは、DJ Marfoxが2011年に放ったEP「Eu Sei Quem Sou」である。そのリリースとともに活動を開始したレーベル〈Príncipe〉は、DJ Nigga Foxの「O Meu Estilo」(2013年)や複数のアーティストが参加した「B.N.M. / P.D.D.G」(2013年)などのリリースを通して、着実にその特異なサウンドの胞子をばら撒いていった。そして2015年、彼らの奇妙なベース・ミュージックは、UKの名門レーベル〈Warp〉によって再発見されることになる。
昨年の春から秋にかけてドロップされたEP3部作「Cargaa」は、OPNの『Garden Of Delete』を除けば、昨年リリースされた〈Warp〉のカタログの中で最も重要かつ最もエキサイティングなタイトルであった。その3枚の12インチは、リスボンのゲットー・サウンドをこれまで以上に広く世界に知らしめるものであると同時に(『ガーディアン』紙のような大手メディアが特集を組んだくらいである)、ベース・ミュージックがどんどんワールド・ミュージックと交錯していく近年の潮流を改めて確認する役割を果たすものでもあった。
もしその「Cargaa」シリーズが1枚のコンピレイションという形にまとめられていたならば、そしてもう少しだけ早くリリースされていたならば、それは〈Planet Mu〉によるジューク集『Bangs & Works』(2010年)や〈Honest Jon's〉によるシャンガーン・エレクトロ集『Shangaan Electro』(2010年)と並んで、後世へと語り継がれる1枚になっていただろう。いつも少し遅いが、ポイントははずさない――たしかにそれこそが〈Warp〉のやり方ではあるものの、このリスボンのゲットー・サウンドに関しては、〈Adam & Liza〉がコンパイルした編集盤『Lisbon Bass』(2012年)がすでにその紹介者としての務めを果たしてしまっていたのかもしれない(ただし、〈Príncipe〉に焦点を絞った「Cargaa」とはコンパイルの趣旨が異なっているが)。
このリスボンのゲットー・シーンをキツネだらけにした張本人が、DJ MarfoxことMarlon Silvaである。〈Príncipe〉の連中がこぞって「フォックス」を名乗るのは、シーンの中心人物である彼に敬意を表してのことらしい。1988年生まれのMarlonは、幼い頃にプレイしていた任天堂のゲーム『スターフォックス64』の主人公から現在のステージネームを思いついたそうだ。
彼は上述の「Eu Sei Quem Sou」(「I know who I am」という意味)で高らかに自らの存在を世界へと知らしめた後、「Subliminar」(2013年)を挟んで、いまはFuture Brownの一員でもあるJ-Cushの主宰する〈Lit City Trax〉から「Lucky Punch」(2014年)を発表し、英米のベース・ミュージック・シーンとの合流に成功する。そして昨年は上述の「Cargaa」に参加したり、レトロスペクティヴな『Revolução 2005-2008』をまとめたりと、これまでの彼らのシーンや自身の歩みを総括するような動きを見せていたが、今年の春にようやく2年ぶりとなる新作「Chapa Quente」をリリースした。
ここ数年の間に〈Lit City Trax〉や〈Warp〉といった英米のレーベルを経由したからだろうか、「Eu Sei Quem Sou」のような無茶苦茶な感じというか、一体どう形容したらいいのかわからない混沌とした感じはほんの少しだけ薄まっているものの、それでも十分強烈なダンス・トラックがこのEPには並んでいる。レゲトンの“Tarraxo Everyday”のみ他の曲とは毛色が異なっているけれど、先行シングルとなった“2685”から最後の“B 18”まで、基本的にはアフリカンな要素を強めに押し出したパーカッシヴなスタイルが貫き通されている。「俺がドンだ」というMarfoxの矜持が示された貫禄の1枚といったところか。
そしてこの夏、〈Príncipe〉本体からCD作品としては初となるレーベル・コンピレイションがリリースされた。DJ Marfoxやすでに名の知られたDJ Nigga Foxをはじめ、「Cargaa」に参加していた面々(DJ Lilocox、DJ Firmeza、K30、Nídia Minaj、Babaz Fox、Puto Anderson、Puto Márcio、Ninoo、DJ Nervoso、Blacksea Não Maya)や、今回が初登場となる新人も名を連ねており、全23曲というお腹いっぱいのヴォリュームである。
まずは、これまでの〈Príncipe〉のイメージを踏襲したスタイルの曲が耳に飛び込んでくる。DJ Danifoxの“Dorme Bem”やNídia Minajの“Festive”、あるいはDJ Nervosoの“Lunga Lunga”など、アフリカンで、トライバルで、パーカッシヴで、ポリリズミックなトラック群は、このリスボンのゲットー・シーンを外へ向けてわかりやすく紹介する役割を担っているのだろう。中でもやはりDJ Nigga Foxは頭ひとつ抜けている感があり(DJ Marfoxの「Chapa Quente」と同じ頃に出たコンピレイション「Conspiración Progresso」に収録された彼のトラックも、異様なもたつき感が脳裏に残り続ける極めてストレンジなトラックだった)、“Lua”のぶっ飛び具合は彼らのシーンの特異性を如実に物語っている。
昨年の「Cargaa」では、まるで「シンプルなリズムを使用してはならない」という戒律でもあるかのようにみながみなポリリズミックに時を刻んでおり、そこに風変わりな上モノが重なることで独特の揺らぎが形成されていたのだけれど、このコンピレイションは「Cargaa」以上に多様なサウンドを差し出して見せる。
DJ Cirofoxによるメロウなヒップホップ(“Moments”)、DJ Lycoxによるジャポニスム(“Dor Do Koto”)、DJ TLによるフェイク・ハウス(“Deep House”)、DJ LilocoxやDJ MabokuによるUKガラージ~ダブステップ(“La Party”、“Ruba Soldja”)、Niagaraによるシンプルな4つ打ち(“Alexandrino”)、Babaz Fox & DJ BebedeiraやNinoo & Wayneによるレゲトン(“Tarraxeí No Box”、“Cabríto”)、Puto Márcioによるフェイク・ダブ(“Não Queiras Ser”)、Blacksea Não Mayaによるエグゾティスム(“Melodias Rádicas”)、……とむりやり既存の言葉を羅列してはみたけれど、そのすべてにアフリカンなギミックが施されており、本当にストレンジなトラックばかりが並んでいる。彼らの果敢な試みに刺戟されたのか、「ドン」であるDJ Marfoxも自身の“Swaramgami”に細かく刻まれたヴォイス・サンプルを挿入するなど、新機軸を打ち出してきている。
おそらくこのコンピレイションは、〈Príncipe〉というレーベルの底の深さを証明するために編まれたものなのだろう。しばしば、どこまでもロックの域を越え出ることのない平凡なバンドに「ミクスチャー」なる不相応な単語があてがわれることがあるが、〈Príncipe〉の連中は「ミクスチャー」という言葉の本当の意味を知っている。世界は俺らの手の中――まるでそう宣言しているかのような多彩なコンピレイションだ。
現実がハードであればあるほど、そこで鳴る音楽は輝きを増す――リスボンの第4世界=ゲットーで生まれたこのベース・ミュージックは、まさにそのことを証明しているのかもしれない。この形容しがたい不思議なサウンドたちは、一体どのような背景から生まれてきたのだろう? かの地のアフリカ系の若者たちは、一体どのような状況に置かれているのか? かの地で進められているジェントリフィケイションは、一体どのような様相を呈しているのか?
〈Príncipe〉の音楽を聴き終えた僕はいま、そのあまりに奇妙なリズムとシンセの狂騒に、キツネにつままれたような気分になっている。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE