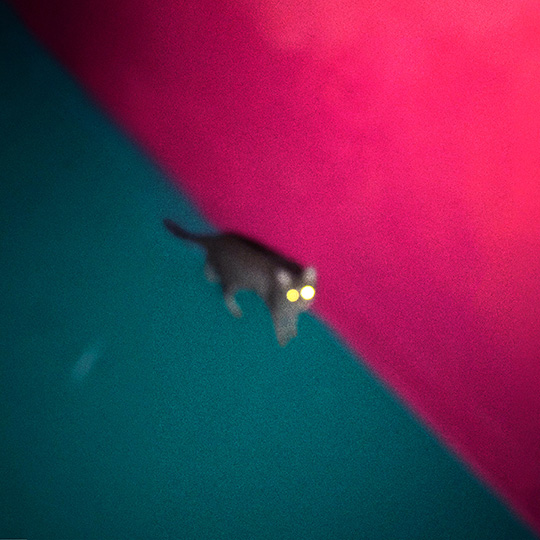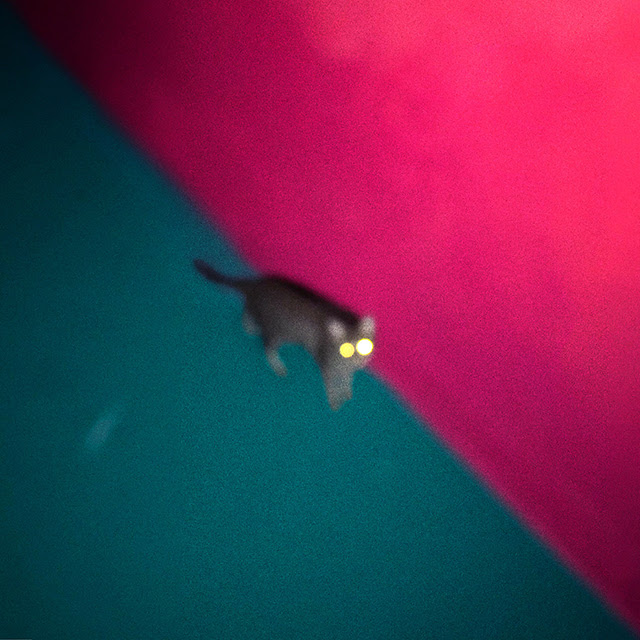MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with !!! (Nic Offer) - 共和党にパンチをお見舞い
ぶん殴る。それがタイトル『Wallop』の意味だ。直球である。アティテュードにかんしていえば当時のニューヨーク市長、ジュリアーニを痛烈に批判した2003年の出世作「Me And Giuliani Down By The School Yard (A True Story)」のころから何も変わっていない。
とはいえもちろん、チック・チック・チックはもう20年以上活動を続けているバンドである。細部のサウンドは幾度も変化を重ねてきた。もろにディスコに傾斜した前作『Shake The Shudder』から2年、今回の新作はだいぶヴァラエティに富んだ内容に仕上がっている。不穏でいかめしげな1曲目から、アコースティックなギターとエディットされた音声のかけ合いが最高の快楽をもたらすハウス調の“Couldn't Have Known”を経て、先行シングル曲“Off The Grid”へといたる序盤の流れや、80年代の歌謡曲のような主旋律とアレンジに、それとは正反対の強烈なドラムスが覆いかぶさる“Serbia Drums”もおもしろいのだけれど、このアルバムの醍醐味はそれ以降の展開にある。もの憂げな“Slow Motion”も新鮮だし、「5万ドルでは俺の心は変えられない」と歌われる“$50 Million”では、ベースがなんとも不思議な動きを見せている。あるいは、チャイルディッシュな電子音が特徴の“Domino”も、チック流ダーク・エレクトロを聴かせる“Rhythm Of The Gravity”も、ともに加工された音声が印象的で、いつもとはちょっと異なる彼らの表情を垣間見させてくれる。1枚のなかにこれほどさまざまなアプローチが同居しているのは、彼ら史上初めてのことではないだろうか。
それら種々の試みすべてに共通しているのはそして、やはりダンスである。どれほど細部に趣向を凝らそうとも、彼らがダンスを忘れることは絶対にない。どんなに社会や政治の状況が絶望的であろうとも、彼らは踊り狂うことでそれを笑い飛ばす。それこそがチック・チック・チックというバンドの本懐であり、また今回の「ぶん殴る」という「反撃」の支柱でもあるのだろう。どこまでもほとばしる熱いパッション……いやはや、秋の来日公演が楽しみでしかたない。
前回の大統領選挙では、共和党からびっくりするようなパンチをくらった気がした。このアルバムは俺たちの反撃を意味している。俺たちもやつらにたいして「Wallop」をお見舞いしたいと思ったんだ。
■今回の新作のアートワークでは、ネコが目を光らせて境界を渡っています。これは、ネコはヒトが決めた境界を軽々と越えていく、というようなメッセージなのでしょうか?
ニック・オファー(Nic Offer、以下NC):(笑)。そうじゃないけれど、その解釈は最高だね。俺のお隣さんが引っ越して出ていったんだけど、俺はその部屋の開け方を知っていたからドアを開けて入った。俺はパーシーという名の子猫を飼っていて、パーシーは基本的には俺の家の部屋という世界しかいままで知らなかった。そのとき、パーシーも隣の家に入ってきて、突然パーシーにまったく新しい世界が開けた。パーシーはとても昂奮して、全神経を研ぎ澄ましていたよ。パーシーが隣のアパートメントに入ったところの瞬間の写真を撮ったんだ。アートを作るとき、俺はそういう感覚でいたい。まったく新しい世界に入り込んだ子猫のような感覚。
■ちなみに、ネコ好きですか?
NC:(笑)。好きかどうかがわからない、というのが問題だよね。ネコは、人間の脳をおかす病気を持っていて、その病気にかかると人間はネコの中毒になってしまうという。そうなるんだよね? よくわからないけど、俺もその病気に感染していることはたしかだ(笑)。俺は初めて会ったときからネコが大好きだ。今回のアルバム・カヴァーの主役となったパーシーも大好きだ。ちょうどこのアルバムの制作に入るときに、子ネコのパーシーをもらってきたから、パーシーは今作に本質的に関連していたのさ。
■今回の新作はチック・チック・チックにとって8枚目のアルバムとなります。もうそろそろヴェテランの仲間入りと言ってもいいかと思うのですが、これまでの歩みを振り返ってみてどう思いますか?
NC:苦労の連続だったよ。でもこれは、つねに俺がやりたかったことなんだ。これに勝る重要なことはいままでに一度もなかった。他のバンド活動をしていたときも、アウト・ハッドを同時進行していたときも、このふたつのバンドは俺たちの子どもみたいなもので、両方ともいちばん大事だった。いままでずっと、この活動は、俺がいつもやりたいと思っていたことだから、あまり立ち止まって考えるということはしなかったね。俺がやってきたことは、つねに、バンドにとって最高のアルバムを次も出せるようにしてきた準備だった。チック・チック・チックというバンドの枠のなかで、俺たちがうまくなって、より良いバンドになっていくというのがつねに課題としてある。
■5枚目の『Thr!!!er』でパトリック・フォードとスプーンのジム・イーノをプロデューサーに迎えて、音が変わりました。その後パトリックとはずっと組んできて、今回も参加しています。彼のどういうところがあなたたちと合うのでしょう? ジムとの違いは?
NC:ジムは昔からいる典型的なプロデューサーという感じで、パトリックは新しいタイプのプロデューサーという感じだね。パトリックは単刀直入にものを言うから、俺たちをムカつかせるときもあるが、そこが俺たちと合っているんだと思う。でも冗談を言い合ったりできる関係性だから、彼は何かが良くないと「それは良くない」と言い、同時に俺たちのことをバカにできる。それは良いことだと思う。核心に触れることができるから。俺たちにたいしてなんでも言えるような人が欲しいからね。彼はその役に適している。パトリックは、俺たちが尊敬できるような、素晴らしい耳を持っている。それに彼とスタジオにいるのは楽しいから、彼と一緒に時間を過ごすのが俺たちはたんに好きなんだ。
■今作にはホーリー・ファックのグラハム・ウォルシュも多くプロデュースで参加していますね。彼が今回あなたたちにもたらしたものとは?
NC:グラハムはホーリー・ファックのメンバーで、そこで彼はホーリー・ファックのやり方で活動している。今回は彼がチック・チック・チックのメンバーとして何週間か加わったような感じだったからクールだった。だから俺たちとはちがうキャラクターやアイデアをバンドにもたらしてくれたよ。俺たちが提案しないようなことを提案してくれる人が好きなんだ。彼の活動しているシーンは俺たちと近いけれど、俺たちとはべつのことを提案してくれる人だったからそれが良かったな。

■“Couldn't Have Known”や“Domino”、“Rhythm Of The Gravity”などでは声が加工されたりチョップされたりしています。あなたたちの音楽において「声」はどのような位置を占めるのでしょう? 特別なものなのか、数あるサウンドのなかの1種類にすぎないのか。
NC:ヴォーカルは特別なものだと思うね。ヴォーカルは映画で言うとスクリーンの中央を占めているものだ。まわりでいろいろなことが起こっていて、メインとなるアクション。だが同時に、サウンドの1種類として扱うのも好きだ。俺たちが好きなダンス・チューンで聞こえるヴォーカルは、リズム楽器のように使われている場合が多い。そういう使い方も好きだね。だからヴォーカルでもなんでも、柔軟性を持って取り組むやり方が良いと思う。
■今後オートチューンを使う予定はありますか?
NC:過去に使ったことはあるよ。オートチューンは俺にとって、フルートやピアノと同じ、ひとつの楽器にすぎない。ピアノも、これから先のアルバム6作に使うかもしれないし、もう二度と使わないかもしれない。オートチューンもそれと同じ考え方だよ。
■“Serbia Drums”の上モノは80年代のポップスを想起させるのですが、それとは対照的にドラムが強烈です。歌詞もビジネスのダーティな側面を暗示させる内容ですが、なぜ「セルビア」なのでしょう?
NC:曲が、セルビアでおこなわれたサウンドチェックの音をもとに作られたからだよ。とても独特に響く空間で、ドラマーのクリス(・イーガン)が「この部屋の響き方は最高だ」と思い、あのビートをドラムで演奏して「これを使って曲にできないか?」と俺たちにファイルを送ってくれた。それは携帯電話で録ったビートだったんだけど、それを使ってラファエル(・コーエン)がこの曲にしたのさ。最初からこの曲は“Serbia Drums”というファイル名で、曲を完成させたときも、「それが曲名だな」と思った。ドラムの響きが特有なのを聴いてもらいたかったからこの曲名にしたというのもあるね。
西洋の世界において昔は、 聖書だけが人びとにとってのエンターテインメントだった。いまの時代はポップ・カルチャーやニュースがエンターテインメントになった。クレイジーな人たちはそれにインスピレイションを受けてクレイジーな行動に出ている。
■7曲目の“Slow Motion”からアルバムの雰囲気ががらりと変わり、“Domino”や“Rhythm Of The Gravity”と、いろんなタイプの曲が続きます。後半はかなりヴァラエティに富んでいると思うのですが、全体をこのような構成にした理由は?
NC:俺たちはアルバムを通しで聴くという世代の人間だ。最近はプレイリストなんかが人気で、音楽の聴き方が、アルバムよりも曲のほうが大事にされていて、シングルや45 rpmの時代に戻ったようで、それはそれでエキサイティングだと思うし、俺たちも気に入っているけれど、同時に俺たちはアルバムを聴いて育ってきた。だからアルバムをつくるというのは、俺たちにとっては夢が叶ったのと同じことだから、アルバムはリスナーが存分に体験できるものにしたいと思っている。映画のように山があり谷があり、サスペンスを感じる瞬間があるようにしたい。だから俺たちは、豊かで、バランスの良いアルバムを作ろうとしている。
■“$50 Million”は、「5万ドルでは僕の心は変えられない/でも、5000万ドル積めば変わるかも」「4900万ドルで手を打つ」というフレーズが印象的です。もし私が「4900万ドルあげるから、トランプ支持者になれ」と言ったら、なりますか?
NC:(爆笑)。たぶんならないだろうね。俺が寝返ると思ったかもしれないけど、俺はそんなことはしないよ。
■素朴に、お金は欲しいですか? ちなみに私は欲しいです。
NC:(爆笑)。いらないよ。ただバンド活動を続けられればいい。“$50 Million”は、「俺は絶対に寝返らないぜ」とやけに聖人ぶった感覚について歌っている曲で、寝返ったやつらを非難している内容なんだけど、同時に自分は絶対に寝返らない、とも言っている。だって絶対にもらえない額を提示しているからね。だから両方の意味があって俺は気に入っている。誰にでも、自分が手を打つ金額というものがある。歌詞にもあるけど、俺は誘惑されたこともあるけど、そんなに頻繁にじゃない。5万ドルでは俺の心は変えられない。
また、チック・チック・チックにとって「寝返る」ということがなんなのか俺にはよくわからない。俺たちはべつに寝返らない。自分たちに合わないと感じたCMの依頼は断ってきたけど、そんなに悪くないなと思ったCMの依頼は受けてきた。複雑で微妙なテーマではあるけれど、俺たちはまだ自分たちのパンクのルーツを主張して、そういう曲を書いてもいいと思っている。
■先週はテキサスとオハイオで立て続けに銃の乱射事件がありました。エルパソの方の事件は、移民にたいするヘイト・クライムだったとも言われています。トランプは自分は差別主義者ではないと言っているようですが、これはトランプが大統領になったことで引き起こされた事件だと思いますか? それとも彼はとくに関係なく、合衆国では以前からずっとそういうレイシズムにもとづく犯罪が多かった?
NC:その両方だと思う。レイシズムにもとづく犯罪はアメリカの歴史の一部として昔からあったことだ。だが、アメリカに住んでいる人なら誰でも明確に感じているのが、ここ数年でアメリカの雰囲気は変わったということ。レイシズムがアメリカに前からあったのはたしかだけど、トランプはそのレイシズムという火に油を注いでいる。その火をかき立てて、より大きなものにしている。あの乱射事件を起こしたやつは狂っていて、精神が病んでいることは間違いない。西洋の世界において昔は、 聖書だけが人びとにとってのエンターテインメントだったから、それをもとにクレイジーなことをするやつがいた。クレイジーなヴィジョンを持って、それをやる必要があると思って実行するやつがいた。いまの時代には、クレイジーなことをするためのインスピレイション源が聖書以外にもたくさんある。ポップ・カルチャーやニュース、そういうものが人びとのエンターテインメントになった。クレイジーな人たちはそういうものにインスピレイションを受けてクレイジーな行動に出ている。
■アルバム・タイトルの『Wallop』には、そういう暗い状況を打ちのめしたい、という想いが込められているのでしょうか?
NC:もちろんだよ。タイトルにはいろいろな意味があるんだけど、「Wallop」という言葉を調べたときに、まずはその言葉じたいに惹かれた。「なんておもしろい言葉だろう!」と思った。少し古臭い言葉で、最近はあまり使われない。でも使うときは、独特な意味を持って使う。「Wallop」という特有の打たれ方として使う。調べたら、「簡潔明瞭で、相手を驚かせる打ち方」とあった。このアルバムも簡潔明瞭に響くものにしたかった。そして驚かせるようなパンチのあるものにもしたかった。前回の大統領選挙では、共和党からびっくりするようなパンチをくらった気がした。俺たちはみんな驚いたよ。このアルバムは俺たちの反撃を意味している。俺たちもやつらにたいして「Wallop」をお見舞いしたいと思ったんだ。
質問・文:小林拓音(2019年8月30日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE