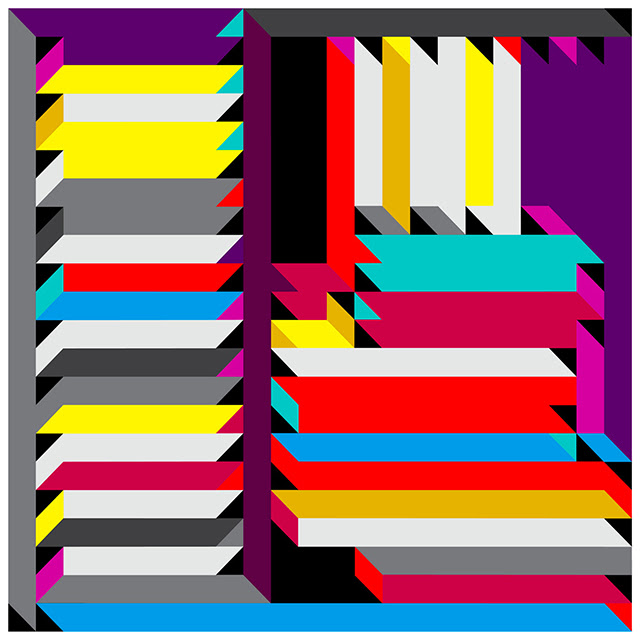MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Battles (Ian Williams) - 素敵な事故が起こるまで
interview with Battles (Ian Williams)
素敵な事故が起こるまで
──バトルス、インタヴュー
Photo by Atiba Jefferson Nov 27,2019 UP
結成から17年。世間的には“Atlas”で一世を風靡したことでも知られるエクスペリメンタル・ロック・バンドのバトルスが、ギター/キーボードのイアン・ウィリアムスとドラムスのジョン・ステニアーのデュオ編成となって初めてのアルバム『Juice B Crypts』をリリースした。4人から3人へ、そして2人へと編成を変えながら、変わることのない鋭角的なサウンドと祝祭的なグルーヴを奏で続けてきた彼らは、11月初頭に恵比寿ガーデンホールで開催され、満員の観客が詰めかけたリリース記念ライヴでも、その圧倒的な個性を聴かせてくれた。いや、むしろプリセットされた音源やシンセサイザーなどを駆使するイアンのサウンドと、サンプラーを使用しつつあくまでも生身のドラミングを力強く披露するジョンのグルーヴは、バトルスの核にある音楽性をより剥き出しにして聴かせてくれたと言ってもいいだろう。ライヴ当日、ステージに出ていく直前のイアン・ウィリアムスに、バトルスの変化と具体的な制作手法、新作『Juice B Crypts』について、さらにはその「モダン」なありようを伺った。(細田成嗣)
オリジナル・メンバーと、新しいメンバーのヒエラルキーができるよりは、ふたりだけの方がいい。
■4年前のアルバム『La Di Da Di』と今作『Juice B Crypts』の一番大きな違いとして、やはりメンバーのひとりデイヴ・コノプカが脱退したということがあると思います。トリオからデュオへと編成が変わるなかで、音楽制作にどのような変化がありましたか。
イアン・ウィリアムス(Ian Williams、以下IW):デュオになったことである意味ではとてもやりやすくなった。というのも曲ごとの方向性が明確に見えるようになったんだ。いまは俺とジョン(・ステニアー)のふたりで楽曲制作をしているんだけど、ジョンはあくまでもドラマーとして存在していて、それ以外のギターやキーボード、あるいはループを使うところのコントロールとかはすべて僕がやっている。デイヴ(・コノプカ)やタイヨンダイ(・ブラクストン)がいた時代は、俺がここにこの音を置きたいって思っていても、みんながいろんなものを持ってきたりするから、なかなか思い通りにはならなかった。でも今回は俺が行きたいところにまっすぐに進めたという意味ですごくやりやすかった。だから曲の形を作るという点でははっきりと自分の意図を出すことができたんじゃないかな。いままでは意図がぶつかり合うことがあったんだけどね。もちろんぶつかり合うことで矛盾が生まれて面白いものができるっていうこともあって、とてもクレイジーで良い方向に進むこともあったんだけど、たまにクレイジーすぎてしまうこともあった。そういったことが整理されたっていう意味では今回のアルバム制作はとてもいい機会だったと思うよ。
■バンドをやめる、あるいは後釜のメンバーを入れるなどの選択肢はあったのでしょうか。
IW:新しいメンバーを入れるというのは、変な感じがするというか、俺とジョンだけの方が正直な感じがする。オリジナル・メンバーと、新しいメンバーのヒエラルキーができるよりは、ふたりだけの方がいい。
■具体的にアルバムを制作するうえで方法を変えたことなどはあったのでしょうか。
IW:俺が前にやってたドン・キャバレロの終わり頃からそうだったんだけど、バトルスの曲作りにおいてつねにインスピレーションを与えてくれるものがある。というのはループ・ペダルを使って音を重ねていく作業をするんだけど、それをバンドという形でやるにあたって、重ねた音をそれぞれの生身のミュージシャンに割り振ったらどうなるだろう、っていう考えがあるんだ。EPとか『Mirrored』の頃もまさにそうで、コール&レスポンスがかなり多い音作りだったと思うんだけど、それはたぶんね、ひとりで作った音を他人と共有するときに生まれる呼びかけ合いみたいなものがあったからなんだと思う。要するにループ・ペダルで使ったものを一旦バラして人に割り振るっていうことから生まれる呼びかけ合いね。今回の新しいレコードでやったことも割とそれと同じなんじゃないかというふうに思っていて。ただ今回はメロディの情報がものすごく多いから、リズムの上にメロディを乗っけるっていうんじゃなくて、サウンドの壁みたいなものにメロディも埋め込まれているというか、構築されたもの全体の一端がメロディになっている。つまりメロディがウワモノとして乗っかっているんじゃなくて、サウンドの壁の中から聴こえてくる、っていうふうに変わったっていうのはこれまでとの違いなのかもしれないな。ただ、自分が作った音楽を表現するやり方っていうのは意外とあんまり変わっていないんじゃないかな。
■ループ・ペダルで作ったものを生身の人間に割り振る際に、機械ではなく身体を用いることによる意想外な出来事がひとつの面白さとして出てくると思うんですが、たとえば長時間のジャム・セッション、つまりインプロヴィゼーションをおこなう中でコンポジションのアイデアを掴んでいく、といったような制作方法をすることもあるのでしょうか。
IW:いわゆるインプロはやらないな。もちろんいまふたりしかいないということもあって、一緒に曲作りをするときにジョンにドラムを叩いてもらって、なんか面白い響きがしてヒントになることはあるにしても、僕らの場合それはたぶんインプロとは違う。インプロと言うよりも「必死の試行錯誤」って言った方が合ってると思う。「あ、いまなんか面白いのができたね」ってなったときに、どうやったか覚えておこうみたいな、そういうことはよくやってる。でもそれは曲作りそのものと同じだから、僕の中では特にインプロだとは思ってない。

新しいものを使ってみるのが好きなんだ。色々なことをやってみて、努力して、事故が起きるという状態まで自分を持っていく。素敵な事故が起こるまで。自分では予測や想像できなかったであろうことが起きるまで、機械と交流するんだ。
■『Juice B Crypts』のもうひとつの特徴として、大勢のゲストが参加されてるということがありますよね。ゲストはどういうふうに選んでいったのでしょうか。
IW:服を着替えるような感じだった。色々と試しては「これ似合うね」とか「他のも試してみよう」とか、そういう感じで選んでいった。だけど特に決まったメソッドがあったというわけじゃなくて、それぞれの曲についてそれぞれの理由で人選していった。曲の求めに応じて解決策を探していったと言えばいいかな。たとえばセニア・ルビーノスに関しては前から好きな声で素晴らしいシンガーだと思っていたんだけど、最初は“Fort Greene Park”をやってもらおうと思って試してみた。だけどなんだか上手くハマらなくて、洋服を色々とあてがってみる感じで彼女に合う曲を探していった。その結果あのソウルフルな感じが“They Played It Twice”に合致してクールな出来になったんだ。
■つまりアルバム全体のコンセプトを先に決めてそれに当てはまるようにゲストを呼んでいったのではなく、曲ごとにそれぞれの理由でゲストとコラボレーションしていったということでしょうか。
IW:そうだね。最初から全体を見ていたわけじゃない。たとえば“Titanium 2 Step”は最初インストで録ってみて、誰だったかに聴かせてみたら「なんかオールド・ロスト・ニューヨークっぽいよね」って言われて。たしかにニューヨークのクラシックなディスコ・パンクというか、70年代終わり~80年代頭ぐらいのノーウェイヴっぽいよなと思って、その手のバンドにいた人っていうことでサル・プリンチパートの名前が浮かんだから、声をかけてみたり。曲によって理由は様々なんだよ。
■台湾の Prairie WWWW とはどのような経緯でコラボレートしたのでしょうか。
IW:彼らを観たのは4年くらい前、台湾の台北だった。とてもクールで変わったバンドだと思ったのを覚えている。彼らは、俺たちがいるステージの反対側に、クラブのフロアで準備していて、大きな帽子をかぶって床に座りながら、変な音をマイクから出していた。すごく奇妙だったんだけどクールな感じだった。だから彼らのことは覚えていて、連絡も取っていた。そこで今回の曲に参加してもらうことになって、クールなコラボレーションが実現したんだ。
■アルバムの構想は、いつ、どのように生まれたのでしょうか。
IW:前作のツアーが終わった後、俺はひとりで新しい音楽の制作に取り組んだ。そしてデイヴが脱退した。俺たちが作る音楽は、何をやっても、良い音楽になるという自負はあった。それが成功するかどうかは全く分からないが、俺たちの音楽はクールなものになるだろうと思っていた。そこでジョンに、「この新しい音源で何かやってみないか?」と聞いたらジョンはやりたいと言った。だからこのアルバムの元となったのは、俺がしばらくの間、作っていた素材なんだ。
■なるほど。それはどのような素材だったのでしょうか。
IW:俺はいつも新しい「楽器」に興味を持っている。「楽器」とカッコ付きで呼ぶのは、エレクトロニック・ミュージックでは色々なものが「楽器」になるからだ。ある種のソフトウェアも楽器だし、シンセサイザーも楽器、伝統的なギターやベースギターもそうだし、ペダルを通すものや、モジュラーシンセサイザーも楽器になる。その全てが今回のアルバムに使われた。俺は、そういう新しいものを使ってみるのが好きなんだ。毎回、違った結果が生まれるからね。色々なことをやってみて、努力して、事故が起きるという状態まで自分を持っていく。素敵な事故が起こるまで。幸運な事故が起こるところまで色々なことを試してみる。実際に起こるまでは、自分では予測や想像できなかったであろうことが起きるまで、機械と交流するんだ。そしてそういうことが起きたときに「すごいな、こんなことが起こったんだ」と思う。そういう作業が大部分を占める。そのような事故が起きるような状況まで自分を持っていく。そのために機材やツールを組み合わせる。今回のアルバムでは、モジュラーシンセサイザー、エイブルトン、スウェーデンの会社のエレクトロン、それから何本かのギターを使ったね。

8分くらいの大曲を書くよりも3分半の短い曲を書く方が難しい。バトルスではいくらでも複雑なことができるわけで、それを一口大で提示してみるっていうのがいわゆる「歌もの」をやることの醍醐味だと思ってる。
■タイヨンダイ・ブラクストンが脱退した後にリリースされた2枚目のアルバム『Gloss Drop』にも多数のゲスト・ミュージシャンが参加されていましたよね。メンバーの脱退後にゲストを呼んでアルバムを制作する、という点では似た経緯を踏んでいるように思いますが。
IW:そういうふうに言う意味はわかる。けれども僕らは『Gloss Drop』のことは意識していなかった。ゲスト・ヴォーカルをたくさん入れるのってとても楽しい試みだと思うんだよね。それはバンドという関係ではできないことができるというか、歌う側もいつもと違うことができて楽しいのかもしれないし、いつもと少し違うヴォーカルを聴いてもらえる機会にもなるのかもしれないし。僕らとしてもバンドのメンバーじゃない人とやるからいい意味でプレッシャーがかかるところもあるんだ。インストの曲ってさ、どれだけ楽器が上手いかとか、どれだけ曲が長尺で複雑で、山あり谷ありで最後には感動させてみせるぞみたいなね、そういうことが問われてしまうところがある。ひけらかし的な部分とか、どれだけ宇宙の彼方まで行って戻ってこられるか的な部分とか。でもそういった側面から自由になれるっていうのが、歌の入った割とコンパクトな曲の醍醐味だと僕は思う。単純に音楽として楽しんでもらえるんじゃないかっていうのがあるんだ。それに実を言えば8分くらいの大曲を書くよりも3分半の短い曲を書く方が難しい。それはたぶん100ページで書くことを10ページにまとめるときの難しさと同じだと思うけど、バトルスではいくらでも複雑なことができるわけで、それを一口大で提示してみるっていうのがいわゆる「歌もの」をやることの醍醐味だと思ってる。もちろんだからといって簡単なことをやってるわけではけっしてなくて、一口大の中にものすごくいろんなものが入ってるっていうことは間違いないけどね。
■一方でもちろん『Gloss Drop』にはなかったような要素も『Juice B Crypts』には数多くあります。前作『La Di Da Di』から今作をリリースするまでの4年間に新しく興味を持った音楽はありましたか。
IW:シンセサイザーをいじることかなあ。具体的なレコードとか人物というよりも、新しいシンセを手に入れて遊んだりすることがすごく刺激になっている。
■今作のプレス・リリースであなたは、モダニズムの概念を鍛錬した美術批評家クレメント・グリーンバーグの「メディウム・スペシフィシティ」に言及していましたよね。
IW:あれは〈Warp〉が勝手に入れたんだよ(笑)。たしかに雑談をしているときに名前を挙げたり、グリーンバーグのコンセプトを語ったりはしたかもしれない。でもそれを元に曲を作ったという話は一切してないよ。ただ、そうだね、たとえば曲の意味を問われたときに「これは恋人のことを想って書いた曲です」とか言っちゃえば簡単なんだけれども、俺の場合は「こういうビートがあります」とか「こういうテクスチャーのサウンドがあります」とか、それがそのまま曲になっているから、モダン・アートの考え方に似てるんじゃないかとは思う。モダン・アートって、たとえばブロックと木片があってそれらを組み合わせて何かを作ったときに、「これは支え合いを意味するのです」とかいう説明をしたらそうなるかもしれないけど、でも実際には単にブロックと木片があるだけだよね。白いキャンバスの上に白い輪っかを描いたとして、何を意味するのかって言われても、それは単純に白だよね。もしくはペンキをぶちまけて何かを描いたとして、それが牛みたいに見えることもあるかもしれないけど、でもそれはただのペンキなんだよね。そういうことなんだよ。素材がそのまま曲になってるっていう意味では、そういう一部のモダン・アートの考え方と近いところがあるよね。
■バトルスの音楽はモダンだと思いますか?
IW:うん。そういうイデオロギーの方が好ましいと思う。
取材:細田成嗣+小林拓音(2019年11月27日)
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
Profile
 細田成嗣/Narushi Hosoda
細田成嗣/Narushi Hosoda1989年生まれ。ライター/音楽批評。佐々木敦が主宰する批評家養成ギブス修了後、2013年より執筆活動を開始。『ele-king』『JazzTokyo』『Jazz The New Chapter』『ユリイカ』などに寄稿。主な論考に「即興音楽の新しい波 ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」、「来たるべき「非在の音」に向けて──特殊音楽考、アジアン・ミーティング・フェスティバルでの体験から」など。2018年5月より国分寺M’sにて「ポスト・インプロヴィゼーションの地平を探る」と題したイベント・シリーズを企画/開催。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE