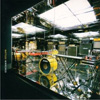MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Battles- Gloss Drop
『グロス・ドロップ』に最初興奮できなかったのは、1曲目を聴いて、このメジャー2作目はハードコアの緊張感をデジタルな感性で再構築した『ミラード』の方法論の延長線上にあり、私は彼らも自己模倣と無縁でなかったのかと複雑な気持ちになったからだが、真剣に何度も聴くうちに『グロス・ドロップ』は『ミラード』の圏域に留まるというよりも、その領域の外へ向かう"ベクトル"を音で描けばこうなるのではないかと思った。反射した鏡像が無限に増殖する数列的なイメージから直線をもたないフラクタルな空間認識へ、ドラスティックなきりかえしがこの2作のあいだにあるということは、アートワークにある種象徴的にあらわれているが、それ以上にバンドにとってタイヨンダイ・ブラクストンの脱退は小さくない事件だった。私は残念ながら今回彼らに取材する機会はなかったので、ことの次第はメディアの伝えることで知るに過ぎないが、メンバーがひとり欠ければバンドの力関係は決定的に変わる。バトルズのように(ほとんど)主従関係をもたない、グループ全体の運動そのものを音楽に転化するスタイルではなおさらで、イアンもジョンもデイヴも途方にくれたにちがいない。しかし私は思うのだが、半分以上作業が進み、完成形が見えた作品を放棄し、いちから作り直すことこそ、モノを作る人間の生き甲斐である。制作過程という、いちばん濃密な空気に戻ることができるからだ。そのとき、発表するあてのない作品は彼らだけのものになり、彼らはこのメジャー1.5作目ともいえる音源をのりこえるべく、3人のバトルズとして作業を再開することになった。
その結果できた『グロス・ドロップ』の第一印象は先に書いた。書き忘れたが1曲目の曲名は"Africastle"という。アフリカとキャッスル(城)を組み合わせた造語だが、アフリカを思わせるところはほとんどないストレートなリズム・ストラクチャーを時間軸に沿って提示する。ところが嵐のような曲調が嵐のように去った後の後半のノンビート部分で曲調はだしぬけにファニーになり、それが2曲目の"Ice Cream"へのブリッジになる。"Ice Cream"はタイヨンダイのヴォコーダー・ヴォイスが印象的だった『ミラード』のシングル曲"Atlas"に対応していて、彼の不在を埋めるようにこの曲では客演に招いた〈Kompakt〉のチリ人、マティアス・アグアーヨの歌声を加工し、"Atlas"路線を伸張しているが、"Africastle"よりこっちの方がアフリカといわないまでもファンキーである。アウトロなどデイヴィッド・モスがドゥーワップをやってるみたいだと書くと苦笑されそうだが、この2曲で例示するまでもなく、『グロス・ドロップ』では各曲のモチーフが他の曲で微妙に変化し反復される。"Futura"と"Inchworm"のリズムの表裏――それが音楽の南と北の関係を暗示するのはいうまでもない――、"Wall Street"のせわしない情景描写とかつて「知っているのは 君と機械のことだけ」("Engineers")と歌ったゲイリー・ニューマンに歌わせた"My Machine"の文明批評......『グロス・ドロップ』の前半はアルバム全体を鏡像のように反転させた『ミラード』(あるいはそのプロトタイプとしてのEPシリーズ)のガッチリした構築性とはちがう、有機的なつながりをもつ。というか、楽曲そのものがシンコペートさせることでプログレ風の組曲形式と似て非なる、ある種の即興音楽に通ずる対話がそこでは行われているだけど、スティールパンを思わせるギターの音色とハンドクラップが跳ねる7曲目の"Dominican Fade"でバトルズの問答はロックからワールドミュージックに意図的に逸れはじめる。もちろんそれはオーソライズされたワールドミュージックではなく、皮膚感覚を頼りにしており、必然的にエキゾチシズムと無縁ではない。ブロンド・レッド・ヘッドのカズ・マキノとボアダムスのEYEの参加をエキゾチシズムとみなすのは異論があるかもしれないが、外国との障壁がほとんどなくなったいまでも、いや、だからこそ、海外のシーンに影響を与えつづけるふたりの日本的な身体性ないしは訛のようなものは『グロス・ドロップ』の"揺らぎ"を象徴するものとして逆説的に浮上せざるを得ない。
バトルズとボアダムスというオルタナティヴ・シーンの両極による幕引きの"Sundome"のトロピカ/リズムとでもいいたくなるメカニカルな祝祭性はトリオ編成になったバトルズが重から軽へ、暗から明へきりかわったことを意味するだけでなく、リズム・アプローチで行き詰まったダンスミュージックとしてのロックがポスト・ダブステップとかJUKEとか、ここしばらくのビートミュージックと拮抗するグルーヴをもちはじめたいち例であるといってもいいすぎではない。
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE