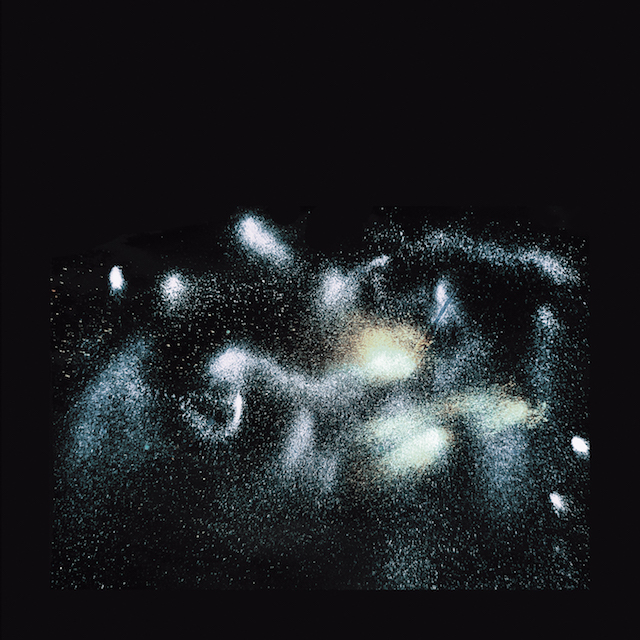MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with James Ellis Ford - シミアン・モバイル・ディスコの1/2、初のソロ・アルバムにかける想い
ジェームス・フォードのことを優れた裏方として認識しているポップ・ミュージック・リスナーは多いだろう。エレクトロ・デュオのシミアン・モバイル・ディスコの片割れとしてニュー・レイヴの時期に台頭し(ニュー・レイヴを象徴する1枚であるクラクソンズ『Myths of the Near Future』(07)のプロデュースを担当している)、アークティック・モンキーズやフローレンス・アンド・ザ・マシーンといった人気アーティストの作品を手がけることで名プロデューサーとしての知名度を高めてきたフォードは、ある意味70~90年代にブライアン・イーノがポップなフィールドでデヴィッド・ボウイやU2に対して担ってきたことを現在請け負っているようなところがある。シミアン・モバイル・ディスコもまたニュー・レイヴ、ニュー・エレクトロの狂騒を離れて地道に作品をリリースするなかでよりストイックなテクノへと向かったわけで、きわめて職人的な立場を徹底してきたのがジェームス・フォードなのである。最近もデペッシュ・モードの新作やペット・ショップ・ボーイズの次作といった大御所とのコラボレーションが続いているが、そこでも彼は縁の下の力持ちの役割をまっとうするのだろう。
だから、〈Warp〉からのリリースとなるジェームス・エリス・フォード名義の初ソロ・アルバムが、彼本人のパーソナリティを強く感じさせる内容に仕上がったのは嬉しい驚きだ。シミアン・モバイル・ディスコのパートナーであるジェス・ショウが病気になったことで活動休止を余儀なくされたことから生まれた作品だが、そのことでフォードは自分自身にフォーカスすることとなった。その結果、マルチ・インストゥルメンタリストとしてフルートやバスクラリネットやチェロといった管弦楽器も含めたすべての楽器を演奏して自身の手でミキシングしているのはもちろんのこと、公の場で歌ったことのないという彼が控えめながらはじめて歌声を披露しているのだ。そして、そのことがアルバムの人懐こい空気感を決定づけているところがある。
音楽的にはオープニングのアンビエント “Tape Loop#7” に始まり、チェンバー・ポップ、サイケ・ロック、プログレ、ファンクなどをゆるくミックスした雑食的でストレンジなポップ作で、とりわけロバート・ワイアットの諸作のようなカンタベリー・ロックからの影響を強く感じさせる。イーノの『Another Green World』(75)を意識することもあったようだ。少なくともシミアン・モバイル・ディスコのようなテクノやエレクトロからは離れており、内省的でメランコリックだが同時にユーモラスで牧歌的なムードは、どこか懐かしいブリティッシュ・ポップを彷彿させる。派手さはないがそこここに遊びと工夫があり、パレスチナ音楽を取り入れるなど発想もオープンで、気取ったところがまるでない。ガチャガチャした音を方々で鳴らしながらゆるいグルーヴを立ち上げるリード・シングル “I Never Wanted Anything” は、フォードの遠慮がちだが落ち着いた歌声も含めて本作のチャーミングさを象徴する一曲だ。
その “I Never Wanted Anything” では若さゆえの野心を失っていることをむしろ心地良く感じている心境を歌っているように、フォードがここで主題にしているのは年を取ること、もっと言えば「老い」だ。未熟なままで親になることなど、そこには不安や憂鬱もたしかにあるのだが、そのすべてをゆるやかに受容しようという感覚が貫かれていて、このアルバムの柔らかな響きと通じている。以下のインタヴューでフォードが語っているように、10代のときにあまり興味がなかった父親のレコード・コレクションの良さが年を取るとともにわかってきたというのもいい話だ。人気者たちを輝かせるために裏方として地道に働いてきたジェームス・エリス・フォードはいま、ささやかな人生の面白さや豊かさをじわじわと感じさせる愛すべきレコードを作り上げたのだ。
自分の音楽はいつも後回しにしてきたというか。「また今度やればいいか」っていう。でも「今度」って絶対ないんだよね。
■『The Hum』を聴きました。ユニークで実験的であると同時に、フレンドリーでもある素敵な作品だと感じました。ただ、今日はプロデューサーとしての側面もお伺いしたいと思っているので、これまでのキャリアについても、まず少し聞かせてください。
あなたは多くのミュージシャンのプロデュースを務めてきましたが、そのときにご自身のパーソナリティを極力出さないようにしているのでしょうか? それとも、ある程度あなた自身のキャラクターを出すようにしていますか? というのも、基本的にはプロデューサーはアーティストの作品にエゴは出さないと思うのですが、著名なプロデューサーが関わった作品を聴くと、彼らそれぞれの個性やキャラクターも作品に反映されていると思うんです。
ジェームス・エリス・フォード(以下JEF):前者かな。僕はつねに、誰かのヴィジョンを実現する手助けをするのが自分の仕事だと考えているから、必要とされているものを提供しようとしているし、ときにはそれが演奏だったり作曲だったり、ときにはシンプルに音的なことだったり、あるいは制作過程のガイド役的なことだったりする。僕にとって、それは彼らのレコードであり、自分はつねに手助けする立場であって……なんというか、あまり好きではないんだよ……もちろん例外はあって、ティンバランドやネプチューンズは大ファンだし、彼らの場合は自分の音楽をほかのひとのために作っているという意味合いが強いけどね。ただ、それってポップ・ミュージック寄りの慣習かもしれない。でも自分の領域では、プロデューサーのサウンドが立ちすぎているものはあまり好きじゃないかな。もちろん自分が下す判断によって自分っぽいサウンドになるとは思うけどね。でも誰かの音楽に自分のサウンドを押しつけるつもりはないんだ。
■プロデューサーの仕事において、あなたがとくに重要だと考えていることは何ですか?
JEF:これまでやってきて学んだおもなことは、柔軟でいることと、平静でいること。制作過程ではいろんな意味で不安要素やストレスが多い場合もあるから。だからそうだね、着実に前に進んでいくことがもっとも重要だと思う。そして様々な状況における様々なひとのニーズを理解して、親切に対応することを心がける。僕がどう貢献するかという点では、ときには制作プロセスの終盤に入っていってミキシング的な作業をする場合もあれば、あるいはリック・ルービン流にドンと構えて自分は手を出さないこともある。そして正直なところ、これまで作った多くのレコードでは何でも屋で、曲を書いて楽器も全部演奏してそれを自分で録音して。なんというか、ピッチをシフトさせ、ギャップを埋めながら、いいレコードを作るために必要なことをするという感じかな。
■シミアン・モバイル・ディスコのファースト・アルバム『Attack Decay Sustain Release』のタイトルが象徴的だと思うのですが、そもそもあなたは音楽制作において、音のパラメータの調整やサウンド・プロダクションに手を入れる作業にもっとも快感を覚えるタイプですか?
JEF:もちろん好きだよ。それって音楽の遊びの部分というか、ものすごく大事なものだと思う。音楽を作る過程にはいくつかの段階があるけど、まずは遊んだり、とにかくいじってみるというところから作り始めるわけだよね。そしてプロジェクトの終盤においては、細部にまでこだわるという部分でもある。EQやコンプレッションのパラメータ、技術的な部分はどこまでも深くいけるし、興味は尽きない。ただし細部に寄りすぎたら引くことを忘れずにいないといけない。「この部分にこだわる価値はあるか?」という。全体像を見失わないということも細部と同じく重要で。そのふたつのちょうどいいバランスを見つけるのが難しい場合もあるんだよね。
■シミアン・モバイル・ディスコの活動が休止したことでソロを制作することになったそうですが、それ以前から、いつかソロ作品を作りたい気持ちはあったのでしょうか?
JEF:そうだな……僕はアーティストになりたいという気持ちはあまりないけれど、音楽を作りたいという欲望はつねにあるんだよ。それで、いろいろなひとといっしょに制作したり演奏したり曲を書いたりすることで、創作面の満足感を得られている。コラボレーションは大好きだからね。シミアン・モバイル・ディスコもすごく好きだったし。それでいくつかのきっかけがあって──まず、いま自宅のスタジオがあって、ドラムキットとかシンセサイザーとかたくさん機材が置いてあって。自分のスタジオを持つのがはじめてで、これができたことによって、夜だったり息抜きの時間に遊んだりいろいろ試したりできるようになったんだ。それから知っての通り、ジェスが病気になりいっしょにスタジオに入ることができなくなったこともあって。それからパンデミックが起こった。そういうわけで自分ひとりで作ることが増えて、それまでずっとスマホやパソコンにちょっとしたアイデアやスケッチを書き溜めていて、本当にしばらくぶりにそういったスケッチを開いて、自分ひとりでそこから先へと進めてみることにしたんだ。そしたら楽しくなってきて、気づくとアルバムができていた。どうしていままでやらなかったんだろうと思うけど、僕はいつも忙しくて、それはとてもラッキーなことだったんだよね。つねに次のプロジェクトが控えていて、次はこのひとと、次はあのひとと、という感じでオファーがあるから。いろんなひとと音楽を作るのは楽しいしさ。だから自分の音楽はいつも後回しにしてきたというか。「また今度やればいいか」っていう。でも「今度」って絶対ないんだよね。

ロバート・ワイアットやケヴィン・エアーズといった70年代前半のイギリスのプログレッシヴ・ロックなんかも大好きで。もちろんブライアン・イーノのソロ作も好きで、僕が趣味で聴くのはそういう感じのものなんだ。
■あなたのように多岐にわたる音楽的知識や技術を持っていると、音楽性をフォーカスするのがかえって難しい側面があると思うのですが、『The Hum』の音楽面においてもっとも重要な課題は何でしたか?
JEF:たしかに僕はこれまで様々なタイプの音楽を作ってきた。今回もアンビエンドのレコードを作ることもできたし、メロディックなインストゥルメンタル・レコードにしてもよかったかもしれないし、もっと曲っぽい感じのレコードにすることもできたかもしれない。実際このアルバムのなかだけでも、すでにかなり多様なんだ。でもとにかく課題としては、作り続けて完成させることだったかな。あと僕にとっての一番のチャレンジは歌うことだったと思う。いや、歌うのはそうでもなかったけど、歌詞を書くことだったかもしれない。そもそも自分はプロデューサーであってシンガーではないしっていう頭があったんだよね。それで曲を作っているときもヴォーカルのメロディを書いて誰かに歌ってもらうかな、なんて考えていた。でも作っていくうちに「なぜ自分で歌わないんだ?」となってきて、頭のなかで自分を押しこめる枠を作っていたことに気がついた。だからその枠にとらわれず、自分自身に挑戦すべく歌ってみることにしたわけなんだ。そうやって新しい領域に自分を追いこんでみるという発想にすごくワクワクしたし、歌詞を書くというのは僕にとってまったく新しいことで、書く過程はとても楽しかった。やっぱり不安だけどね、とくにこれからライヴをやらなくちゃならないわけだし、歌詞について話さなきゃいけなくなるから。でも自分で安全地帯の外に出て、これは自分がやりたかったことなんだと自分に言い聞かせるんだ。
■シミアン・モバイル・ディスコとはまったく違うことをやりたいという気持ちはありましたか?
JEF:一番の望みは、正真正銘これが自分だというものを作ることだったと思う。自分の音楽の趣味、これまで聴いてきたものだったり散歩のときに聴くもの、つまりは楽しみとして聴くものはかなり深遠だったり、かなり静かなものが多くて。ロバート・ワイアットやケヴィン・エアーズといった70年代前半のイギリスのプログレッシヴ・ロックなんかも大好きで。もちろんブライアン・イーノのソロ作も好きで、僕が趣味で聴くのはそういう感じのものなんだ。もともと僕の父がそういったサウンドに傾倒していて、それで僕もそれを聴いて育ったようなところがあるんだよ。DNAに組みこまれているというか。僕はこれまで作ってきた音楽はテクノ、ハウス、ポップ、フォーク、ロックと、あらゆるものが混ざっている。だから今回は本当にただ、自分自身の旗を立てて、これが僕の作る音楽だ、ということを示したかったんだ。
■楽器の演奏も歌もエンジニアリングもほとんどあなたでコントロールしていますが、『The Hum』において「すべて自分で作る」のがなぜ重要だったのでしょうか?
JEF:ある意味コラボレーションしないという実験だったんだよね。なぜならコラボレーションは毎日のようにやっているから。それはそれですごく恵まれていて、とても楽しいものだけどね。でも、だからコラボレーションしなかったら何が起こるのかを知りたくなったのかもしれない。自分以外の人間が誰も関わらなかった場合に何が出てくるのか。幸い楽器もいろいろあるし、自分で演奏できるしね。それにおそらく15年前には自信がなかったかもしれないけれど、いまだったら前に進んでいけるという自信もあった。それにもともとはただこの小さな空間で実験しようとしていただけで、誰かに聴かせるつもりもなかったんだ。
質問・序文:木津毅(2023年5月18日)
| 12 |
Profile
 木津 毅/Tsuyoshi Kizu
木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE