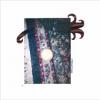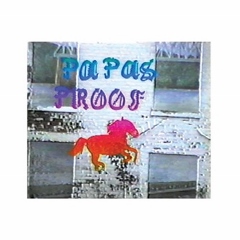MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
Home > Reviews > Album Reviews > Ela Orleans- Mars Is Heaven
〈ウッジスト〉や〈キャプチャード・トラックス〉はじめ、〈メキシカン・サマー〉や〈ノット・ノット・ファン〉にいたるレーベル群が2010年前後のインディ・ミュージック・シーンに提示したイメージは、「スロー・ライフ」や「スロー・フード」等の「スロー」の思想と親和性が高い。彼らが体現するローファイ、あるいは中音域を強調したプロダクションは、大量生産的でファストな音への批評もしくは違和の表明であるとも言えようし、アナログ・メディアにこだわったリリース形態や、地元志向で小ロットかつ小規模な「顔の見える」レーベル運営も、グローバルにひらかれることで損なわれてしまう利益や、画一化されてしまう音楽的キャラクターを、自力で保護せんとする取り組みであるようにもみえる。そうした意図を明言しているわけではもちろんないが、彼らが時代のムードとしてそのような趨勢を反映し象徴していると考えることにそう異論はないものと思う。「いつの頃からかつるつるとした音がいやでたまらなくなった」そしてさまざまなノイズの中に安らぎを見出すようになったというエラ・オーリンズもまた、彼女自身の方法でもって自給的な音の空間を設計するアーティストである。余談ではあるが、地産地消ならぬ自産自消的なベッドルーム・ポップが鋭く生き生きとしたリアリティを備え、それがはからずもグローバルな伝達経路にのって大きな支持と注目を集めたというのがチルウェイヴの顛末であったことを考えてみれば、なるほどチルウェイヴという俺得音楽にはスロー・ミュージックとしての役割を担い得る特性があったのだろう。先に挙げたレーベル群の志向性はもちろんのこと、エラの仕事がいまのタイミングで評価されることもまた、こうした動きともつれあうようにして生まれてきた状況である。
エラ・オーリンズは冷戦期のポーランドに生まれ、社会主義体制下の東欧諸国が経験した貧困と悲惨を目のあたりにして育った。そうした境遇がどのくらい彼女の音楽に影響を与えたのか、わかりやすい形で確認できるわけではないが、東西に分かれるよほど前のヨーロッパの香りをとどめていることはたしかである。エラ自身が大きく影響を受けた自国のアーティストとしてはカロル・シマノフスキやクシシュトフ・ペンデレツキ、ヴォイチェフ・キラールなどが挙げられており、現代音楽や映画音楽への造詣をしのばせる。古い映画音楽からのサンプリングだろうか、いずれの曲にもはげしくディレイのかかったギターやヴァイオリンの即興(あるいはループ)に、手間ひまかけて録り編集したというサンプル音源が絡んで、いわくいいがたい、甘美なノスタルジーを生み出している。ノイズとノスタルジー。これがエラ・オーリンズのコアだ。懐古され恋われているのは、おそらくは「昨日の世界」(シュテファン・ツヴァイク)......第一次世界大戦前の、光りかがやき、栄光にみちた、失われしヨーロッパ文明ではないだろうか。
その懐古の手つきは非常に理知的なもので、同じく知的な女性アーティストの中でもアマンダ・ブラウンやグルーパー、ラモナ・ゴンザレスらとはまた別種の、男性的とさえ言ってよい雰囲気がある。不鮮明な音像には情念が渦巻くかにみえて実際のところ冷たい計算を隠した構築性が感じられる。詞には飛翔や着地のイメージが多用されるが、これはほかならぬ彼方の栄光への飛翔と、現在という場所への着地とを暗示するのだろうと筆者の想像は広がる。それは(栄光の)終わりのつづきとしての現在への、苦い着地である。精神は過去の偉大な時間へと向かう、しかし、肉体はこの終わってしまった時間につながれている。そのことへの詮なき嘆息である。
こうした想像・解釈には、少なくとも筆者にとって彼女の音や詞やたたずまいをリニアにつなぐような整合性がある。そして高い教養や精神性の宿ったエラの音楽へ、筆者なりに寄せたリスペクトでもある。まわるレコードはこの飛翔と着地の堂々めぐりを視覚的に描き出す。普段はアナログ・メディアを愛好しない筆者であるが、この作品ばかりはCDで聴くことが正解であるとどうしても思えない。七尾旅人とやけのはらの"ローリン・ローリン"においては、ターンテーブルの上で可視的に消費される「いま」という時間は、あくまで愛しいものとして、ロマンチックに、そして肯定的にとらえられていた。エラの音楽はその裏側を幽霊のように徘徊する。「わたしたちは夜になる/するとわたしはすばらしい/あなたはすばらしい/わたしたちはすばらしい/だが彼らはちがう」"ワンダフル・アス"
そこは夜だ。そしてそこにいるかぎりわたしたちはすばらしい存在だ。だが「彼ら」とはだれか。パンダ・ベアを思わせる、浴場のような音響に溶かし込まれたオールディーズ風の終曲では、あかるく典雅なメロディにのせて何度も「ゼイ・アー・ノット」と歌われ、それがいつまでも耳に残る。
最後にノートとして。エラはヴァイオリンやピアノを幼少から学んでいたが、どちらかといえば映画やファイン・アートへの憧れの方が強く、アート・スクールを出てグラスゴーに渡り、その後に音楽に出会い直したというような紆余曲折があるようだ。彼女のウェブ・サイトには「耳の映画」と銘打たれていて、彼女自身の来歴と音楽へのスタンスをはっきりと表明するものになっている。ソロになる前はハッスル・ハウンドというバンドで活動し、アルバムも制作されている。ソロとしては2009年のアルバム・リリース(本人はあまり評価していないようだが)の後、昨年のダーティ・ビーチズとのスプリットで静かな注目を集めた。だが聴くべきはやはり本作だろう。シーンのムードとしても本人のキャリアとしても、本当にいま充実の時期を迎えていると感じる。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE