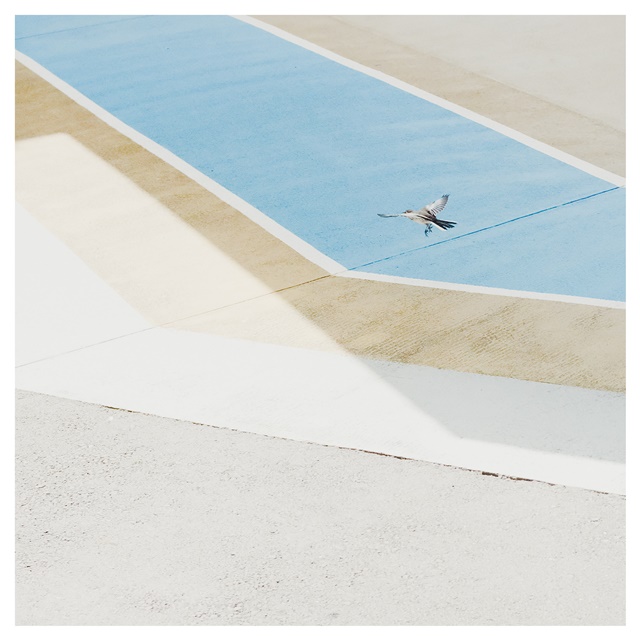MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home > Reviews > Album Reviews > グソクムズ- グソクムズ
このアルバム『グソクムズ』は、懐かしい。この懐かしさは確かに、「〇〇のような」(〇〇に代入されるのは、サニーデイ・サービスであったり、キリンジであったり、キンモクセイであったり、デビュー間もない頃の never young beach であったりするだろう)という、これまでの邦ポップス史に現れた様々なアーティストとの音楽的類似によるのも大きいだろうが、そのような参照関係を超えた、何かもっと複層的で多面的な「懐かしさ」を蔵しているふうだ。
「はっぴいえんど史観」という言葉がそれなりの説得力をもって流通している通り、1990年代以降の邦ポップス・シーンにあって、都会的な洗練をまとったフォーク・ロックの系譜というのは、かなり豊かなものがある。グソクムズもそうした系譜の上に現れたバンドであることは、そのサウンドを聞いてみてすぐにわかるだろうし、「“ネオ風街” と称される4人組バンド」とプレス資料にあるように、そうした都会的フォーク・ロックと、かつてのティン・パン・アレー~シュガー・ベイブ周辺のシティ・ミュージックを大いに参照しているのもわかる。
主に北米の1970年代ポップス~ロックの芳醇な蓄積を源泉に据え、〈URCレコード〉や〈ベルウッド・レコード〉から連綿と流れる、フォークからニュー・ミュージックへと発展していく同時代の日本産音楽に多大なインスピレーションを受けたインディー・ポップ。これらを指してここ10年ほどで盛んに用いられた(やや漠然とした)用語に、「グッド・ミュージック」というのがあるが、グソクムズの音楽はまさしくこの「グッド・ミュージック」志向の最新継承形と考えるのが適当だろう。
グソクムズは、東京・吉祥寺を拠点に活動するバンドだ。「風街」とは、(松本隆のコンセプトによれば)1964年の東京オリンピックを境に様変わりしてしまった青山・渋谷・麻布界隈のかつての原風景を空想的/詩的に捉えようとした概念であったわけだが、その「風街」喪失の物語類型も、後の都市開発の波とともにだんだんと西方に遷移してきて、いまでは吉祥寺に根をおろしている、ということなのかもしれない。都心部の「あの頃」を映したはずの「風街」は、いつしか郊外の「あの頃」を映すようになった。
これは、グッド・ミュージック的系譜の主な発信地が、都心から渋谷、下北沢、吉祥寺等の武蔵野地域へと時代を下りながら移っていったのにも対応しているように思う。つまり、「風街」というコンセプトのリアリティが都市の中心から徐々に周縁化していく軌道と、シティ・ミュージックからシティ・ポップ、渋谷系、ポスト渋谷系から東京インディーへ、という都会的ポップスの展開の時系列的変遷が対応しているのではないか、ということだ。そういった意味で、2021年においてグソクムズの音楽が奏でられるのは、おそらく必然的に吉祥寺でなければならなかったわけだ。
アーバンとルーラルの境界の混じり合った性質=郊外性が、吉祥寺という街の微妙な文化的アイデンティティを形作ってきたのは間違いのないところだろう。「風街」からやってくる東風がそよぎわだかまる場所としての吉祥寺にはかつて、日本のフォークの歴史を振り返るときに外せない「ぐゎらん堂」があったり、アヴァンギャルド・ミュージックの梁山泊たる「マイナー」もあった。1980年には(元祖「風街」文化圏とも何かと関連の深い)PARCOがオープンしているし、いまももちろん現役で街の音楽文化をもり立てる「曼荼羅」グループの各店をはじめ、様々な音楽関連施設がある。
私自身、数年前まで吉祥寺の近くに暮らしていたので、実際、グソクムズの若々しくも品のあるフォーク・ロック・サウンドが、あの街の風景によく馴染みそうなのがよくわかる。どこかでローカリティと非洗練の匂いを残している街並みには、このアルバムで聴けるような(あるいは、はっぴいえんどが架空的に鳴らしたような)、都会的洗練と泥臭さが入り交じったサウンドが似合う。「都市に暮らしている」ということへの自己言及性と、それゆえの含羞としてのルーラル志向が拮抗する様。もしかすると、それこそがはっぴいえんど以来の都会人による邦ポップスを駆動してき基調論理だったのかもしれない、と思ったりもする。
既に見たように、「風街」という概念には、その発祥の時点からしてノスタルジアが含まれていた。とすると、グソクムズの「ネオ風街」は、さらにその外側にもう一枚のノスタルジアを纏っている、ということになる。
実のところ、こうした「二重のノスタルジー」というべきものは、例によってはっぴいえんど以後の系譜をたどっていくと、さして珍しくはない。というか、はっぴいえんどという(この場合、バンドというかコンセプト)を、(無自覚な例も含めて)事後から参照するにあたって必然的に引き受けなければならない戦略だともいえる。かつて1990年代にサニーデイ・サービスが描いた音楽の中には、その時点ですでに1970年代初頭の風景への集合的ノスタルジアが溶け込んでいたし、更には、1970年代初頭(ポスト「1968年革命」時代)に芽生えた更に前の時代へのノスタルジアが折りたたまれていた。昨今のシティ・ポップ流行りにしてもそうで、ある側面からみれば、1950年代末〜1960年代初頭の『アメリカン・グラフィティ』的な風景への憧憬を孕んだ1980年前後のニュー・ミュージックを、更に現在から愛でているという現象でもある。
ここで、無粋を承知の上であえて比較してみたいのが、2010年代に隆盛したヴェイパーウェイヴにおけるノスタルジア観だ。
ヴェイパーウェイヴでのそれは、過去(主に1980年代から1990年代前半にかけて)に抱かれていた輝かしい未来像にノスタルジアを投影する入り組んだ構造=「挫折した未来へのノスタルジア」が見られたわけだが、「風街」系譜のノスタルジアとは、やや性格を異にしている(ドメスティックな系譜としての「グッド・ミュージック」的価値観は、そもそもヴェイパーウェイヴ的なものとは長らく交わらずに来た)。
「ネオ風街」は、ヴェイパーウェイヴがそうしたようにテクノロジカルな未来像を追慕するのではなく、「素朴なノスタルジア観へのノスタルジア」を含み込んでいると言うのが適当だろう。当然これは、通常の一義的なノスタルジア欲求とも違う。つまりここでは、挫折した未来観を懐かしむというヴェイパーウェイヴ的ノスタルジアの反響的相似形として、1970年代からそれ以前を眼差した場合のようにありし日を思慕しようとする素朴なノスタルジアを現在では懐き得ないことへの哀切の念=「素朴なノスタルジア観へのノスタルジア」が喚起されているのではないだろうか(オリジナルの「風街」コンセプトが、そのように素朴な心性に起動されていたものだったのか、そしてそれは多分違うだろう、という議論はここでは置いておきたい。重要なのは、かつての「風街」的ノスタルジアが、現在ではそのように「好ましく」「素朴」なものとしても眼差されているのではないか、という点だ)。
「素朴なノスタルジアを抱き得たあの時代」への追慕/哀切の念が、また新たなノスタルジアを駆動するような状況。要するに、「素朴なノスタルジアを抱くことに対するメタ的なノスタルジア」。これこそが、「ネオ風街」という概念が辛うじて、しかしごく批評的な機能をもって現在性を担保し得ている領域なのではないか。素朴に過去を思慕する契機を奪われた現在の若者たちが、「風街」からの引導を受け取りながら、いま一度好ましく過去を想うための時空を、音楽を通じて立ち上がらせようとしている……という。
『グソクムズ』は、その音楽も「グッド・ミュージック」的であるとすれば、当然その言葉(歌詞)も「グッド・ミュージック」の粋を集約したものに聴こえてくる。
主情主義的な感情の吐露は巧みに抑えられ、あくまで身近な「風景」を切り取り、それらを自然主義的に描写する品の良い言葉が列せられていく。一方で、「君」と「僕」はあくまで彼らの生活意識の延長に配置され、奥ゆかしい描写でもってキャラクタライズされていく。こうした音楽を奏で歌うグソクムズのメンバー自身の生活風景も、きっとこのようにさりげないあれこれに彩られているのだろうと想像させてくれる。少しの憂いや倦怠も、こうした風景の切り取り術にとってはむしろ望ましいペーソスなのかもしれない……。
このように書くと、何やら彼らの歌詞をいかにも「リアリティ」に欠けた「雰囲気重視」だと指弾しているように思われるかもしれないが、必ずしもそうではない。ある意味でこれは、(そのサウンドと同じく)従前の邦ポップス史において豊かに実践されてきた手法の率直な継承であるし、元をたどるならやはり、かつて松本隆がはっぴいえんどで試みた風景論的詩作法(繰り返すが、ここにはかなりハイコンテクストな問題提起があったはずなのだが)を素朴に内在化し、彼らなりにコンバートしたものだろう。
これもまた、上のノスタルジアの議論を通過した耳で聴くと、そのような詩作がなされた「あの時代」への憧憬と追慕ゆえの(結果的にメタ的な批評性を帯びざるをえない)実践ととるのが適当かもしれない。
はっきりといえば、ここに描かれたような「ネオ風街」の風景からは、「社会」が剥落しているのではないか。私にとってはそう聴こえてくるし、「ネオ風街」という「思想」も、あたかも現在の社会的アクティヴィティからの柔らかなシェルターのようにも思えてくる。その点をもって、夢想的なエスケーピズムの匂いを嗅ぎ取って論難するのは簡単だろう。しかし、グソクムズのメンバーが無自覚だったとしても(というより、無自覚だったとしたらより一層その効果を増すわけだが)この音楽は、素朴なノスタルジアを抱きえた時代への追慕・哀切がみずみずしく鳴らされているという点で、結果的に現在の社会への批評的視座が付与されている、ともいえる。
この音楽が、「社会不在」に聴こえてしまうのなら、ある意味でそれは、現代都市社会が抱え込んだなにがしかの不全ゆえのことかもしれないのだ。
柴崎祐二
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE