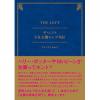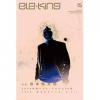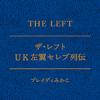MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > 『ザ・レフト──UK左翼列伝』刊行記念筆談(前編) - ブレイディみかこ×水越真紀
あるいは単純に、UKセレブの面白人物伝かもしれないが、それは、左翼がサヨクになったこの国で、いまあらためて「左翼」を考える契機かもしれない。それは、ガチガチに固く、真面目にしか政治を語れないことへの刺激剤かもしれない。それは、政治家に舐められている我々への励ましの言葉かもしれない。「ザ・レフト──UK左翼列伝」の刊行を記念して、紙エレキングでも人気の、ブレイディみかこと水越真紀の筆談をお届けしよう。
日本を含め、左翼が衰退したすべての国で言われていることだと思いますが、左翼は往々にしてほかの左翼に対して心が狭い。自分こそが正しい左翼なんだと分裂を繰り返し、弱体化してきました。──水越真紀
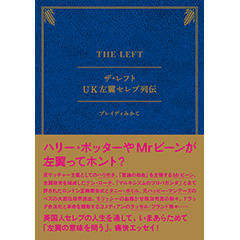 ブレイディみかこ ザ・レフト─UK左翼セレブ列伝 |
水越真紀 『ザ・レフト──UK左翼列伝』、一言で言うと、めちゃめちゃ面白かったです。ケン・ローチやダニー・ボイルなど日本人もよく知る正統派の「左翼」から意外性のあるミスター・ビーンやハリボタの作者J・K・ローリング、それに日本から見ていると右派左派理解の難しいモリッシーやジュリー・バーチル、ハチャメチャな元ハッピー・マンデーズのベズ(好きだな、この人)やフットボール選手のジャスティン・ファシャヌのような非正統派など多岐にわたる「左翼」たちを、UKの歴史や現実を踏まえた分析でそのレフト性を浮き彫りにしていますね。
たとえばスコットランド独立に対する意見にしても移民政策やナショナリズムの考え方にしてもここに登場する人たちの考え方はそれぞれに違う。違うけれど、たしかに全員が「レフト」なんだと読み解かれてていく。日本を含め、左翼が衰退したすべての国で言われていることだと思いますが、左翼は往々にしてほかの左翼に対して心が狭い。自分こそが正しい左翼なんだと分裂を繰り返し、弱体化してきました。日本でもイラク戦争や原発事故などがあると、左翼の結集が試みられますが、持続した力にはなっていません。なんてことを思いながら読むと、どの人物の言動にもぶれずに、なおかつ寄り添うブレイディさんの視線はとても示唆的でした。このラインナップはすぐに決まったんですか?
ブレイディみかこ そう言ってくださると救われます……。わたしはずっとウェブで書いて来たので書き下ろしって初めてで、書いたらすぐ人前に出せるウェブとは違い、一人で闇夜を延々と自転車こいでるような感じでしたから。
ラインアップは、最初はケン・ローチでというのは決めてました。今年は個人的に彼の『ザ・スピリット・オブ・45』を見たというのが大きくて、あれで英国への疑問が一気に解けた感じがありました。安倍氏が「戦後レジームからの脱却」と言ってますが、英国の戦後の起点は「どレフト」だったという。そしてサッチャーが「戦後スピリットからの脱却」をはじめていまのブロークン・ブリテンに至っている様がばーっと綺麗に繋がった気がしたんです。左派の分裂と弱体化についても、「レフト・ユニティー」という彼の政党の名はいかにも象徴的なので、そこからはじめたいと思っていました。
それ以外の人選は行き当たりばったり。というか、今年の時事問題や自分が考えていたことの遍歴になってる気がします。たとえばUKIPの台頭が騒がれるとモリッシーを思い出したり、スコットランド独立投票が近くなるとJ・K・ローリングを思い出したり。「左翼とはこういう人だ!」が書きたかったわけではなく、どちらかといえばそういうのを揺るがすような人選にしたいと思ってました。左翼本って「こうでなくてはいけない」になりがちな印象がありますから。エレキングなんで本当はもっとミュージシャンがいたら良かったんでしょうが、アーティストはレフトで当たり前みたいなところもあるし、やっぱ闇夜の自転車こぎですから、自分で書いてて退屈しない人というのが最優先でした。
水越 へえ! 行き当たりばったりとは思えないですね。でもそう思えないというのは実は、こんなにバラエティに富んだ「レフト」の生き方、考え方があるという「現実の当然さ」と私の「左翼」への先入観のギャップから生まれる印象なのかもしれないですね。その多様な人たちへのブレイディさんの一貫した共感的な視線は、移民という立場ならではの冷静さによるのかなとも思いました。生まれる国は選べないけど、暮らす国は選ぶことも出来る。その選び続ける視線であることの温かさと冷静さに、日本で生まれてそこに住み続け、日本を見ているる私の視線が批評されているようにも感じました。生まれた場所にその後も住むことを“選んでいる”と意識するのは難しいことですね。
この「レフト」たちの考え方に共通して通底している階級意識へのブレイディさんの共感が説得力になっています。格差が問題になっているこの数年の日本では、よく「格差は悪いことではなく、悪いのはそれが世代を超えて固定することだ」と言われます。また、ブレア時代に「イギリスの階級社会はもうほとんどないといってもいい。階級間の出入りはそれほど簡単になっている」と書いたものを読んだこともありました。どちらも格差、階層を否定するものではなく、努力次第で上昇できるかが重要なのだという考え方ですが、「階級(格差)社会である」ということが資本主義社会の動かぬ前提であるとするなら、その社会で(上昇しない)アンダークラスも人間らしい暮らしが出来ることが重要だという考え方だってあることを私はつい忘れちゃう。女は、というか男女雇用均等法が施行された80年代日本の“女の時代”フェミニズムは男たちより一足早く新自由主義的競争社会を「要求させられて来た」ようなところがあるし……。
ブレイディさんが英国で暮らしてから20年くらい? 日本にいる頃からパンク少女だったということだから、移住前から知識はあったでしょうが、実際に暮らす間に「階級社会」への感じ方、見方に変化はありましたか?
ブレイディ 96年に英国に出直して来て、最初の数年はロンドンの日系企業で働いて所謂ジャパニーズ・サークルのなかで生きていましたから、その頃は階級とかそういうのは新聞のなかで読むことでした。海外在住邦人って、よく「日本人は階級の外」って言うんですよね。実際、あの日系サークルのなかで暮らしているとそういう錯覚に陥るのはわかる。それは「私たちは度外視されてる」という意識なのか、「私たちは特別」という意識なのか、たぶん両方なんですが、多くの日本人はすごいコンプレックスと優越感を両方持ってる。国民としてナルシスティックなのかもしれないですね。だから安……、いや、ここではやめときます。
で、わたしが自分も階級の一部だと実感するようになったのは地方に引っ込んでからです。日本人からアジア系移民になったというか。いろんなタイプの英国人を知るようになったのもそれからですし。
英国は政治もなんだかんだ言ってずっと2大政党制で、「右 & 金持ち層」の保守党 vs「左&労働者層」の労働党というわかりやすい構図なので、レフト or ライトの観念と階級は切り離せません。どこの階級にいるか(またはどこの階級に優しい政治を志向するか)が政治のコアにある。これは日本人のわたしには新鮮でした。あと、貧乏なのは自分の責任。という所謂サッチャー的アイディアは英国ではどうも広まりきれないというか、ちゃんと働いている自分が貧乏なのは社会の責任だろ。みたいな主張を堂々とする気質が庶民には根強くあって、貧乏だから恥ずかしいというより、そっちの方が先に来る。なんでだろうなあ? と思っていたんですが、それも『ザ・スピリット・オブ・45』で解けました。あれが起点ですから、そらそうなるだろうと。
たとえば、ブライトンは超リベラルと言われている街で、英国で唯一みどりの党の国会議員を輩出し、市議会もみどり一色なんですが、彼らの支配がはじまって住民税がめっちゃ上がってる。環境に優しい政策は金がかかりますから。下層民はそれに苦しめられていて、左翼グループがみどりの党の選挙運動にカウンターをかけたりしていている。レフトというのは理想論を唱える人ではなく、貧民に寄り添う人という考え方が古典的にあるんだと思います。やっぱディケンズの国というか。
わたしは貧乏な家庭の子供でしたが、貧乏なのは親のせいだと思っていたし、母親は「力のない親でごめんね」といつも謝ってました。けれども日本の政治の冨の分配の仕方が違ったら異なるシナリオもあり得たんだと気づいたのは、「庶民が真面目に働いても貧乏なのは政治のせいだ」と高らかに言える人びとがいる英国に来てからです。だから今回の本でもそこら辺は根底にあります。それはいまの日本にも大事なことに思えましたし。
Profile
 ブレイディみかこ/Brady Mikako
ブレイディみかこ/Brady Mikako1965年、福岡県福岡市生まれ。1996年から英国ブライトン在住。保育士、ライター。著書に『花の命はノー・フューチャー』、そしてele-king連載中の同名コラムから生まれた『アナキズム・イン・ザ・UK -壊れた英国とパンク保育士奮闘記』(Pヴァイン、2013年)がある。The Brady Blogの筆者。http://blog.livedoor.jp/mikako0607jp/
Profile
 水越真紀/Maki Mizukoshi
水越真紀/Maki Mizukoshi1962年、東京都生まれ。ライター。編集者。RCサクセション『遊びじゃないんだっ!』、忌野清志郎『生卵』など編集。野田努編『クラブミュージックの文化誌』などに執筆。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE