MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > Electronica Classics- ──いま聴き返したいエレクトロニカ・クラシックス10枚
さて、「エレクトロニカの“新”新世紀」と銘打って、とらえがたくも魅力的なエレクトロニック・ミュージックの現在を示している作品群を取り上げる本特集だが、一般的に「エレクトロニカ」という名で認識されている作品にはどのようなものがあっただろうか。リアルタイムで聴いてこられた方も多いことと思われるが、あらためていま聴き返したいエレクトロニカ名盤選をお届けします。
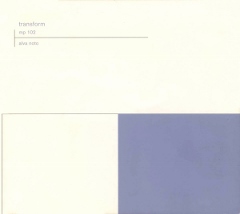
Alva noto - Transform
Mille Plateaux (2001)
キム・カスコーンが「失敗の美学」と名づけたデジタル・グリッチの活用によって、90年代後半から00年代前半にかけてのノンアカデミックな電子音響が始まった。カールステン・ニコライ=アルヴァ・ノト/ノトは、そのグリッチ・ノイズをグリッドに配置することで、ステレオの新美学とでもいうべき電子音響を生み出していく。とくに本作の機械的でありながら優美で洗練されたサウンドは、2001年の時点ですでにポスト・グリッチ的。数値的なリズム構成が生み出すファンクネスには、どこかクラフトワークの遺伝子すら感じるほどだ。00年代以降のエレクトロニカに大きな影響を与えた傑作。
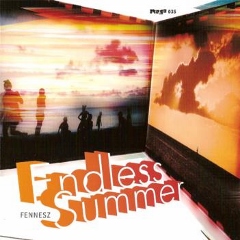
Fennesz - Endless Summer
Mego (2001)
ティナ・フランクによるグリッチなアートワークは、リアルな「永遠の夏」そのものではなく、いわばポップ・ミュージックの記憶から生成するヴァーチャルな世界=記憶の表象であり、このアルバムの魅力を存分に表現していた。これはテン年代的(インターネット的)な光景・環境の源流のようなサウンド/イメージともいえ、たとえば、甘いギター・コードに介入する刺激的なグリッチ・ノイズは、「歯医者で聴いたフィル・コリンズ」というOPNのコンセプトへと接続可能だろう。ヴェイパーウェイヴ以降のインターネット・カルチャー爛熟期であるいまだからこそ新しい文脈で聴き直してみたい。

Jim O'Rourke
I'm Happy, And I'm Singing,
And A 1, 2, 3, 4
Mego (2001)
ジム・オルークの唯一の「ラップトップを用いたオリジナル・アルバム」は、00年代以降、多くのエレクトロニカの雛形ともなったアルバムでありながら、しかしほかの何にも似ていない孤高のアルバムでもあった。じじつ、この弾け飛ぶような電子音には、ヴァン・ダイク・パークスのポップネスから、メルツバウのノイズまでも圧縮・解凍されており、ジム・オルーク的としかいいようがない豊穣な音楽が展開されている。フェネス、ピタらとのフェノバーグとは違う「端正さ」も心地よく、まさに永遠に聴ける電子音楽的名盤といえる。2009年に2枚組のデラックス・エディションもリリースされた。

Ekkehard Ehlers
Plays
Staubgold (2002)
このアルバムこそ、00年代後半以降の「ドローン/アンビエント」のオリジン(のひとつ)ではないか? コーネリアス・カーデュー、ヒューバード・フィヒテ、ジョン・カサヴェテス、アルバート・アイラー、ロバート・ジョンソンなどをソースとしつつも、それらのエレメントを弦楽的なドローンの中に融解させ尽くした美しい音響作品に仕上がっている(元は12インチシリーズであり、本作はそれをアルバムにまとめたもの)。“プレイズ・ジョン・カサヴェテス2”における超有名曲(“グッド・ナイト”?)を思わせる弦楽にも驚愕する。イックハルト・イーラーズの最高傑作ともいえよう。
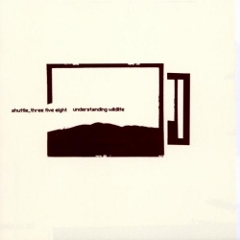
Shuttle358
Understanding Wildlife
Mille Plateaux (2002)
00年代初頭に人気を博したクリッキーなビートはエレクトロニカの「ポップ化」にも貢献した。LAのシャトル358(ダン・エイブラムス)が、2002年に〈ミル・プラトー〉よりリリースした本アルバムは、その代表格。細やかに刻まれるビートに、朝霧のように柔らかい電子音が繊細にレイヤーされ、00年代初頭の小春日和のような空気を見事に象徴している。耳をくすぐるカラカラとした乾いた音響が気持ちよい。2015年には11年ぶりのアルバム『キャン・ユー・プルーブ・アイ・ワズ・ボーン』を老舗〈12k〉よりリリース。こちらは森の空気のようなアンビエント作品に仕上がっていた。

Frank Bretschneider &
Taylor Deupree
Balance
12k (2002)
電子音響とエレクトロニカの二大アーティストの競演盤にして、ミニマル/クリック&グリッチ・テクノの大名盤。初期テイラー・デュプリー特有のミニマル・テクノな要素と、フランク・ブレッシュナイダーのクリッキーかつグリッチなエレメントが融合し、緻密なサウンドのコンポジションを実現している。シグナルのような乾いたビートと、チリチリとした刺激的なノイズが交錯し、マイクロスコピックな魅力が横溢している。ミニマル・グリッチな初期〈12k〉の「思想」を象徴する最重要作といえよう。フランク・ブレッシュナイダーはシュタインブリュッヘルとのコラボ作もおすすめ。
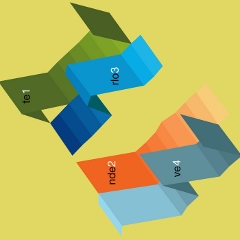
SND
Tenderlove
Mille Plateaux (2002)
マーク・フェルとマット・スティールによるクリック/グリッチ・ユニットSNDのサード・アルバム。近年でもファースト・アルバムがリイシューされるなど常に高い評価を得ている彼らだが、本作は、そのキャリア中、もっともハウス・ミュージックに接近した問題作である。ハウス・ミュージックの残滓を残した甘いコード感と、シンプル/ミニマルな音響の中で分断されていくダンス・ビートなどは、現在のアルカなどにも繋げていくことも可能だろう。後年、〈エディションズ・メゴ〉や〈ラスター・ノートン〉などからリリースされたマーク・フェルのソロ作も重要作。あわせて聴きたい。
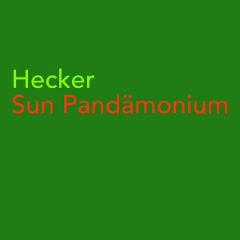
Hecker
Sun Pandämonium
Mego (2003)
なんというノイズか。まるで太陽のように眩く、獰猛であり、優雅でもある。嵐のようなノイズの奔流はラッセル・ハズウェル級であり、まさに取り扱いが危険な盤だが、しかしその強靭な音響は一度ハマると抜け出せなくなる快楽性がある。いわば90年代末期に誕生したピタなどのグリッチでノイジーな電子音響と、2010年代的なインダストリアル/ノイズをつなぐアルバムといえ、いまをときめく〈パン〉が、2011年にアナログ盤でリイシューしているのも頷けるというもの。まさにヘッカーの最高傑作だ。刀根康尚やデヴィッド・チュードアなど実験音楽や電子音楽の系譜にも繋げて聴いてみよう。

Pan Sonic
Kesto
Blast First (2004)
キム・カスコーンがグリッチ・ムーヴメントの最重要バンドと認識するパン・ソニック。ファースト・アルバム『ヴァキオ』(1993)が有名だが、ここではあえて本作を紹介したい。彼らの5枚目のオリジナル・アルバムにして、脅威の4枚組。ブルース・ギルバート、灰野敬二、スーサイド、スロッビング・グリッスル、アルバン・ルシエなどに捧げられた楽曲群は、インダストリアルから電子ノイズ、果ては静謐なドローンまで実にさまざまで、さながらパン・ソニック流の電子音楽/ノイズ史といった趣。グリッチ以降の電子音響が行き着いた「宇宙」がここにある。アートワークも素晴らしい。
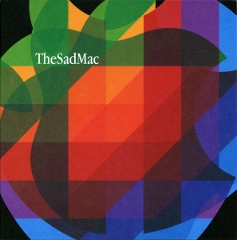
Stephan Mathieu
The Sad Mac
HEADZ (2004)
フィールド・レコーディングに弦楽のようなドローンがレイヤーされ、記憶の層が再生成していくような美しい音響作品であり、同時に「作曲家」ステファン・マシューの個性が前面化した最初の作品でもある。弦楽曲のもっとも美しい瞬間を、まるで記憶のスローモーションのように引き伸ばすシネマティックな作風は、電子音楽とエレクトロ・アコーステイックの境界線を静かに融解させていく。アルバム・タイトルは愛用してきたマックのクラッシュを表現しているようで、いわばマシンへのレイクエムか。現在のアンビエント/ドローンの系譜を振り返るときに欠かせない重要なアルバム。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE


