MOST READ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- KEIHIN - Chaos and Order
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- 「土」の本
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん
- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定
Home > Columns > 大胆不敵な音楽の熟達者たち――AMM論
AMM の足跡を音盤で辿り返す
ここで AMM の活動の変遷を音盤を参照しつつ辿り返してみよう。なおアルバムに付随する年号は彼らのアーカイヴの表記の仕方に従ってリリース年ではなく録音年を中心に記している。
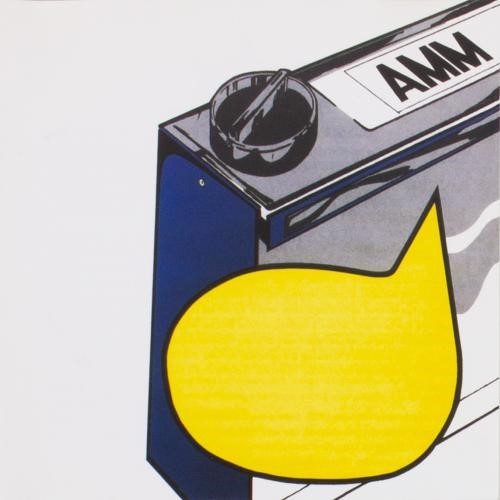
『The Crypt』(1968)
【コーネリアス・カーデュー在籍時代――60年代】
最初期の録音として先に触れた「ロイヤル・カレッジ・オブ・アート」での1966年のライヴ演奏が収録されたコンピレーション『Not necessarily "English music"』がある。ただし同作品はデイヴィッド・トゥープが2001年に編纂したもの――英国実験音楽/電子音楽の歴史の再検証として注目に値する仕事だった――であり、リアルタイムでは日の目を見ていない。実質的なファースト・アルバムとしては AMM 史上もっともよく知られているだろう『AMMMusic』(1966)がある。フリー・ジャズのエネルギッシュな箇所を音響的に取り出したかのような極めてノイジーな作品だ。だがこの録音ののちローレンス・シーフは AMM を去り、音楽活動をもやめてしまうことになる。そして入れ替わるようにして1968年にはカーデューの教え子でもある打楽器奏者のクリストファー・ホッブスが加入。そしてこのメンバーで同年にロンドンのスペース「ザ・クリプト」でおこなわれたライヴが1970年に MEV とのスプリット盤『Live Electronic Music Improvised』としてリリースされることになる。このときのライヴの長尺版はおよそ10年後に『The Crypt』として、1979年にプレヴォーが立ち上げた〈Matchless Recordings〉から発表された。ファースト・アルバムに引き続きノイジーであるもののより持続音が主体となった演奏は、グラブスが言うような「音色という側面におけるAMMの即興的な反応のあり方」(*11)を確立させた記念碑的作品だった。フリー・ジャズ由来の集団即興におけるようにそれぞれの演奏家の発語的な対話に焦点が当てられるのとは異なり、むしろ「音色の変容は各パフォーマーに、探究的な聴取を要求する」(*12)という極めて特異なアンサンブルの在り方。またこの作品には AMM の活動をアーカイヴした冊子の復刻版が付されており、その中の「AMM活動報告書1970年10月」には「1965年6月(AMMがロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで11ヶ月にわたり毎週行なったセッションの開始時期)から1970年9月25日までの間にグループが行なったコンサート、ワークショップ、録音セッション、メンバー個々が行なったレクチャーのすべてが記載されてい」(*13)た。そこに記されている公演のなかには、1969年におこなわれた AMM のメンバーを含む総勢50名以上もの集団によってプレヴォーの「Silver Pyramid」という図形楽譜を演奏するという試みもあった。ドキュメンタリー的なその模様は2001年にリリースされた『Music Now Ensemble 1969』というアルバムから聴き取ることができる。

『It Had Been an Ordinary Enough Day in Pueblo, Colorado』(1979)
【第一次分裂時代――70年代】
プレヴォーは1971年に「今や、物たちのみが、変化する時に変化するのであり、その方がよっぽどよい」(*14)と言ったそうだ。AMMの音楽が円熟の境地に達しつつあることを示した言葉だが、他方では70年代に入るとグループ内部に亀裂が走りはじめることにもなる。毛沢東主義に傾倒したカーデューとそれに従ったロウが、音楽においても自らの政治を反映しなければならないとする一方、プレヴォーがそうした二人の意向を批判することによって、グループ内部の関係が悪化していったのである(*15)。1972年にはカーデューとロウがグループを脱退し、AMM にはプレヴォーとゲアの二人が残されることになった。カーデューの弟子クリストファー・ホッブスもこのころにはグループを離れている。こうした事情もあって70年代の AMM の活動は停滞するが、その間の記録としてゲアとプレヴォーのデュオによる『At the Roundhouse』(1972)と『To Hear and Back Again』(1974)が残されている。この二枚のアルバムについて誤解を恐れずに述べるとするならば、まったくもって AMM の良さが感じられない内容になっている。つまりフリー・ジャズのデュオとしては極めてスリリングで白熱した記録なのだが、サウンド・テクスチュアを探求してきた AMM の音楽性とはまるで別物なのだ。その後1976年に関係解消の兆しが見え、カーデュー、ロウ、プレヴォー、ゲアの四人で非公開セッションをおこなうこともあったものの、翌77年にはこうしたいざこざに愛想を尽かしたゲアがこんどは脱退する。カーデューもまた自らの活動に専念し――1974年にはエッセイ本『シュトックハウゼンは帝国主義に奉仕する』を出版して自らの60年代の活動さえ批判していた――、結果的にプレヴォーとロウが残されることになった。その頃の模様は「AMMⅢ」とクレジットされた『It Had Been an Ordinary Enough Day in Pueblo, Colorado』(1979)で聴くことができる。〈ECM Records〉からリリースされたこのアルバムは異色作と言ってよく、フィードバックを駆使したリリカルなギター・フレーズを奏でたりボサノバ風のバッキングを奏でたりするロウを聴くことができる貴重な作品だ――ただしこの意味でやはり AMM 的とは言い難い内容ではあるものの。
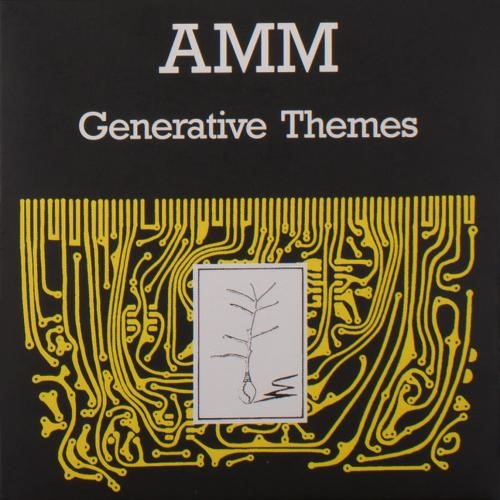
『Generative Themes』(1983)
【ジョン・ティルバリーの参加――80年代】
コーネリアス・カーデューが轢き逃げに遭いわずか45歳にしてこの世を去ったのは1981年12月のことだった。この痛ましい事件が発生した直後に、ジョン・ティルバリーが AMM に参加することになった。ティルバリーはモートン・フェルドマンの作品を演奏する逸材として知られ、これまでにも60年代にときおりカーデューの代わりに AMM とともに演奏をおこなっていたピアニストである。当時は思いもよらなかったのかもしれないが、彼の加入によって20年以上も継続する AMM のラインナップが揃うことになる。トリオとなった最初の成果は『Generative Themes』(1983)として発表された。教育思想家パウロ・フレイレの「生成テーマ」をタイトルに冠したこの作品は、それまでの持続音主体の騒音的合奏からは大きな変化を遂げ、トリオというもっともミニマムな合奏形態によりながら節々に切断の契機を挟んでいく。こうした傾向は続く『Combine + Laminates』(1984)でも聴くことができるが、同作品のリイシュー盤にはカーデューの「Treatise」の演奏も収録されており、ティルバリーを迎えたトリオとなってからもカーデューの仕事を継承しようとしていたということがわかる。1986年から94年にかけてはさらに新たなメンバーとしてチェリストのロハン・デ・サラムが参加しており、その唯一の記録として『The Inexhaustible Document』(1987)が残されている。デ・サラムの演奏が聴こえるたびに室内楽的あるいはクラスター的に響くアンサンブルは、13年ぶりにゲアが参加した『The Nameless Uncarved Block』(1990)とは対照的な内容だ。後者の録音ではジャズ的なゲアのサックス・フレーズが奏でられると一気に全体がジャズ・セッションの趣を呈していくのである。非正統性を貫く AMM はカメレオンのようにサウンドの意味を変化させることができるのだ。また80年代後半には例外的な試みとしてトム・フィリップスのオペラ作品を複数のゲストを交えてリアライズした『IRMA – an opera by Tom Phillips』(1988)もリリースされている。作曲家のマイケル・ナイマンは74年の著作『実験音楽』のなかで「初期の頃には、AMMは、もっと意識的に、新しい音、普通でない音の実験を行なっていたようだ」(*16)と述べ、その一方で「年を追うに従って、楽器による新しい手法は、少なくなってゆき、音響は、川の自然な流れのように、それ自身のカーヴを描くように放っておかれるようになった――優しく、単調で、速い流れもあれば、驚きもあるような」(*17)と書いているものの、こうした特徴は70年代初頭よりむしろ80年代以降のトリオ編成での彼らに当て嵌まるだろう。もっと言えばその後も90年代からゼロ年代にかけてこうした傾向は深化していった。あるいはナイマンはそうした AMM の行く先を予言的に感じ取っていたのかもしれない。
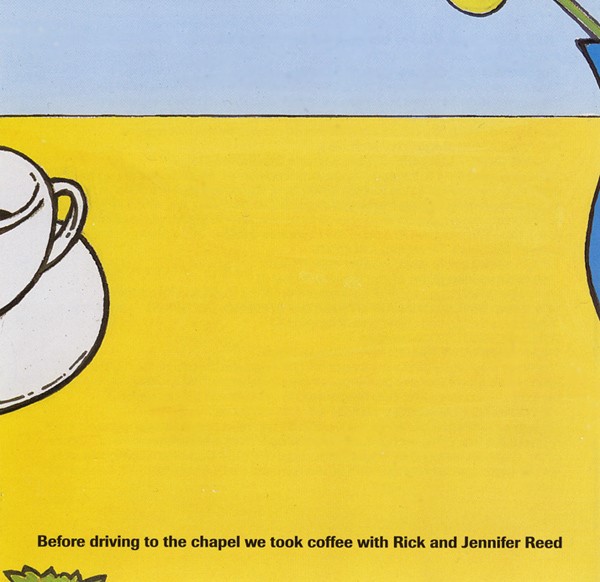
『Before Driving to the Chapel We Took Coffee with Rick and Jennifer Reed』(1996)
【「音響的即興」との共振――90年代】
90年代以降のAMMはますます「物たちのみが、変化する時に変化する」と言うべき自在境に到達し、音響の襞をあるがままに揺蕩わせていく。この時期のトリオの豊穣な記録として、カナダでのライヴを収めた『Newfoundland』(1993)、ペンシルベニア州アレンタウンでの『Live in Allentown USA』(1994)、来日時の記録『From a Strange Place』(1995)、さらにテキサス州ヒューストンでの『Before Driving to the Chapel We Took Coffee with Rick and Jennifer Reed』(1996)と、彼らは世界中を巡りながら矢継ぎ早に年一回のペースで録音を残していった。さらに1996年にリリースされた『1969/1982/1994: LAMINAL』では、60年代のクインテット時代、80年代のティルバリー参加初期、そして90年代という三つの時代を比較しながら聴くことができる内容になっている。持続から切断へ、騒音から静寂へと変化してきた彼らが、90年代には物音の接触する微細な響きをアンサンブルの基層に置いていることがわかる。それは録音環境が向上し微細な響きを記録できるようになったというテクノロジカルな条件もあったには違いないが、少なくともそのような条件を含めて変化した彼ら自身の新たな音楽性を打ち出すためにこの音盤をリリースしたのだと言うことはできるだろう。薄層が重なり合う微弱音への接近は『Tunes without Measure or End』(2000)で物音の動きそのものが中心にくるほどにまでクローズアップされ、『Fine』(2001)ではダンサーとの共演において踊る身体の痕跡と分け隔てなく立ち上がる響きを聴かせるまでになる。この頃のAMMの演奏がどのようなものだったのかについては、一つの証言として「現在の彼らは、音楽的なクライマックスに向かうほど音数は減っていく。(註:ライヴ演奏の)半ばを過ぎたあたりから、幾度も終曲と間違えそうな沈黙が訪れ、やがて退屈すら通り過ぎて、会場の衣擦れの音まで鮮やかに聞こえ始めた。初期とは隔世の感がある」(*18)という2000年のライヴ・レポートを読むことができる。また他の作品としてはエイフェックス・ツインらが参加したアンビエント・ミュージックのコンピレーションに「Vandoevre」(1994)と題したトラックを、メルツバウとのスプリット盤には「For Ute」(1998)と題したトラックを寄せている。カーデュー没後20年の節目には「Treatise」をリアライズした『AMM & Formanex』(2002)を出し、同楽曲を取り上げたアルバムを制作していたグループの Formanex と共演。またおよそ30年振りの MEV との共作アルバムとして『Apogee』(2004)がリリースされている。幾分物語的な演奏を聴かせる MEV と比べたとき、物語の彼岸で物音の変化に焦点を当てるAMMの特徴は一層際立って聴こえてくる。

『Norwich』(2005)
【第二次分裂時代――ゼロ年代以降】
MEV と共演する前年にロウはティルバリーとのデュオ・アルバム『Duos For Doris』(2003)を録音している。これに限らずロウは90年代終盤からゼロ年代初頭にかけて、AMM での活動とは別にソロをはじめ集団セッションまで短期間に数多くのアルバムをリリースしていた。そのなかの一枚であり2000年にリリースされたソロ作品『Harsh』が、その2年後に刊行されたプレヴォーの著書『Minute Particulars』のなかで批判的に言及されてしまう。これを一つの契機としてプレヴォーとの関係は再び悪化し、ロウは二度目の AMM 脱退を経験することになる。『エクスペリメンタル・ミュージック』の著者フィリップ・ロベールによれば、プレヴォーが「ソロ・アルバム『Harsh』の極限的な騒音経験は人々の苦痛への感情移入を生み出すだけだったとしてロウを非難した」(*19)そうだ。そのため AMM はプレヴォーとティルバリーのデュオとして活動することを余儀なくされる。実はロウが脱退する直前にすでにこのデュオによるアルバム『Discrete Moments』(2004)はリリースされていたのだが、AMM 名義で最初に発表されたデュオ作品は全曲無題の『Norwich』(2005)だった。それまでの AMM の弱音を基層に置く志向をさらに推し進めた内容になっているものの、ときに耽美的に奏でられるティルバリーのピアノ演奏が前面に出てしまうデュオ編成は、それぞれのサウンドが屹立しながらも淡く混じり合っていたトリオ時代とは異なるものであり、あえて言えばやはり AMM 的とは言い難い。即興というよりも楽曲のように構成的に響くこうした傾向はその後リリースされた複数のアルバム『Uncovered Correspondence: A Postcard from Jaslo』(2011)『Two London Concerts』(2012)『Place sub. v』(2012)『Spanish Fighters』(2012)においてより洗練されていくことになる。またジョン・ブッチャーを招いた『Trinity』(2009)、そしてブッチャーの他にクリスチャン・ウォルフとウテ・カンギエッサーが参加した『Sounding Music』(2010)もリリースされており、とりわけ後者のアルバムはデュオよりも AMM らしい音響の襞の重なりを揺蕩わせている。ちなみに同年にはティルバリーとロウによる『E.E. Tension and circumstance』(2010)も録音されていて、この二人の関係は続いていたことを明かしている。また2014年には英国即興音楽シーンの現代の揺籃の地「カフェ・オト」において、エヴァン・パーカーの古希を祝したイベントがおこなわれ、その際に AMM とパーカーが共演した演奏が『Title Goes Here』として翌2015年に音盤化された。同じく15年にはベイルートのアコースティック即興グループ A trio とコラボレーションした『AAMM』も録音されている。
- (註)
- *11 同前書、250頁。
- *12 同前書、同頁。
- *13 同前書、235~6頁。
- *14 マイケル・ナイマン『実験音楽 ケージとその後』(椎名亮輔訳、水声社、1992年)240頁。
- *15 この騒動に関してカーデューは「AMMは神秘主義者と社会主義者に分裂した」といった言い方をしている。次を参照。小杉武久「コーニリアス・カーデューと語る」(『音楽のピクニック』書肆風の薔薇、1991年)、松平頼暁「コーネリアス・カーデュウ」(『音楽=振動する建築』青土社、1982年)「反応する集団」(『現代音楽のパサージュ』青土社、1995年)。
- *16 マイケル・ナイマン『実験音楽』238頁。
- *17 同前書、240頁。
- *18 野々村禎彦「AMM&エヴァン・パーカー 来日公演より」(『季刊エクスムジカ第3号』ミュージックスケイプ、2000年)93~94頁。
- *19 フィリップ・ロベール『エクスペリメンタル・ミュージック 実験音楽ディスクガイド』(昼間賢・松井宏訳、NTT出版、2009年)115頁。
COLUMNS
- Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns
Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025


 DOMMUNE
DOMMUNE