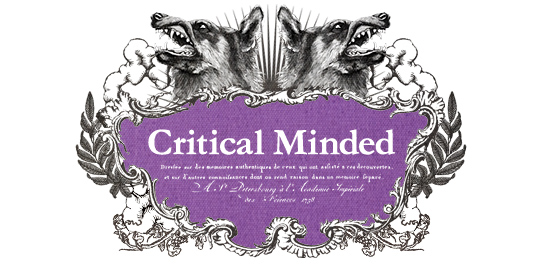MOST READ
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- aus - Eau | アウス
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース
- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- 忌野清志郎さん
- ele-king vol.36 特集:日本のシンガーソングライター、その新しい気配
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス
Home > Regulars > Critical Minded > 第6回 THE VERY THOUGHT OF YOU(前編)
子供のいない僕たちにとって、チーとアーは唯一の家族だった。二匹なのだから唯一という言い方は可笑しいのかもしれないけれど、全員でひとつという意味で、それはまさに唯一だった。僕ら夫婦が今まで上手くやってこれたのは、2人きりだと息が詰まってしまう時に風通しをよくしてくれ、2人の心が離れそうな時は間に入ってくれる彼女たちがいてくれたおかげだと思う。4年前の春、歳上の友人である石田義則さん――と言うよりは、ラッパーのECDと言った方が話が早いだろう――から、家で子猫が生まれたから貰い手を捜しているという連絡が来た。彼が07年に出した小説『失点イン・ザ・パーク』には、飼猫、プーちゃんの出産シーンがある。今度の子猫たちはその次、2度目の出産だった。2人とも猫が好きで、兼ねてから飼いたかったものの、ペット・ショップで買うのはどこか抵抗があった僕たちは喜んで下北の石田さんの自宅に向かった。招き入れられまま家の中に入れば、片付けることが苦手な僕もちょっと驚くぐらい荒れた果てた部屋の中で、猫たちはまるで森の中を駆け回るように遊んでいた。4、5匹いたのだろうか。「どの子にする?」。石田さんに訊かれ、決めあぐねていると、「この子とこの子は仲良しだから一緒にもらってあげて欲しいな」、そう言いながら、2匹でも片手で抱えられそうな小さなメス猫たちを手渡された。その当時、僕は豪徳寺のアパートに引っ越したばかりで、そのまますぐに連れて帰ったように思う。ついさっきまでの住処に比べると、まるで森から草原にやってきたようにガランとした部屋の中を2匹は恐る恐る嗅いで歩きながら、ゆっくりとテリトリーを広げ始めた。「名前は何にしようか?」「鼻が茶色い方がチーで、赤い方がアー」。どちらともなく適当に決めたのに、その後、彼女たちは、チーはチー、アーはアーとしか言いようがない、まるで生まれる前からそう決まっていたかのような猫に育っていった。
2匹は姉妹らしく仲が良くて、いつも合わせ鏡みたいにぴったりと顔を寄せ合って寝ていたし、ふと見ると全く同じポーズで佇んでいることもしばしばだったけれど、キャラクターは真逆で、チーはチーという名前の響き通り少し惚けた、アーはアーという名前の通り少し神経質な性格だった。チーは甘えん坊で、常に人の膝に座りたがったし、音楽に合わせて操り人形みたいに踊らせても、嫌な顔ひとつしなかった。一方、アーは誇りが高くて、ひとと触れ合うのは自分がそうしたいと思った時だけで、無理矢理抱き上げられたりするのが好きではなかった。身繕いに関してもチーは無頓着でアーは丁寧。アーがじっくり自分の身体を舐めていると、チーは自分のことそっちのけで手伝おうと、アーの顔を舐め始め、最初はアーも気持ち良さそうにしているのだが、それがあまりにもしつこいので、そのうちイライラしてきて、アーが飛び掛り、チーがこてんぱんにされるのがお決まりのパターンだった。アーは機嫌が悪い事も多く、壁中に引っ掻き傷を付けたが、チーは手がかからない猫で、喉を鳴らしている時間の方が長いんじゃないかと思うぐらいだった。1歳になったぐらいだろうか、アーは血尿を出し、慌てて動物病院に連れて行くと結石だと診断され、以降、治療用の餌を食べていた。だから、チーが死んだと知った時、一瞬、アーの間違いじゃないかと疑ったものだ。でも、ひょっとしたら、アーは定期的に病院に連れて行っていたけれど、チーは放ったらかしだったので、病気が発見出来なかったのではと思うと、悔やんでも悔やみきれない。僕たちの中でチーは元気でひょうきんなイメージしかなかった。出発前日の夜、チーは部屋に広げられた見慣れないアタッシュ・ケースに興味津々で、ふと目を離した隙に中に潜り込み、「連れていけって言ってるよ」と僕らは笑い合った。
チーとアーは家から出したことがなかった。猫を外に出さないのは、今や都会の愛猫家の間では常識である。家に閉じ込められていたら窮屈ではないかと思う人もいるだろうが、猫のテリトリーというのは実はとても狭く、外に出しても家の周辺をウロウロしているだけで、あまり変わらないのだそうだ。何より、車の事故や、感染病といったリスクを回避する事が出来る。しかし、外の世界を知らない事は確実に猫自身の性格に影響を及ぼすとは思う。チーもアーも、既に生後4年を越えた立派な成猫だったが、顔はまるで子猫ように幼く、可愛らしいままだった。臆病で、わがままで、いつもニューニャー鳴きながら僕たちの後ろを付いて回った。野良猫のふてぶてしく、逞しい表情や態度と比べれば違いは明らかだ。そして、また、そのことは猫と人間の関係性にも多大な影響を及ぼす。例えば、詩人の長田弘が71年に出したエッセイ集『猫に未来はない』を読むと、約40年前の日本では、猫と人間は今よりももっと緩やかに、大らかに付き合っていたことが分かる。この本にはそれまで猫嫌いだった長田が、大の猫好きの女性との結婚を機に猫を飼い始め、段々と猫好きになっていく過程が書かれている。今年に入って知ったこの本に出てくる、彼等が飼う最初の猫も、偶然にもチイという名前なのだけれど、その一代目チイも、二代目チイも、三番目に飼われるジジも、皆、家出してしまったり、他の猫との喧嘩に負けて死んだりしてしまう。夫婦は一代目チイがいなくなり、落ち込んでいる時、チイをくれた猫好きの知人に「そのくらいのことでグシャグシャになっちまうようじゃ、ほんとうのねこ好きにはなれないな。ねこ好きのひとはみんな、一度ならずじぶんのねこがいなくなったり死んだりすることに耐えることで、まえよりもっとねこ好きになってきたんだからね」と励まされ、次の猫を飼う決心をする。そこにある想いは現代と何ら変わるところはないし、この言葉にはとても励まされる。
しかし、驚くのは2代目チイと、ジジをくれる、近所の猫好きおばさんが生まれたばかりのジジを手渡す時に言うこんな台詞だ。「待ってたかい? やっと昨日生まれたんだよ。混血の器量よしだよ。(中略)四ひき生まれたんだけどさ、ほら、ここんとこあまり次つぎにみんないなくなっちゃうだろ? また他人ちにやると、それだけあとでがっかりする気もちを分けてやるみたいになっちゃうのが、どうにもわたしにゃ気が重いのさ。まあ、あんたたちにだけは約束してたからね、そんなかでいちばん好いのを選ってさ、あとはこう(と、手をひねるそぶりをみせて)しちゃったんだ」。この、要するに子猫を間引いたという描写は、何てことのない、とてもさり気ない調子で出てきて、それについて特に言及されることもない。勿論、現代だって行なわれていることなのだろうけれど、数年前に日経新聞で作家の坂東真砂子が子猫を間引くエッセイを書いて激しくバッシングされた事からも分かるように、今では大っぴらに書くことは許されないエピソードだろう。猫好きにも関わらず、この話を普通に聞き流す長田夫婦の感性は、外で飼うことが原因で愛猫を何回も失っているにも関わらず、何の対策も講じないし、去勢すらしようとしない事にも繋がっているし、その背景にはこのような思想があると思う。同書に収められたもうひとつのエッセイ『ねこ踏んじゃった』で長田は書いている。「おそらくねこぐらい、あるひとたちにとってはひどく好かれながら同じぐらいあるひとたちには評判のわるい愛玩動物も、ほかにはまずいないといっていいんじゃないでしょうか? そのことは、ぼくたちにとってねこと同様に親密な動物である犬とくらべてみるとき、いっそうはっきりします。犬が、数千年におよぶ人間とのつきあいの歴史のなかで、じぶんの生きかたを、犬は人間にとっての犬なんだというしかたに変えてきたことにくらべれば、ある動物学者のいうように"数千年にわたる人間とのつきあいで、ねこほどかわらなかった動物はない"のですから」。「人間は猫を飼うことである種の禊をしているのだ」というような事を言ったのは、中島らもだった。つまり、長田の、猫を愛しているにも関わらず、現代からすると妙にそっけない態度とは、人間にとっていちばん身近な野生である猫の本能に対する敬意とは解釈出来ないだろうか。それに対して、我々の猫との付き合い方は良く言えばより親密になって来ているし、悪く言えば、その親密さとは猫の野生性を殺すことで得たものであり、また、親密さは依存と置き換えることも出来るだろう。社会のポスト・モダン化によって人間たちに引き起こされた絶対的な孤独を癒すために、猫たちは本能を奪われてしまったのだろうか。果たして、それは彼らにとって幸せなことなのだろうか。
Profile
 磯部 涼/Ryo Isobe
磯部 涼/Ryo Isobe1978年、千葉県生まれ。音楽ライター。90年代後半から執筆活動を開始。04年には日本のアンダーグラウンドな音楽/カルチャーについての原稿をまとめた単行本『ヒーローはいつだって君をがっかりさせる』を太田出版より刊行。
COLUMNS
- Columns
Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁


 DOMMUNE
DOMMUNE