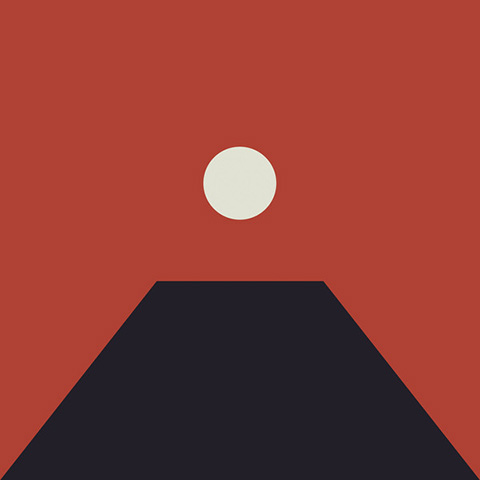MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Tycho - もっとクリアに、もっとハイファイに、美しき音響の彼岸へ
去年の「ザ・美しい音響&テクスチャー大賞」がジョン・ホプキンスだとしたら、今年はティコだろう。
ティコ(じっさいは「タイコ」と発音する模様)ことスコット・ハンセンはもともと、もろにボーズ・オブ・カナダに触発されるかたちでダウンテンポ~エレクトロニカに取り組んでいたアーティストである。その影響は実質的デビュー作の『Past Is Prologue』(2004/06年)にもっともよくあわわれているが、今回の新作でも“Into The Woods”や“No Stress”といった曲にその影を認めることができる──とはいえ『Dive』(2011年)以降、BOCの気配はあくまで旋律や上モノの一部に残るに留まり、むしろダンサブルなビートと生楽器による演奏の比重が増加、『Awake』(2014年)からはバンド・サウンドに磨きがかかり、まさにそれこそがティコのオリジナリティとなっていく。その集大成が前作『Epoch』(2016年)だったわけだけれど、重要なのはそのようなロック的昂揚への傾斜(およびノスタルジーの煽動)と同時に、サウンドの透明感もまたどんどん研ぎ澄まされていった点だろう。この美麗さはBOCにはないもので、そのようなテクスチャーにたいするこだわりは、次なるステップへと歩を進めるために〈Ninja Tune〉へと籍を移し、ほぼすべての曲にセイント・スィナーことハンナ・コットレルの魅惑的なヴォーカルを導入、アートワークの連続性も刷新した新作『Weather』においても健在だ。
前作でキャリアにひと区切りがつき、いま新たな一歩を踏み出さんとするティコ。はたして今回のアルバムに込められた想いとは、どのようなものだったのか? フジロックでの公演を終え、東京へと戻ってきていたスコット・ハンセンに話を聞いた。
毎回もっと聴きやすい作品にしたいと思っている。ロウファイな音楽のなかで興味があったのは、ほんとうにひとつかふたつくらいの要素くらいしかなかったんだ。もっとハイファイにしたいし、クリアな音にしたいと思っている。
■いまも活動の拠点はサンフランシスコですか?
スコット・ハンセン(Scott Hansen、以下SH):いまでもそうだよ。もう13年くらいいるね。
■日本は湿気が多くて蒸し暑いですけれど、おそらくサンフランシスコはぜんぜんちがいますよね。
SH:まったくちがうね。この暑さには慣れていないよ。サンフランシスコはそこまで暑くならなくて、夏でも短パンをはけるのが2~3週間あるくらい。それ以外は涼しかったり、風が吹いたり、霧が濃かったり。天候のちがいとか雲の動きとかが見えるから、あの気候はけっこう好きだね。
■今回のアルバムのタイトルは『Weather』ですが、音楽制作にその土地の気候は影響を与えると思いますか?
SH:たしかに『Weather』という名前をつけたけれども、直接的な意味というよりは、移り変わりというか、いまこの時代いろいろなアップダウンがあって、自分のコントロールの範囲外のこともたくさんあるなかで、それを受け容れていかなければいけない状況、みたいなことも意味してるんだよ。それから、僕がつくる音楽は自分の体験がもとになっていて、僕は自然が好きなんだけど、そういうところに行って、自然を音楽に反映させている。サンフランシスコだと、自然のエネルギーだとか天気の移り変わりだとか、そういうものが直接的に感じられるから、それは音楽につうじていると思うよ。『Weather』には天候という意味もあるけど、ふたつの意味を与えているんだ。
■前作の『Epoch』がビルボードのエレクトロニック・チャートで1位をとったり、グラミー賞にノミネートされたりしましたけれど、そういうショウビズ的な成功は、あなたにとってどんな意味がありますか?
SH:僕の目標は音楽をつくるということであって、そういったショウビズ的な成功にはあまり惑わされないようにしてるけど、グラミーとかビルボードで話題にあがったことはすごく光栄だし、じっさいに僕の音楽が仕事として認められたということはすごく嬉しい。もともと僕はグラフィックデザイナーをやっていて、それほど長くは音楽活動をしていないんだよね。だから、アーティストとして認められたということにはひと安心したし、今後もアーティスト活動に集中できるからすごくいいことだと思うよ。自分の音楽はメインストリームの音楽ではないので、グラミーやビルボードに自分の話が出たことにはとてもびっくりしているよ。
■まわりの反応も変わりましたか?
SH:うん、そのおかげで一般の人たちが、じっさいに僕が何をやっているのかということを理解できたと思う。両親や友人の一部は僕が何をやっているのかよくわかっていなかったんだ。「DJをやっているの?」とか言われたりね。エレクトロニック・ミュージックをやっている人はけっこう誤解されると思う。じっさいの音楽のつくり方がふつうの人たちにはあまりわからなかったりするからね。だから、グラミーのノミネートとか、ビルボードのチャートインという実績があったことで僕が本物のミュージシャンだということを理解してもらえたのでそれはよかったね。
■今回の新作は全体的に、前3作にあったような、わかりやすくダンサブルなビートが減って、ダウンテンポ的な曲が増えたように思いました。それには何か心境や環境の変化があったのでしょうか?
SH:循環というか、一周してきたような感じがするね。『Dive』(2011年)はチルでダウンテンポな感じだった。アルバムを出したあとにツアーをやって、ライヴでエネルギッシュな感じでギターの音やドラムの音を出していった。エキサイティングなものにしたかったから、エネルギーのレヴェルがあがったんだよね。その感じを捉えたくて、『Awake』(2014年)にはもう少しエネルギーが入っている。ロックっぽい感じの音になったと思う。そのあと僕はDJとかダンス・ミュージックにハマるようになっていったんだ。もともと90年代からずっと好きで、それが音楽を作るインスピレイションになっていたんだけど、そこにまた興味がわいてきた。それが2014年から2016年ころの話。そのあとに作ったのが『Epoch』(2016年)で、これはちょっと原点に戻るというか──僕が好きな音楽はゼロ7とかザ・シネマティック・オーケストラとかシーヴェリー・コーポレーションとか、ヴォーカルが入っていてちょっとトリップホップみたいな感じの90'sのころの音楽で。自分もそういうものをつくりたいなと思って、今回はもともと僕が好きだった音楽にふたたび返るような感じでつくったんだ。
■いまおっしゃったように、今回のアルバムの最大の特徴は、ほとんどの曲にヴォーカルが入っていることです。
SH:もともとヴォーカル入りの作品はずっとつくりたかったんだよ。でもつくり方を知らなかったというか、まずはベーシックなところから、たとえばシンセをレコーディングしてとか、そういうところからやらないといけなかったんだ。2004年の『Past Is Prologue』にもヴォーカルのトラックはあったんだけど、以降ずっとインストゥルメンタルをやる結果になってしまってね。ただ今回は、ハンナ・コットレル(Hannah Cottrell)と出会うというきっかけがあった。そのときに迷ったんだ。次のアルバムは、すごくヴォーカルに片寄るかインストに片寄るか、どっちかにしようと思っていて。あまりいろんなゲストをフィーチャーして入れるよりも、もっと強いステイトメントみたいなものを出したかった。ヴォーカルをたくさん入れると、けっこうコアで強いメッセージ性が出ると思う。ティコはそういうアルバムこそがメインのアーティストだと思ってるから、アルバムとして強い主張をするならけっこうわかりやすく──今回みたいにヴォーカル寄りなほうがリスナーにとってもわかりやすいかなと思ったんだ。
■ハンナ・コットレルはどういう人なのでしょう? 彼女とはどのような経緯で?
SH:共通の友人がいて、それがきっかけで出会ったんだ。彼女がサンフランシスコの親戚に会いに行くことになって、僕が住んでいるサンフランシスコにたまたま来るということになった。そのとき僕はアルバムの曲をけっこうつくっていて、これにヴォーカルを入れるにはどうしたらいいかってちょうど考えていたんだ。友人はそのことを知っていたから、ハンナを紹介してくれたんだけど、僕もそのときまでハンナのことはぜんぜん知らなかったんだ。彼女はそんなに活動もしていなくて、リリースもしていなかったからね。でもとりあえずやってみようということで、2曲やってみた。最初にやったのが“Skate”という曲なんだけど、彼女が歌いはじめたら感動して、これはすごいと思った。ぜひ彼女とのコラボレイションを追求するべきだと思ってアルバムを制作していったら、結局はアルバムのすべてができあがった。すごくインスピレイションになったよ。
■リリックは完全に彼女が? あなたからのディレクションはあったのでしょうか?
SH:ハンナがすべての歌詞を書いた。彼女の世界感を表現したかったので、僕はその邪魔をしたくなかった。自分がすべての主導権を握って何もかもをやるというのではなくて、ほかの人の観点も入れて、僕の作品と掛け合わせたものを今回は作りたかったんだ。インストの曲って、聞いた人によっていろんな解釈ができるというか、すごくオープンで、余白が残されている。聴いた人それぞれが各自の旅路、空間にハマっていけるみたいな自由度があるよね。今回はヴォーカルを入れることによって、ハンナというひとりの人間の体験と音楽とを掛け合わせている。これまではリスナーが、自分のストーリーを紡ぎ出したりしていたわけだけど、今回はハンナの物語というか、映画というか、彼女というひとりのキャラクターをとおして僕の音楽をみてもらう──これまでとはちょっとべつの見方をしてもらうためにこの作品をつくったんだよ。
■つまり、シングル曲“Pink & Blue”のジェンダーをめぐる歌詞であったり、“Japan”の日本も、全部ハンナの体験ということですね。
SH:そう、ぜんぶ彼女が書いたもので、それは僕の見方や体験とはまったくちがうものなんだ。それじたいが美しくて素晴らしいことだと思う。彼女の世界観は僕では想像できないものだし、理解できないところもあるけど、僕の音楽と彼女の歌詞が新しい何か特別なものを生み出しているということじたいが素敵だなと思う。
僕のなかの記憶だったり懐かしい感じだったり、あとは失われた感じ、喪失感みたいなもの、そういう感情をたいせつにして創作のための活力にしているから、それが音楽にもあらわれているんだと思う。
■ヴォーカルを入れるにあたって苦労した点は?
SH:いちばん難しかったのは、余白を見つけること、空間を見つけることだった。僕の曲はたくさんのレイヤーが多層に入っていていろんな要素があるから、難しいんだ。自分だけの音楽だと「じゃあここのシンセを下げよう」とか微調整できるんだけど、今回はヴォーカルがあるから、それをメインの要素として前面に出したいという思いがあった。その一方で、トラックのほかの音の要素、繊細なテクスチャーをどうやって引き出すかという、バランスの作業が難しかったね。
■オートチューンだったり、あるいはスクリューのような声の使い方に関心はありますか?
SH:たしかにそういう加工には興味があるし、じっさい僕もときどきやるよ。1曲目の“Easy”では彼女の声を細かく刻んで加工している。これまで自分が作ってきたヴォーカルの曲もそういうふうにやってきたから、まったく抵抗はないね。僕はエフェクト、リヴァーブとかディレイは楽器みたいにして使いたいと思ってるから、ヴォーカルも同じように処理したいと思うんだけど、今回のヴォーカルにかんしては、彼女自身の声がすごく美しかったので、なるべくそこはシンプルにピュアに、誠実に彼女の声に近い感じで、あまりやりすぎないようにしたんだ。でもそういうことには興味はあるし、僕も実験しているよ。
■3部作あたりから美しい残響、とくにギターの音の響かせ方がティコの音楽の最大の特徴になっていったと思っていて、イーノ=ラノワを思い起こす瞬間もあるのですが、ご自身としてはいかがでしょう?
SH:そのコメントはすごく嬉しいよ。僕は自分のことを巧みな楽器奏者だとは思ってなくて、プロデューサーという自覚のほうが強い。スタジオを楽器として使うとか、エフェクトを楽器として使うみたいなことをやっているから、もちろんメロディに感情を込めたいという思いもあるけど、音の響きとかテクスチャーとか、そういったものをいちばん大事にしてるんだ。だから音楽をつくるときも、最初からピアノでまるごとぜんぶ、ということはできなくて、ピアノをちょっとだけ弾いて、エフェクト、リヴァーブをかけたりして、そういうのを重ねることでおもしろい音になっていって、それにインスピレイションを受けてさらに作曲も続く──という感じでつくっているね。
■ジョン・ホプキンスも思い浮かべました。
SH:彼とはじっさいに知り合いだよ。いい人で、コンテンポラリーな音楽をつくる人のなかでも優秀なひとりだと思ってる。
■ティコの音楽は、初期の『Past Is Prologue』はいまよりもくぐもった感じ、ロウファイさがありましたけれど、作品を追うごとにサウンドがクリアになり、ハイファイになっていっている印象を受けます。
SH:たしかにそうだね。毎回もっと聴きやすい作品にしたいと思っている。たしかにロウファイに興味があった時期もあったね。あらあらしいというか、ざらざらしたような音が好きだったんだけど、よくよく考えてみたら、そのロウファイな音楽のなかで興味があったのは、ほんとうにひとつかふたつくらいの要素くらいしかなかったんだ。いまではもっとハイファイにしたいし、クリアな音にしたいと思っている。ハイファイのなかでも自分が好きな音の響き方であったりテクスチャーであったり、ロウファイなもののなかで好きな要素だけを残して、どんどんハイファイにしていきたいと思ってるよ。

■今回はレーベルも変わって、〈Ninja Tune〉と〈Mom + Pop〉からの共同リリースというかたちになりました。
SH:以前のレーベルは〈Ghostly International〉だったね。彼らとは最初から一緒にやってきて、付き合いも長くて、すごく素晴らしかったんだけど、今回はそれとはちがうことをやりたかったんだ。〈Ninja Tune〉は僕が昔からすごく好きなレーベルで、オデッザやボノボもいるし、今回新しい作品をつくるにあたってちょっとこれまでとは異なる基盤というか、そういうものが欲しかったから変えたんだよ。
■いまの〈Ninja Tune〉は90年代のころとはだいぶ音楽性が変わりましたけれど、やはりいまのオデッザやボノボの路線のほうが好き?
SH:いま〈Ninja Tune〉にはいろんなアーティストがいるし、その歴史も素晴らしいものだと思う。僕は95年ころに〈Ninja Tune〉のコンピレイションを買ったんだけど、それでエレクトロニック・ミュージックを初めて聴いたといっても過言ではないくらいで。それまで聴いてきたものとまったくちがったから衝撃的で、「これはなんだ!」って、すごくインスピレイションを受けたよ。昔からすごく好きだね。ただ、いまの〈Ninja Tune〉のほうが、自分のやっている音楽に近いかなという気持ちはある。昔の〈Ninja Tune〉のままだったら、いまの自分の音楽とは合わないかもしれないね。
■ティコの音楽にはノスタルジーを感じさせる部分があります。それは意図したものでしょうか?
SH:意図的にというよりは、僕のなかの記憶だったり懐かしい感じだったり、あとは失われた感じ、喪失感みたいなもの、そういう感情をたいせつにして創作のための活力にしているから、それが音楽にもあらわれているんだと思う。たとえば過去を振り返ったりして、子どものときの記憶を思い出したり、幼いころに聴いた音とか、そういうものを思い出して音楽に使ったりしているので、それがノスタルジア、懐かしさみたいな感じで出ているんじゃないかな。
■ティコが初期に影響を受けていたボーズ・オブ・カナダや、前作『Awake』のリミックス盤に参加していたビビオも、そういった感覚を呼び起こさせる音楽家ですけれど、あなたのノスタルジーは彼らのそれとは異なるものでしょうか?
SH:ボーズ・オブ・カナダは僕のいちばんのインスピレイションといっても過言ではないね。だいぶ前に彼らに会ったことがあって、そのときに彼らの音楽を聴いて、自分もこれをやりたい、こういう音がやりたい、音楽をはじめたいって思ったんだ。だからすごく影響を受けているよ。ただ、たしかにノスタルジーはあると思うけど、彼らのほうがダークな感じがあると思うね。もう手に届かない、もう戻れない、喪失感、そういった感覚は共通してあると思っている。僕とボーズ・オブ・カナダは歳も近いんだ。僕たちの世代にはそういう感覚を持っている人は多いんじゃないかな。
■今回のアルバムのリミックス盤を作る予定はありますか? もし作るとしたら誰に依頼したいですか?
SH:じつはいまもういろんな人にリミックスを頼んでいて、それがどう仕上がるか、楽しみに待っているところなんだ。コム・トゥルーズ、クリストファー・ウィリッツ、ビビオは以前にもやってもらって、素晴らしいと思うから、またやってもらいたいな。
取材・文:小林拓音(2019年8月27日)
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE