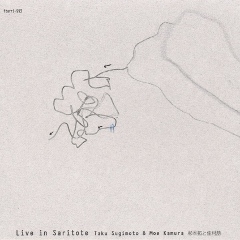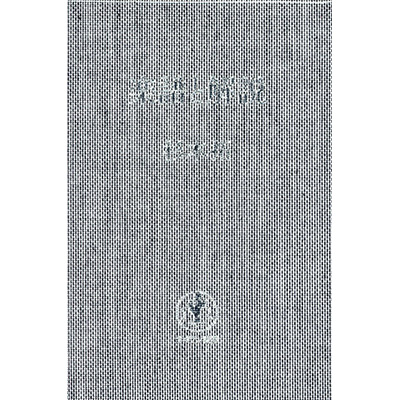MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Reviews > Album Reviews > 杉本拓と佳村萠- Live in Saritote
杉本拓がギターを爪弾くかたわらで、佳村萠の吐息は洩れる。即興と作曲が交錯し、漂う空間のざわめきを抱え込みながらふたりが縺れ合うような音楽。あるいは杉本の指先が、そのまま佳村の口唇に触れるようにして生まれる「さりとて」の、新たなアルバムがリリースされた。異様に長尺な「無音」を奏するなどラディカルな試みで知られるギタリストの杉本と、不定形ポップ・ユニット「ほとらぴからっ」などで愁いを帯びた歌声を聴かせる佳村が、「さりとて」の活動をはじめたのは2007年。これまで世に送り出してきた2枚のアルバムがスタジオで録音されたものであったのに対し、本作品は2010年から2013年までに行われたライヴの記録を収めたものである。ジョン・ケージを批判的に継承する杉本の思想が垣間見える「さりとて」の活動を鑑みるに、3枚めにしてライヴ・アルバムが発表されたことは、その音楽的特長を先鋭化させた結果であるように思われる。
というのも、前2作を注意深く聴けばわかるように、「さりとて」の音楽には、環境音の肌理を曝け出そうとするストラテジーが備わっているからだ。中空を遮る航空機、遠のく車両、犬らしき吠え声から鳥のさえずりまで、多重録音によるものなのかどうかはともかく、白紙の状態からコンポジション/インプロヴィゼーションを立ち上げていくことが可能であるはずのスタジオ録音においてこれらのサウンドスケープが聴かれるということは、彼らが意図的にそうしたのだ、と考えられる。もともとトーンを抑えた音楽である「さりとて」の背景をなす「静寂」に注視することで、微細な音の蠢きがクローズアップされ、聴者の中に圧倒的な「喧騒」が呼び覚まされる。とはいえ「喧騒」は、あくまでカッコつきでなければならない。なぜなら、杉本と佳村の演奏音が、音量に上限を設けてしまうことで、環境音はある一定の弱音として聴かれざるを得ないからだ。ここでは聴者は、いわば透聴力をもってサウンドに接することを余儀なくされる。そしてこのような試みを音盤上で繰り広げていくことを考えたとき、それは必然的にライヴ・アルバムという形に結実する。
ライヴ音源とは、ある種のフィールド・レコーディングである。演奏者が録音機器を志向するのではなく、録音機器が「演奏者」を指向する。ここでいう「演奏者」とは、マイクに集まる無差別な音響群のことだ。それには演奏音も含まれれば環境音も含まれる。スタジオ録音からライヴ録音となることによって、それまでは保たれていた音の前景(演奏音)と後景(環境音)の区別が、同じグランドノイズの上に屹立する「図」の対立へと移り変わる。たとえば本作品において、8曲めの“ビコーズ・イット・ブリーズド”から9曲めの“ア・ウィンド”にかけて、耳を澄ませてほしい。2010年8月5日の、いまはもう閉鎖されてしまったイヴェント・スペース〈Loop-Line〉のざわめきが、続く2011年9月17日アメリカはニューヨークの〈Issue Project Room〉におけるグランドノイズと接続されることで、そのあられもない姿を曝け出すことに、聴者の意識は向けられる。さらに言えば、“ビコーズ・イット・ブリーズド”と“ア・ウィンド”の間に僅かに挟まれた数値上の無音状態は、聴者の意識を彼の現実世界における基調音それ自体の肉感的な物質性へと向かわせる。異質な時/空間の対立が、音楽の前提条件となるサウンドそのものの異貌性を露わにするのだ。
ここで急いで付け加えなければならないことがある。これまで述べたようなラディカリズムは、一方で「音響派」のマンネリズムでもあった。「さりとて」にアクチュアルな意義があるとすれば、こうした杉本が求め続ける実験精神を内包したまま、他方では佳村の声によって、ポップネスの様相を呈してもいるのだ、ということである。アルバムも終わりに近づき、宮城県に伝わる数え唄“ひとりでさびし”の、あまりにも抒情的なアレンジを耳にした人々は、知的意匠を施されつつも大衆的共感で身を纏った音楽のその表面に、率直なノスタルジーを感じることだろう。それは「現代音楽」をカジュアルに消費できるようになった今日の社会において音楽的実験を継続させるための一つの方策として、高く評価されるべきものなのではなかろうか。どれほど知的な聴取を望めども、音は感性を刺激し続けるのだから。
細田成嗣
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE