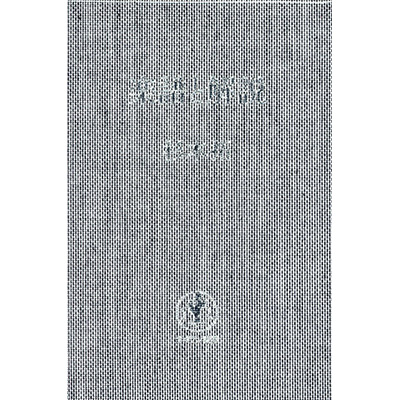MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 楽譜と解説- 杉本拓
思弁的作曲に関する覚書――杉本拓『楽譜と解説』に寄せて
カバーに覆われていない、剥き出しのままの灰色の表紙。表表紙にはタイトルと著者名が銀箔のように輝く文字となって刻まれている。ひっくり返して裏表紙を眺めていたら、濃淡のある灰色の平面に一箇所だけ黒い点がついていることに気がついた。よく目を凝らして見てみると、灰色に見えた表紙は黒の経糸と白の緯糸が平織に編み込まれることによって作られている。けして均等ではない編み具合が濃淡を生み出していたのだ。そして裏表紙の右下辺りからは経糸がひょっこり飛び出していた。黒点に見えたそれはおそらく何かの拍子についた傷なのだろう。しかし本当にそうだろうか。もともとその箇所だけ黒点に見えるように経糸が飛び出していたのではないか。あるいは使用するうちに黒点がついていくような装幀としてあらかじめデザインされていたのかもしれない。もちろん装幀を手がけた人物に訊けば「答え」はわかるだろう。だがたとえ「答え」を手中に収めたとしても、いまここに黒点のついた書物があるという事実からは、あり得たかもしれない複数の「答え」を考え出してみることができるはずだ。
ギタリスト/即興演奏家/作曲家としていわゆる実験音楽シーンで活躍してきた杉本拓による、待望の、初の単著が〈サボテン書房〉から刊行された。杉本はこれまでもブログから雑誌まで様々な媒体で文章を発表するなど活発な言論活動をおこなってきており、なかでも角田俊也と吉村光弘とともにゼロ年代半ばから後半にかけて編集・発行していた「音と言葉をめぐる批評誌」の『三太』は、同時代のローカルな「実験音楽」を制作者の視点を交えつつ言語化していく貴重かつ重要な試みだった。そこでは杉本は自らの作品の解説をはじめ日常生活の体験談からアート作品や書籍など様々な対象を取り上げつつ、多くの人々が自明のものとして素通りしてきた音と音楽をめぐる問いに真正面から向き合うような言葉を書き連ねていた。全編書き下ろしによる本書『楽譜と解説』はこの『三太』で問われてきた問いが一層の深化を見せひとつの形を成したものだと言ってもよいだろう。2002年から2016年のあいだに手がけてきた作曲作品を取り上げて、実際の楽譜を交えて時系列順に解説していくという本書の内容は、音を聴くだけではわからなかったような作曲の構造が詳らかにされるなど、主にゼロ年代以降の杉本の作曲活動を俯瞰できる一冊となっている。しかし同時に楽曲の解説はあくまでもきっかけに過ぎず、そこから彼が音楽をどのように考え実践しているのかといった哲学的思索が随所で披瀝されることにもなる。ときには本文を大きく凌駕する分量の注釈がつけられていることもあり、それだけでも一本の論考たり得る濃厚かつ刺激的な読み物となっている。
秋山徹次と中村としまるとともに90年代終わりに企画していた即興イベント「The Improvisation Meeting at Bar Aoyama」をはじめ、即興演奏家として、それも当時の言説を踏まえれば「音響的即興」とも呼ばれたような活動をしてきた杉本は、2002年ごろから作曲活動に重きを置くようになっていった。その動機は一見するとシンプルであり、「即興ではできないことをやる」(1)ことにあったという。一般的に言って、即興演奏では他の誰にも真似できないような個性的表現が尊ばれる傾向がある。だが杉本にとって「『作曲』でやりたいことのひとつはこの『個性』を抹殺すること」 だった。ただしそれはオリジナリティを消し去るという意味ではない。「いろんなもの——つまりシステムに支えられているがゆえの個性的表現や技法——をとっぱらったあとに残るもの、それが『オリジナル』であるなら、それは抹殺の対象ではない」(2)。ここには「個性」に対する興味深い捉え方がある。つまり即興演奏における「個性」とは、他の誰にも似ていない純粋な「オリジナリティ」などではなく、つねにすでに他者に侵され規定されてしかあり得ないものとして捉えられているのだ。杉本が「抹殺」する対象としたのはこうしたいわばまがいものの「個性」だった。それはかつてデレク・ベイリーが「非イディオム的即興」と呼んだ方法論を彷彿させもするが、言うまでもなくベイリーと同じく杉本もまた、まっさらな「オリジナリティ」を取り出すために「個性」を批判しているわけではない。「誰でもできる、しかし実現が困難であるような状況」(3)を志向する杉本にとって、「個性」を剥いだ先にあるのは、先走って述べるならば「即興の可能世界」とでも言うべきものだった。たとえば集団でおこなわれる即興演奏について杉本は次のような想いを馳せている。
即興においては順番にひとりずつ音を出すなどということはけっして起こりえないだろうと誰もが思っていても、それは習慣と制度の問題にすぎず、もしかしたら私たちがいま「即興」と呼ぶもののなかに、「順番に演奏する」というような形式(あるいは様式)を含む、そんな音楽のありかたがありえたのではないか(4)
すなわち「習慣や制度」といった「個性」を取り去るとき、そこには「即興においても論理的には可能なこと」(5)が浮上してくるのである。論理的には可能であるにもかかわらず、通常はほとんど聴かれることがない演奏。それは即興演奏が「自由」だとされているがゆえに胚胎する「不自由」とも関係するだろう。自由に演奏してよいはずの即興演奏において無意識のうちに形成されてしまう暗黙のルール。率直に言って、即興演奏だから「自由」に演奏してよいということは、「自由」でないかに聴こえる演奏をしてはならない、ということへと容易に反転する。何が「自由」であり何がそうでないのかは時代や環境および状況に左右されるのだとすれば、「自由」を志向する即興演奏は「習慣や制度」であるところの不文律のルールに積極的に縛られていく行為だとも言えるだろう。いずれにしても「順番にひとりずつ音を出す」ということは即興演奏であれば原理的には生起し得るはずである。杉本が作曲をおこなうことの動機のひとつにはこうした「異なる即興の可能性」(6)を具現化しようとする側面がある。
私のいう「即興」は、じっさいにそうなることはまずなかったとしても、論理的には可能なそれのありかたすべてを含む。そして、そのなかからとても起こりそうにない即興演奏の状況を考え、そしてそれを導く、というのも「作曲」によってできることなのではないかと私は考える。(7)
ここで即興と作曲は対立をなしていないことに注意してほしい。むしろ作曲は「個性」に満たされた即興によって逆説的に覆い隠されてきた、即興それ自体の可能性を救い出すことへと向けられている。繰り返しになるが「自由」を志向する即興演奏はそうであるがゆえに「不自由」を胚胎する。その結果、本来ならどのような演奏でもおこなわれてよいはずの「自由」なセッションにおいて、ある一定の型が生まれ、あたかもそれをなぞるかのようなクリシェに陥ってしまうことがある。ひとつとして同じではないはずの即興演奏がどれも似たり寄ったりになってしまうことについては、かつてギャヴィン・ブライアーズがデレク・ベイリーに対して向けた批判を想起することもできるだろう(8)。ブライアーズが即興に見切りをつけて作曲活動を本格化したように、杉本もまた作曲へと目を向け始めたわけだが、彼の場合即興とはまったく別の問題系へと飛躍したというよりも、先に見たような「即興それ自体の可能性」を従来の即興概念を超えて摑み取ろうとするテーマが横たわっていた。「私の本業は実験音楽であり、音楽を作ることは、それをとおして、音楽とは何かを問いたいからなのである」(9)と主張する杉本にとって、ある種の作曲とは即興における音楽の問いを別用のアプローチとして探り直していく作業に他ならない。
そしてその問いのひとつは次のようなものだっただろう。先に述べたように杉本は即興演奏の論理的な可能性、いわば即興の可能世界について言及していたのだった。彼の作曲活動においてはさらに作曲それ自体の可能世界を現出する試みがなされていく。一般的に言って作曲は事前の準備として演奏の前におこなわれるものである。だが杉本は作曲→演奏→聴取という単線的なヒエラルキーからは想像もおよばないような作曲の在り方を提起する――演奏や聴取の後に作曲することは可能か? という驚くべき問いとして。たとえばある作曲作品があるとき、そこでは記譜された規則やルールに基づいた演奏がおこなわれることになる。だがその演奏を聴くわたしたちにとって、あるいは演奏された音そのものにとって、同じ音楽を導く規則やルールは必ずしもひとつとは限らない。そこからは実際の記譜とは別の規則やルールを排除するに足る理由づけを得ることができないからだ。後に述べるように厳密に言えばどのような音楽においても複数の規則やルールを想起することは可能だろう。しかしよりそうした側面を想起させる音楽とそうでない音楽という区分けはできる。あからさまに特定の作曲ルールを想起させる現代音楽や、身体感覚としてルールが浸透したポップスからは思考し難いもの。「aka to ao」(2006)という楽曲について杉本は、「私の曲に限っていえば、じっさいの音を導く規則が複雑ではないのと、完成した曲であってもそれが現実には有限の時間と空間を占める以上、それを聴いて、私のもちいた規則とは別の複数の規則を推測することが可能になるだろう」(10)と書き記している。
複数の規則を推測する(speculate)こと。言い換えるならば作曲の思弁(speculation)へと赴くこと。「aka to ao」において杉本はひとまずこうした作曲の思弁が可能であることを示したと言える。さらに可能であるばかりか推測=思弁される規則は複数だとされていることを見落としてはならない。すなわち「個性」の先にある即興/作曲の可能世界はつねに複数であり、そうであるがゆえにたとえ一回的なライヴ・パフォーマンスがおこなわれたとしてもけして他の可能性を排除することがない。このような音楽を聴くことは特権的ではなくあくまでも偶然的な体験だ。複数の可能性のなかから理由なしで到来した一回を聴くことは、聴取体験を脱神秘化し、民主化し、もっと言えば聴くことと聴かないことが限りなく近づいていく。そしてそれは「音と聴取の相関」から離れた場所にある作曲それ自体の可能性を明かすことになるだろう。こうした問題についてわたしは以前次のように書いたことがある。
かつて批評家の佐々木敦は、体験を前提とし聴かれることを目指しているという点においてコンセプチュアル・アートとは異なるものとしながら、「一回性の中に、他の可能性を排除するに足る理由づけ」のないような、「聴かなくても聴いてることと無限に同じになる」ようなものこそが、「即興的な、偶然的な要素を取り入れたヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」だと述べていたことがある。いわば充足理由律を否定する思弁的な作曲に可能性を見ていたのであって、それは音をあるがままにするはずのケージ主義的な実験音楽の多くの試みが、しかし音の物的状態ではなく、あくまでも聴くこととの関わりにおいてのみ可能な実践でしかなかったのに対して、聴取および演奏とは区別された作曲それ自体を提起していたジョン・ケージ自身の試みにおいては、「聴取と音の相関」を抜け出す手掛かりをみることができるのであり、その方向性を相関主義の隘路に陥ることなく推し進めたものとして「ヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」を捉えることもできる。(11)
杉本の音楽はまさしくこの意味で「ヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」だと言うことができる。そしてそれは演奏や聴取とは区別された作曲それ自体を思弁する試みとして、いわば「思弁的作曲」とでも呼ぶべきものとして捉えることができるだろう。もちろん杉本自身は「思弁的作曲」などという言葉は一切発していないし、本書『楽譜と解説』のなかのどこにも登場することがないということはここで強調されなければならない。それはあくまでも彼の音楽を形容するために持ち出されているに過ぎない。そしてさらにこの言葉は、中世ヨーロッパにおいて実践的な音楽に対置されるものとして探究された「ムジカ・スペキュラティヴァ」や、それをもとにジョスリン・ゴドウィンが理性を超越した音楽のエゾテリックな原理を解明しようとして描いた「思弁的音楽」とも関係がない。杉本の音楽における思弁は極めて実践的な音楽において遂行されていくからだ。作曲を演奏および聴取に先行する事前の準備として捉えるのではなく、まったく反対に、すでにある音や演奏、あるいは聴取といったものを手掛かりにして、あり得べき作曲のルールを考え出していくこと。それはまた聴取を特権化する俗流音響派論とも異なる。正確にはあらゆる解釈へと開かれていることは必要だが十分な条件ではない。あくまでも論理的に可能な即興/作曲それ自体の可能性が問われているのだ。
その根拠となるのが聴取と音の事実性である。「人は何らかの文脈のもとで音楽を聴いている。そして、そう聴いてしまった事実は変えようがない」(12)。この事実性によって「聴取と音の相関」はいわば内破へともたらされる。たとえばライヴ演奏をおこなっていると見せかけてスピーカーから録音音源を流していた吉村光弘の例や、ラップトップから電子音を流していると思わせて人間の声を発していたマッティンの例を杉本は挙げている。「タネが明かされたあとも、そのときその音楽をどのように聴いたか、という聴取体験そのものは変わらない。吉村くんのコンサートでは、それを生のフィードバックとして、マッティンのコンサートでは、それをコンピュータによる合成音として聴いていたという事実は変えようがないのだ。それに聞こえた『音そのもの』が変わるわけでもない(そんなことは不可能だ)」(13)。ある作曲作品が実演され、ある音が生起する。そこに立ち会うわたしたちは、特定の音の発生と個別の聴取体験を経ることになる。この事実が作曲の思弁――聴取および演奏とは区別された作曲それ自体へのアクセス――を可能にする。たとえ後から作品の「真相」を知ったとしても聴取と音の事実性は変わることがないからだ。実際の楽譜があったとして、作曲者が手がけた規則やルールがその音楽を生み出していたことを事後的に知ったとしても、音と聴取の事実性が消えない限り、それを起点にして複数の作曲作品を推測=思弁することの強度は損なわれることがないのである。
2014年、遂に杉本は「思弁的作曲」を明示的に実践することになる。ヴァンデルヴァイザー楽派のスイスの作曲家マンフレッド・ヴェルダーによる作品「4 performers」を演奏したときのことである。カルテットで実演する際に、4人がそれぞれ別の楽曲を同時に演奏しようということになったという。ただし「4 performers」に指示されていない音を出すわけにはいかない。あくまでも同時に演奏されなければならないからだ。メンバーの中には身体動作だけを指定した「楽曲」を同時に演奏した者もいたというが、そこで杉本は「mada」(2014)というあくまでも音を指示する楽曲を制作した。それは「4 performers」とは異なるルールに基づいた作曲作品だった。にもかかわらずまったく同じ音響結果をもたらし得る作品でもあった。「mada」について杉本は次のように説明している。
これが書かれた目的はただひとつで、「4 performers」の演奏中に弾かれた私のギターを、まったく違う譜面を使ってたどることが可能であるということを、じっさいに譜面を作ることで、いってみたかったからだ。(……)遠い未来、「4 performers」のあるページを演奏した録音物と私のこの譜面が同時に発掘されたとしよう。(……)未来の人は、録音された曲を聴いて、それがどのようなルールで演奏されたと思うであろうか?(14)
この楽曲は実際には弾かれることがなかったそうだ。というのも演奏中に杉本は「mada」の譜面を一切見ることがなかったのである。たしかに杉本自身は弾かなかったかもしれない。そして多くの聴き手にとってもそれは弾かれなかったと解釈されるかもしれない。だが音そのものはそれが弾かれたことを否定することがない――だからこそ「未来の人」は「4 performers」の録音物を「mada」として聴くことになるだろう。このことはたとえ「未来の人」があらわれなかったとしても、つまり誰ひとり「mada」として聴くことがなかったとしても、それが「mada」という作品であり得る可能性を示している。このとき音は作曲によって組織づけられ構築されるものではなく、むしろ複数の作曲作品が導き出される源泉として、あるがままの姿であり続けていることになる。それは音楽を人間による創作として捉えるというよりも、すでにある音の論理を観察することから音楽を「発見」していく作業だと言い換えることもできる。だからこうした試みは必ずしも人間によって組織づけられた音響でなければならないわけではない。たとえば周囲の環境から聴こえてくるサウンドであったとしても、規則性やルールを見出していくことによって、その音を体現する複数の――この複数性が重要だ――記譜作品を制作するという、類を見ない音楽の愉しみを夢想することさえできるだろう。
本書の半ばあたり、純正律だけを用いて制作した最初の作品である「quartet」(2013)の項からは、微分音や倍音列を用いた純正律の音楽についての記述が多くなる。2002年に演奏することになったラドゥ・マルファッティによる作曲作品にギターのハーモニクスを用いる指示があり、それをきっかけに杉本はハーモニクスや倍音列に関心を抱いていったという。「私の微分音音楽への取り組みは、まずクォーター・トーンに始まり、しだいにそれを倍音列上の音に近似値としてあてはめるようになり、最後には純正律に向かうこととなった」(15)。なかには高次倍音の求め方や実際の鳴らし方まで詳細に記されている箇所もある。ヴァイオリンのハーモニクスだけを用いて脱基音主義を実践した「solo for violin」(2014‐2015)や、上方倍音に加え実際には鳴ることのない下方倍音を7つの楽器に割り振った「septet」(2015)など、現在の杉本の興味はこうしたところにこそあるのだろう――言うまでもなく同時に、発音と沈黙の時間的な構造化(「for castanets」(2014‐2015))や、声と官能(「Songs」(2016‐))など、杉本の興味範囲はけして微分音音楽だけに収束しているわけではないものの、しかしそのようにして作られた音楽においてもまた、わたしたちはこれまでに見てきたように作曲の思弁へと赴くことができる。それだけにとどまらず本書が開示する杉本拓の音楽思想は、音を介したあらゆる出来事に潜む即興/作曲の可能世界へと聴き手を誘うことになるのである。
(1) 同前書、6頁。
(2) 同前書、6頁。
(3) 同前書、74頁。
(4) 同前書、24頁。
(5) 同前書、24頁。
(6) 同前書、25頁。
(7) 同前書、26頁。
(8) 「演奏の展開はいつも同じで、まず手探りのようにはじまり、まんなかで盛り上がり、静かにおわる。この曲線がかならずついてまわる。これ以上の形式がないとしたらまったく空疎だとしかいいようがない」「いま私がインプロヴィゼーションに反対しているおもな理由のひとつは音楽とそれを創造している人物とがかならず同一視されてしまうことだ。(……)そのために、インプロヴィゼーションでは、音楽じたいが自立することができない」(ギャヴィン・ブライアーズの発言、デレク・ベイリー『インプロヴィゼーション』236~237頁)。杉本による即興批判はブライアーズと問題意識を共有しているように思われる。たとえば杉本は次のように述べている。「私の体験では次のような即興が多かった。まず、それぞれが周りの反応をうかがうようにして音を出しながら、やがて、1つや複数の旋律やリズムが重なるようにしてモチーフのようなものができ上がり、これが発展していくなかでまた変化が現れ、それが別の展開を生み出していくことになるのだが、ある時点でネタがつき、また探り合いが始まる。これが繰り返される」「多くの即興的要素をもった演奏は、他者の発する音が契機となって、それに反応するように音を出していくから、ある音(ひとりひとりの奏者による塊としての音も含まれる)それ自体がひとつの存在(曲の本体というべきか?)として認識されることはない」(『楽譜と解説』25頁)。
(9) 同前書、51頁。
(10) 同前書、49頁。
(11) 「即興音楽の新しい波──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」。
(12) 『楽譜と解説』、63頁。
(13) 同前書、62頁。
(14) 同前書、147頁。
(15) 同前書、96頁。
細田成嗣
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE