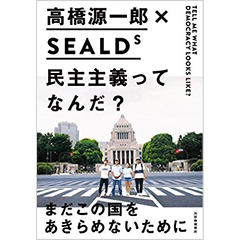MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > 国会前でシルヴィア・ストリプリンが流れたことについて
安保法制をめぐって、国会前デモが盛り上がりを見せている。納得できないことがあれば声をあげるべきだし、デモなんてどんどんやればいい。それ自体は健全なことだ。反対派の議論に対する批判はありうるとしても(僕自身、今回の安保法案に対しては反対の立場である一方で、「戦争法案」というスローガンには批判的な気持ちがある)、デモをすること自体は批判されるべきではない。
 Sylvia Striplin Give Me Your Love Pヴァイン |
 田我流 STRAIGHT OUTTA 138 FEAT. ECD MARY JOY / JET SET |
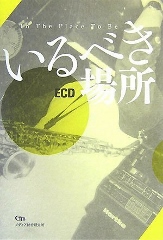 ECD いるべき場所 メディア総合研究所 |
さて今回、SEALDsをはじめとして、若い世代が声をあげたことが注目されている。特徴としては、従来の政治運動と比べてノリがより音楽的になった、ということが挙げられる。ライムスター宇多丸は自身のラジオで、国会前デモのシュプレヒコールを「日本語ラップ以降」だとしていた。僕自身、実際にデモに行ったとき、言葉の乗せかたがオフビート気味で、その点に「日本語ラップ以降」感を覚えたのはたしかだ。具体的に言うと、裏から入る「民主主義ってなんだ!」と「安倍はやめろ!」というシュプレヒコールが、すごく「日本語ラップ以降」的だと思った。あるいは、僕が行ったときのデモでは、シルヴィア・ストリプリン“ギヴ・ミー・ユア・ラヴ”が流されていたが、この曲はヒップホップの定番ネタとして有名なディスコ・クラシックである。さらに言えば、いまではすっかり定着した感のある「言うこと聞かせる番だ、俺たちが」というかけ声は、ECDが、田我流による反原発ソング“Straght Outta 138”に客演したさい披露したパンチラインである。このように、国会前デモでは、ヒップホップのマナーが多く意識されていた。
ところで、この「言うこと聞かせる番だ、俺たちが」というラインだが、ECDはそれ以前、「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」というリリックを書いている。というのも、2003年、渋谷でイラク戦争に反対する大規模なサウンド・デモがおこなわれたさい、ECDは「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」というデモ参加者の声を受けて、即日“言うこと聞くよな奴らじゃないぞ”と題された曲を発表した。朱里エイコの曲に合わせてラップした“言うこと聞くよな奴らじゃないぞ”は、のちに7インチとCD-Rのかたちで自主制作され、円盤などで売られることになる。リリックの出自、トラックもろ使いという形式、流通の形態。どれをとってもオルタナティヴな経済圏を体現する、素晴らしい名曲だ。そしてこの曲が、2000年代後半、高円寺界隈のサウンドデモのアンセムになっていき(この経緯については、ECDの音楽的自伝『いるべき場所』を参照のこと)、震災後の“Straight Outta 138”において、「言うこと聞かせる番だ、俺たちが」と言い換えられていく。現在国会前で叫ばれる「言うこと聞かせる番だ、俺たちが」は、このように10年以上のときを経てのものである。本人の口を離れて、人々に口ずさまれながら生き延びていく言葉。個人的には、ラップの言葉とは、そういうものだと思っている。だから、とくに年長者が、元ネタを知らないだろうままECDのパンチラインを叫んでいるのを見ると、僕なんかは、日本語ラップのファンとして感慨深くなったりする。このように、現在の国会前デモは、確実にここ10年くらいのデモの蓄積がある。現在の国会前デモは、確実に、渋谷のサウンドデモや高円寺のサウンドデモ以降のものとしてある。宇多丸が指摘する「日本語ラップ以降」のシュプレヒコールは、一方で、そのようなサウンドデモの水脈から派生したものである。
とは言え、「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」から「言うこと聞かせる番だ、俺たちが」への推移には、大きな態度変更があるとも感じる。政治学者の栗原康は、2012年の官邸前デモについて、興味深い感想を書いている。栗原によれば、官邸前デモは行儀がよすぎるみたいだ。
たぶん、こういうことなのだろう。官邸前デモは、毎週のようによびかけられている。主催者はひとを大量動員して、なんどもなんども首相や議会に圧力をかけたい。そのためにはデモ参加者はおとなくして、問題をおこさないようにしなくてはならない。つぎがなくなったらこまるからだ。とりわけ、原発という生死のかかった問題では、ぜったいにそうしてもらわなければこまるというのだろう。有効な方法だ。でも、そのために、ひとをモノみたいにあつかってもいいのだろうか。これでは、震災直後に政府がやっていたこととかわらないのではないだろうか。しかも、そうおもったとたん、またスピーカーから声がきこえてきた。「暴力行為はやめてください」。ちくしょう。ふと、ため息をついて空をみあげると、ポンポンとペットボトルが宙をまっているのがみえた。警官や主催者のほうにとんでいく。わたしは率直にこうおもった。ざまあみやがれ。(『現代暴力論』)
たしかに似た印象はある。素人の乱が中心になっていた高円寺のデモは、もっと雑多でわけがわからなかった。その理論的支柱には、いくぶんか単純化されたかたちかもしれないが、「マルチチュード」(ネグリ&ハート)という概念があった印象がある。それに比べると、現在の国会前デモは方向性がたいへん明確である。両者の違いは、引用部の栗原の言葉を借りれば、「動員」への意志の有無ということになろう。高円寺のデモにおいては「動員」はありえなかったが、国会前デモにおいては、それなりの「動員」および政治への働きかけが目指される。つまり、高円寺デモのアンセムであった「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」が、各々が無方向的に勝手にふるまうことを目指すのに対して、国会前デモで叫ばれる「言うこと聞かせる番だ、俺たちが」は、ある方向性に対して自らが「動員」をかけることを目指すのだ。この「動員」性をどう考えるかについては、デモ参加者のなかでも立場が分かれるかもしれない。この変化は、まあ状況的には、当然と言えば当然なのだろう。栗原が言うように、勝手に踊っている場合ではなく、ある程度の意見集約をして政策に反映させなければいけない、「動員」して制度化しなければならない、ということなのだろう。たしかに震災後とは、そういう時代である。ちょうど水越真紀がSEALDsについての文章を書いているが、そこでのキーワードを借りれば、「連帯を恐れず」という気分が、国会前デモにはたしかに存在する。
個人的に興味深いのは、この「動員」の性質が、音楽的にあらわれているのではないか、ということである。ECDはかつて、サウンドデモで使用される音楽について、「4つ打ちは制度的だから、フリージャズが良い」と言っていた。時期的には「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」の頃である。高円寺デモというのは、そういうECD的な意志が反映されてか、音楽ジャンルからしてすでに雑多であった。DJブースからかかっていた音楽は、覚えている限りでは、トライバル系のヒップホップ(フィラスティンやザ・バグ、M.I.Aなどがかかっていた)、RUMIやMSCなどメッセージ性の強い日本語ラップ、ときどきデトロイト系のハウスやテクノあたりだったか。そして、そのうえにサックスや打楽器などの鳴りものが入って、結果的にフリージャズのような響きを獲得していた。ハードコアのバンドも多くいた。総体として眺めると、とてもユニークであった。ここで重要なことは、リズムが単一でないことである。参加者は、思い思いのリズムに乗ったり乗らなかったりしながら、「マルチチュード」感を体現していた。あるときモーニング娘。“LOVEマシーン”が流れて、一気にシラけていたことも強烈に思い出すが、いずれにせよ、ただ盛り上がればいいわけではなかったと思う。雑多であることを維持し、「動員」的にならないことが、たぶんあの場では重要だったのだ。複雑なリズムの音楽たちは、そのなかで要請されていたはずである。したがって、これは想像するしかないが、もし高円寺の路上デモでシルヴィア・ストリプリンが流れていたら、そのリズムのシンプルさに、やはり少しシラけたのではないかと思う。あの場はやはり、ティンバランド以降のサウンドでないとしんどかったのではないか。
 V.A.(東海林太郎、上原敏、近江俊郎、藤山一郎、市丸etc) みんな輪になれ ~軍国音頭の世界~ ぐらもくらぶ |
そもそも、音楽と「動員」というのは、切っても切れない関係である。僕自身もジャケットとライナーノーツを書いたCDに、『みんな輪になれ! ~軍国音頭の世界』(監修:辻田真佐憲、ぐらもくらぶ)というのがあるが、「みんな」で拍子を合わせて、同じ振り付けを踊る音頭という形式は、非常に「動員」性の強い音楽であり、それは軍歌にも利用された。軍国音頭ほど露骨にイデオロギッシュではないが、70年代後半の日本のディスコも「動員」性が強い。その証拠に、音頭歌謡とディスコ歌謡のジャケット裏面には、同じような踊り方指南が付されている。オンビートの退屈な振り付けである。このように、日本のダンス音楽は多くの場合、「みんなで踊る」という「動員」のものとしてあるのだ。この性格は、現在のオタ芸やヴィジュアル系における振り付け、あるいは“恋するフォーチュン・クッキー”にいたるまで続いている。高円寺デモにおいては、おそらく、この音楽の「動員」の性格を極力退けようとしていた。いや、音楽を流して高揚感を得るところまでは同じなのだが、その高揚感が安易な一体感になることには警戒していたように思う。興味深いことに、栗原が参照する大杉栄は、「音頭取りの音頭につれて、みんなが踊って」いることを批判して、「みんなが勝手に踊るけいこをしなくちゃならない」と主張している(大杉栄「新秩序の創造」)。だとすれば、栗原の不満は、デモから「みんなが勝手に踊る」という性格が抜け落ちてしまったことによるのだろう。実感としては、理解できる。
冒頭で書いたとおり、現在の国会前デモは「日本語ラップ以降」とされる。ポピュラー音楽史的に言うと、ヒップホップはディスコのアンチとして出現している。日本でもそれは同じで、決まった振り付けとお約束の選曲にしばられた、ディスコ的なハコDJのアンチとして、気ままに踊らせるクラブDJが登場した。したがって、現在の国会前デモは、高円寺デモほど無方向ではないにせよ、振り付け的「動員」に対してはノーを突きつけていると言える。音楽性の部分で。おそらく国家前デモにおいては、この、振り付け的「動員」と高円寺的無方向との、ちょうどあいだを取るようなバランス感覚が重要だろう。たしかに4つ打ちは制度的だが、ラップはその制度のうえで個性ゆたかなフロウを獲得し続けている。「動員」の性格はあるが、音頭や往年のディスコほど一挙手一投足を統制しようとしていない。シルヴィア・ストリプリンの曲に乗せて、「日本語ラップ」以降的なシュプレヒコールを上げる、というバランス感覚は、その意味でクレバーであり現代的である。政治への働きかけを目指して、それなりに一丸とならなくてはいけない国会前デモにおいては、ひたすら過激で破壊的な音楽が周到に避けられている。多くの人たちを巻き込みつつ、だが安易な「動員」も避けつつ、ぎりぎりシュプレヒコールとして成立するくらいのサウンドと言葉。これこそが、国会前デモでは求められていたものだ。「日本語ラップ以降」とは、そういうバランスである。ちなみに言えば、デモの中心こそシュプレヒコールがあがるが、周縁ではちんどんやパーカッションなど雑多なサウンドが鳴っていたりもする。良くも悪くも、一枚岩ではないことは強調しておきたい。
ディスコからヒップホップへ。振り付けからダンスへ。音頭からラップへ。現在の国会前デモを音楽的な面から見ると、誰もが参加できる制度を敷きつつ個性を尊重する、という思想が横たわっているように感じる。そこでは、制度と個性を共存させようとする態度が大事だ。というか、制度こそが個性を担保する、という立場かもしれない。なるほど、SEALDsの面々が、かつて新左翼から攻撃された丸山真男を選書リストに入れている理由がわかる。僕自身は、「高円寺一揆」と名指された合法デモで目撃した、あの知性と創造性が、いまだに忘れられないところがある。しかし、現在の状況を考えたとき、安保法案をめぐる国会前デモが、いかに頭と身体を使ったものであるか、とも思う。なにより、政治的な歌詞を歌っていれば政治的なのだ、というレヴェルをはるかに超えて、音楽のありかたそのものが、結果的に政治性を体現しているという状況に、いま・ここを生きる音楽ファンとしては、刺激を受ける。音楽が鳴る場所は、イヤフォンやコンサート会場だけではない。いたるところだ。
ここまで書いて思い出したが、高円寺デモでは、じゃがたら“でも・デモ・DEMO”もアンセムになっていた。反復するドラムとベースに鋭角的なギター、無方向に飛び散るサックス。この曲は、サウンド的には、ファンクとパンクとフリージャズのハイブリッドだ。僕はDJで、“でも・デモ・DEMO”からハウスにつなぐことが多い。4つ打ち対応可能で、かつ雑多なサウンドが入り乱れる“でも・デモ・DEMO”はあらためて、社会を問い直すさいのサウンドトラックとしてすぐれていると思える。歌詞でなくサウンド的に。デモは、社会に対する、逆接であり、示威であり、試作なのだ。
Profile
 矢野利裕(やの・としひろ)
矢野利裕(やの・としひろ)1983年生まれ。ライター、DJ、イラスト。共著に、大谷能生・速水健朗・矢野利裕『ジャニ研!』(原書房)、宇佐美毅・千田洋幸編『村上春樹と一九九〇年代』(おうふう)などがある。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE