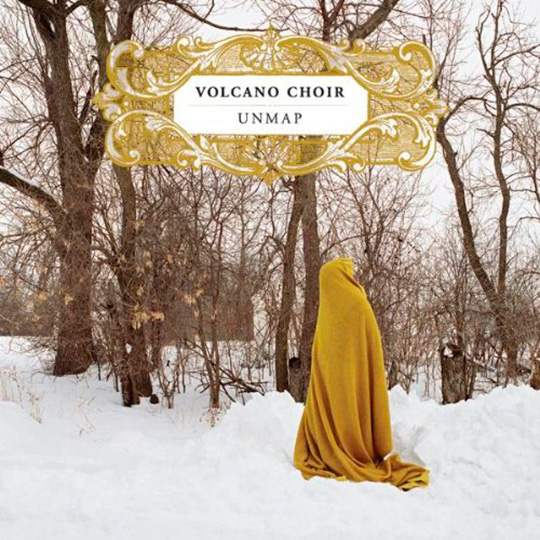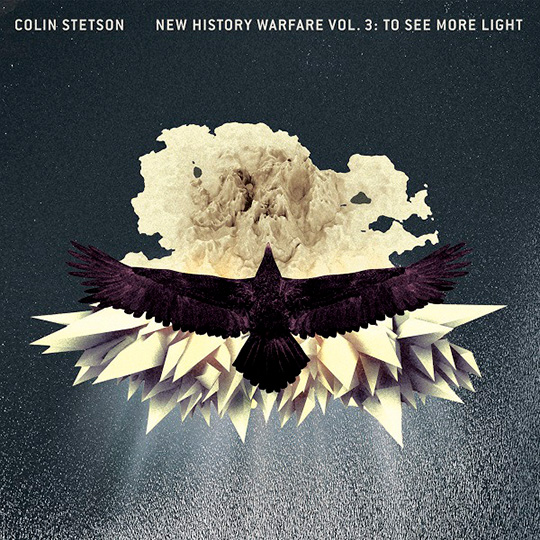MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > Essential Disc Guide to "Good Winter"- ――ジャスティン・ヴァーノン、全キャリア概観
2016年に注目を集めた音楽の特徴のひとつが折衷性だったすれば、ボン・イヴェールの新作、『22、ア・ミリオン』はまさにその象徴だ。いまだ世間的には山小屋の弾き語りフォークのイメージが残っているようだが、そのアルバムでは、何よりも音がそれに反証する。ヒップホップ、ジャズ、エレクトロニカ、ドローン、アンビエント……などが次々と現れ、ぶつかり合い、フォークとゴスペルのもとで融和しようとしている。なぜジャスティン・ヴァーノンはそのようなサウンドに辿りついたのか? それは彼が優れたシンガーソングライターだっただけでなく、プレイヤーでありプロデューサーでもあったことが関係している。
ヴァーノンによるヴォーカルやギターでの他ミュージシャンの作品へのゲスト参加、プロデュース・ワークを振り返れば、その人脈、音楽性がじつに多岐に渡ることが見えてくる。それは閉じていく世界に対する音楽のせめてもの理想主義である……と結論づけるのはいささか大げさかもしれないが、実際、彼のキャリアは超メインストリームからアンダーグラウンドまでをごく自然に行き来し、膨大なジャンルをやすやすと横断する、他に類を見ない非常にユニークなものである。ここでは自身の作品、ゲストやプロデュースで参加した作品のなかから重要作をピックアップし、彼の「良い冬」がどのように生み出されていったかを振り返りたい。
選・文:木津 毅
ボン・イヴェールのはじまりを説明するときに必ず触れられる「ダメになった前身バンド」がこのデヤーモンド・エディソンである。本作は比較的いまも手に入りやすいその代表作だ。歌心溢れる素朴なフォーク・ロックで、すでにアンビエントの音響への興味も随所に覗かせてはいるが、まだ善良で大らかなアメリカン・ロックの枠を超えているとは言い難い。ヴァーノンのキャリアを考えたとき、このデヤーモンド・エディソンとボン・イヴェールとの共通点よりもむしろ違いが重要なのではと思われる。すなわち、黒人のフィメール・シンガーからの影響としてのファルセット・ヴォイス、ブラック・ミュージックへの接近だ。元メンバーは現在、メガファウンやフィールド・レポートとして活動しており、デヤーモンド・エディソンとしてもライヴやコンピレーションで再結成もしている。
オープニング「フルーム」の歌いだしの、よく伸びるファルセット。パーソナルだが、匿名性と抽象性の高い歌詞。アコースティック・ギターの弦の最後の震えも記録するような、アンビエントを意識した録音。繊細だが芯の通った歌……。アルバムの背景にあった冬の孤独の物語があまりにもキャッチーだったのはたしかだが、ヴァーノンはここでたしかにそれを音と歌にする才能を開花させた。この時点ですでに多重コーラスで意識されているのは明らかにゴスペルであり、ボン・イヴェールというコンセプトがヴァーノンのブラック・ミュージック解釈ではないかと考えられる。自主制作のリリースの翌年に流通盤がリリース。森の奥で無名の青年が歌った愛の歌は、やがて〈ジャグジャグウォー〉にとってもっとも売れたアルバムとなった。
『フォー・エマ~』のアウトテイク的なポジションの4曲入りEP。アルバムよりはややリラックスした内容になっているが、特筆すべきは表題曲と“ウッズ”だろう。“ブラッド・バンク”は珍しくかなり明確なストーリーラインがあるラヴ・ソングで、これがアルバムから外されたというのは逆に言えば、それはボン・イヴェールの本流とは少し異なるということだ。そして、オートチューンで加工した声をループで繰り返し重ねた異色のア・カペラ・ゴスペル・ナンバー“ウッズ”。それはジェイムス・ブレイクよりも早く、しかも爆発的にエモーショナルだった。そしてこの1曲こそが、のちのヴァーノンのキャリアを大きく動かしていくことになる。
ポストロック・バンドのペレを前身とするインストゥルメンタル・バンド、コレクションズ・オブ・コロニーズ・オブ・ビーズとヴァーノンが合流。すでにドローン・プロジェクトを始動していたジョン・ミューラーがいたこともあり、ゴスペルとフォークとポストロックとドローンが混淆する不思議な感触の演奏と音響が聴ける。はじめはレコーディング・プロジェクトの予定だったが、のちに日本でライヴが実現。そのエモーショナルなバンド・アンサンブルの経験から、ボン・イヴェールののちの方向性が決まっていく。また、音響的な感覚としてはヴァーノンが2000年前後のポストロックやエレクトロニカの強い影響下にあることもよくわかる。
世界中からクールな才能を見つけて貪欲に取り込んでしまうカニエ・ウェストが、それでもボン・イヴェールに目をつけるとは誰も想像できなかったのではないか。はじめは例の“ウッズ”のサンプリング程度を想定していたかもしれないが、折衷的なゴスペルという要素でわかり合ったのか、ゲスト・ヴォーカルだけでなく音楽的な部分でもヴァーノンはここで関わっている。のちにヴァーノンがエレクトロニック・ミュージックに接近していくのは本作や次作『イーザス』の影響だとよく言われるが、自分はどちらかと言えば「俺が必要なのはプッシーと宗教だけだ」とライヴで歌わされた経験のほうがカニエとのコラボでは大きかったのではないかと邪推している。
まあ正直、カニエといるときよりもこっちのほうが生き生きしているというか……とにかくリラックスしている。ライアン・オルセンをリーダーとし、メガファウン、ソリッド・ゴールド、ドゥームトゥリーのメンバー、そしてハー・マー・スーパースターらが集まったスーパーグループ……なのだが、地元の仲間連中がふざけて激甘ソフトロックをやってみたら、というようなユニークなアルバムだ。BPMを10ccの“アイム・ノット・イン・ラヴ”と同じ69に全編固定するなど芸が細かく、その上でひたすら甘ったるくラウンジーな時間が過ぎていく。なかでもゴドレイ&クリームのカヴァー“クライ”がキラー。ヴァーノンのファルセット・ヴォイスもギターもボン・イヴェールのときとは聞こえ方がまるで違い、このプロジェクトはぜひまたやってほしいところ。
この当時、インディ・ロック・シーンの顔役であったザ・ナショナルのアルバムに、スフィアン・スティーンヴンスとともにヴァーノンが参加した意義は大きい。やはりザ・ナショナルが監修した2000年代のインディ・ロックの隆盛を記録したコンピレーション『ダーク・ワズ・ザ・ナイト』(2009)と並んで、ここでボン・イヴェールが現在のインディ・ロック・シーンの柱のひとつであることがはっきりと示されたのだ。ザ・ナショナルがアメリカで絶大な人気を誇るのはその文学性の高さによるが、ヴァーノンはそうしたアメリカの知的なインディ・ロック・バンドの系譜をたしかにここで引き継ぎつつ、ヒップホップ・シーンやエレクトロニック・ミュージックともアクセスできるというかなり独自のポジションをすでに獲得していた。
ある意味で、ボン・イヴェールというプロジェクトが覚醒した瞬間である。フォークとゴスペルという基本は押さえつつもフル・バンドによるアレンジメントは複雑さとスケールを増し、より描く感情の幅を広げている。それはジャスティン・ヴァーノンひとりの感傷や孤独が分かち合われることで、音楽的なコミュニティが築かれているということだ。そこで歌は切なさを伴いながらも、勇壮なドラムによく表れているようにタフで力強いものとして鳴らされているのである。だから本作はセルフ・タイトルなのだろう……これこそが「ボン・イヴェールだ」と。ヴァーノンはここで音楽的な欲求に誠実に向き合っただけだが、本作でグラミー賞という名声を得ることによってかえって孤独を深めていくのは皮肉な話だ。結果、ここからボン・イヴェールの次作まで5年のブランクが開く。
“フォール・クリーク・ボーイズ・クワイア”で参加、これは納得のコラボレーション。というか、シンガーソングライター/プロデューサーとしてヴァーノンともっとも感覚が近いのがジェイムス・ブレイクではないかと僕は考えている。アウトプットが個に向かうか公に向かうかでその姿勢は異なるものの、自らのゴスペルが「本物」にならないことをよく分かっていて、声を加工したり他のジャンルと組み合わせることによってオリジナルなものにしようとしている、と言えばいいだろうか。じじつ、ヴァーノンの情熱的な歌声がどこかゴーストリーなコーラスのなかで繰り返されるこの曲は、両者の特色がちょうど中間地点で見事に融合していると言える。
1930年代のアラバマの盲学校で結成されたゴスペル・グループの新作を、インディ・ロックの現在を代表するミュージシャンがプロデュースしたら……。ヴァーノンにとって、キャリアのなかでも悲願叶った1枚なのではないだろうか。たしかな歴史がある、いわば「本物」のゴスペルをエレクトロニカやアンビエントの感性を通過した自分のフィールドに取り込みつつ、モダナイズすること。それは彼にとって大いなる挑戦であり、喜びであったにちがいない。チューン・ヤーズやマイ・ブライテスト・ダイアモンドなどインディ・ロック界隈のゲストも参加、ヴァーノンのプロデュースによってここでも理想主義的な音楽コミュニティが作られている。
ボン・イヴェールにも参加しているサックス奏者、コリン・ステットソンのソロ作。ドゥーム・ジャズともミニマル・ドローンとも言われるコリン・ステットソンのサックスの咆哮は肉感的でおどろおどろしく、あっけらかんと狂気じみている。ヴァーノンは3曲で参加しているが、その声が聞こえてくるだけでこのアヴァンギャルド・ジャズがホーリーな感触になるのはおもしろい。ヴァーノンにとってはボン・イヴェールのもっともアンダーグラウンドな回路と言え、新作には明らかにその人脈の活躍の跡が見える。隠れたキーパーソンである。ところで、ホーリーな感触と書いたが、カオティックな“ブルート”ではヴァーノンの珍しいデス声(?)が聴ける。
ニューヨーク拠点のシンガー/プロデューサーによるR&B/シンセ・ポップ/ヒップホップ・プロジェクト、ヴァーノンはプロデュースやゲスト・ヴォーカルで数曲参加している。フランシス自身が開発したというヴォーカル・エフェクトであるプリズマイザーを駆使した、ユーモラスでチャーミングなR&Bといった感じだ。カニエ……はともかくカシミア・キャットなども参加しているこのアルバムはいまのヒップホップ、ビート・ミュージックのある部分をプレゼントする1枚だと言えるだろう。フランシスはチャンス・ザ・ラッパーのアルバムにも参加しているが、結果、ヴァーノンがその辺りまで繋がっているのは2016年のポップ・ミュージック・シーンのひとつのトピックだった。
Profile
 木津 毅/Tsuyoshi Kizu
木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE