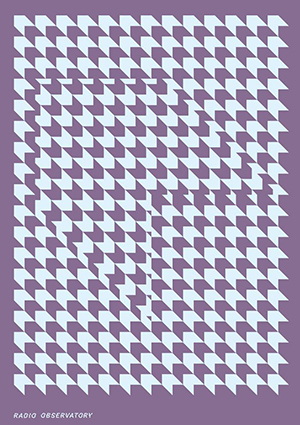ぼくが初めて買ったスウィンドルのレコードは、〈ディープ・メディ〉から出た2012年の“ドゥ・ザ・ジャズ”なので、彼の音楽を最初からリアルタイムで聴いてきたわけではない。彼がロンドンの〈バターズ〉からシングルをリリースしていたことも、2009年にすでに自分のレーベルからアルバム『カリキュラム・ヴィータイ(履歴書)』を出していたことも、あの赤いスリーヴが店頭に並んだときは知らなかった。でもあのベースラインとハンドクラップを聴いて、一瞬でぼくは彼の虜になってしまった。当時のダブステップ界隈ではテクノへの接近がひとつの流れになっていて、DJのピンチが言うように、それはある意味「コールド」な感覚を有するものだ。そこにスウィンドルがあのジャジーでファンキーな熱い曲を持ってきたのだから目立たないわけにはいかなかった。
2013年、スウィンドルが〈ディープ・メディ〉からアルバム『ロング・リヴ・ザ・ジャズ』をリリースし、それにともなうライヴをUKで行うと発表したとき、ぼくは迷うことなくロンドン行きのチケットを買った。そのときにピンチのコールドなセットも、アコードのひとりシンクロの透き通ったベース・ミュージック・セットも、ジェイムズ・ブレイクのクラシック・ネタ満載のDJも見たけれど、それらと比べ物にならないほどスウィンドルのライヴはポジティヴに感じられた。このインタヴューで彼が言うように、自身のルーツにも目を向けたその音楽は、流動的なシーンのなかでも強いのである。
 Swindle Peace, Love&Music Butterz / Pヴァイン |
初来日の2013年にはじまり、これまでにスウィンドルは4回も来日しており、世界中をツアーでまわってきた。2015年に先述の〈バターズ〉から発表した『ピース, ラヴ&ミュージック』は、ツアー先で出会ったミュージシャンとの共作を多く収録し、JMEとフロウダンというグライムの重鎮MCも参加した快作だ。
2016年、スウィンドルは〈バターズ〉のレーベル・メイト、フレイヴァDと来日ツアーを行った。東京公演にはレーベル・オーナーであるイライジャとスキリアムも急遽参加し、その夜が大いに盛り上がったことは言うまでもない。この取材はそのバックステージで行われた。投げかける質問に対して、そのことばの意味を噛みしめるようにして、スウィンドルはじっくりと答える。彼の音楽が情熱的なように、彼自身もまた素晴らしい男だ。そのことが少しでも伝わればと思う。
スウィンドル / Swindle
スウィンドルはロンドン出身のマルチ奏者、プロデュサー、DJとして活動している。2006年より自主制作で自分の音楽をリリース、多くのプロジェクトに関わってきた。2013年にはベース・ミュージックの人気アーティストマーラの〈ディープ・メディ〉レーベルより『ロング・リヴ・ザ・ジャズ』をリリースし、DJ、ライヴ・アクトとして世界規模のツアーを行ってきた。
ジャイルス・ピーターソンのワールドワイド・アワードにて披露したパフォーマンスと、ボイラールームでのジャズの伝説的キーボーディスト、ロニー・リストン・スミスとのギグが大きな話題を呼び、現代における最も将来有望なエレクトロニック音楽の若手として今後の活動が期待されている。
俺は何かオファーをされたら、その依頼の内容には完全には従わないタチだ(笑)。音楽以外でもそう。もし「黄色い外観、赤い屋根、窓はふたつ、芝生つきの家を作れ」って言われても、絶対にその通りには作らないと思う。俺は自分の住みたい家しか作らないだろうな(笑)。
■『ele-king』に本人が登場するのは初めてなので、最初の質問は「スウィンドルって誰?」にしましょう。
スウィンドル(Swindle、以下S):オーケー! スウィンドルは平和と愛と音楽の使者。ファンク、ジャズ、ベース・ミュージックに根付いた新しいサウンドの開拓に、その人生の大半を捧げている。1987年生まれ、ロンドンのクロイドン出身。料理が好き。スポーツはやらないしテレビも見ない。
■では音楽をはじめたのはいつですか?
S:小さいときから何かしら音で遊んでいて、12歳ぐらいのときにキーボードをはじめたね。プレイステーションと同じように楽器もオモチャみたいなものだった。それで14歳のときにトラック・メイクにハマって、DJをするようになったのもちょうどその頃だ。絵に描いたような音楽好きな家族からの影響がデカいね。
■たしかお父さんはギターを弾いていますよね?
S:そうそう! 実は親父は『ピース, ラヴ&ミュージック』のジャケットに写っているんだよ。俺とマーラといっしょにいるのがおやじ。2013年にロンドンのファブリックでライヴをやったんだけど、そのときにいっしょに撮った(笑)。
■そうなんですか! ぼく、あの日ファブリックへあなたのライヴを見に行ったんですよ。DJ EZからロスカ、ジョーカー、ピンチまで出ていて豪華な夜でしたよね。あなたはグライムやダブステップのプロデューサーとして知られていますが、最初はどんなジャンルが好きだったんですか?
S:ドラムンベースだね。あとGファンク。そのふたつといっしょに育ったようなもんだよ。
■ダンスミュージックからR&Bのようなトラックまで手掛けるあなたのスタイルからプリンスを連想したりもしました。あなたはいろんな楽器ができますから、プロデューサーとしてだけではなく、マルチ・プレイヤーという点でも共通しています。
S:なるほどね。でもオレはプリンスのレコードをそこまで持ってないんだ。もちろん聴いてはいるけれど、それはオレの音楽を聴いたひとが「お前はもっとプリンスを聴いたほうがいいよ」ってオススメしてくれたから。でも彼がアーティストのプリンスとして完成するまで、多くのファンク・ミュージシャンと共演してるだろ? ブーツィ・コリンズやジョージ・クリントンとかとね。俺も彼らから多大な影響を受けているから、その意味ではプリンスと音楽的に共通点があってもおかしくないよ。
■ではあなたが理想とするミュージシャンは誰ですか?
S:クインシー・ジョーンズだね。間違いない。彼は究極のプロデューサーだと思っているよ。
■UKアンダーグラウンドでは?
S:ロニ・サイズやデリンジャー。数え切れないくらいいる。
■ドラムンベースのプロデューサーですね。あなたはダブステップ・プロデューサーのシルキーとも共作を残しています。あなたのスタイルは彼にも通じるところがありますよね。ダブステップのシーンで、シルキーはフュージョンやファンクをいち早く参照していました。
S:たしかに。シルキーに初めて会ったきっかけも、知り合いに彼をチェックした方がいいってアドバイスされたからなんだけどね。それで実際に会っていっしょにやることになった。ブリストルのジョーカーともそんな感じだったな。俺たちにはサウンド面で共通点があるけど、お互いの音からインスパイアされているわけではない。似たような音楽経歴を持っていたから共感できたんだと思う。俺が17歳くらいのときあいつとはネットで知り合った。それから曲を交換して意見を出し合っていたけど、実際に会ったのはその数年後だったね。
■インターネット世代らしいですね。ちなみに〈バターズ〉のイライジャとはどうやって知り合ったんですか?
S:それもネットだね。あれは2009年だったかな。テラー・デインジャが俺たちを繋げてくれたんだ。MSNってサイトでみんな連絡を取っていた。当時はフェイスブックとかはなかったんだけど、そういったソーシャル・メディアとMSNの違いは相手の顔がわからなくて、曲だけが公開されているってこと。だから余計な情報なしに、音だけで相手を判断できたってわけだね。「うお!こいつの曲ヤベえじゃん!」と思ったらすぐに連絡、みたいな感じだった。
■アルバムのライナーにはあなたがイライジャの「グライムを作ってみれば?」というオファーを断ったエピソードが載っています。詳しく教えていただけますか?
S:そのときにはもう普通なことはやりたくなかったんだ。それは自分のスタイルじゃないってわかっていたからね。一生グライムのトラックを作ることはできるよ。でも俺は何かオファーをされたら、その依頼の内容には完全には従わないタチだ(笑)。音楽以外でもそう。もし「黄色い外観、赤い屋根、窓はふたつ、芝生つきの家を作れ」って言われても、絶対にその通りには作らないと思う。俺は自分の住みたい家しか作らないだろうな(笑)。
■なるほど。でもあなたの曲はジャズやファンクの要素が強いけれども、グライムのフォーマットを完全に捨て去ったこともありませんよね。グライムの何があなたを魅了するのでしょうか?
S:グライムは常に「新しいアイディア」でできているってとこだ。グライムの主役は若者で、17とか18、ひょっとしたらそれよりも若いやつらが音楽を作っている。その世代の多くには養う家族も恋人も子供もやるべき仕事もないだろ? だから全ての想像力が音楽に向かう。その結果、ルールに縛られない興味深い音楽が生まれてくるわけだ。ロックやファンクが好きなのも同じ理由だよ。ジェームズ・ブラウンがオーディエンスを驚かせたとき、彼には従来のルールなんか通用しなかった。シカゴのフットワークだってそう。ルールがない場所からヤバい音楽はやってくる。
[[SplitPage]]
人生でベストDJができたと語る2015年3月21日DBSの様子
世界をツアーして、旅先の音楽を自分の音楽に取り入れるってことの重要性もマーラから学んだ。いまって世界中をツアーで回るDJはたくさんいるけど、彼らがその経験を自分たちの曲に反映させることって、あんまりなくない? それってすごくつまんないことだ。未知なる場所での新しい出会いから得られるものってすごく大きいし、その影響は絶対に音楽にもいい形で現れるって俺は思うんだけどね。
■ちなみにMCをやったことはないんですか?
S:実は昔、ドラムンベースのMCをやっていたよ(笑)。マジメにやっていたわけじゃなかったけどね。MCでは自分を表現できないってわかったから、そっちの方向には進まなかったな。
■あなたがファンクやドラムンベースに熱中しているとき、周りのひとたちもそういった音楽を聴いていたんですか?
S:親父がジャズ、友だちはガラージやドラムンベースって感じだったね。だから俺のなかで音楽のバランスが取れているんだと思う。グライムやファンキー・ハウスを聴くようになっても、いろんなジャンルを並行して聴いていたよ。
■当時のあなたはオーバーグラウンドのチャート・ミュージックをどのように捉えていましたか?
S:あんまりチェックはしてなかったね。自分がフォローすべき音楽があまりないように思えたんだ。チャートのなかには金儲けにために作られているようにしか思えない曲もあったしね。そういった類のモノに昔から興味が持てなくてね。いまでもメジャーのラジオ番組は全然聴かない。
■ラジオということばが出ましたが、『ピース, ラヴ&ミュージック』ではラジオのような編集がされている箇所もあります。10代の頃、あなたは海賊ラジオを聴いて育ったとも聞いています。
S:その通り。毎日聴いてたよ。俺にとってラジオとは海賊ラジオだっていうくらいにね。10代? もっと若かったよ(笑)。初めて海賊ラジオを聴いたのって、たぶん6歳のときだ。うちに古いコンピューターがあって、それを使ってカセットにラジオを録音してたのを覚えているな。海賊ラジオの電波を探すのって本当に巡り合わせが重要だったんだよ。特定の日、サウス・ロンドンの特定の場所、特定の時間。この条件が揃わないと電波を受信することすらできなかったし、かっこいい曲がかかった途端に電波が途切れて、同じ曲には二度と出会えないってことなんてしょっちゅうだったよ。ネットのポッドキャストやCDじゃ絶対に味わえない体験だった。
■エリック・ドルフィーみたいですね。「音楽を聴き、終わった後、それは空中に消えてしまい、二度と捕まえることはできない」。
S:それそれ(笑)! ホント、音を捕まえるためにカセットがあってよかった(笑)。そういった具合に、本当のラジオが何なのかを知る前に海賊ラジオに出会ったわけ。
■6歳だったわけですもんね(笑)。このアルバムでは、グラスゴーのマンゴズ・ハイファイとの“グローバル・ダンス”の前に、ラジオ中継のようにマンゴズの会話が入ってきます。
S:それは彼らがやっている本物のラジオ番組からの抜粋なんだよね。曲を作った日にそのラジオの放送があったんだけど、そこに俺も出演したんだよ。音楽に対して正直になることはオレのテーマなんだけど、ラジオは人生の重要な一部でそのテーマともつながってもいる。
■そうでしたか。あなたはその曲でコラボしているグライムMCのフロウダンとグラスゴーでプレイしています。スコットランドってグライムがそんなに人気がないようにも見えるんですが、あなたはどう思いますか? またスコットランドとイングランドとオーディエンスの反応に違いはありますか?
S:いまはそんなことないんだよ。スコットランドに限らず、UKのメインストリームでもグライムはすごく大きな存在感を持っている。反応の違い? 酒だよ(笑)。「こいつらどれだけ飲むんだ!?」っていうくらいスコティッシュはウィスキーが好きだよね。ケルトの血はクレイジーだ(笑)。ロンドンは雰囲気的にちょっと閉じているところもあるけど、スコットランドはオープンだからやりやすかった。
■2013年にあなたはソロと『マーラ・イン・キューバ』のキーボーディストとして2回来日していますよね。マーラからバンドへの参加のオファーがあったそうですね。
S:マーラとはいっしょに作業をする機会があったんだけど、ちょうどそのときに彼は『マーラ・イン・キューバ』をライヴでやることを計画していてね。「キーボード弾けるんだからセッションに参加しないか?」って誘われて、すぐに了解の返事をしたよ。
あの作品、それから一連のセッションからはものすごくインスパイアされた。音楽を表現するのに必ずしもDJである必要はないんだって気づけたから、自分のバンドを持とうと思ったし、それを実行する上でマーラ・バンドへの参加は大きな自信にもなった。
世界をツアーして、旅先の音楽を自分の音楽に取り入れるってことの重要性もマーラから学んだ。いまって世界中をツアーで回るDJはたくさんいるけど、彼らがその経験を自分たちの曲に反映させることって、あんまりなくない? それってすごくつまんないことだ。未知なる場所での新しい出会いから得られるものってすごく大きいし、その影響は絶対に音楽にもいい形で現れるって俺は思うんだけどね。
■おっしゃるように、あなた自身も自分のバンドを率いて演奏を行いますが、それは文字通りライヴです。いまって、クラブにラップトップを持ち込んでエイブルトンのコントローラーをいじっているだけでもライヴって呼ばれる時代ですよね。そういう状況についてどう思いますか?
S:すごい音楽をやるプレイヤーもいるから、そのスタイルを決して否定はしないよ。でもなかにはステージに立ってタバコ吸ってプレイ・ボタンを押して金を貰っているヤツもいる。ふざけんなって話だよな。そんなのオーディエンスにとっては、家でユーチューブを見ているのと変わらない。ちなみに俺もよく「ツアーでエイブルトンを使ってライヴをやれば?」って言われるんだけど、これからもそれは絶対にやらないと思う。やっぱり俺が考えるライヴはバンドがいてこそ成り立つものなんだよね。それにDJするのも大好きだから、ひとりでツアーをするときはDJで十分だよ。もし現場にキーボードがあったら曲に合わせて弾きたいけどね。
■マーラのレーベル、〈ディープ・メディ・ミュージック〉から出した“ドゥ・ザ・ジャズ”であなたを知ったリスナーは多いと思います。あの曲はどうやって生まれたのか教えてくれますか?
S:オーケー。本当のことを話そう。あの曲が生まれたのは、母親の家の地下室で夜も遅かったな。それで俺はめちゃくちゃクサを吸っててさ……(笑)。で、気づいたら朝になっていて曲が完成してたんだよ。作っている間のことはまったく覚えてない。あのベースラインが先にできたのか、ハンドクラップが先だったのかも記憶にないね(笑)。
Swindle - Do The Jazz (DEEP MEDi Musik) 2012
[[SplitPage]]
どれだけ「愛と平和」を叫んでも、「愛と平和」がこの世界に満ち足りたことってないだろ? だったらそれを打ち出す必要があると俺は思う。それがダサいって言われようとも、自分のことを「平和と愛と音楽の使者」って呼ぶことに何の躊躇もしないよ。それに、なんで「愛と平和」はダメで、「ギャングスタ」や「悪」のイメージはいいんだ? 売れるから? そんなのおかしいと思うね。だったら俺は言いたいことを言うよ。
 Swindle Peace, Love&Music Butterz / Pヴァイン |
■では『ピース, ラヴ&ミュージック』についてお訊きします。作品が発表された2015年はグライムのアニヴァーサリー・イヤーとも言える年で、ボーイ・ベター・ノウの結成、それからロール・ディープのファースト『イン・アット・ザ・ディープ・エンド』のリリースからちょうど10年という節目でした。そしてあなたは今回のアルバムでボーイ・ベター・ノウのJME、ロール・ディープの主要メンバーだったフロウダンと共演しているわけです。ノヴェリストやストームジーといった若手も注目されていますが、なぜこのふたりを選んだのでしょうか?
S:そうか、気づかなかったけどたしかに10年だね。当時からふたりの大ファンだったよ。俺は曲を作るときに、「この曲には絶対にあのアーティストが必要だ!」って制限を設けるようなことはしないし、いまの流行りとか、売れ線とかが共作者を選ぶ基準にはなることもない。だって音楽じゃん? 自分の意図が伝わる相手といっしょにやらなきゃ、結局は自分に嘘をつくことになる。今回も音楽を優先した結果、相手がフロウダンとJMEになっただけだよ。「音楽がビジネスを決めるのであって、ビジネスが音楽を決めるのではない」。これに尽きるね。
■あなたから見たふたりの違いとはなんでしょうか? 音楽的、人間的、どんな側面でもかまいません。
S:うーん、違いは多いね(笑)。だから共通点について言わせてもらうよ。ふたりともどんな状況でも自分自身になることができるよね。そこがふたりの魅力だよ。だからこそスタイルの違いが出てくるんだと思う。
ちなみにさっき若手MCの名前が出たけど、俺は彼らのスキルがベテランたちに劣っているとはこれっぽっちも思わない。というかそれは個性の問題であって、優劣の問題ではないよね。いつの時代も比較の上での良し悪しをつけるのは簡単だし、その基準は個人によっても変わる。だから音楽を楽しむ上では個性の違いを尊重するべきだと思うんだよ。
■ネット上の動画などであなたのスタジオを見ることができますが、今作はあそこで作られたんですか?
S:このアルバムは世界のいたるところで作ったよ。ちなみにこのアルバムを作っている間、俺は3回引っ越しててさ(笑)。ちょうどそのときロンドンでいい物件が見つからなくてね。いまロンドンでは昔から住んでいるひとたちが、街を出ていかざるを得ない深刻な状況になっているんだよ。ロンドンの外からやってくる人口の増加や家賃の高騰が影響している。だから俺もロンドンを離れるしか術がなかったんだ。いまでもロンドンが大好きだし、自分のことをロンドナーだと思っているけど、音楽のためにはロンドンを出るしか選択肢はなかった。やっぱり都会だと隣人との間隔が狭くて満足に音を出せないからね。いまはロンドンから1時間くらいはなれた田舎に住んでいる。住民の誰も俺のことをしらないような街だよ。だからゆっくりできるし、音楽にも没頭できている。ツアーで刺激的な場所に行くことができるから、いまの街に何もないことは大して問題にならないね。
■世界のいたるところで曲を作ったとおっしゃいましたが、例えば一曲目のアッシュ・ライザーとのコラボ曲“ロンドン・トゥ・LA”はロサンゼルスで作ったということですか?
S:その通り! いつもスタジオを持ち歩いていたからね。俺はロスのロウ・エンド・セオリーでプレイしたんだけど、この曲はそのショーの前にだいたい完成していたよ。
■スタジオを持ち歩いていた……?
S:つまり、バッグにサウンド・カード、スモール・マイクとか必要なものを詰め込んでツアーに出かけた(笑)。ロサンゼルスはエコパークが最高だったね。それで現地でレコーディングしたものをイングランドに持ち帰って編集をした。あとから外国の知り合いに音を送ってもらったりもしたね。アルバムの日本語の部分はパーツースタイルのニシピーにお願いしたよ。
■あなたはよくシンガーと共演していますが、どのように歌が生まれるのでしょうか?
S:理想としては音楽と歌詞が同時にできることが望ましいよね。“ロンドン・トゥ・LA”では俺がどういう歌詞にしたいかシンガーに要望を伝えた。曲を作ったとき、俺は文字通りロスにいるロンドン・ボーイで、気分は2パックの“トゥ・リヴ・アンド・ダイ・イン・LA”や“カルフォルニア・ラヴ”みたいだった。そのときの俺の気持ちを知ってほしくて、あの歌詞ができたってわけ。
Swindle - London To LA Ft. Ash Riser
■世界各地に思い入れがあると思いますが、日本はあなたにとってどんな場所ですか?
S:たくさんの場所に行ったけど、日本は世界で一番音楽をプレイするのが楽しい場所だよ。けっしてお世辞じゃない。オーディエンスの反応、人間性、どれも最高だ。前回ロスカと出たDBSは、俺の人生で一番楽しいDJだった。いつか日本で自分のバンドのライヴをやりたい!
■今回のアルバム収録曲の多くにはあなたのツアー先での様子が動画で収められていますが、それを試みた理由とはなんでしょうか?
S:そのアイディアを思いついたのは『ロング・リヴ・ザ・ジャズ』のあとだね。俺は日本に来るのがこれで4回目なんだけど、音楽をやっていなかったらフィリピンにも南アフリカにもロサンゼルスにもグラスゴーにも行けなかったと思う。あんまり恵まれていない境遇だったからね。そんな俺に音楽が世界に出る機会をくれたんだ。だから自分は音楽に感謝する必要があると思ったし、それを自分の作品に還元する必要性を感じた。自分のツアー先での様子をドキュメンタリー的に動画に残すことはその方法のひとつだね。
それと別にあることを伝えたかった。俺は世界中を回って、人種、文化、言語といったあらゆる差異を目の当たりにしてきたけど、ひとつだけ共通点を発見したんだ。クラブで俺がプレイ・ボタンを押したあとのフロアの反応は、世界のどこに行ったって変わらなかった。そのことをどうしても記録してみんなに見せたかったね。それから、素晴らしいパーティには、必ず素晴らしいひとびとが関わっていることも伝えたかった。
■個人的には“マシンボ”のPVで、フィリピンのコミュニティへあなたが出向いて、現地のミュージシャンたちとセッションする様子にびっくりしました。
S:あれはすごい体験だったなぁ。フィリピン土着の竹でできた楽器を“マラシンボ”ではメインで使っている。共作者のヒラリアス・ドーガのスタジオで録音したんだけど、その小屋も竹でできてんだよ(笑)! 自分が住んでいる地域の山に生えてる竹を自分で採ってきて作ったらしくて、その山の名前がマラシンボって言うんだよね。もちろんフルートからパーカッションにいたる彼の楽器は自作で竹でできている。いままでそんな人間に会ったことがなかったから衝撃だったよ。彼はすごくスピリチュアルなひとで、霊のために音楽を作っているらしい。
こんな出来事があった。俺はヒラリアスとレコーディングをするために彼の
場所へ行ったんだけど、そこは電話も通じないようなところでさ。フェスに俺は出る予定だったから、他の出演者を含めて5人でヒラリアスに会いでかけた。その場所に着くとヒラリアスがいて、彼の楽器も置いてあるわけ。で、連れのひとりがその楽器のなかからフルートを手に取って吹こうとしたとき、ヒラリアスが「やめとけ! そのフルートには霊が入っているから危険だぞ!」って言うんだ。でも彼はそのフルートを吹いちゃってさ。それでしばらくして振り返って彼を見たら意識を失っていた……。「だからやめとけって言ったんだよ。霊が彼に憑依したんだな」ってヒラリアスは言うんだ。40分くらいで彼は目覚めたんだけど、彼は自分が寝ていることさえ覚えていなかった。言っとくけど本当の話の話だからね。だから“マラシンボ”を聴くとその出来事を思い出すよ。
Swindle - Malasimbo Ft. Hilarius Dauag (Philippines)
■アルバムのタイトルに「平和と愛と音楽」を掲げた理由を教えてください。
S:その3つが世界的にどんな人間にも共通している事柄だからだね。それに、たとえ音楽をやらないひとでも平和と愛を必要とする。それに音楽を聴いたときって、好き嫌いを問わずに何かしらの感情を抱くだろ? そういった意味でも音楽は全人類に共通していると思ったから選んだんだ。
■なるほど。でもポピュラー音楽の歴史を振り返ってみると、「愛と平和」は散々歌われてきたテーマで、現在はシニカルな態度をとって、それを口にするミュージシャンを馬鹿にするひとも少なくありません。そういう状況で「愛と平和」を打ち出すことに躊躇しませんでしたか?
S:まったくしなかったよ。だってどれだけ「愛と平和」を叫んでも、「愛と平和」がこの世界に満ち足りたことってないだろ? だったらそれを打ち出す必要があると俺は思う。それがダサいって言われようとも、自分のことを「平和と愛と音楽の使者」って呼ぶことに何の躊躇もしないよ。それに、なんで「愛と平和」はダメで、「ギャングスタ」や「悪」のイメージはいいんだ? 売れるから? そんなのおかしいと思うね。だったら俺は言いたいことを言うよ。
■そういう覚悟がある上でやっているからこそ、あなたの音楽は多くの人に届いているのかもしれません。あなたのライヴをロンドンで見たとき、最初は「白人がやっぱり多いんだな」と思っていたんですけど、いざライヴがはじまって周りを見回したら、ブラック、アジア系もたくさんいてびっくりしました。あなたの音楽はフロアの人種をミックスしていたんです。
S:それは俺が音楽をやる上で超重要なテーマだ。俺が作っているのは特定のジャンルの音楽っていうよりもミクスチャー・ミュージックだと思う。俺の母親はホワイト、父親がジャマイカ人で、ジャマイカ、イングランド、イタリアの血が俺には流れている。でも見た目がブラックだから俺と兄弟は幼い頃につらい差別を受けたこともあった。だから人種や文化をミックスすることは、俺の人生においてとても重要なことだと意識するようになったね。個人的には音楽においてその壁を越えることは、差別するよりも簡単だと思うんだ。俺はブラックやアジアン、どんな音楽も好きだけど、ただ好きになりさえすれば壁は越えられる。音楽にもう「色」は関係ないね。
俺がベース・ミュージックをやる理由のひとつには、そのルーツがレゲエにあることも関係しているよ。レゲエはジャマイカ人の苦しみから生まれたけど、いまはジャマイカにルーツがあるかどうかなんて関係なく世界中でポピュラーになっているだろ? それはまさに俺が音楽でやりたいことだ。どんどん人種や文化の壁を壊していきたいね。
■これからの活躍に期待していますね。では最後に日本のリスナーにメッセージをお願いします。
S:これで4回目の来日だけど、毎回日本に来るたびに素晴らしいオーディエンスの期待に応えようと思えるよ。ツアー中、2年前に撮った俺との写真を見せてくれるひとや、今夜来るのが初めてだってひとにも会えて最高だった。また絶対に戻ってくるよ! 素晴らしいイベントを企画してくれたDBS、グッドウェザー、それから日本で俺の作品の流通に関わっている方々にも感謝したい。みんな本当にありがとう!
取材協力:DBS
Swindle All Time Best
Quincy Jones – Body Heat – A &M Records – 1974
Herbie Hancock – Just Around The Corner – CBS – 1980
George Benson – White Rabbit – CTI Records – 1971
Ed Rush & Optical – The Creeps(Incredible And Deadly!) – Virus Records – 2000
Bad Company – Inside The Machine – BC Recordings – 2000
Dr. Dre – 2001 – Aftermath Entertainment – 1999
Zapp &Roger – So Ruff, So Tuff – 1981
Parliamentの全ての作品