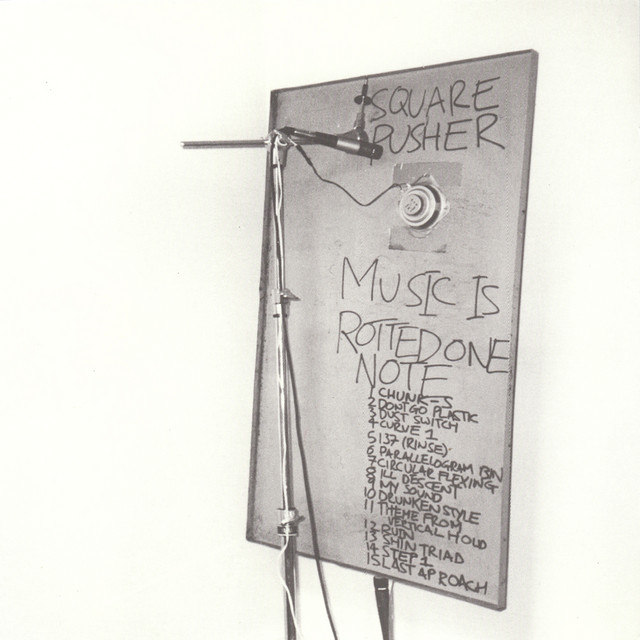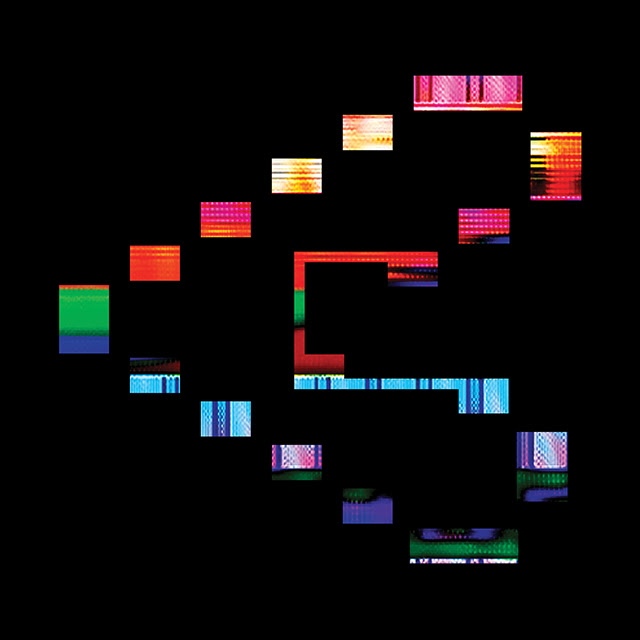2000年代にはリアルなアフリカを舞台にした超大作がハリウッドでも次から次へとつくられ、小品にも忘れがたい作品が多かったものの、現在では『ブラックパンサー』のようにおとぎ話のようなアフリカに戻ってしまうか、そもそもアフリカを舞台にした作品自体が激減してしまった(90年代よりは多い。あるいはセネガルなど現地でつくられる作品にいいものが増えてきた)。アフリカに対する注目は音楽でも同じくで、ボブ・ゲルドフとミッジ・ユーロがライヴ・エイドから20周年となる2005年に世界8大都市で「ライヴ8」を同時開催し(日本ではビョークやドリームズ・カム・トゥルーが出演)、G8の首脳にアフリカへの支援を呼びかけたり、ベルギーの〈クラムド・ディスク〉がコンゴのコノノNo. 1をデビューさせてアフリカの音楽に目を向ける機会を増大させてもいる。これに続いてデイモン・アルバーンはアフリカ・エクスプレスを組織したり、コンゴの現地ミュージシャンたちと『DRC Music』を制作、ベルリンのタイヒマン兄弟も同じくケニヤなどに赴いて『BLNRB(ベルリンナイロビ)』や『Ten Cities』といったコラボレイト・アルバムを、マーク・エルネスタスはセネガルでジェリ・ジェリ『800% Ndagga』をそれぞれつくり上げている。こうした動きはしかし、第1次世界大戦前にイギリスとドイツが次々とアフリカ各地を植民地にしていったプロセスともどこか重なってみえる、個々の動きとは別に全体としては複雑な感慨を呼び起こす面もある(ディープ・ハウスのアット・ジャズが早くから南アフリカのクワイトにコミットしていったことも多面的な要素を持つことだろう)。アフリカの音楽産業は、規模でいえば1に南アフリカ、2にナイジェリアである(北アフリカとフランスの関係は煩雑になりすぎるので省略)。西アフリカを代表するナイジェリアではイギリスとアメリカの資本が暴れている一方、この数年で東アフリカを代表し始めたのがウガンダで、同地にもイギリスやドイツ、そして中国の資本が相次いで投入されている。イギリスのコンツアーズとサーヴォが現地のパーカッション・グループとつくり上げた『Kawuku Sound』、ゴリラズのジェシ・ハケットによる『Ennanga Vision』……等々。
「先進国から来る人たちは演奏を録音して持って帰るだけ。出来上がったものを聞かせてもくれない」という不満は以前から少なからずあったらしい。アフリカと先進国の関係を変える契機が、そして、クラブ・ミュージックとともにやってくる。ウガンダのクラブ・ミュージックを牽引してきたのはDJ歴20年を超えるDJレイチェルと、2013年ごろから始動し始めた〈ニゲ・ニゲ・テープス(Nyege Nyege Tapes)〉である。東アフリカ初の女性DJとされるDJレイチェルはレコードも売っていないし、わずかなCDも高価で手の届かないものだったという90年代からDJやラップを始め、それは彼女が中流で、平均的な家族よりもリベラルな親だったから可能だったと本人は考えている(https://blog.native-instruments.com/globally-underground-dj-rachaels-journey/)。ウェデイング・プランナーとして働く彼女は結婚式で使うサウンドシステムをDJでも使いまわすことでなんとか生計を立てているようで、CDJが国全体でも3台しかないというウガンダではレンタルも簡単にはできないという。一般的にウガンダで音楽を楽しむにはスマホしかなく、それは『Music From Saharan Cellphones』(11)の頃も現在もあまり変わっていないらしい。ヒップホップからゴムまで横断的に扱うDJレイチェルの流儀に応えるかのようにして、そして、〈ニゲ・ニゲ〉がスタートする(詳細はあまりに膨大なので詳しくは→https://jp.residentadvisor.net/features/3127)。〈ニゲ・ニゲ〉の特徴を2つに絞るなら最新のエレクトロニック・ミュージックと伝統的な過去の音楽を等価に扱っていること、そして、ウガンダだけではなく、南に位置するケニアやタンザニア、あるいは西アフリカのマリやマダカスカル島東方に浮かぶレユニオンで活動するプロデューサーたちの音源もリリースしていることだろう(〈ニゲ・ニゲ〉のリリースで大きな注目を集めたタンザニアのシンゲリを紹介するコンピレーション『Sounds Of Sisso』については→https://www.ele-king.net/review/album/006179/)。〈ニゲ・ニゲ〉自体は音楽を生み出す母体として機能しているというよりDJ的な編集センスで存在感を示しているといえ、その頂点に位置しているのが現在はカンピレ(Kampire)である。DJレイチェルと同じくアクシデントでDJになったというカンピレは音楽に対する知識がなかったことが幸いしたと自身のユニークさを説明する。彼女がミックスすると、嫌いだった曲まで魅力的に聞こえてしまうので、僕もかなり舌を巻いた(ということは以前にも当サイトで書いた)。
「ウガンダのアンダーグラウンドはどんどん大きくなっている。〈ニゲ・ニゲ〉は国際的に認知され、多くの西側メディアがウガンダを記事にしている」(DJレイチェル)
そして、〈ニゲ・ニゲ〉が2018年にクラブ専門のサブ・レーベル、〈ハクナ・クララ(Hakuna Kulala)〉をスタートさせる(ようやく本題)。「安眠」というレーベル名とは裏腹にあまり聞いたことがない種類のベース・ミュージックをぶちかますケニヤのスリックバック(Slikback)やウガンダのエッコ・バズ(Ecko Bazz)などアルバムが楽しみなプロデューサーばかりが名を連ねるなか、〈ニゲ・ニゲ〉のハウス・エンジニアを務めるドン・ジラ(Don Zilla)と、ベルリンからやってきたエルヴィン・ブランディによるユニット、ヴィラエルヴィン(Villaelvin)のコラボレイト・アルバム『Headroof』がまずは群を抜いていた。バンクシーのように公共空間を使ったアート表現でも知られるというブランディはこれまで3人組のイエー・ユー(Yeah You)として4枚の実験的なアルバムをリリースした後、ソロでは本人名義の「Shelf Life(賞味期限)」などでアルカもどきの極悪インダストリアル路線をひた走り、とくにアヴリル・スプレーン(Avril Spleen)名義では混沌としたサウンドを背景にリディア・ランチばりの絶叫を聞かせてきた(それはそれで完成度の高い曲もある)。これがドン・ジラと組んだことでグルーヴを兼ね備えたインダストリアル・テクノへと変化。ドン・ジラ自身は昨年、やはり〈ハクナ・クララ〉から「From the Cave to the World」でデビューし、シンゲリを意識したようなトライバル・テクノや不穏なダーク・アンビエントを披露したばかり(コンゴ出身の彼は自分の音楽をコンゴリース・テクノと呼んでいる)。2人が起こしたアマルガメーションはアフリカとヨーロッパの音楽が混ざり合うという文脈でもすべてが良い方に転んだといえ、それぞれの音楽性が互いにないものを補完し合うという意味でも面白い結果を引き出している。インダストリアル・ノイズをクロスフェーダーで遊んでいるようなオープニングからシンゲリにはない重量感を備えた“Ghott Zillah”へ。タイトル曲の“Headroof”ではコロコロとリズムが変わる優雅なインダストリアル・アンビエントを構築し、これだけでも次作があるとすれば、それは〈パン〉からになるような気がしてしまう。ゴムをグリッチ化したような”Ettiquette Stomp”からアルヴァ・ノトとDJニッガ・フォックスが出会ったような“Zillelvina”へと続き、”Hakim Storm”ではチーノ・アモービを、ダンスホールを取り入れた“Kaloli”ではアップデートされたカンをもイメージさせる。全編にわたって知的でダイナミック。想像力とガッツにあふれたアルバムである。
〈ハクナ・クララ〉の最新リリースはアフリカ・エクスプレスにも参加していた南アのインフェイマス・ボーズによるメンジ(Menzi) 名義のカセット「Impazamo」で、これがなんとも不穏でダークなインダストリアル・ゴムに仕上がっていた。〈ニゲ・ニゲ〉がこれまで大々的にプッシュしてきたシンゲリとはだいぶ異なっった雰囲気であり、こうした方向性はしばらく維持されるに違いない(シンゲリを発展させたリリースももちろん〈ニゲ・ニゲ〉は続けている)。さらには、この夏、〈ニゲ・ニゲ〉の最初期からリリースを続けてきたナイヒロクシカ(Nihiloxica)のデビュー・アルバムが〈クラムド・ディスク〉から、という展開も。母体をなすのはドラムセット1人に7人のパーカッションが加わったウガンダの伝統的な打楽器グループ、ニロティカ・カルチャラル・アンサンブル(Nilotika Cultural Ensembl)で、この編成で彼らは昨年、〈メガ・ミュージック・マネージメント〉から『KIYIYIRIRA』というラヴリーなアルバムをリリースしたばかり。これにイギリスでアフロ・ハウスの佳作を連打してきた〈ブリップ・ディスク〉から“Limbo Yam”をリリースしていたスプーキー~Jとpq(もしかして〈エクスパンディング・レコーズ〉から『You'll Never Find Us Here』をリリースしていたpqか?)がプロデュースとシンセサイザーで加わり、ニロティカにニヒリズムの意味を加えたナイヒロクシカと名称を変形させたもの(pqは前述したエッコ・バズのプロデューサーも務めている)。イギリスの地下室とアフリカの伝統を結びつけたと自負するナイヒロクシカは2017年に〈ニゲ・ニゲ〉からカセットでデビューし、1年間ツアーを続けたことで伝統音楽「ブガンダン」に対する理解を深めたと確信し、そのままスタジオ・ライヴを収めたEP「Biiri」を昨年リリース、これをアルバム・サイズにスケール・アップさせたものが『Kaloli』となる。怒涛のドラミングは冒頭からアグレッシヴに響き渡り、まったくトーン・ダウンしない。次から次へとポリリズムが乱れ飛び、スリリングなドラミングをメインにした構成はさながら23スキドゥー『Seven Songs』の38年後ヴァージョンだろう。本人たちはこれを「ブガンダン・テクノ」と称し、「不吉なサウンド」であることを強調してやまない。エンディング近くに置かれた“Bwola”などはそれこそ『地獄の黙示録』でウィラード大尉が血だらけの顔を河から浮かび上がらせたシーンを思わせる。エンディングでは少し気分を変えるものの、全体に漲るパッションはとても暗く、情熱的である。
世界中からヴォランティア・スタッフが集まり、4日間も続くという〈ニゲ・ニゲ・フェスティヴァル〉(CDJは2台!)はもちろん警察から狙われ、今後は新型コロナウイルスの影響も避けられないだろう。ウガンダはしかし、政府がしっかりとした広報機能を兼ね備えていないらしく、コロナ対策もオーヴァーグラウンドで人気のヒップホップやダンスホールが音楽に乗せて民衆にその知識を伝え、いまのところ死者はゼロだという。つーか、タンザニアでも6月7日に終息宣言が出たものの、「神の恩恵により新型コロナウイルスを克服できた」というマグフリ大統領の言葉を聞くとかえって不安に……。韓国とともにメガ・チャーチが猛威を振るうウガンダはLGBTに対してかなり厳しい視線を向けるらしく、前述したDJレイチェルもレズであることがわかった途端に友だちを何人か失ったそうで、〈ニゲ・ニゲ〉に集まる人たちのなかには、そこが「安全地帯だから」という理由も少なからずあるらしい。
健全なオーヴァーグラウンドがあり、必要なアンダーグラウンドが機能している。ウガンダの音楽状況をイージーにまとめるとしたら、そんな感じになるだろうか。そして、それはなかなか容易に手に入るものではない。