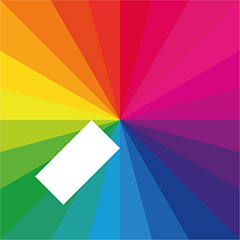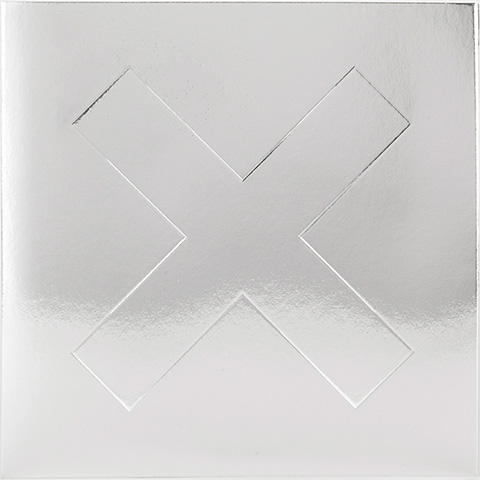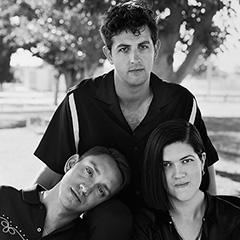MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Jamie XX- In Colour
ハウス・ミュージックは、最高の娯楽、最高の快楽のひとつだ。
たしかにレイヴ・カルチャーは公共性をめぐる大衆運動にリンクしたかもしれない。また、URやムーディーマン、ザ・KLFやハーバートのような人たちがこのフォーマットに政治的なメッセージを混ぜたのも事実だ。
だが、ダンス・ミュージックのほとんどのプロデューサーは、意味よりも機能性を、ムードとグルーヴを重んじている。そして、気持ちE追求の姿勢が切り開いた文化なのだから、それは悪いことではないのだ。
どんなにご託を並べたところで、基本、ダンス・ミュージックは快楽を目的とする。たとえそれが商業のなかに取り込まれようと、あるいは頽廃と呼ばれようと(深夜遊ぶことが頽廃そのもの)、この音楽が途絶えることはない。トーフビーツのように心配するにはおよばない。ダンスは終わらないのだ。
きっと、ジェイミーXXの『イン・カラー』を聴く多くの若い人にとって、これが最初のハウス・ミュージック体験になるのだろう。だとしたら、このアルバムは、今日におけるハウスの魅力があまりにも瑞々しく記録されている、入口としてはこのうえなく素晴らしい作品だと断言しておく。ぼくのように、ハウスを何年も聴いてきた人間さえもワクワクさせる。下手したら、ザ・XXの2枚のアルバムよりも良いんじゃないだろうか……と思えてくる。
ついでながら、日本盤には、最高の曲“All Under One Roof Raving(ひとつのレイヴの屋根の下のすべて)”が収録されているし、その未発表ヴァージョンも入っている。この1曲を聴くために、円安のため高価商品になった12インチを買うかどうか迷っていた人にとって、なんとも嬉しい話だ。
さて、この『イン・カラー』だが、あまりにも評判がいいためか、UKやUSのいちぶメディアは、早速「おぼっちゃまソウル」とか「新自由主義世代のクラブ・ミュージック」とか言いがかりを付けているのだが、こんなシニカルな言葉は放っておくのがいちばんだ。アンダーグラウンド・ミュージックがメインストリームにまで影響力を持ってしまったときは、だいたい賛否龍論が起きるものだから。誰もが褒めるのも気持ち悪いし、売れたらけなすというアングラ根性もぼくは嫌いじゃないが、この音楽を1992年へのノスタルジーとして批判する向きには反対したい。
「1992年におまえはどこにいた?(Where Were U In '92?)」という標語に従えば、まさにぼくは「クボケンとその場」にいたのだけれど、はっきり言って1992年のレイヴ・ミュージックはこんなに洗練されていなかった。もっとダサかったし、チープだった。良くも悪くも。
「美」というものを絶対視するとナチズムにさえも手を貸してしまうと指摘したのはスーザン・ソンタグだったっけ? うっかりナチズムを讃えてしまったブライアン・フェリーの過ちもそこにあったよね。同じように、ただ気持ちEだけでは疑問を忘れ、批評精神を放棄し、管理社会に手を貸してしまうのではないかと、これも昔から言われていることだ。
が、しかし、実は、あるレヴェルにまで気持ちEが達っしてしまうと、あらゆる管理装置(同調圧力や政治や慣習)から解放されてしまうもので、ハウスではそれを「I've Lost Control」という言葉で表現してきたのだけれど(アシッド・ハウスというのがそれ)、これがどういうことかと言えば、あらためて我が身の不自由さに気がついてしまうのである。人間いちどはそのぐらい気持ちEを追求してもいいんじゃないかね。なるべく若いウチに。
とはいえ、快楽が産業化したとき、考える余地や休む暇さえ与えないほど、情報がぱつんぱつんに詰め込められて、しかもやたらめったらアッパーになる。で、それはちょっと身体感覚として違うだろうと抗したのが20年前のディープ・ハウス・ムーヴメントだった。
『イン・カラー』は音楽的にはディープ・ハウスに繫がっている。もちろん焼き直しではない。ベース・ミュージック以降の感性のうえで成り立っている若々しい作品だ。1曲目の“ゴッシュ”の後半からの見事な展開、雲のうえを歩いていくような2曲目“スリープ・サウンド”への繋がり、そしてブレイクビーツのうえをロニーの歌う3曲目“シーソー”と、ここまで聴いてわからなかったら……あなたはダンス・ミュージックに近寄らないほうがいいかもしれない。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE